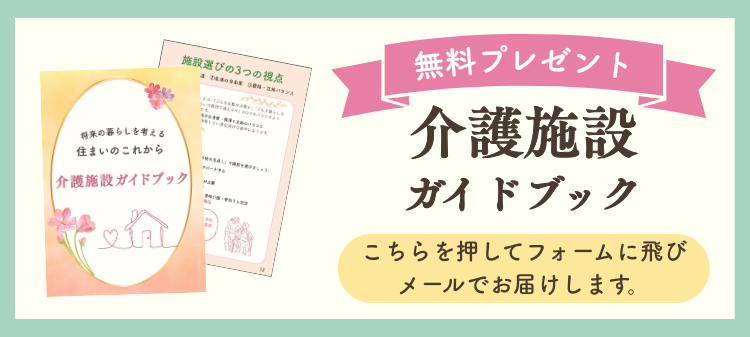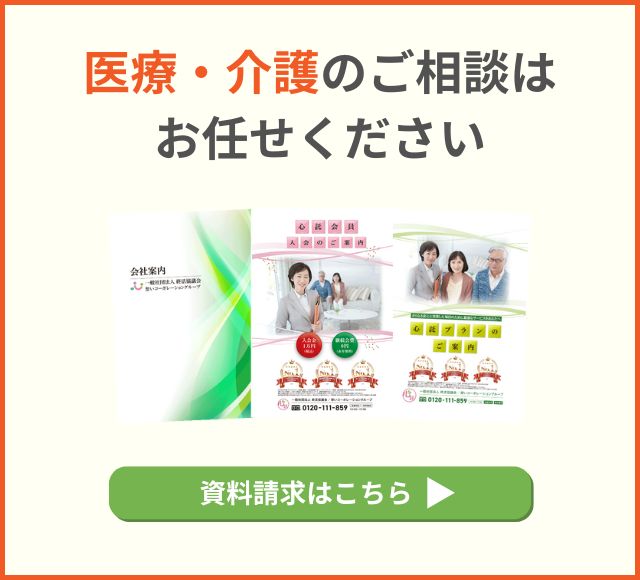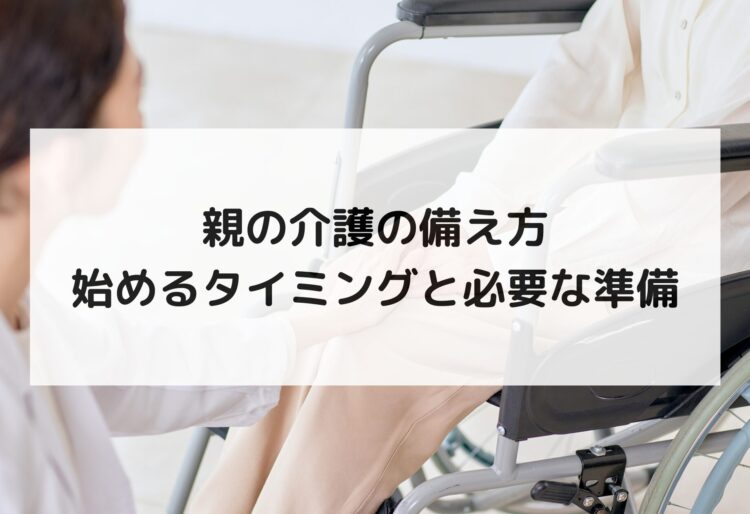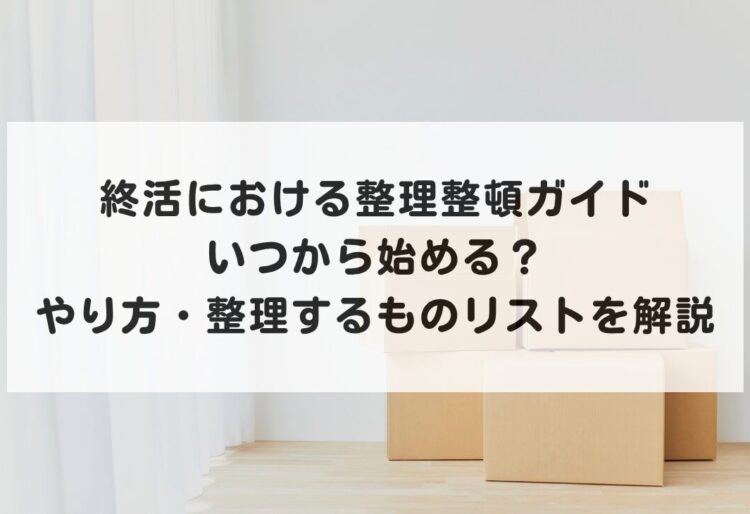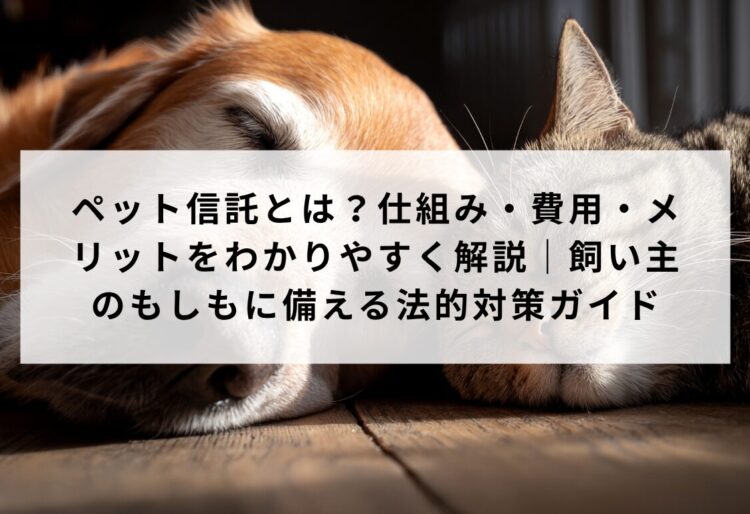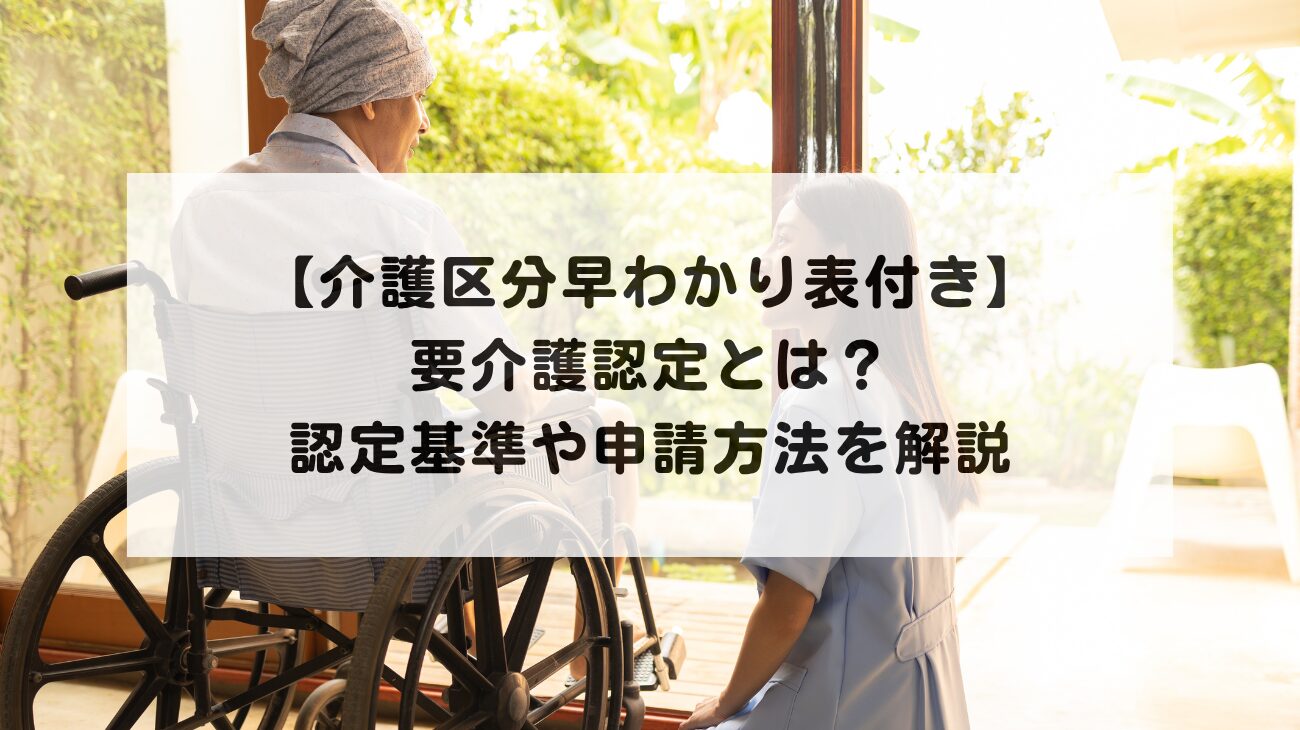
ご家族の介護が必要になったとき、まず直面するのが「要介護認定」という言葉ではないでしょうか。
要介護認定とは、公的な介護保険サービスを利用するために「どのくらいの介護や支援が必要か」を客観的に判断し、区分分けするための公式な手続きです。
この認定を受けることで、デイサービスや訪問介護、福祉用具のレンタルといった多様なサービスを、原則1〜3割の自己負担で利用できるようになります。
この記事では、要介護認定の基準や、認定調査の申請方法について、詳しくご紹介いたします。
- 要支援・要介護の違いと区分け
- 要介護認定の申請方法から認定までの流れ
- 認定結果に納得できないときの対処法
一般社団法人 終活協議会では、要介護認定の申請に関するご相談を行っています。
「要介護認定に関して何もわからない」
「申請方法ってどうすればいいの?」
という方、ぜひ一度ご相談ください。
終活のプロがあなたのお悩みに寄り添い、全面的にサポートいたします。
まずは資料をご請求ください。
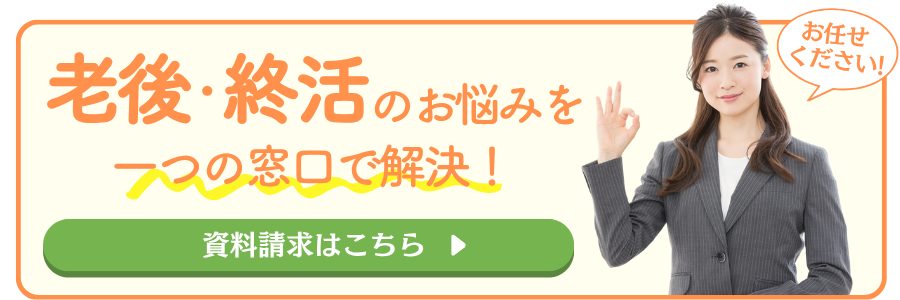
目次
【早わかり表】介護の度合いを表す8つの区分
「うちの場合は、どのくらいの区分になるんだろう?」と気になる方も多いでしょう。
要介護認定の基準は、お住まいの地域によって差が出ないよう、全国で統一された基準が設けられています。
認定は、支援の必要性が比較的軽い「要支援1・2」と、より手厚い介護が必要な「要介護1〜5」の合計7つに分けられ、そこに自立を合わせ合計8区分で表されます。
| 要介護度 | 要介護認定の目安 | 状態の目安となる具体例 |
|---|---|---|
| 非該当(自立) | 支援が必要ない状態。 | 日常生活を一人で支障なく送ることができる。 |
| 要支援1 | 基本的な日常生活は一人でできるが、家事などの支援が必要。 | 食事や排泄はほぼ自立。家事や掃除に一部サポートが必要。 |
| 要支援2 | 基本的に一人で生活ができるが、要支援1より手段的日常生活動作(調理や買い物など)を行う能力の低下が見られる。 | 立ち上がりや歩行に不安定さが見られ、転倒の危険性が高まる。 |
| 要介護1 | 基本的な日常生活は一人でできるものの、要支援2よりも身体能力や思考力の低下がみられ、日常的に介助を必要とする。 | 排泄や入浴に一部介助が必要。立ち上がりや歩行が不安定で、見守りや支えが必要な場面が増える。 |
| 要介護2 | 食事、排泄などは一人でできるが、生活全般で見守りや介助が必要。 | 食事や排泄、入浴、着替えなどに一部または全般的な介助が必要。歩行や立ち上がりが自力では困難な場合がある。 |
| 要介護3 | 自分一人でできることが減り、日常生活にほぼ全面的な介助が必要。 | 食事や排泄、入浴、着替えなど、日常生活のほぼ全般に介助が必要。自力での立ち上がりや歩行が困難。 |
| 要介護4 | 介助なしでは日常生活を送ることが困難。 | 食事や排泄、入浴、着替えなど、すべてにおいて介助がないと行えない。 思考力や理解力の低下が顕著に見られる場合がある。 |
| 要介護5 | ほぼ寝たきりの状態で、介助なしでは日常生活を送ることができない。 | 食事や排泄を含め、生活全般において全面的な介助が必要。意思の疎通も困難な場合が多い。 |
この区分を判断する客観的な指標となるのが「要介護認定等基準時間」です。
これは、介護にかかる手間を時間で表したもので、厚生労働省によって定められています。
具体的には、以下の5つの行為について、どのくらいの時間が必要かを推計します。
- 直接生活介助:入浴、排せつ、食事などの介護
- 間接生活介助:洗濯、掃除などの家事援助
- 問題行動関連行為:徘徊への対応や不潔行為の後始末など
- 機能訓練関連行為:歩行訓練や日常生活を送るための訓練
- 医療関連行為:褥瘡(床ずれ)の処置や輸液の管理など
これらの合計時間をもとに、コンピュータによる一次判定が行われ、その後の専門家による審査会を経て最終的な要介護度が決定されます。
つまり、単に病気の重さや年齢で決まるのではなく、「日常生活を送る上で、どの程度の時間と手間を要する介助が必要か」という客観的なデータに基づいて判断される仕組みになっているのです。
要支援と要介護の決定的な違いとは?
要介護認定の結果は、「要支援」と「要介護」の大きく2つに分かれます。
この2つの違いを正しく理解しておくことが、適切なサービス利用に繋がります。
要支援とは、日常生活の基本的な動作(食事や入浴など)はほとんど自分で行えるものの、掃除や買い物といった複雑な動作に一部手助けが必要な状態です。
目的は、今後、要介護状態になることを「予防」することにあります。
そのため、利用できるサービスも「介護予防サービス」が中心となります。
一方、要介護とは、基本的な日常生活動作においても何らかの介助が必要な状態を指します。
立ち上がりや歩行が不安定であったり、認知機能の低下が見られたりするなど、生活全般にわたって「介護」が必要となります。
利用できるサービスも、訪問介護やデイサービス、施設入所など、より本格的な「介護サービス」となります。
要介護度別・介護保険支給限度額の目安
要介護度によって、利用できるサービスの量(支給限度額)が異なります。
ここでは、在宅サービスを利用する場合の1ヶ月あたりの支給限度額を一覧表にまとめました。
ご自身の状況と照らし合わせる際の参考にしてください。
| 要介護区分 | 支給限度額(月額) | 単位 |
|---|---|---|
| 非該当(自立) | 介護保険サービスは利用不可(※) | - |
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217 |
※非該当(自立)と判定された場合でも、市町村が実施する独自の介護予防事業を利用できる場合があります。
※支給限度額は1単位10円で計算した場合の目安です。自己負担額は所得に応じて原則1割(一定以上の所得がある場合は2〜3割)となります。
出典:令和7年版 厚生労働白書
【完全ガイド】要介護認定の申請から認定までの5ステップ
要介護認定の手続きは、一見すると複雑に感じるかもしれません。
しかし、全体の流れを把握し、一つひとつのステップを確実に進めていけば、決して難しいものではありません。
ここでは、申請の準備から結果が通知されるまでの一連の流れを、5つのステップに分けて具体的に解説します。
一般的に、申請から認定結果が通知されるまでの期間は、原則として30日以内とされています。
ただし、自治体や申請状況によっては2ヶ月程度かかる場合もありますので、介護サービスの利用を考え始めたら、早めに準備を進めることをお勧めします。
- ステップ1:申請の相談と準備 - どこに相談し、何を用意すればよいかを確認します。
- ステップ2:認定調査(訪問調査)と主治医意見書 - 専門家が心身の状態を確認する重要な段階です。
- ステップ3:一次判定(コンピュータ判定) - 調査結果を基に機械的な判定が行われます。
- ステップ4:二次判定(介護認定審査会) - 専門家たちが最終的な要介護度を決定します。
- ステップ5:認定結果の通知 - 手続きの結果が郵送で届きます。
これらのステップを一つずつ丁寧に進めることが、適切な認定を受けるための鍵となります。
次の項目から、各ステップで「何をすべきか」を詳しく見ていきますので、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてください。
ステップ1:申請の相談と準備
要介護認定の第一歩は、申請窓口への相談と必要書類の準備から始まります。
まず、誰が申請できるのかを確認しましょう。
申請は、原則として介護サービスを利用したいご本人が行いますが、ご本人が入院中であったり、手続きが困難な場合には、ご家族や親族が代理で申請することが可能です。
また、専門機関に代理申請を依頼することもできます。
申請の窓口は、ご本人がお住まいの市区町村の役所(「介護保険課」や「高齢福祉課」など)になります。
しかし、いきなり役所に行くのはハードルが高いと感じる方も多いでしょう。
そんなときに頼りになるのが、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」です。
ここでは、申請手続きの代行を含め、介護に関するあらゆる相談に無料で応じてくれます。
何から手をつけていいか分からない場合は、まず地域包括支援センターに電話してみることを強くお勧めします。
専門のスタッフが、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれるはずです。申請に必要な書類もここで受け取れることが多いです。
どこに相談すればいい?地域包括支援センターの活用法
地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域で支えるための「総合相談窓口」です。
保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門家が配置されており、介護保険の申請手続きはもちろん、健康や医療、福祉、生活に関するさまざまな相談に対応しています。
申請書の書き方で分からない点や、今後の介護生活への不安など、どんな些細なことでも親身に相談に乗ってくれます。
まさに、介護を始めるご家族にとっての心強い味方です。
お住まいの地域のセンターの場所は、市区町村のウェブサイトなどで確認できます。
【チェックリスト】申請に必要な書類一覧
申請手続きでつまずかないために、必要書類を事前にしっかり準備しておくことが重要です。
自治体によって若干の違いはありますが、一般的に以下の書類が必要となります。
申請前に市区町村の窓口や地域包括支援センターに確認し、漏れがないようにしましょう。
- 要介護・要支援認定申請書:市区町村の窓口やウェブサイトから入手できます。
- 介護保険被保険者証(緑色またはオレンジ色):65歳以上の方に交付されています。紛失した場合は、窓口で再発行の手続きが必要です。
- 医療保険被保険者証(健康保険証):40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が、特定疾病を原因として申請する場合に必要です。
- 主治医(かかりつけ医)の情報がわかるもの:病院名、所在地、電話番号、医師名を正確に記入する必要があります。診察券などを用意しておくとスムーズです。
- 本人確認書類とマイナンバーが確認できる書類:申請者のマイナンバーカードや運転免許証など。代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
ステップ2:認定調査(訪問調査)と主治医意見書
申請書を提出すると、次は認定の判断材料となる情報を集める段階に入ります。
ここでの柱となるのが「認定調査(訪問調査)」と「主治医意見書」の2つです。
これらは、ご本人の状態を多角的に把握し、客観的で公正な認定を行うために欠かせないものです。
認定調査(訪問調査)とは、市区町村の職員や委託されたケアマネジャーなどの調査員が、ご本人の自宅や入院先の病院などを訪問し、心身の状態について聞き取りを行う面談のことです。
所要時間は1時間程度が目安です。
この調査で、日常生活の詳しい状況が確認されます。
主治医意見書は、市区町村がご本人の主治医(かかりつけ医)に作成を依頼する書類です。
申請者が直接用意するものではありませんが、申請書に主治医の情報を正確に記入しておくことが重要です。
この意見書には、病気やケガの状況、認知症の有無など、医学的な観点からの所見が記載され、認定の重要な判断材料となります。
ステップ3:一次判定(コンピュータ判定)
認定調査で聞き取った内容と、主治医意見書の一部は、コンピュータに入力されます。
そして、全国一律の基準に基づいて「要介護認定等基準時間」が算出され、7つの区分のいずれかに自動的に割り振られます。
これが「一次判定」です。
この段階は、あくまで客観的なデータに基づいた機械的な判定です。
調査票だけでは分からない個別の事情や、ご本人の特別な状況などはまだ反映されていません。
そのため、この一次判定の結果がそのまま最終的な認定結果になるわけではない、ということを覚えておきましょう。
ステップ4:二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果が出ると、次は「介護認定審査会」による二次判定が行われます。
この審査会は、医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士といった保健・医療・福祉の専門家5名程度で構成されています。
審査会では、一次判定の結果、主治医意見書の全ての記載内容、そして認定調査員が聞き取った特記事項(調査票の項目だけでは表現しきれない個別の状況など)を総合的に確認します。
そして、専門家たちがそれぞれの知見から議論を重ね、一次判定の結果が妥当かどうか、個々の状況を考慮してどの区分が最も適切かを最終的に判断します。
このプロセスにより、より実態に即した公正な判定が下されるのです。
ステップ5:認定結果の通知
二次判定が終了すると、要介護度が正式に決定されます。
市区町村は、原則として申請日から30日以内に、その結果を本人宛に郵送で通知します。
届く書類は主に「認定結果通知書」と、新しい要介護度が記載された「介護保険被保険者証」の2種類です。
通知書には、認定された要介護度(要支援1〜2、要介護1〜5、または非該当)と、認定の有効期間が明記されています。
介護保険サービスは、この有効期間内に利用することができます。
サービスを継続して利用するためには、有効期間が満了する前に更新手続きが必要になることも覚えておきましょう。
この通知を受け取った時点から、いよいよ具体的な介護サービスの利用に向けたステップに進むことになります。
認定調査(訪問調査)で後悔しないための準備と心構え
要介護認定の申請プロセスの中で、ご家族が最も緊張し、不安に感じるのが「認定調査(訪問調査)」ではないでしょうか。
「何を話せばいいんだろう?」「うまく伝えられなかったらどうしよう…」と心配になるお気持ちは、とてもよく分かります。
いくつかのポイントを押さえて準備をしておけば、ご本人のありのままの状態を調査員に正確に伝えることができます。
調査で最も大切な心構えは、「普段通りの、ありのままの姿を伝えること」です。
調査員の前で見栄を張って「できます」と答えてしまったり、逆に実際よりも大げさに「何もできません」と言ってしまったりすると、実態とは異なる認定結果に繋がる可能性があります。
そうなると、本当に必要なサービスが受けられなくなってしまうかもしれません。
調査はテストではありません。
普段の生活で「できていること」「できていないこと」「手助けが必要なこと」を、正直に、そして具体的に伝えることが何よりも重要です。
調査員は何を見る?評価される項目のポイント
認定調査は、調査員の個人的な感想で行われるわけではありません。
全国共通で定められた「基本調査票」というマニュアルに沿って、74の項目について聞き取りが行われます。
調査員は、これらの項目についてご本人の状態を客観的に評価します。
評価される項目は、大きく以下のカテゴリーに分かれています。
- 身体機能・起居動作:麻痺の有無、寝返り、起き上がり、歩行など
- 生活機能:移乗、移動、食事、排泄、入浴、着替え、金銭管理、服薬管理など
- 認知機能:意思の伝達、短期記憶、自分の名前や生年月日を言うことなど
- 精神・行動障害:ひどい物忘れ、作り話、感情の不安定さ、昼夜逆転など
- 社会生活への適応:集団への不適応、買い物、簡単な調理など
調査員は、これらの項目について単に「できる/できない」の二択で判断するわけではありません。
「どのくらいの頻度で介助が必要か」「見守りがあればできるのか、それとも直接的な手助けが必要か」といった、介助の度合いや頻度を細かく確認しています。
この点を意識して回答することが、実態を正確に伝えるコツです。
【具体例】訪問調査でよく聞かれる質問と回答のポイント
調査当日に慌てないよう、よく聞かれる質問と、どのように答えるべきかのポイントを具体例でご紹介します。
ポイントは「はい/いいえ」だけでなく、具体的な状況を付け加えて説明することです。
質問例1:「お一人で着替えはできますか?」
- 良くない回答例:「はい、できます。」(実際はボタンを留めるのに時間がかかったり、靴下が履けなかったりするのに…)
- 良い回答例:「上着を羽織ることはできますが、細かいボタンを留めるのは難しいです。特に、ズボンや靴下を履くときは、ふらついてしまうので誰かに支えてもらう必要があります。」
質問例2:「お食事はご自身でできますか?」
- 良くない回答例:「はい、食べています。」(実際は家族が食べやすいように刻んだり、むせないように見守ったりしているのに…)
- 良い回答例:「お箸を使って自分で口に運ぶことはできます。ただ、むせやすいので、とろみをつけたり、細かく刻んだりする準備が必要です。食事中も誰かに見守ってもらわないと不安です。」
このように、できることとできないこと、どのような手助けがあればできるのかを具体的に伝えることで、調査員はより正確にご本人の状態を把握することができます。
家族としてできること|調査当日の立ち会いと的確な情報提供
認定調査には、ぜひご家族が立ち会うようにしてください。
ご本人は、調査員の訪問に緊張して普段の様子と違う行動をとったり、遠慮して「大丈夫です」と答えてしまったりすることが少なくありません。
また、認知症がある場合は、ご自身の状態を正確に説明することが難しい場合もあります。
ご家族が同席することで、ご本人が答えに詰まったときに助け舟を出したり、調査員の質問の意図を分かりやすく伝えたりすることができます。
何より、普段の生活を一番よく知るご家族から、「最近、夜中に何度も起きるようになった」「薬の飲み忘れが増えている」といった具体的なエピソードを補足説明することが、非常に重要な情報となります。
事前に、日常生活で困っていることや、介助に手がかかる場面などをメモにまとめておき、調査の最後に調査員に渡すのも非常に有効な方法です。
認定結果が届いたら|ケアプラン作成からサービス利用開始までの流れ

無事に認定結果通知書が届いたら、いよいよ介護サービス利用に向けた具体的なステップが始まります。
要介護認定はゴールではなく、あくまで適切なサービスを受けるためのスタートラインです。
ここからは、認定結果を受けてから実際にサービスを利用開始するまでの流れを解説します。
まず重要なのは、認定結果によって最初の相談先が異なるという点です。
- 「要支援1・2」と認定された場合:お住まいの地域の「地域包括支援センター」に連絡します。ここで、介護予防サービスを利用するための「介護予防ケアプラン」を作成してもらいます。
- 「要介護1〜5」と認定された場合:「居宅介護支援事業者」を選び、所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)と契約します。そして、そのケアマネジャーに介護サービスを利用するための「ケアプラン」を作成してもらいます。
居宅介護支援事業者がどこにあるか分からない場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターで事業者リストをもらうことができます。
ケアプラン(または介護予防ケアプラン)が完成したら、その計画に沿ってデイサービスや訪問介護などのサービス事業者と契約を結び、サービスの利用が開始されます。
この一連の流れをスムーズに進める上で、鍵となるのが「ケアマネジャー」の存在です。
ケアマネジャーの選び方と上手な付き合い方
ケアマネジャーは、介護保険の専門家であり、ご本人やご家族の状況に合わせて最適なケアプランを作成し、サービス事業者との連絡・調整などを行ってくれる、介護生活における最も重要なパートナーです。
どの居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼するかは、自分で選ぶことができます。
【ケアマネジャー選びのポイント】
- 経験と専門性:担当してほしい方の病気や障害に関する知識や経験が豊富か。
- 相性・人柄:話しやすく、親身になって相談に乗ってくれるか。
- 対応の迅速さ:連絡がつきやすく、フットワークが軽いか。
- 地域への精通度:地域の介護サービス事業者に詳しく、多様な選択肢を提案してくれるか。
良いケアマネジャーと出会うためには、複数の事業所に問い合わせてみたり、実際に担当者と面談してみたりすることをお勧めします。
そして、契約後は遠慮せずに何でも相談することが大切です。
「こんなことを言ったら迷惑かな」と思わず、ご本人の希望やご家族の悩み、困りごとを率直に伝えましょう。
それが、より良いケアプランと満足のいく介護生活に繋がります。
ケアプラン作成のポイントと注意点
ケアプランは、今後どのような目標を持って、どの介護サービスを、いつ、どのくらい利用するのかを具体的に定めた「介護の設計図」です。
この作成費用は全額が介護保険から支払われるため、利用者の自己負担はありません。
【ケアプラン作成のポイント】
- 本人の意思を最優先する:ご本人が「どう暮らしたいか」「何をしたいか」という希望をケアマネジャーにしっかり伝えましょう。
- 家族の状況も伝える:「家族が仕事で日中は不在」「夜間の介護で眠れていない」など、介護するご家族の状況や負担も正直に話すことが重要です。
- 具体的な要望を伝える:「週に2回はデイサービスでリハビリがしたい」「入浴の介助は訪問介護にお願いしたい」など、具体的な要望を伝えましょう。
ケアマネジャーは、これらの情報をもとに、専門的な視点から最適なサービスの組み合わせを提案してくれます。
また、ケアプランは一度作成したら終わりではありません。
ご本人の心身の状態やご家族の状況は変化していくものです。
必要に応じていつでも見直し(変更)が可能なので、状況が変わった際には速やかにケアマネジャーに相談しましょう。
認定結果に納得できないときは?不服申し立て・区分変更申請の方法
申請から約1ヶ月、緊張して待っていた認定結果。
しかし、届いた通知書を見て
「思ったより軽い区分だった」
「これでは必要なサービスが受けられない」
と感じるケースも、残念ながら少なくありません。
ご本人の状態を一番よく知るご家族だからこそ、その判定に疑問を持つこともあるでしょう。
そんなとき、決して泣き寝入りする必要はありません。
認定結果に納得できない場合に取れる、2つの正式な手続きがあります。
それは「区分変更申請」と「不服申し立て」です。
これらの制度を知っておくことで、万が一の際に落ち着いて対応することができます。
どちらの手続きを選ぶべきかは状況によって異なりますので、その違いをしっかり理解しておきましょう。
「区分変更申請」と「不服申し立て」の違いと選び方
「区分変更申請」と「不服申し立て」は、目的も手続きも全く異なります。
どちらが適切か、状況に合わせて判断することが重要です。
【区分変更申請】
これは、「認定を受けた後に、心身の状態が変化(悪化)した」場合に行う手続きです。
例えば、認定後に転倒して骨折してしまった、病状が急に進行した、認知症の症状が重くなった、といったケースが該当します。
手続きの流れは、新規申請とほぼ同じで、再度、認定調査や審査会が行われます。
ポイントは、前回の認定時からの「状態の変化」を明確に伝えることです。
認定結果そのものに不服があるのではなく、あくまで「状態が変わったので、今の状態に合った区分に見直してほしい」という申請になります。
【不服申し立て(審査請求)】
こちらは、「認定の調査内容や判定プロセスそのものに誤りや不当な点があり、結果に納得できない」場合に行う手続きです。
例えば、認定調査で十分に話を聞いてもらえなかった、事実と異なる内容で報告されている、といった場合です。
申し立て先は、市区町村ではなく、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」となります。
結果が出るまでに数ヶ月かかることもあり、申し立てが認められるハードルは一般的に高いとされています。
しかし、手続きの正当性を問うための重要な権利です。
【どちらを選ぶべきか?】
まずは、なぜ結果に納得できないのかを整理しましょう。
状態の悪化が明らかなら「区分変更申請」が現実的です。
手続きの進め方に明確な疑問があるなら「不服申し立て」を検討します。
判断に迷う場合は、まず市区町村の介護保険担当窓口や、担当のケアマネジャー、地域包括支援センターに相談し、専門家の意見を聞いてみることをお勧めします。
まとめ
要介護認定は、ご本人とご家族が安心して介護生活を送るための、非常に重要な第一歩です。
複雑に見える手続きも、一つひとつのステップの意味を理解し、流れに沿って準備を進めれば、決して難しいものではありません。
最も大切なのは、認定調査で普段のありのままの状況を具体的に伝えることです。
この記事でご紹介したポイントやチェックリストが、その一助となれば幸いです。
一人で抱え込まず、地域包括支援センターやケアマネジャーといった専門家の力も借りながら、適切な介護サービスに繋げていきましょう。
要介護認定の手続きでお困りの方は一般社団法人 終活協議会にお任せください
要介護認定の申請は、必要書類の準備や認定調査への対応など、ご家族だけでは時間や手間がかかり、不安に感じることもあるかもしれません。そのような際には、専門家への相談も有効な選択肢の一つです。
一般社団法人 終活協議会の『心託(しんたく)サービス』では、終活の一環として、要介護認定の申請に関するご相談や手続きのサポートを行っています。
介護に関するお悩みや手続きがご不安な方は、ぜひ資料をご請求ください。
24時間、365日受け付けております。
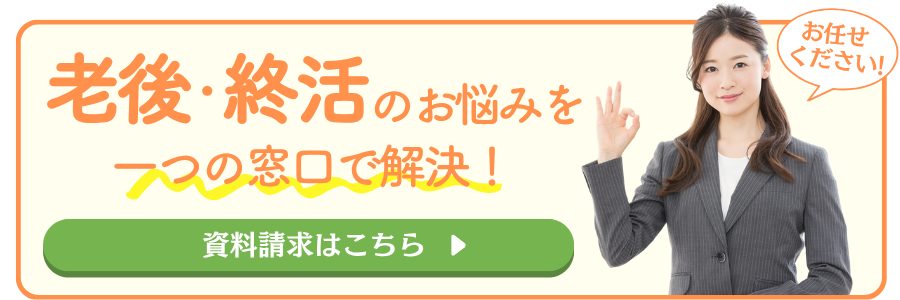
まずは直接お話を聞いてみたい、という方はお電話での相談も受け付けております。
年中無休・全国対応可能なため、お悩みに合わせて終活のプロが対応いたします。
少しでも悩んでいる方、ご不安な方は、どうぞお気軽にお電話ください。
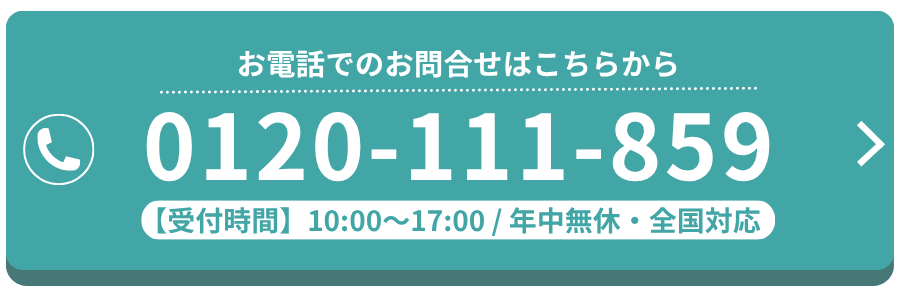
介護施設ガイドブックプレゼントはこちら!
こちらに必要項目を記入して頂き、「確認」ボタンを押してください。ご登録いただいたメールにお届けいたします。
確認ボタンを押すと、登録確認画面に遷移します。登録内容に間違えがなければ、「登録する」を押してください。
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お葬式・お墓2026年2月27日葬儀の生前予約とは?費用・手続き・注意点まで徹底解説【安心の終活】
お葬式・お墓2026年2月27日葬儀の生前予約とは?費用・手続き・注意点まで徹底解説【安心の終活】 死後事務2026年2月27日身寄りがない老後の相談はどこへ?安心して頼れる支援先まとめ
死後事務2026年2月27日身寄りがない老後の相談はどこへ?安心して頼れる支援先まとめ お金・相続2026年2月27日家族信託の手続きを自分で進める方法と注意点をわかりやすく解説
お金・相続2026年2月27日家族信託の手続きを自分で進める方法と注意点をわかりやすく解説 身元保証2026年2月27日身元引受人がいない方でも安心して施設に入る方法
身元保証2026年2月27日身元引受人がいない方でも安心して施設に入る方法
この記事をシェアする