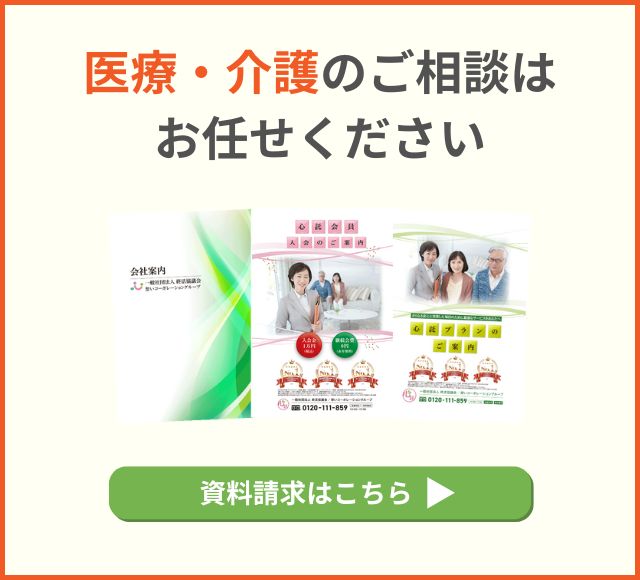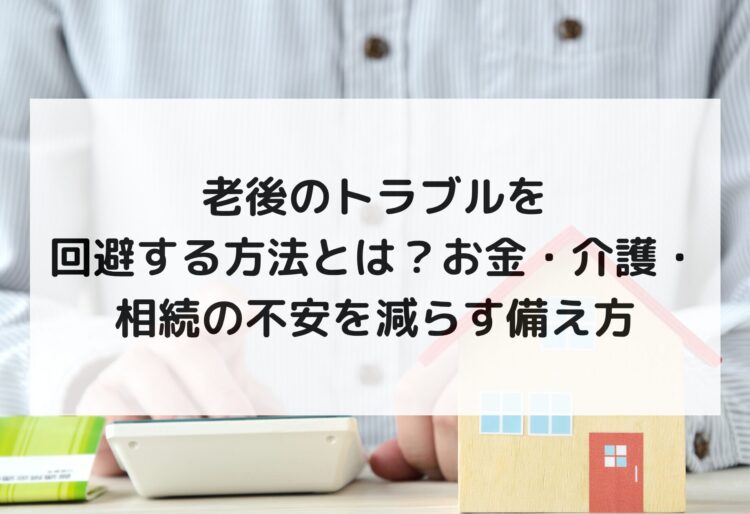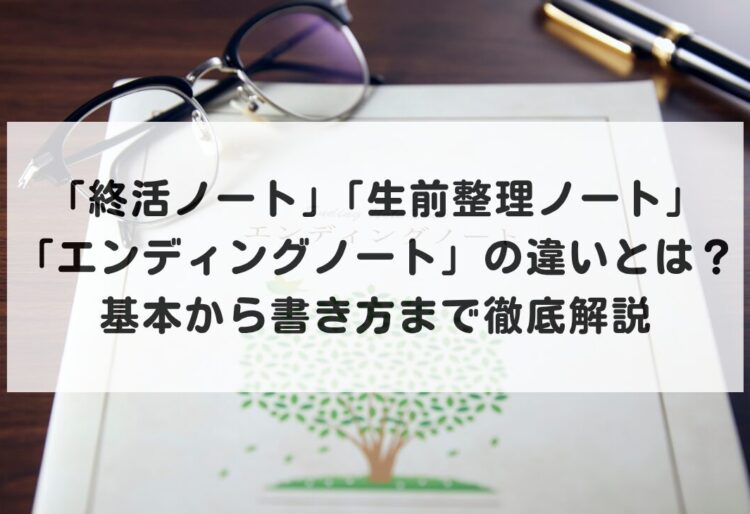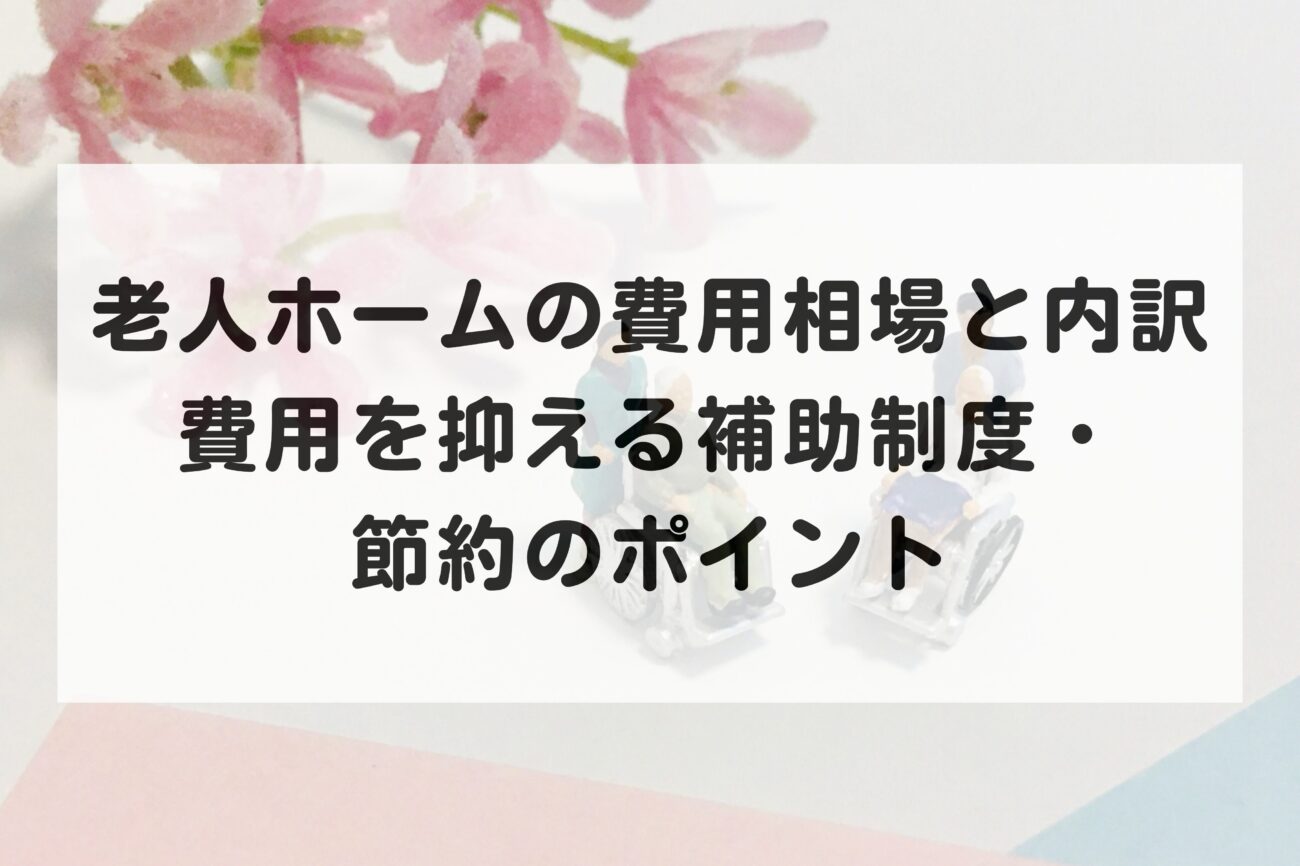
親の介護や自身の終活について考えていると「老人ホームの費用相場はどのくらい?」「いくら貯金しておけばいいの?」と不安に感じることもあるでしょう。
老人ホームの費用には入居一時金と月額費用があり、内訳は施設によってさまざまです。
そこで今回は、老人ホームの費用相場とその内訳について解説していきます。
費用を抑えるポイントについても触れていますので、親の介護や自身の終活について考えている方はぜひ最後までお読みください。
- 老人ホームの費用相場と施設別の特徴
- 費用を抑えるための補助制度
- 老人ホーム選びに悩んだときの対処法
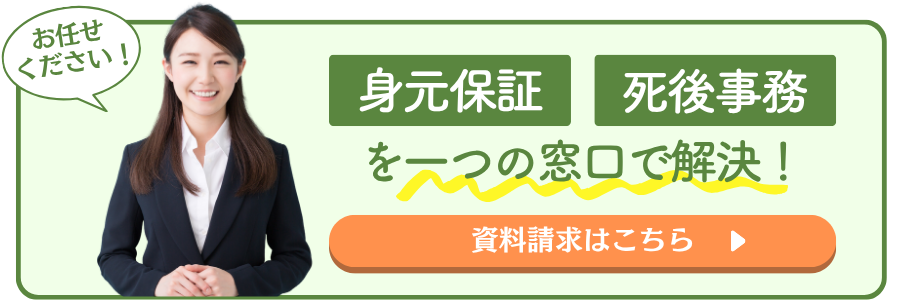
目次
老人ホームの費用は2種類|まず知るべき「入居一時金」と「月額費用」
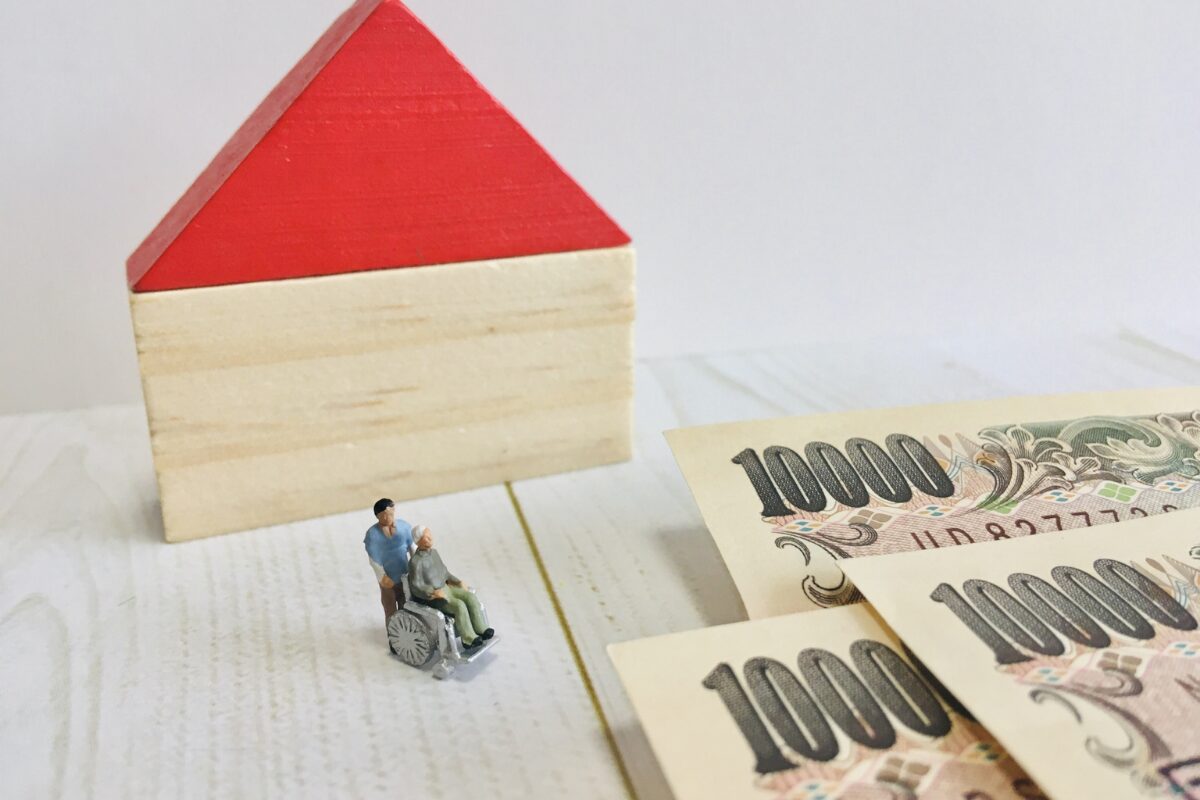
親御さんの介護やご自身の将来を考えたとき、多くの方が最初に直面するのが老人ホームの費用に関する不安ではないでしょうか。
「一体どのくらいかかるのだろう?」と、漠然とした金額の大きさに戸惑うのは当然のことです。
まずは費用の基本構造を理解することから始めましょう。
老人ホームの費用は、大きく分けて「入居一時金」と「月額費用」の2つで構成されています。
この2つの柱を理解するだけで、費用全体のイメージがぐっと掴みやすくなります。
それぞれの役割と特徴を知り、複雑に見える費用体系を一つひとつ解きほぐしていきましょう。
この基本を押さえることが、適切な資金計画を立てるための第一歩となります。
入居一時金とは?費用の目安と役割
入居一時金とは、老人ホームに入居する際に支払う初期費用のことです。
賃貸住宅でいう「敷金」や「礼金」に似ていますが、その役割は主に「家賃の前払い」に相当します。
施設によっては数十万円から数千万円、高級な施設では数億円にのぼることもありますが、近年では「入居一時金0円」というプランを設けている施設も増えています。
この一時金は、想定される入居期間(償却期間)にわたって毎月少しずつ家賃として割り当てられていきます。
もし償却期間内に退去した場合は、未償却分が返還されるのが一般的です。
高額な一時金を支払うプランは月々の負担を軽くできるメリットがありますが、初期費用を抑えたい場合は0円プランを選ぶなど、ご家庭の資金状況に合わせて選択することが重要です。
月額費用とは?毎月継続してかかる費用のこと
月額費用は、その名の通り、老人ホームでの生活を続けるために毎月支払う費用のことです。
これは日々の生活に直結するコストであり、資金計画を立てる上で最も重要な要素の一つと言えるでしょう。
月額費用の内訳は、主に居室の家賃にあたる「居住費」、日々の食事代である「食費」、共用施設の維持管理やスタッフの人件費などに充てられる「管理費・運営費」、そして介護保険サービスを利用した際の自己負担分である「介護サービス費」などで構成されています。
その他にも、理美容代やおむつ代、医療費といった個別のニーズに応じた「その他の生活費」が別途かかる場合があります。
施設の種類や提供されるサービス内容によって金額は大きく変動するため、契約前には何が含まれていて、何が別料金なのかを詳細に確認することが不可欠です。
【一覧表】老人ホームの種類別費用相場|公的・民間の違いを比較
老人ホームと一言でいっても、その種類は多岐にわたります。
そして、どの種類の施設を選ぶかによって、費用相場は大きく変わってきます。
施設は大きく「公的施設」と「民間施設」の2つに大別できます。
公的施設は、社会福祉法人や地方自治体などが運営しており、費用が比較的安価なのが最大の魅力です。
一方、民間施設は、民間企業が運営し、多様なサービスや充実した設備を提供しているのが特徴で、その分費用は高くなる傾向にあります。
どちらが良い・悪いということではなく、入居される方の心身の状態や、ご家族が支払える予算、求めるサービスの質によって最適な選択は異なります。
まずは、それぞれの特徴と費用感を一覧で把握し、ご自身の場合どのタイプが合っているのか、大まかな方向性を探ってみましょう。
公的施設・月額利用料の相場
| 公的施設 | 相場 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 5万円~15万円 |
| 介護老人保健施設(老健) | 5万円~15万円 |
| 介護医療院 | 10万円~20万円 |
| ケアハウス(軽費老人ホーム) | 8万円~15万円 |
民間施設・月額利用料の相場
| 民間施設 | 相場 |
|---|---|
| 介護付き有料老人ホーム | 15万円~40万円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 12万円~30万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) | 10万円~30万円 |
| グループホーム | 15万円~30万円 |
費用が安い傾向にある「公的施設」の費用相場
公的施設は、国や自治体からの補助を受けて運営されているため、民間施設に比べて費用を大幅に抑えられるのが最大のメリットです。
入居一時金が不要なケースがほとんどで、月額費用も所得に応じた負担軽減措置が設けられていることが多く、年金の範囲内で利用できる可能性もあります。
ただし、費用が安い分、人気が高く入居待機者が多いという側面も持ち合わせています。
また、入居には「要介護3以上」といった要介護度の条件が定められている場合が多く、誰でもすぐに入れるわけではない点には注意が必要です。
費用面での安心感は大きいですが、入居までの期間や条件を考慮し、早めに情報収集を始めることが重要になります。
特別養護老人ホーム(特養)
特別養護老人ホーム(特養)は、常に介護が必要で、自宅での生活が困難な高齢者のための施設です。
原則として要介護3以上の方が入居対象となります。
「終の棲家」としての役割を担うことが多く、看取りまで対応してくれる施設も少なくありません。
費用は公的施設のなかでも特に安価で、入居一時金は不要、月額費用は所得に応じて異なりますが、おおむね5万円~15万円程度が目安です。
費用負担の軽さから非常に人気が高く、地域によっては数年単位の待機期間が発生することもあります。
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設(老健)は、病気やケガで入院した後、すぐに在宅復帰するのが難しい方が、リハビリテーションを中心としたケアを受けながら、在宅生活への復帰を目指すための中間施設です。
入居期間は原則として3~6ヶ月と定められています。
医師や理学療法士などが常駐しているのが特徴です。
費用は入居一時金が不要で、月額費用は要介護度や部屋のタイプによりますが、おおむね5万円~15万円程度が目安となります。
あくまで在宅復帰が目的のため、長期的な入居はできません。
介護医療院
介護医療院は、長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者のための施設です。
2018年に新設された比較的新しい施設形態で、特養や老健では対応が難しい、たん吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な方を受け入れています。
医師が常駐し、日常的な健康管理から看取りまで対応可能です。
費用は入居一時金が不要で、月額費用は10万円~20万円程度が目安です。
医療ニーズの高い方が、安心して療養生活を送るための重要な選択肢となっています。
ケアハウス(軽費老人ホーム)
ケアハウスは、身の回りのことは自分でできるものの、独立して暮らすには少し不安がある60歳以上の方を対象とした施設です。
食事の提供や緊急時の対応といった生活支援サービスが受けられます。
施設には「一般型」と、要介護者向けの「介護型」の2種類があります。
入居一時金は0円~数百万円と施設によって幅があり、月額費用は8万円~15万円程度が目安です。
比較的自立度が高い方向けの住まいであり、他の入居者との交流を楽しみながら、安心して生活できる環境が提供されます。
サービスが充実した「民間施設」の費用相場
民間施設は、民間企業によって運営されており、公的施設に比べて費用は高額になる傾向があります。
しかしその分、入居者の多様なニーズに応えるための、きめ細やかなサービスや豪華な設備、豊富なレクリエーションなどが提供されているのが大きな魅力です。
ホテルのような快適な居住空間や、24時間看護師が常駐する手厚い医療体制、レストランで選べる食事など、施設ごとに特色あるサービスを打ち出しています。
入居一時金や月額費用は施設によってまさにピンからキリまで。
選択肢が非常に広いため、予算と希望するライフスタイルを照らし合わせながら、じっくり比較検討することが失敗しないための鍵となります。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、食事や清掃といった生活支援から、入浴や排泄などの身体介護まで、施設スタッフが24時間体制で提供する施設です。
都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けており、介護サービスが包括的に提供されるため、要介護度が上がっても住み続けられる安心感があります。
入居一時金は0円から数億円、月額費用は15万円~40万円程度と非常に幅広く、施設の立地や設備、人員体制によって大きく異なります。
手厚い介護を求める方にとって、最も代表的な選択肢の一つです。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、食事の提供や見守りなどの生活支援サービスが中心の施設です。
介護が必要になった場合は、入居者自身が外部の訪問介護やデイサービスといった介護事業者と個別に契約してサービスを利用する点が「介護付き」との大きな違いです。
比較的自立度の高い方が多く入居しており、必要なサービスを自分で選べる自由度の高さが特徴です。
入居一時金は0円~数千万円、月額費用は12万円~30万円程度が目安ですが、これに加えて外部の介護サービス費が別途かかります。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、バリアフリー構造の賃貸住宅で、安否確認と生活相談サービスが義務付けられています。
一般的な賃貸住宅に近い感覚で、自由度の高い生活を送れるのが魅力です。
介護が必要な場合は、住宅型有料老人ホームと同様に外部サービスを利用します。
入居一時金は敷金として0円~数十万円程度、月額費用は家賃や管理費、サービス費を含めて10万円~30万円程度が目安です。
自立した生活を続けたいけれど、万が一の備えは欲しいという方に適しています。
グループホーム
グループホームは、認知症の診断を受けた高齢者が、5~9人程度の少人数単位で共同生活を送る施設です。
家庭的な雰囲気のなかで、スタッフの支援を受けながら、食事の支度や掃除などの家事を分担して行います。
住み慣れた地域で、他の入居者やスタッフと交流しながら穏やかに暮らすことを目的としています。
入居一時金は0円~数十万円、月額費用は15万円~30万円程度が目安です。
認知症ケアに特化している点が最大の特徴です。
老人ホームの「月額費用」の詳しい内訳を解説
老人ホームの費用を検討する際、「月額費用」が具体的に何に使われているのかを正確に理解することは非常に重要です。
パンフレットに記載されている月額費用は、あくまで基本的な料金であり、それ以外にも追加で費用が発生することが少なくありません。
「一体何にいくらかかっているの?」という疑問を解消し、費用の透明性を高めることで、入居後の資金計画のズレを防ぐことができます。
ここでは、月額費用を構成する主な5つの項目(①居住費、②食費、③管理費・運営費、④介護サービス費、⑤その他)について、それぞれ詳しく解説していきます。
①居住費(家賃相当)
居住費は、施設の居室を利用するための費用で、一般の賃貸住宅における「家賃」に相当します。
この金額は、施設の立地(都心部か郊外か)、居室の広さや設備(個室か多床室か、トイレ・キッチンの有無など)、建物の新しさなどによって大きく変動します。
民間施設では各施設が独自に設定しますが、特別養護老人ホームなどの公的施設では、部屋のタイプごとに国が定めた基準額が設けられています。
入居一時金を支払っている場合は、その一部が毎月の居住費に充当される形になります。
②食費
食費は、施設で提供される食事にかかる費用です。
多くの施設では、栄養バランスが考慮されたメニューが1日3食提供されます。
料金体系は、1ヶ月分の食費が固定で設定されている場合(喫食の有無にかかわらず定額)と、食べた分だけ請求される場合(1食ごとの単価設定)があります。
施設によっては、刻み食やミキサー食、治療食といった特別な食事形態に対応してくれる場合もありますが、追加料金が必要になるケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。
③管理費・運営費
管理費・運営費は、施設の共用部分(食堂、リビング、浴室など)の維持管理や清掃、水道光熱費、事務スタッフや生活相談員などの人件費に充てられる費用です。
入居者が快適で安全な生活を送るために不可欠な経費と言えます。
この費用の中にどこまでのサービスが含まれるかは施設によって異なります。
例えば、居室の清掃やリネン交換などが管理費に含まれている場合もあれば、オプションサービスとして別途料金がかかる場合もあるため、契約内容をよく確認しましょう。
④介護サービス費(自己負担分)
介護サービス費は、入浴、排泄、食事の介助といった介護保険が適用されるサービスを利用した際にかかる費用です。
この費用の総額は、入居者の要介護度に応じて国が定めた単位数によって決まります。
実際に利用者が負担するのは、そのうちの1割~3割(所得に応じて変動)です。
介護付き有料老人ホームでは、要介護度に応じた定額制となっているのが一般的ですが、住宅型有料老人ホームなどでは、利用したサービスの分だけ支払う出来高制となります。
⑤上乗せ介護サービス費・その他の生活費
これまでの4項目以外にも、日常生活を送る上で様々な費用が発生します。
例えば、国の基準以上に手厚い介護職員を配置している施設でかかる「上乗せ介護サービス費」や、理美容代、おむつ代、新聞・雑誌の購読料、レクリエーションの材料費、個人の医療費(通院費や薬代)などがこれにあたります。
これらの費用は月額の基本料金には含まれていないことがほとんどです。
月々の支出を正確に把握するためには、これらの「その他の費用」が月にどのくらいかかるのか、平均的な金額を施設側に確認しておくことが大切です。
年金だけで老人ホームに入れる?収入別の費用シミュレーション

「親の年金だけで、老人ホームの費用をまかなえるだろうか?」これは、多くの方が抱く切実な疑問であり、最大の心配事かもしれません。
結論から言うと、受給している年金の種類や金額、そして入居する老人ホームの種類によって、その答えは大きく変わってきます。
一般的に、国民年金よりも受給額が多い厚生年金であれば、選択肢は広がります。
しかし、多くの場合、年金収入だけですべてをカバーするのは簡単ではありません。
ここでは、厚生年金と国民年金、それぞれの平均的な受給額を基に、具体的な費用シミュレーションを行い、年金だけで老人ホームに入居する場合の現実的な可能性を探っていきます。
厚生年金の場合のシミュレーション
厚生労働省の調査(令和4年度)によると、厚生年金(国民年金を含む)の平均受給額は月額約14.5万円です。
この収入で老人ホームの費用をまかなえるか考えてみましょう。
例えば、費用が比較的安価な公的施設である「特別養護老人ホーム(多床室)」の場合、月額費用の目安は約9万円~11万円程度です。
このケースでは、年金収入で基本的な月額費用を支払い、残ったお金をその他の生活費や医療費に充てることが可能かもしれません。
しかし、個室タイプのユニット型特養(月額約13万円~)や、民間施設(月額15万円~)となると、年金だけでは不足する可能性が高くなります。
厚生年金を受給していても、施設選びは慎重に行う必要があり、ある程度の貯蓄の取り崩しや、ご家族の支援を視野に入れた資金計画が現実的と言えるでしょう。
国民年金の場合のシミュレーション
一方、自営業者などが加入する国民年金の平均受給額は、月額約5.6万円(令和4年度)です。
この金額で老人ホームの費用を支払うのは、残念ながら非常に厳しいと言わざるを得ません。
最も費用が安いとされる特別養護老人ホーム(多床室)でも月額9万円以上かかるため、年金収入だけでは大幅に不足してしまいます。
この場合、年金に加えて、これまで蓄えてきた貯蓄を計画的に取り崩していくことが必須となります。
また、後述する「介護保険負担限度額認定」などの費用軽減制度を最大限に活用したり、ご家族からの経済的な援助を検討したりする必要が出てくるでしょう。
国民年金のみで老人ホームへの入居を考える場合は、早い段階から具体的な資金計画を立て、利用できる制度について詳しく調べておくことが極めて重要です。
年金だけでは厳しい場合の資金計画
シミュレーションで見たように、多くの場合、年金だけで老人ホームの費用をすべてまかなうのは困難です。
そのため、年金以外の資金をどのように準備するかが重要な課題となります。
最も一般的な方法は、預貯金を取り崩して不足分に充てることです。
どのくらいの期間、毎月いくら補填する必要があるのかを計算し、総額でいくら必要になるのかを把握しておきましょう。
また、持ち家がある場合は「リバースモーゲージ」という制度を利用し、自宅を担保に生活資金を借り入れる方法もあります。あるいは、不動産を売却してまとまった資金を作ることも選択肢の一つです。
いずれにせよ、親御さんの資産状況を正確に把握し、ご本人やご家族が納得できる形で、無理のない資金計画を立てることが大切です。
老人ホームの費用負担を賢く抑える5つの方法
老人ホームの費用は決して安いものではありませんが、工夫次第で負担を軽減することは可能です。
高額な費用を前にして諦めてしまうのではなく、利用できる制度やサービスを最大限に活用し、賢く費用を抑える方法を知っておくことが大切です。
公的な補助金制度を正しく理解して申請することから、施設選びの視点を少し変えてみることまで、実践できる方法はいくつもあります。
ここでは、ご家族の経済的な負担を少しでも軽くするために、ぜひ知っておきたい5つの具体的な方法をご紹介します。
これらのポイントを押さえることで、より多くの選択肢の中から、ご本人にとってもご家族にとっても最適な施設を見つけられる可能性が広がります。
方法1:公的な補助金・助成制度を活用する
介護にかかる費用負担を軽減するため、国や自治体は様々な補助制度を設けています。
これらの制度は、知っているか知らないかで、年間の支出が数十万円単位で変わってくることもあるほど重要です。
しかし、ほとんどの制度は自分から申請しなければ適用されません。
どのような制度があり、自分が対象になるのかを事前に調べ、積極的に活用していく姿勢が求められます。
代表的な制度には、介護サービス費の自己負担額に上限を設ける「高額介護サービス費制度」や、所得の低い方の食費・居住費を補助する「介護保険負担限度額認定」などがあります。
まずは、これらの基本的な制度を理解することから始めましょう。
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費制度は、1ヶ月に支払った介護保険サービスの自己負担額(1割~3割負担分)が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。
例えば、住民税課税世帯で一般的な所得の方の上限額は月額44,400円です。
この上限額を超えて支払った分は、後から市区町村に申請することで還付されます。
自動的に適用されるわけではないため、該当した場合は忘れずに手続きを行うことが重要です。
ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみましょう。
高額医療・高額介護合算療養費制度
この制度は、医療保険と介護保険の両方を利用している世帯の負担を軽減するためのものです。
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、その合計額が所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が支給されます。
医療費も介護費も高額になりがちな方にとっては、非常に助かる制度です。
こちらも申請が必要ですので、加入している公的医療保険の窓口(国民健康保険、後期高齢者医療制度、会社の健康保険組合など)に問い合わせてみてください。
介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)
この制度は、所得や資産が一定以下の方を対象に、介護保険施設(特養、老健、介護医療院など)やショートステイを利用した際の「食費」と「居住費」の負担を軽減するものです。
「負担限度額認定証」の交付を受けることで、所得段階に応じた上限額までの負担で済むようになります。
例えば、住民税非課税世帯の方であれば、食費や居住費が大幅に減額される可能性があります。
対象となる施設に入居する際は、必ず市区町村の介護保険担当窓口で申請手続きを行いましょう。
医療費控除
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額(通常10万円)を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税や住民税が還付・軽減される制度です。
老人ホームの費用の中にも、この医療費控除の対象となるものがあります。
}例えば、特別養護老人ホームの施設サービス費(自己負担額)の2分の1や、介護老人保健施設の費用の全額などが対象に含まれます。
対象となる費用の領収書は必ず保管しておき、確定申告の際に忘れずに申告するようにしましょう。
方法2:入居一時金0円プランを検討する
初期費用をできるだけ抑えたい場合に有効なのが、「入居一時金0円プラン」を検討することです。
まとまった資金を準備するのが難しい場合でも、入居のハードルを大きく下げることができます。
これにより、施設選びの選択肢が格段に広がるでしょう。
ただし、注意点もあります。
入居一時金は家賃の前払いという側面があるため、一時金が0円のプランは、その分だけ毎月の月額費用(特に家賃相当額)が高めに設定されているのが一般的です。
短期的な入居を想定している場合はメリットが大きいですが、長期的な入居を考えると、結果的に総支払額が高くなる可能性もあります。
トータルでかかる費用をシミュレーションし、ご自身の資金計画に合ったプランを選ぶことが重要です。
方法3:立地や居室の条件を見直す
施設の費用は、立地や居室のタイプによって大きく左右されます。
もし費用を抑えたいのであれば、これらの条件を見直してみるのも一つの手です。
一般的に、都心部や駅に近い便利な場所にある施設は費用が高く、郊外や交通の便が少し不便な場所にある施設は安価な傾向があります。
ご家族が面会に通いやすい範囲で、少しエリアを広げて探してみると、予算に合う施設が見つかるかもしれません。
また、居室のタイプも重要です。
プライバシーが確保された個室は快適ですが、その分費用は高くなります。
複数の入居者で部屋を共有する「多床室」であれば、居住費を大幅に抑えることが可能です。
ご本人の希望と予算のバランスを考えながら、条件に優先順位をつけて検討してみましょう。
方法4:リバースモーゲージや資産活用を検討する
もしご本人やご家族が持ち家を所有している場合、それを活用して入居費用を捻出する方法もあります。
その代表的なものが「リバースモーゲージ」です。これは、自宅を担保にして金融機関から融資を受け、契約者が亡くなった後にその自宅を売却して借入金を返済する仕組みです。
住み慣れた家を手放すことなく、毎月一定額の融資を受けられるため、老人ホームの月額費用の支払いに充てることができます。
また、自宅を賃貸に出して家賃収入を得たり、思い切って売却してまとまった資金を作ったりすることも有効な選択肢です。
ただし、これらの方法は資産計画に大きく関わるため、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しながら、慎重に検討を進めることをお勧めします。
方法5:将来の費用変動リスクに備える
老人ホームの費用は、入居時に提示された金額がずっと続くとは限りません。
将来的に費用が変動するリスクがあることも念頭に置いておく必要があります。
例えば、入居後に介護度が上がると、介護サービス費の自己負担額が増加します。
また、物価上昇に伴い、食費や施設の管理費が改定される可能性もゼロではありません。
さらに、おむつ代や医療費など、身体状況の変化によって新たにかかるようになる費用もあります。
資金計画を立てる際は、現在の費用だけで計算するのではなく、将来的な費用増加を見越して、ある程度の余裕を持たせておくことが大切です。
長期的な視点で備えることが、後々の「こんなはずではなかった」を防ぎます。
費用だけで決めると後悔する!失敗しない老人ホーム選びのポイント
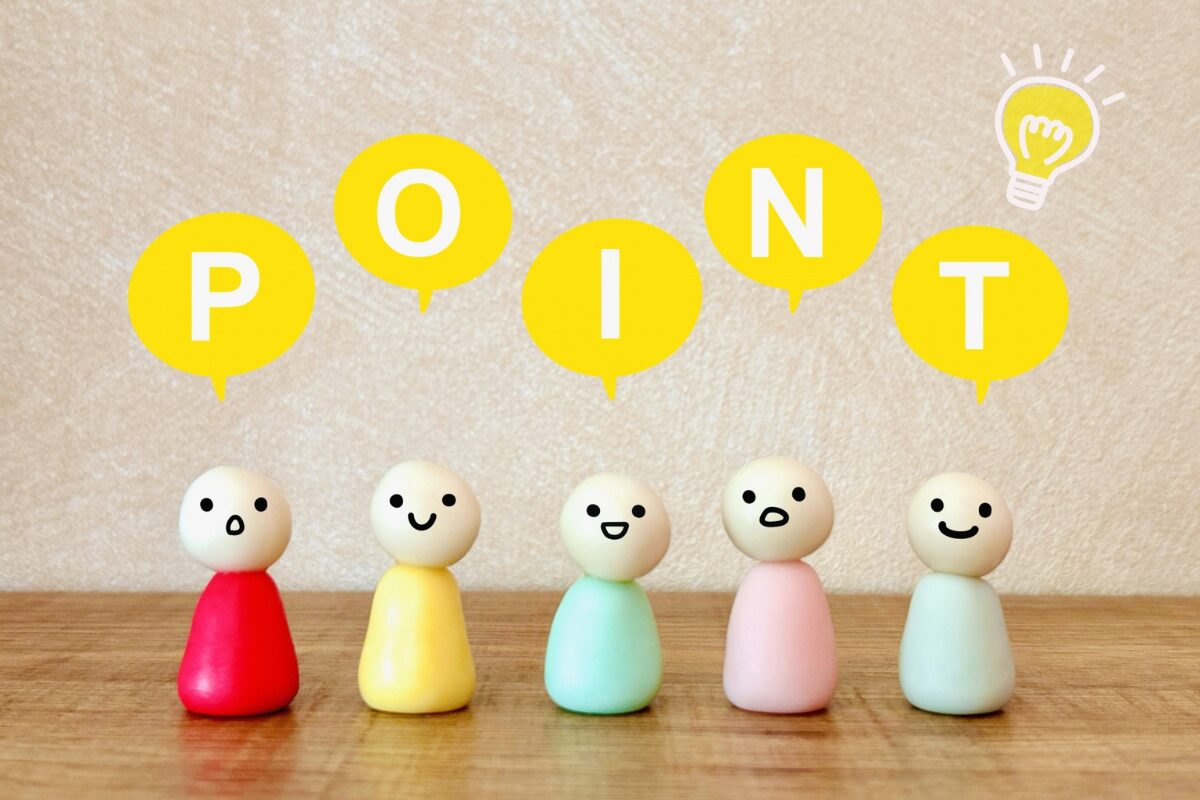
ここまで老人ホームの費用について詳しく解説してきましたが、最もお伝えしたい大切なことがあります。
それは、「費用だけで施設を決めないでほしい」ということです。
もちろん、予算内で無理なく支払えることは大前提ですが、費用という数字だけを比較して決めてしまうと、入居後に「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースが少なくありません。
その施設で提供されるケアの質、スタッフの人柄、生活環境の雰囲気といった、数字では測れない部分こそが、ご本人の穏やかな毎日を支える基盤となります。
ここでは、費用面と合わせて必ずチェックしてほしい、失敗しないための老人ホーム選びのポイントを解説します。
必ず複数の施設を見学して比較する
パンフレットやウェブサイトの情報だけで判断するのは非常に危険です。
必ず、候補となる施設を複数(できれば3ヶ所以上)見学し、ご自身の目で直接比較検討しましょう。
実際に足を運ぶことで、施設の清潔感、日当たりの良さ、共用スペースの雰囲気、そして何より、入居されている方々の表情などを感じ取ることができます。
見学の際は、案内してくれるスタッフに遠慮なく質問をぶつけてみましょう。
費用の詳細な内訳はもちろん、一日の過ごし方やレクリエーションの内容、医療体制など、気になる点はすべて確認することが大切です。
スタッフの対応や施設の雰囲気を確認する
施設見学で最も注意深く観察したいのが、スタッフの働きぶりです。
入居者に対して丁寧な言葉遣いで、笑顔で接しているか。
スタッフ同士が気持ちよく連携できているか。
忙しい中でも、見学者に対して親切に対応してくれるか。
こうしたスタッフの姿は、その施設のケアの質を映す鏡です。また、施設全体の雰囲気も重要です。
入居者の方々がリビングで楽しそうに談笑していたり、穏やかな表情で過ごしていたりする施設は、居心地の良い場所である可能性が高いでしょう。
ご本人がその場に溶け込めるかどうかを想像しながら、じっくり観察してみてください。
専門家(地域包括支援センターなど)に相談する
老人ホーム選びは、ご家族だけで抱え込むと情報収集や判断が難しく、心身ともに疲弊してしまうことがあります。
そんな時は、公的な相談窓口である「地域包括支援センター」を頼ってみましょう。
地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを支える総合相談窓口で、各市区町村に設置されています。
保健師や社会福祉士、ケアマネジャーといった専門家が、介護に関する悩みや老人ホーム選びの相談に無料で乗ってくれます。
お住まいの地域の施設情報に詳しいため、予算や希望に合った施設を紹介してくれることもあります。
無料相談サービスを利用する
公的な窓口の他に、民間企業が運営する無料相談サービスを利用するのも有効な手段です。
これらのサービスでは、専門の相談員がご本人やご家族の状況を丁寧にヒアリングした上で、数多くの提携施設の中から条件に合う施設をピックアップし、提案してくれます。
一般社団法人 終活協議会では、施設選びだけでなく、施設見学の付き添いや複雑な手続きのサポートなど、時間的・精神的な負担を大きく軽減できます。
多くの選択肢の中から効率的に情報を集め、比較検討したい場合に非常に心強い味方となってくれるでしょう。
一人で悩まず、まずは専門家の力を借りることも大切です。
⇒終活協議会の施設選びサポートを詳しく見る
まとめ
本記事では、老人ホームの費用相場や内訳、費用を抑えるポイントについて解説しました。
老人ホームの費用には入居一時金と月額費用があり、施設の種類や立地によって料金設定はさまざまです。
終活を考える上でも、予算にあった施設選びは大切です。
施設入所するにあたっては、身元保証人も必要です。
身元保証人を立てられずに施設入所が難航するケースは少なくありません。
「一般社団法人 終活協議会」では、身寄りのない方の日常生活の支援や、病院・介護施設利用時に必要な保証人代行サービスなどを提供しています。
資料請求は24時間365日受け付けています。
終活について考えていたり、将来の施設入居に不安を感じたりしている方は、お気軽にご相談ください。
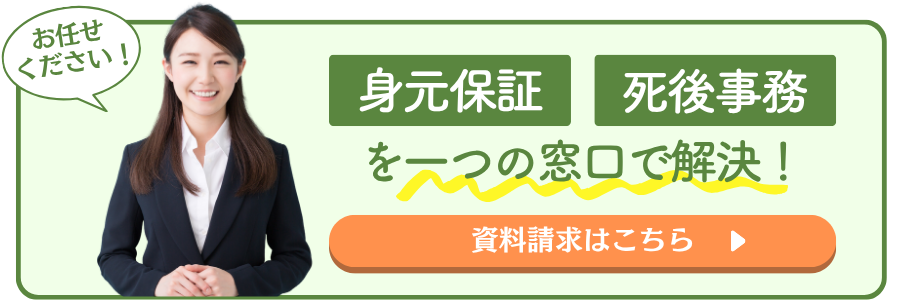
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする