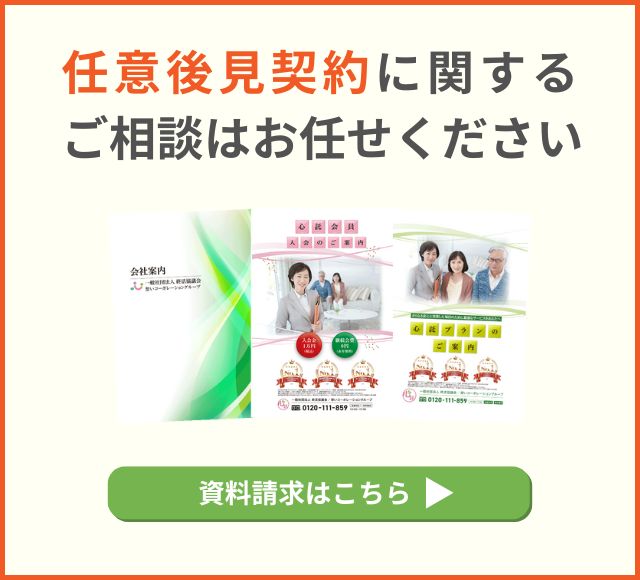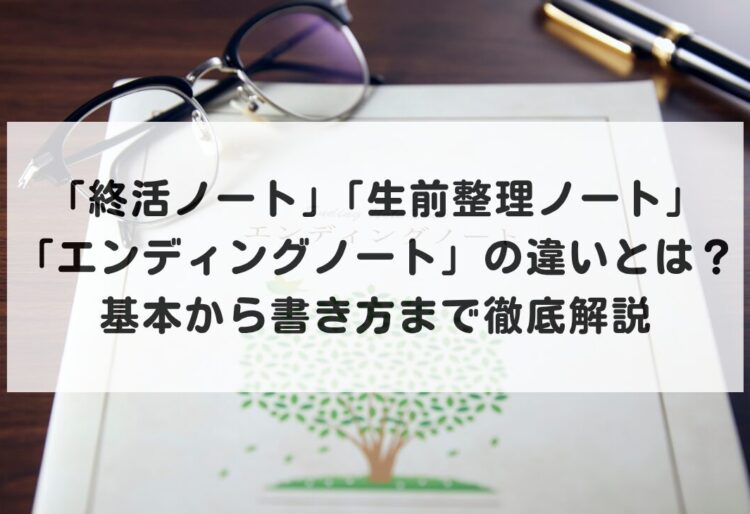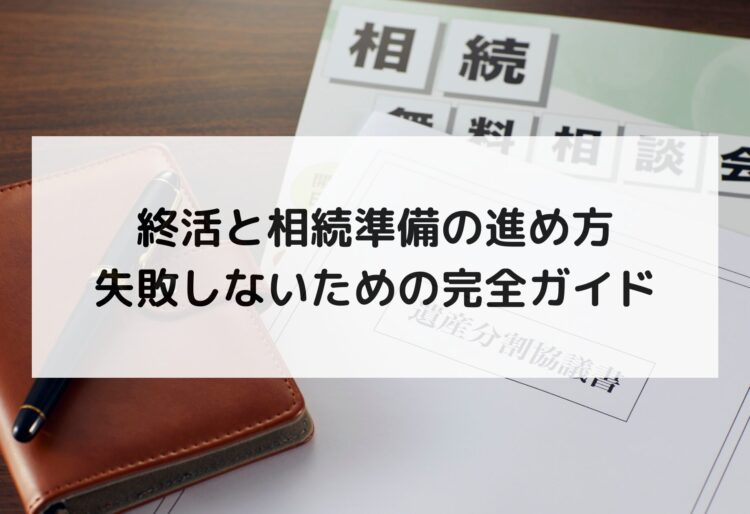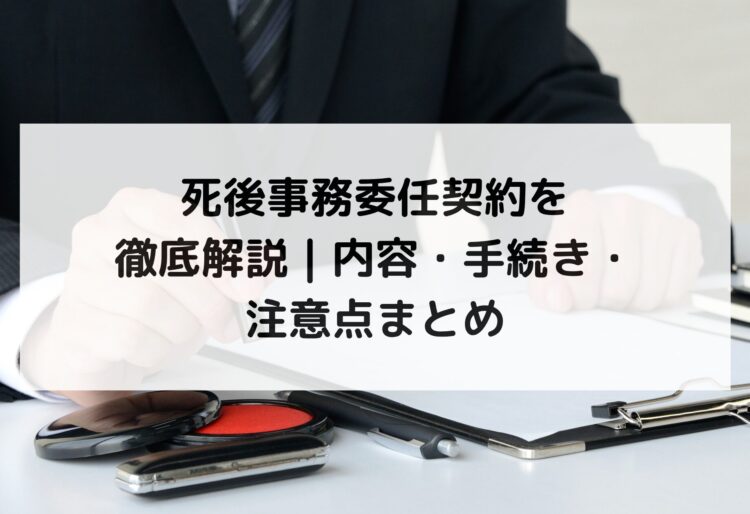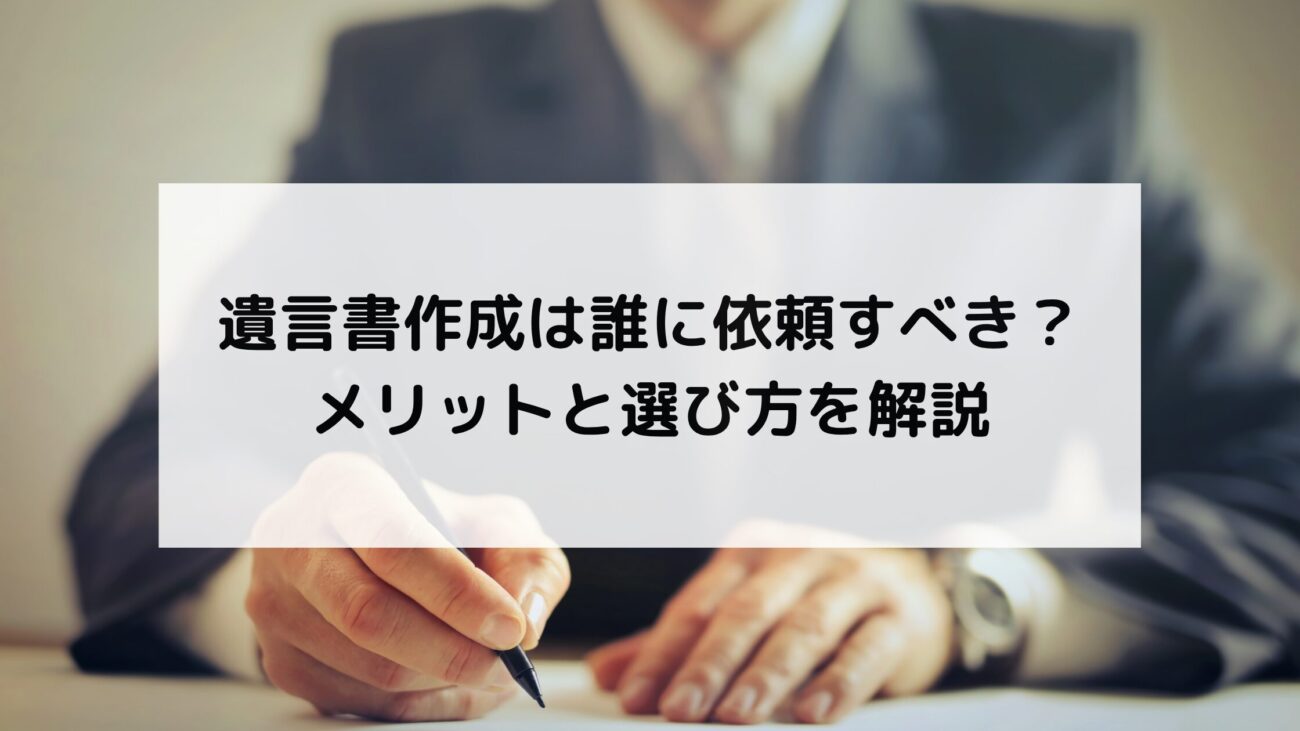
遺言書は、自分の財産や想いを正しく次の世代に伝えるための大切な手段です。
しかし「自分で書けばいいのか」「誰に依頼すれば安心なのか」と迷う方も少なくありません。
この記事では、遺言書作成のメリットや注意点、依頼先の選び方までをわかりやすく解説します。
これを読めば、自分に合った方法で安心して遺言書を作成できるようになりますよ。
目次
1. 遺言書の作成を依頼するメリットとは?
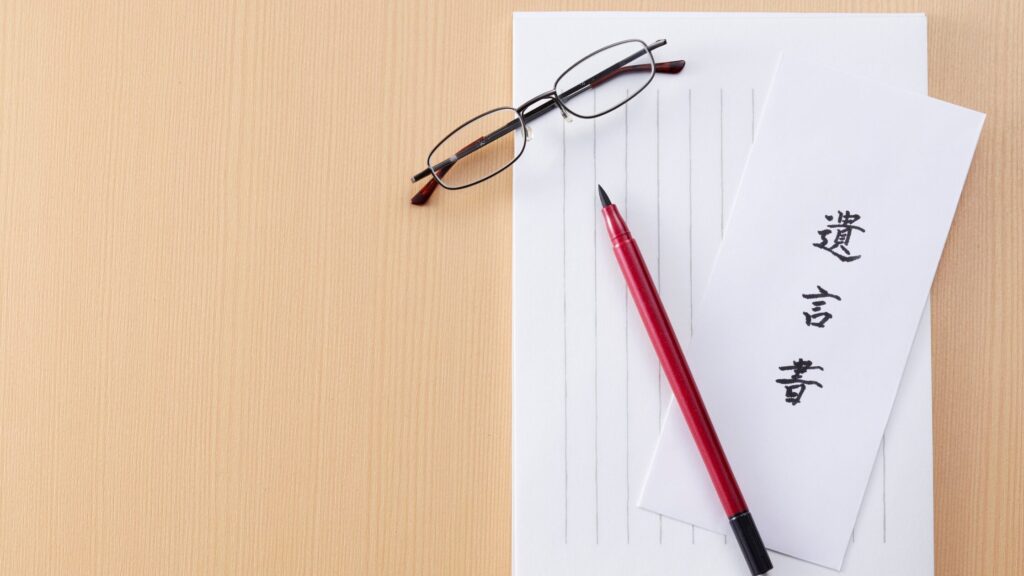
1.1 自分で作るよりも安心できる理由
「自分で遺言書を作れば、費用もかからないし簡単そう」と思っていませんか?
確かに自筆証書遺言なら自分一人で作成できますが、意外と落とし穴が多いんです。
たとえばこんな失敗が多いです。
- 書き方に不備があって法的に無効になる
- 日付や署名の記載漏れでトラブルになる
- 意図が伝わらず相続人間で争いに発展する
こうしたトラブルを防ぐには、専門家に遺言書作成を依頼するのが安心です。
法律のプロが内容や形式をチェックしてくれるので、形式的ミスを防げます。
日常の例でいうと、料理初心者がレシピなしで作るのと、料理教室でプロに教わって作るのでは仕上がりが違いますよね。それと同じで、遺言書もプロのサポートがあるだけでグッと安心感が増します。
さらに公正証書遺言にすれば、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
その分、残された家族の手間やストレスが減り、スムーズに相続が進められます。
1.2 専門家に依頼することで得られる具体的な効果
専門家に依頼することで得られる効果は、書面の整合性だけではありません。
相続の全体像を整理し、トラブルの種を事前に摘むことができるんです。
たとえば、以下のようなメリットがあります。
- 財産分配のバランスを客観的に確認できる
- もめやすいポイントを避けた文言にできる
- 誤解のない表現で意図が正確に伝わる
特に複数の不動産や口座がある場合、それぞれの扱いを細かく記載しなければなりません。
専門家ならその財産の整理からサポートしてくれるので、負担がグンと減ります。
「相続でもめるくらいなら、きちんと整えておきたい」
そんな気持ちに応えてくれるのが専門家への依頼です。
また、将来的に遺言の内容を変更したくなったときも、以前の記録をもとにスムーズに対応できます。相談履歴が残っていることも、安心材料のひとつです。
2. 遺言書作成でよくある失敗とその対策

2.1 書き方のミスで無効になるケース
自筆証書遺言は手軽に書ける反面、形式ミスが多く、無効になることがあります。
特に多いのが以下の3つです。
- 日付が「令和◯年◯月吉日」など曖昧な表記
- 署名や押印が抜けている
- 財産や受取人がはっきり書かれていない
これらの形式不備があると、せっかくの遺言書が法的に無効になります。
解決策としては、公正証書遺言にすることが一番確実です。公証人が作成をサポートし、内容を正式に記録してくれるので、形式ミスの心配がありません。
また、専門家に相談することで、自筆証書遺言でも正確な書き方を教えてもらえます。
「形式的な失敗を防ぐには、専門家のチェックが欠かせません」
2.2 内容が曖昧で相続トラブルに発展するケース
内容が曖昧だと、相続人同士で解釈が食い違い、争いに発展することがあります。
たとえば、
- 「長男に不動産を相続させる」とだけ書いてある
- 「預貯金を子どもたちに分配」と書いただけで割合が不明
- 特定の財産の記載が抜けている
このような記述では、誰に何をどれだけ渡すのかが明確になりません。結果として遺産分割協議で意見が割れ、関係がこじれる原因になります。
こうした曖昧さを避けるには、以下のような工夫が有効です。
- 財産は「不動産の登記簿記載」「口座番号付き」で具体的に記載
- 「相続人の名前+分配割合」などで明確に記述
- 付言事項で気持ちや意図を補足
専門家に依頼すれば、誤解のない表現に修正してくれるので安心です。
事前に家族との意見調整をしておくのも重要ですね。
2.3 保管場所や見つけ方が不明で混乱を招くケース
意外と多いのが、遺言書の「保管方法」による失敗です。
せっかく作った遺言書が見つからず、相続人が困ってしまうパターンもあります。
主な失敗例はこちらです。
- 自宅のどこにあるかわからない
- 通帳などと一緒に保管し忘れた
- 誰にも伝えずに保管していた
こうしたケースでは、遺言書が発見されなかったり、発見されても無効になる可能性も。
相続が遅れて財産の手続きが進まない原因になります。
この問題を避けるには、公正証書遺言の活用がおすすめです。
公証役場で正式に保管され、死後に検索も可能なため、遺族の手間を減らせます。
また、自筆証書遺言でも2020年から法務局での保管制度がスタートしており、確実に管理できるようになりました。
「作るだけで終わりにせず、どこにどう保管するかがとても大事です」
3. 遺言書作成を依頼する前にやっておきたい準備

3.1 財産の棚卸しとリスト化のポイント
遺言書をスムーズに作成するには、まず「財産の全体像」を把握することが大切です。
どこに何があるか自分ではわかっていても、他の人には伝わっていないことが多いんです。
たとえば、こんな種類の財産があります。
- 預貯金(銀行口座ごとに一覧化)
- 不動産(所在地・登記内容を明記)
- 株式や投資信託(証券口座・銘柄)
- 借金やローン(残高・返済条件)
- 家財や貴重品(価値のある物を中心に)
「把握できていない財産は、遺言に書けません」
まずは紙でもExcelでも構いませんので、一覧表にして整理しておきましょう。
忙しい日常の中でも、週に1回30分だけでも時間をつくって進めれば、1か月ほどでしっかり整理できます。
「思ったより多かった」「忘れていた口座があった」という声もよくあります。
3.2 相続人・関係者との情報整理
次に整理しておきたいのが「誰に何を遺すのか」という点です。
相続人や、遺贈したい相手の情報を明確にしておきましょう。
主な確認ポイントはこちらです。
- 配偶者や子どもなどの基本的な法定相続人
- 特別に財産を残したい人(兄弟姉妹、孫、内縁の配偶者など)
- 住所・続柄・年齢など、正確な情報
これを明確にしておかないと、専門家に依頼したときにも手続きが進まず、作業が長引いてしまいます。
また、誰に何を渡すかを考える中で、気持ちの整理にもつながります。
「長男には家、不動産は次男に…」というように分けて考えると、より具体的な遺言内容が固まります。
トラブルを防ぐためにも、できれば早めに家族に考えを伝えておくと安心です。
3.3 気持ちを整理するためのヒント
財産の整理や関係者の情報がまとまったら、最後は「気持ちの整理」が大事です。
遺言書は、ただの財産分配の書類ではありません。
自分の思いや感謝の気持ちを込めることができる、大切なメッセージでもあるんです。
よくある例としては、
- 子どもたちへの感謝の言葉
- 生前お世話になった方へのお礼
- 遺された家族への励ましや希望
こうした「付言事項」は法的拘束力はありませんが、心のこもった一文が残された家族を支えてくれます。
「数字だけの遺言では伝わらない気持ちがある」
そう思って、一言だけでもメッセージを添えてみてください。
静かな時間に、昔の写真を見返しながら考えるのもおすすめです。
過去の思い出を振り返ることで、自分が何を大切にしてきたかが見えてくるはずです。
4. 遺言書作成を依頼するなら?専門家の選び方とポイント
4.1 司法書士・行政書士・弁護士の違い
遺言書の作成を依頼する際、多くの人が最初に迷うのが「誰に頼むべきか」という点です。
司法書士、行政書士、弁護士、それぞれに得意分野があるため、目的に応じて選ぶのがポイントです。
それぞれの違いを表で比較してみましょう。
| 専門家 | 得意な手続き | 向いているケース | 注意点 |
| 司法書士 | 相続登記、公正証書遺言の手続き支援 | 不動産が関わる相続や、登記も依頼したい場合 | 法的トラブルには対応不可 |
| 行政書士 | 自筆証書遺言の文案作成、書類提出代行 | 法的トラブルがなく、形式面を整えたい場合 | 複雑な法解釈には不向き |
| 弁護士 | 相続争い対応、法的アドバイス | 家族間でもめる可能性がある、遺留分への配慮が必要な場合 | 費用が高くなる傾向あり |
たとえば、財産に複数の不動産が含まれていたり、過去に家族間でもめた経験がある場合には、弁護士に相談する方が安全です。
一方で、「形式をしっかり整えて安心しておきたい」という程度であれば、司法書士や行政書士でも十分です。
「状況に合った専門家を選ぶことが、スムーズな遺言書作成につながります」
4.2 専門家選びで確認すべきポイント
専門家の肩書きだけで判断するのではなく、「実際の対応力」や「相談のしやすさ」に注目することが大事です。
以下のような視点でチェックしてみてください。
- 遺言書作成の実績はどのくらいあるか?
→ 年間で何件対応しているか聞くと、経験値がわかります。 - 公正証書遺言や法務局保管制度の知識があるか?
→ 制度変更に柔軟に対応できる専門家を選びましょう。 - 見積もりが明確か?後から追加費用がかからないか?
→ 契約前に細かく確認しておくと安心です。 - オンラインや訪問対応が可能か?
→ 体が不自由な方や、忙しい方にとって重要なポイントです。
また、初回の相談時に「こちらの話をしっかり聞いてくれるか」「具体的な提案をしてくれるか」も重要です。
一方的に話すだけの専門家は避けた方が良いでしょう。
「一度の相談で判断せず、2〜3人に話を聞くのもおすすめです」
時間と手間はかかりますが、長期的に見ればその方が確実に満足のいく遺言書が作れます。
4.3 実績や相談しやすさも大事な判断材料
遺言書は非常に個人的な内容を含みます。
「どんな家族構成なのか」「どんな思いで財産を遺すのか」など、話しにくいことも多いですよね。
だからこそ、以下のような“人としての相性”がとても大事です。
- 穏やかな口調で話を聞いてくれる
- 専門用語を使わずわかりやすく説明してくれる
- 否定せず、気持ちに寄り添ってくれる
たとえば、相談者が「家族に秘密で遺言書を作りたい」と話したとき、頭ごなしに否定する専門家よりも、「そのお気持ち、わかります」と共感しつつ選択肢を提示してくれる人の方が安心できます。
また、信頼できる専門家は、単に「遺言書を作って終わり」ではなく、その後のフォローまで見据えてくれます。
将来的に遺言の内容を見直すことになった場合にも、再相談しやすい関係が築けていれば、ずっと安心です。
「専門家との相性が良ければ、相談のストレスもグッと減ります」
費用や知識だけでなく、信頼関係を築けそうかどうかも判断材料に加えてください。
5. 遺言書作成を依頼する流れと費用の目安
5.1 相談から作成までの一般的な流れ
遺言書作成を専門家に依頼する場合、どのような流れになるのか気になりますよね。
大まかなステップは以下のとおりです。
- 初回相談・ヒアリング
現状の財産、家族構成、希望内容を丁寧に確認します。 - 財産の整理・情報提供
財産リストや関係者情報を提出。事前にまとめておくとスムーズです。 - 遺言内容の草案作成
希望に基づいた案を専門家が作成。細かな調整も行います。 - 文案の確定・証人手配
内容が固まったら証人を準備し、公正証書の場合は公証役場と調整します。 - 正式な作成・署名・押印
自筆証書または公正証書として完成させます。 - 保管方法の確認・アドバイス
自宅保管か法務局・公証役場での保管を選択し、将来への備えを整えます。
このように進めることで、「無理なくスムーズに遺言書が完成できます」
1~2か月程度で完成するケースが多いですが、内容の複雑さにより前後することもあります。
5.2 費用相場とプランの比較
遺言書の作成費用は、依頼内容や専門家によって差があります。
以下は一般的な費用相場の目安です。
| 内容 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
| 書類作成サポート | 3~5万円 | 5~10万円 |
| 公証人手数料 | 不要 | 1万1千円~数万円(財産額による) |
| 合計費用 | 3~5万円程度 | 6~15万円程度 |
プランによっては、財産調査や相続対策もセットになっているものもあります。
「公正証書で確実にしたい」「保管も任せたい」といったニーズに応じて選びましょう。
なお、追加で相続登記や死後事務委任契約まで含めると、費用が上乗せされる場合があります。
予算に不安がある場合でも、まずは無料相談を活用するのがオススメです。
5.3 終活協議会の「心託(しんたく)サービス」で叶える、死後も安心なサポート体制
「もしものときに家族に迷惑をかけたくない」
そう考える方から選ばれているのが、終活協議会の「心託(しんたく)サービス」です。
遺言書作成はもちろん、死後の手続きをすべて代行する包括的なサービスです。主なサポート内容は以下の通りです。
- 葬儀や納骨の手配
- 関係者への連絡代行
- 行政手続きの代行(住民票・保険・公共料金等)
- 遺品整理・不動産処分のサポート
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行手続きの代行
- 相続支援・財産整理まで
「遺言書を作って終わりではなく、実行まで安心して任せられる」という点が大きな特徴です。
終活協議会は47都道府県に支部を持ち、会員数は20,000名以上。
1.000名以上の専門家ネットワーク(弁護士・司法書士・行政書士・税理士などにより幅広い対応が可能です。
また、専任コンシェルジュが一人ひとりに付き、財産開示は不要。
プライバシーを守りつつ、きめ細やかな対応が受けられます。
「身寄りがいない」「遠方の家族に負担をかけたくない」
そんな方にとって、「心託(しんたく)サービス」は大きな安心の支えとなるサービスです。
6. まとめ:遺言書作成はプロへの依頼でスムーズに
6.1 自分と家族の安心を守る第一歩
遺言書の作成は「まだ先の話」と思われがちですが、実際には早めに準備を始める方がスムーズです。
相続のトラブルは予期せぬタイミングで起こりやすく、いざというときに「準備しておけばよかった…」と後悔する人も少なくありません。
遺言書をきちんと整えておくことで、
- 家族の相続手続きをスムーズにできる
- 不要な争いを未然に防げる
- 自分の意思をしっかり残せる
といった効果が得られます。
「自分と家族の安心を守るための第一歩が、遺言書作成の依頼です」
形式や内容のミスを避けるためにも、専門家のサポートは欠かせません。
財産の種類や相続人の状況に応じて、ベストな方法を提案してもらえます。
6.2 終活協議会の心託サービスで不安ゼロの終活を
遺言書作成を考えるなら、アフターケアまで見据えた終活サポートが重要です。
終活協議会が提供する「心託サービス」は、遺言書作成から死後事務、身元保証までを一括してサポートする充実の終活支援です。
特に注目すべきポイントはこちらです。
- 全国47都道府県に支部を展開し、地域を問わず対応可能
- 士業従事者が選ぶ「一生任せたい終活支援会社No.1」の信頼実績
- 会員数20,000名以上、終活ガイド資格取得者30,000名以上の実績
心託サービスには、以下の3つの基本プランがあります。
| プラン名 | 主な内容 | 特徴 |
| 安心プラン | 身元保証・生活サポート | 入院や施設入居時の保証対応に特化 |
| 万全プラン | 死後事務全般 | 葬儀・納骨・遺品整理・遺言作成などを網羅 |
| 完璧プラン | 身元保証+死後事務 | 将来に備えてすべてを包括したフルサポート型 |
「遺言書を整えるだけでなく、死後も安心できるサポート体制が整っている」
それが終活協議会の大きな魅力です。
さらに、財産開示は不要で、月額・年会費もゼロ。
費用も明瞭で安心です。
もし、遺言書の作成に迷っているなら、終活協議会の無料相談や説明会を活用してみてください。
あなたの希望に合ったプランを、専任のコンシェルジュが丁寧に提案してくれます。
終活サポートなら終活協議会にお任せください
遺言書作成から死後事務、身元保証まで、専門家が一貫してサポートする「心託サービス」が好評です。
全国47都道府県対応、会員数20,000名以上の実績があるから、安心して終活の一歩を踏み出せます。
詳しくは終活協議会の公式サイトをご覧ください。
→一般社団法人 終活協議会の「心託(しんたく)サービス」について
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする