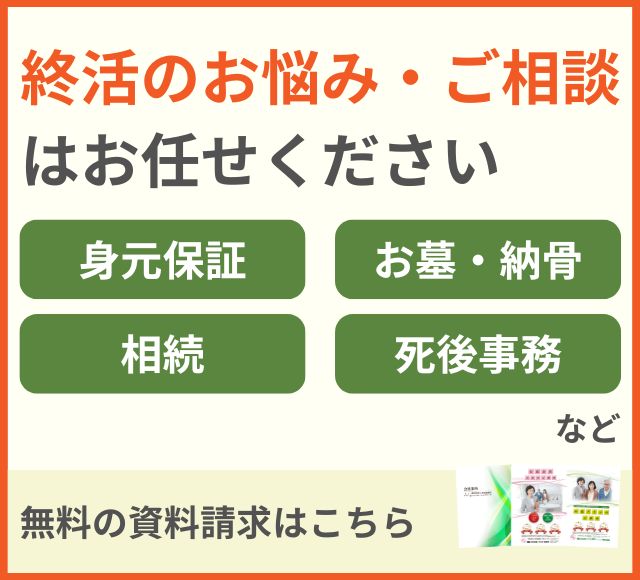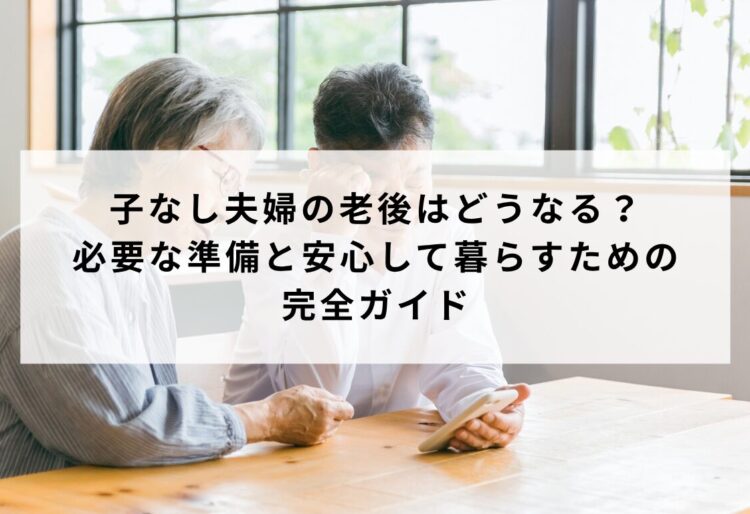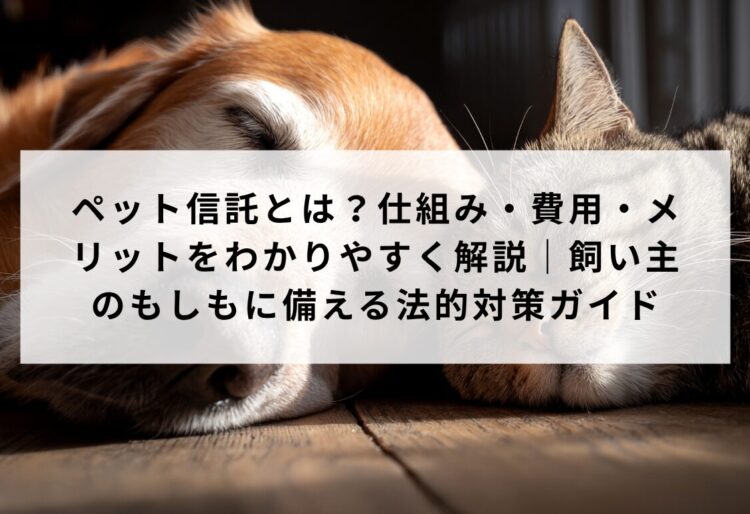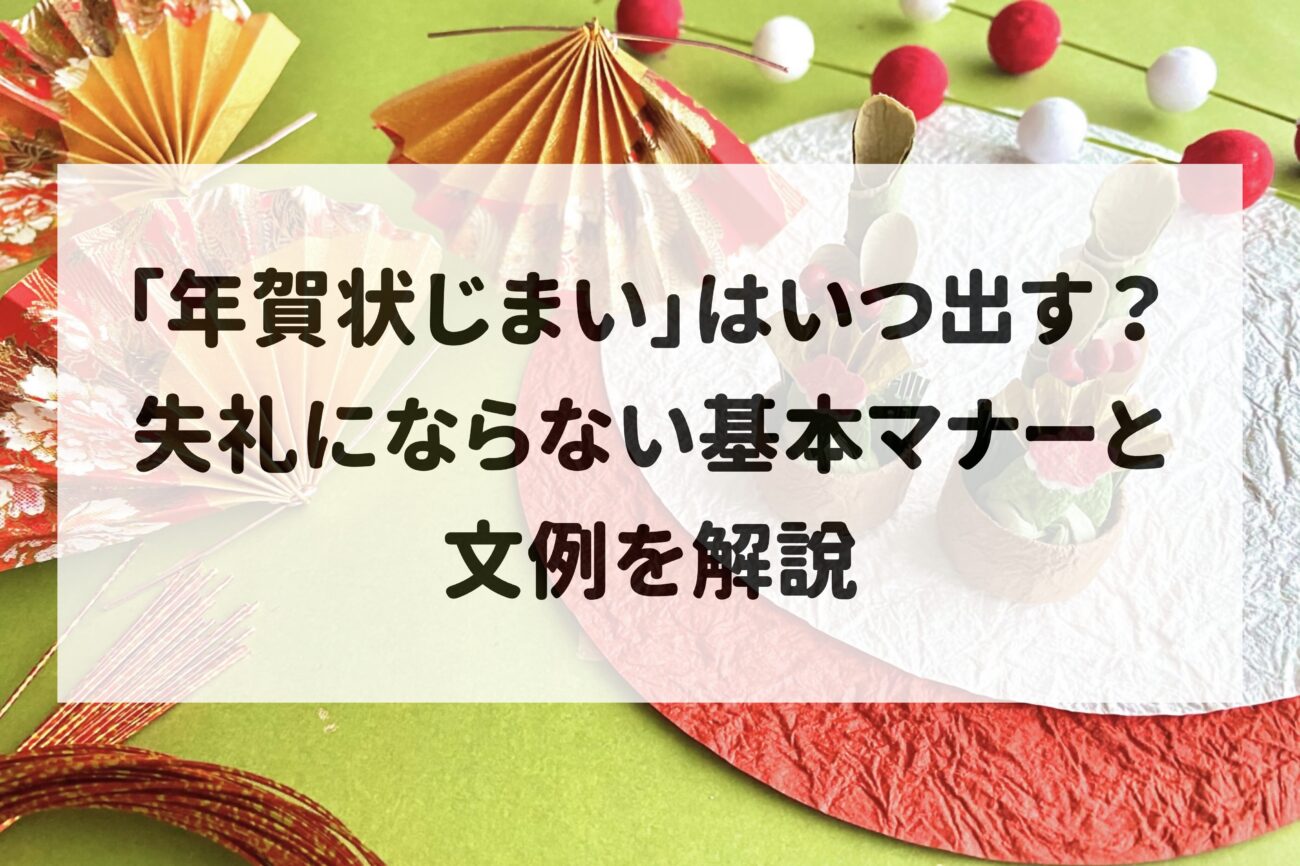
平安時代から続く日本独自の文化である“年賀状”ですが、近年じわじわと広まっている「年賀状じまい」という言葉を耳にしたことはありますか?
今回は「年賀状じまい」を考えている方のために、基本マナーの解説や文例をご紹介いたします。
- 年賀状じまいとは?いつやるべき?
- 年賀状じまいのメリット・デメリット
- 年賀状じまいの基本マナーと文例
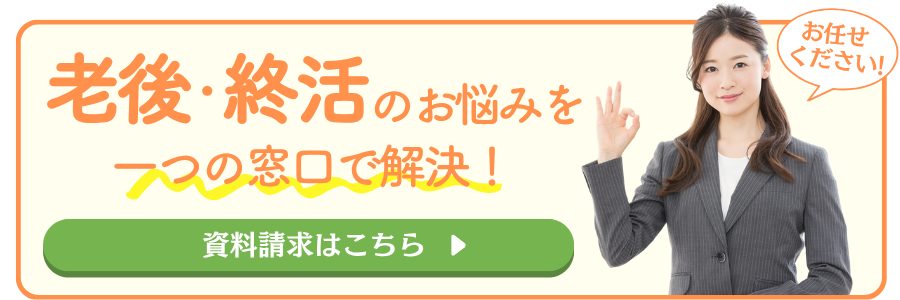
目次
そもそも「年賀状じまい」とは?

「年賀状じまい」とは、これまで年賀状のやり取りをしていた方々に対して、「来年以降は年賀状によるご挨拶を控えさせていただきます」という意思を伝え、年賀状の交換を終えることを指します。
これは単に年賀状をやめるだけでなく、感謝の気持ちを込めて、最後の挨拶状を送る一連の行為を意味します。
多くの方が「失礼にあたるのではないか」と心配されますが、これは人間関係を断ち切るためのものではありません。
むしろ、相手への配慮から、突然やり取りを止めて心配をかけることのないよう、丁寧にお知らせするための大切なステップです。
正しいマナーと心を込めた伝え方をすれば、相手との良好な関係を保ちながら、新しいお付き合いの形へと移行することができます。
多くの方が同じように悩んでいますが、大切なのは感謝の気持ちを伝えることです。
年賀状じまいが増えている背景とは
近年、年賀状じまいを選ぶ人が増えている背景には、いくつかの社会的な変化があります。
・SNSやメール、LINEといったデジタルコミュニケーションツールの普及
・「終活」の一環としての整理
・働き方やライフスタイルの多様化
こうした時代の流れが、年賀状じまいという選択を後押ししているのです。
「失礼」と思われないための大前提
年賀状じまいを考えている方が最も心配されるのが、「相手に失礼だと思われないか」という点でしょう。
失礼にならないための大前提は、「一方的に関係を終えるのではなく、これまでの感謝を伝え、今後の変わらぬお付き合いをお願いする」という姿勢を明確に示すことです。
突然連絡を絶つのではなく、きちんと挨拶をすることで、相手への敬意を表します。
大切なのは、年賀状という形での挨拶は終えるけれども、あなたとのご縁はこれからも大切にしたい、という気持ちを誠実に伝えること。
この配慮があれば、年賀状じまいは決して失礼な行為にはなりません。
年賀状じまいを伝える最適な時期はいつ?タイミング別メリット・デメリット

年賀状じまいを成功させる鍵は、相手に伝える「タイミング」にあります。
相手が年賀状の準備を始める前に知らせるのが、最も丁寧で親切な方法です。
もしタイミングを逃してしまうと、相手はあなたの分の年賀状を用意してしまい、かえって気を遣わせてしまう可能性があります。
逆に、あまりに早すぎても忘れられてしまうかもしれません。
主に2つのタイミングが考えられますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
ご自身の状況や相手との関係性を考慮して、最適な時期を選びましょう。
多くの方が悩むポイントですが、基本は「相手への配慮」を忘れないことです。
ここでは、代表的な2つのタイミングについて、その特徴を詳しく解説します。
① 最後の年賀状で伝える(12月上旬まで)
最も一般的で推奨されるのが、最後の年賀状で年賀状じまいの意思を伝える方法です。
この場合、相手が年賀状の準備を始める前の12月上旬までには投函するのが理想的です。
メリットは、新年の挨拶と同時に伝えられるため、話の流れが自然であること。
また、相手も年賀状を受け取る心づもりがあるため、メッセージに目を通してもらいやすい点です。
デメリットとしては、おめでたい新年の挨拶に少し寂しいお知らせを添えることになるため、文面に一層の配慮が必要になる点が挙げられます。
しかし、この方法が最も誤解なく、スムーズに気持ちを伝えられる選択肢と言えるでしょう。
② 寒中見舞いで伝える(1月8日〜立春まで)
もし年賀状の準備が間に合わなかった場合や、相手から年賀状を受け取った後に年賀状じまいを決めた場合は、寒中見舞いで伝える方法があります。
寒中見舞いは、松の内(一般的に1月7日)が明けた1月8日から立春(2月4日頃)までに出します。
メリットは、年賀状をいただいたことへのお礼を述べた上で、次年からの辞退を丁寧に伝えられる点です。
デメリットは、相手によっては寒中見舞いを出す習慣がなく、見落とされてしまう可能性があることです。
この方法を選ぶ際は、いただいた年賀状への感謝をまず伝えることが大切です。
【基本構成】年賀状じまいの書き方と3つのポイント

年賀状じまいの文面を考えるとき、「何から書けばいいのか分からない」と戸惑うかもしれません。
しかし、基本となる構成さえ押さえれば、誰でも失礼のない、丁寧な文章を作ることができます。
大切なのは、相手への感謝と敬意を忘れずに、自分の気持ちを誠実に伝えることです。
ポイントは以下の3つです。
・これまでの感謝を伝える言葉を添える
・年賀状じまいをする理由と辞退の意志表示をする
・今後の変わらぬお付き合いをお願いする言葉を入れる
この3つのポイントを順番に盛り込むだけで、心のこもった年賀状じまいのメッセージが完成します。
この構成は、相手が友人であっても、目上の方であっても応用できる基本の型です。まずはこの3つの要素を柱にして、ご自身の言葉を肉付けしていくと良いでしょう。
ポイント1:これまでの感謝を伝える言葉
文章の冒頭では、まず新年のご挨拶とともに、これまでの年賀状のやり取りや、長年のお付き合いに対する感謝の気持ちを伝えましょう。
「毎年素敵なお便りをいただきありがとうございました」
「長年にわたり温かいご厚情を賜り、心より感謝申し上げます」
といった言葉を添えることで、文章全体が柔らかく、温かい印象になります。
この感謝の一言があるだけで、年賀状じまいが決してネガティブな理由からではないことが伝わり、相手も安心して受け止めてくれるはずです。
最初に感謝を述べることは、最も重要なマナーの一つです。
ポイント2:年賀状じまいをする理由と辞退の意思表示
に、年賀状を辞退する旨とその理由を伝えます。
理由は、正直かつ簡潔に伝えるのがポイントです。
「誠に勝手ながら、本年をもちまして年始のご挨拶状は控えさせていただくことといたしました」
のように、辞退の意思を明確に記します。
理由の部分は
「年齢を重ね、筆をとるのが難しくなってまいりました」
「近年の生活様式の変化に伴い」
など、相手を不快にさせない個人的な事情を簡潔に述べると良いでしょう。
詳細に書きすぎる必要はなく、相手が納得できるような、当たり障りのない表現を選ぶのが賢明です。
ポイント3:今後の変わらぬお付き合いをお願いする言葉
最後に、年賀状という形は終わっても、今後も変わらず良好な関係を続けたいという気持ちを伝えて締めくくります。
「今後とも変わらぬお付き合いをどうぞよろしくお願い申し上げます」
「皆様の益々のご健勝を心よりお祈り申し上げます」
といった結びの言葉が一般的です。
もし、メールやSNSなど他の連絡手段がある場合は、
「今後はSNSにて近況をお伝えできれば幸いです」
のように具体的に触れるのも良いでしょう。
これにより、相手に「関係を断ちたいわけではない」という真意が伝わり、安心感を与えることができます。
【そのまま使える】相手別・理由別に見る年賀状じまいの文例集
ここでは、実際に使える年賀状じまいの文例を、送る相手や理由別にご紹介します。
基本構成は同じですが、相手との関係性によって言葉の選び方や丁寧さを調整することが大切です。
親しい友人には少し柔らかい表現を、上司や恩師といった目上の方には最大限の敬意を払った言葉を選びましょう。
また、年賀状じまいをする理由によっても、ニュアンスは変わってきます。
これらの文例はあくまで一例です。ぜひ、ご自身の状況に合わせてアレンジし、あなたらしい言葉で気持ちを伝えてみてください。そのまま使える便利な文例ですが、もし可能であれば、手書きで一言「お元気でいらっしゃいますか」などと添えるだけで、より一層心が伝わりますよ。
相手別の文例
親戚・友人など親しい間柄の場合
謹んで新春のお慶びを申し上げます
毎年楽しい年賀状をありがとう!
誠に勝手ながら、来年からどなた様にも年賀状でのご挨拶を控えさせていただくことにしました
今後はLINEやメールで気軽に連絡を取り合えたら嬉しいです
これからも変わらず仲良くしてくださいね
皆様にとって幸多き一年となりますようお祈り申し上げます
上司・恩師など目上の方の場合
謹んで新春のお慶びを申し上げます
旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました
さて、誠に勝手ではございますが、本年をもちまして年賀状による年始のご挨拶を控えさせていただきたく存じます
今後はメールにてご挨拶をさせていただければ幸いです
今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます
先生の益々のご健勝を心よりお祈り申し上げます
仕事関係・取引先の場合
謹んで新春のお慶びを申し上げます
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます
誠に勝手ながら、弊社では本年より皆様への年賀状によるご挨拶を控えさせていただくこととなりました
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます
理由別の文例
高齢を理由にする場合(終活の一環として)
んで新春のお慶びを申し上げます
長年にわたり温かい賀状を賜り、誠にありがとうございました
さて、私も〇〇歳を迎え、筆をとることが年々難しくなってまいりました
つきましては、誠に勝手ながら、本年をもちまして年賀状でのご挨拶は失礼させていただきたく存じます
今後は電話やメールなどでお話できれば幸いです
皆様の益々のご健勝を心よりお祈り申し上げます
時代の変化やライフスタイルの変化を理由にする場合
けましておめでとうございます
皆様にはお変わりなくお過ごしのこととお慶び申し上げます
さて、誠に勝手ながら、近年のデジタル化の流れを受け、本年をもちまして年賀状でのご挨拶を控えさせていただくことになりました
今後はSNS等で繋がらせていただければ幸いです
今後ともどうぞよろしくお願いいたします
年賀状じまいを伝える際の心理的配慮と関係維持のヒント
年賀状じまいは、単なる事務的な連絡ではありません。
長年続いてきた習慣を終えることに対して、相手が寂しさを感じてしまう可能性も考慮する必要があります。
だからこそ、文面や伝え方には細やかな心理的配慮が求められます。
大切なのは、形式的な挨拶を終えるだけで、あなたとの関係を終えるわけではない、というメッセージを明確に伝えることです。
少しの工夫で、年賀状じまいは「関係の終わり」ではなく、「新しい関係の始まり」のきっかけになり得ます。
丁寧な対応を心がけることで、あなたの誠実さが伝わり、今後の関係も円滑に続くでしょう。
相手を寂しくさせない一言を添える工夫
印刷された文面だけでは、どうしても冷たい印象を与えてしまうことがあります。
そこで効果的なのが、手書きで個人的な一言を添えることです。
「〇〇ちゃんの成長、いつも楽しみにしています」
「また近いうちにお会いできるのを楽しみにしています」
など、相手の顔を思い浮かべながら書いたメッセージは、温かみがあり、あなたの気持ちをまっすぐに伝えてくれます。
この一手間が、相手の寂しい気持ちを和らげ、「自分のことを大切に思ってくれている」という安心感につながるのです。
もし自分が「年賀状じまい」を受け取ったら?
逆に、あなたが年賀状じまいの挨拶を受け取る側になることもあるでしょう。
その場合、基本的には返信は不要です。
相手はやり取りを終えたいという意思表示をしているため、こちらから年賀状を送るとかえって気を遣わせてしまいます。
もし何か伝えたい場合は、寒中見舞いや手紙などで「お知らせいただきありがとうございます。こちらこそ、長年ありがとうございました」と感謝を伝えるのが丁寧な対応です。
まとめ:感謝を込めて、丁寧な「年賀状じまい」を

「年賀状じまい」は、決して人間関係を断ち切るための冷たい行為ではありません。
むしろ、これまでの感謝を伝え、相手への配慮を示しながら、お付き合いの形を新しくするための前向きなステップです。
多くの方が「失礼にならないか」と不安に感じますが、大切なのはその伝え方です。
最適なタイミングを選び、感謝の気持ち、辞退の意思、そして今後の変わらぬお付き合いを願う言葉という3つのポイントを押さえた丁寧な文面を用意すれば、きっとあなたの誠実な気持ちは相手に伝わるはずです。
この記事でご紹介した書き方や文例を参考に、あなた自身と相手との関係を大切にしながら、円満な年賀状じまいを進めてみてください。
心を込めた最後の挨拶が、これからのより良い関係へと繋がっていくことでしょう。
『終活』のご相談は終活協議会へ
一般社団法人終活協議会では、年賀状じまいのご相談はもちろん、終活に関する幅広いお悩みやご相談に対応しております。
お墓のこと、相続のこと、将来への漠然とした不安...など、どんな些細なことでも誠心誠意サポートいたします。
ぜひ一度ご相談ください!
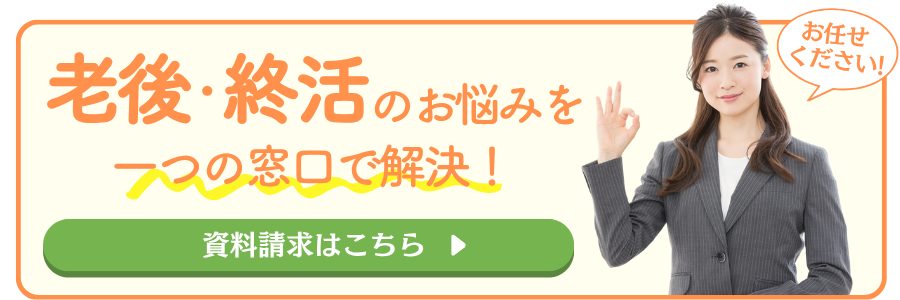
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする