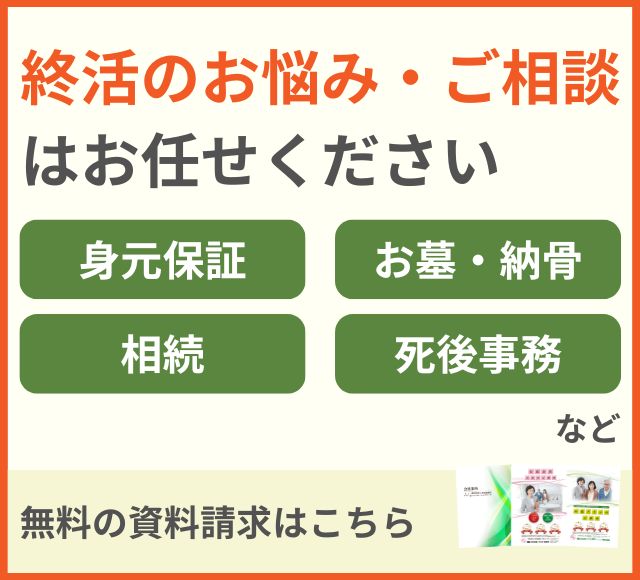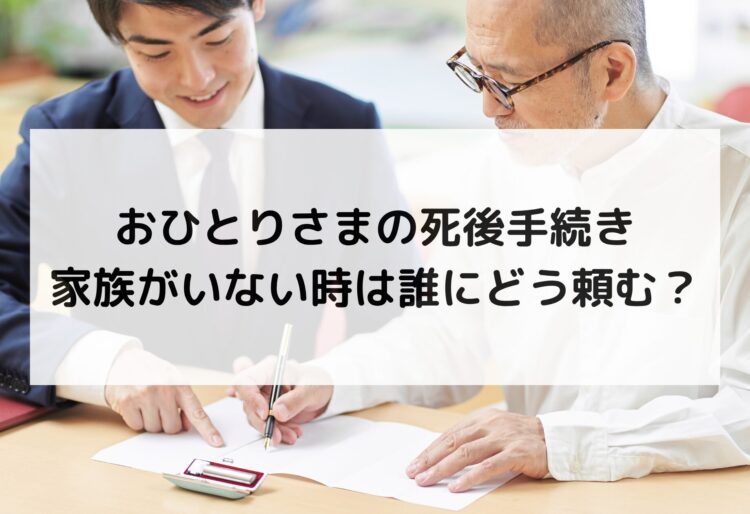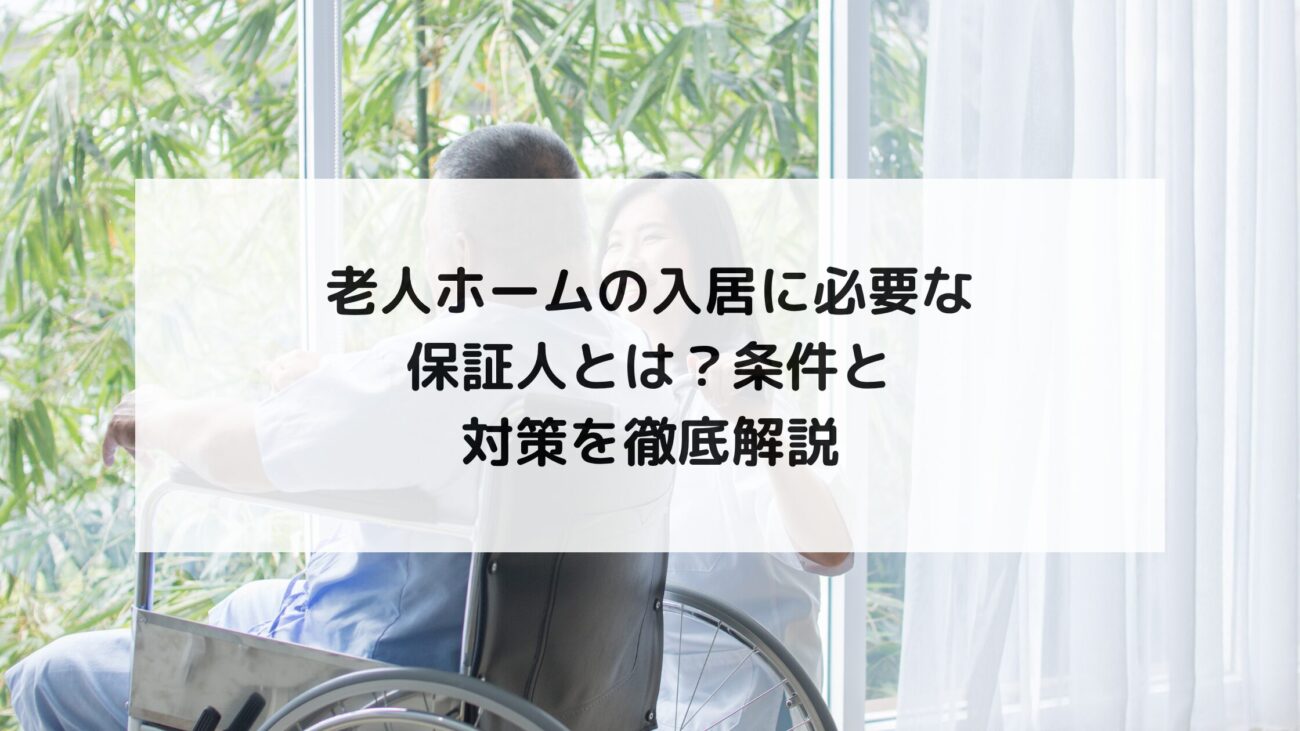
「老人ホームへの入居を考えているが、保証人がいない」「保証人を頼むのは気が引ける」と感じていませんか?
実は、多くの老人ホームでは入居時に保証人を求められます。
これは、入居者が契約上の義務を果たせない場合に備えて、金銭面や身元引受に関する責任を代わりに負うためです。
しかし、おひとりさまの方や、家族や親しい人に頼むのが難しい場合もありますよね。
この記事では、保証人の役割や必要性、保証人がいない場合の対処法、そして保証人を立てる際の注意点について、わかりやすく解説します。
- 老人ホームの入居の際に必要になる保証人とは
- 保証人がいない場合の対策
- 保証人が必要な方におすすめのサービス
目次
1. 老人ホームの入居時に求められる保証人とは

1.1 保証人の役割と必要性
老人ホームに入居する際、多くの施設で「保証人」を求められます。
これは入居者本人が契約上の義務を果たせない場合に備えて、金銭面や身元引受に関する責任を代わりに負う人を確保するためです。
たとえば、入居後に医療費や施設費用の支払いが滞った場合、施設としては保証人に請求することができます。
また、体調が急変して本人が判断できなくなった時、保証人が緊急対応の相談役としても機能します。
こんな場面を想像してみてください。
急な入院が必要になったとき、本人と連絡が取れなかったらどうしますか?
施設としては、頼れる保証人がいないと、対応に時間がかかってしまいますよね。
保証人は単なる形式的な存在ではなく、入居者の生活全体をサポートする重要な立場です。
保証人が必要とされる具体的な役割には、以下のようなものがあります。
- 入居契約書への署名・捺印
- 入居費用・月額費用などの支払い保証
- 緊急時の医療方針の相談
- 万が一の死亡時の遺体引き取りや荷物整理
- トラブル発生時の対応者としての窓口
よくある誤解と注意点
この保証人制度には、いくつかの誤解や失敗もあります。
代表的なものを3つ紹介します。
- 「連帯保証人」と「保証人」の違いを理解していない
連帯保証人は本人と同等の支払い義務が発生します。名前だけ貸すつもりで引き受けると大変です。 - 本人と保証人との関係性が曖昧
血縁者でなくても保証人になれますが、責任が重いため、信頼関係がないとトラブルになりがちです。 - 保証人を依頼しづらく、入居が遅れる
家族に頼めない場合、友人や知人にも頼みにくく、入居が先送りになることがあります。
これらを避けるには、入居前に保証人の役割や必要性をしっかり把握し、信頼できる人に依頼する準備が大事です。
1.2 保証人と身元引受人の違い
老人ホームへの入居時に混同されやすいのが、「保証人」と「身元引受人」の違いです。
名前は似ていますが、果たす役割はまったく異なります。
保証人と身元引受人、それぞれの役割
まず、それぞれの役割を整理してみましょう。
- 保証人:主に経済的な責任を負う存在。
入居者が費用を支払えなくなったとき、代わりに負担する義務があります。 - 身元引受人:主に生活・身上のサポートを行う存在。
入居中に問題が発生した場合の連絡先になり、必要に応じて意思決定を行うことも。
このように、保証人は「金銭」、身元引受人は「生活や身の回りのこと」と分けて考えるとわかりやすいです。
混乱しやすいポイントと注意点
実際の手続きの中では、この2つが明確に分かれていない施設もあります。
そのため、よくある混乱や失敗も多く見られます。
- 役割が曖昧なまま書類に署名してしまう
「連絡先程度だと思っていたら、支払い責任もあった」というトラブルが発生しやすいです。 - 同一人物に両方を依頼してしまう
身元引受人と保証人の両方を1人に任せると、負担が大きくなり、後々問題になりやすいです。 - どちらも家族に頼めず、入居手続きが止まる
近親者がいない高齢者では、どちらの役割も担ってくれる人が見つからないことも。
解決策と事前準備のコツ
これらのトラブルを防ぐには、以下のような準備が効果的です。
- 施設側に「保証人」と「身元引受人」の違いを明確に確認する
- 書類の内容を丁寧に読み込み、役割を理解したうえで署名する
- 家族に頼れない場合は、外部の保証サービスや成年後見制度を検討する
「保証人」と「身元引受人」の役割をしっかり理解しておくことで、安心して入居準備が進められます。
1.3 老人ホームの入居に保証人が必要な背景
老人ホームが保証人を求めるのには、いくつかの背景があります。
それは単に「支払い保証」のためだけではなく、入居者の生活を継続的に支えるための備えでもあります。
なぜ保証人が求められるのか?
施設側が保証人を必要とする主な理由は以下の通りです。
- 契約リスクの回避
入居者が費用を支払えなくなった場合の対応として、保証人がいれば未収金のリスクを軽減できます。 - 身元の確認とトラブル時の連絡先
認知症などで判断力が低下した場合、本人だけでは意思決定ができません。
保証人がいれば、緊急対応や退去時の調整がスムーズに行えます。 - 社会的孤立への対策
家族がいない高齢者も増えていますが、施設側としては対応に限界があります。
そのため、外部とのつながりを担保する保証人の存在が求められます。
よくある課題と現場の現状
高齢者の単身化が進むなかで、保証人の確保が難しくなっているのが現状です。
よくある課題を3つ紹介します。
- 独身・子なし・配偶者に先立たれた方が増えている
親戚関係も疎遠になっていることが多く、頼れる人がいないという声が目立ちます。 - 高齢の兄弟姉妹や友人は保証人になれない場合がある
健康上の問題や経済的な不安から、保証人を引き受けてもらえないケースがあります。 - 保証人の責任が重すぎると感じられる
万が一の時に大きな負担を求められる可能性があるため、依頼しにくくなってしまいます。
施設側の対応と選択肢の広がり
こうした背景を受けて、近年では以下のような対応を取る施設も増えています。
- 保証人を不要とする施設の登場
- 民間の身元保証サービスと提携するケース
- 成年後見制度を活用できる仕組みの整備
高齢化社会の進行にともなって、保証人制度にも柔軟な対応が求められる時代になっています。
2. 保証人がいない場合の対処法

2.1 成年後見制度の利用
保証人が見つからない場合の有力な対処法として、「成年後見制度」の利用があります。
これは判断能力が不十分な人に対し、法的に支援する人を家庭裁判所が選任する制度です。
成年後見制度とは?
成年後見制度には3つの類型があります。
- 後見:判断能力がほとんどない場合に利用
- 保佐:判断能力が著しく不十分な場合
- 補助:判断能力が不十分な場合
それぞれに応じて、家庭裁判所が「後見人」「保佐人」「補助人」を選任し、本人の財産管理や契約手続き、医療方針の決定などを支援します。
老人ホームの入居における活用方法
入居時に必要な契約行為を後見人が代行することで、本人に判断力がなくてもスムーズに手続きできます。
また、保証人が見つからない場合も、後見人が契約を支援する存在となり、施設側とのやりとりを代行できます。
成年後見制度を使うことで、保証人がいなくても入居できる道が開かれます。
よくある課題と注意点
制度自体は非常に有効ですが、いくつかの課題もあります。
- 申立に時間と費用がかかる
家庭裁判所への申立から選任まで、2~3か月ほどかかるのが一般的です。
手数料や医師の診断書代などで、3万~10万円程度の費用も見込まれます。 - 親族の同意が必要な場合がある
本人に近しい親族がいる場合、後見人の選任に同意が求められることもあります。 - 後見人に選ばれる人は自由に選べない
専門職(弁護士、司法書士など)が選任されるケースが多く、信頼関係の構築に時間がかかることがあります。
利用前に知っておきたいポイント
成年後見制度を使う前に、以下の点を確認しておくとスムーズです。
- 入居予定の施設が後見制度を利用可能かどうか
- 家庭裁判所への申立方法と必要書類の準備
- 費用と期間の見通しを立てておく
特に高齢者単身世帯では、この制度が唯一の選択肢となるケースもあります。
早めに市区町村の相談窓口や、終活サポート団体に相談するのがおすすめです。
2.2 身元保証サービスの活用
保証人がいない場合、民間の「身元保証サービス」を活用するという選択肢もあります。
これは高齢者の入居時や入院時などに、契約上必要な保証人や身元引受人の役割を代行してくれるサービスです。
身元保証サービスとは?
身元保証サービスは、次のような場面で支援を行います。
- 老人ホーム入居時の契約保証
- 緊急時の連絡対応・医療判断
- 入院手続き・退院時のサポート
- 死後事務(遺品整理や役所手続きなど)
利用者は契約時に一定の初期費用と、月額または年額の利用料を支払います。
専門の法人が保証人として契約に同席し、万一の場合の責任も引き受けてくれます。
安心して活用するためのポイント
身元保証サービスを選ぶ際は、以下のポイントを押さえましょう。
- 契約前に料金体系を明確に確認する
- 提供されるサービス内容を細かくチェックする
- 面談や相談が丁寧で、信頼できる対応をしてくれるかを見る
- 複数の業者を比較し、相見積もりを取る
信頼できる保証サービスを選べば、家族がいなくても安心して老人ホームに入居できます。
2.3 保証人不要の施設を探す方法
近年、高齢者の単身化や保証人確保の難しさを背景に、「保証人不要」の老人ホームも増えてきました。
保証人がいなくても入居できる施設を選べば、精神的にも手続き的にもグッと楽になります。
保証人不要の施設とは?
保証人不要の施設とは、入居時の契約や支払いについて、保証人を立てなくても受け入れてくれる施設のことです。
このような施設は、以下のような対策を取っている場合が多いです。
- 初期費用や退去時清算に備えて、敷金を多めに設定
- 身元保証サービスや後見制度の利用を前提にしている
- トラブル時の対応を法人契約などでカバーできる仕組みを持つ
探すときに使える具体的な方法
保証人不要の施設を見つけるには、次のような方法が効果的です。
- 高齢者向け住宅紹介センターや終活サポート団体に相談する
- 地域包括支援センターに条件を伝えて紹介してもらう
- インターネット検索で「保証人不要 老人ホーム+地域名」で探す
- 施設に直接問い合わせて、保証人不要の可否を確認する
また、「終活協議会」のようなサポート団体を通じて探すと、条件に合った施設を効率よく見つけやすくなります。
3. 保証人を立てる際の注意点

3.1 保証人の条件と選び方
老人ホームに入居する際、保証人を立てる必要がある場合、誰に依頼するかは非常に重要なポイントです。
単に「家族だから」「昔からの知人だから」という理由だけで選ぶと、後々トラブルになることもあります。
保証人に求められる一般的な条件
施設によって異なりますが、多くの老人ホームで保証人に求める条件は次のようなものです。
- 成年(20歳以上)であること
- 入居者と一定の関係性(親族・知人など)があること
- 日本国内に住んでおり、連絡が取りやすいこと
- 継続的な支払い能力があること(収入・資産が安定している)
とくに支払い能力の確認は重要で、所得証明や印鑑証明の提出を求められることもあります。
安心して依頼できる人の選び方
以下のような視点で候補者を選ぶと、トラブルを避けやすくなります。
- 自分の生活状況や希望を理解してくれている人
- 金銭的な信頼性があり、収入証明などの提出にも協力してくれる人
- 長期間にわたって連絡が取りやすい人
- 契約内容や責任範囲をしっかり理解してくれる人
「誰でもいい」ではなく、「責任を共有できる信頼関係」があることが一番の条件です。
3.2 保証人とのトラブル事例と対策
保証人は信頼関係のもとに成り立つ制度ですが、現実にはトラブルも少なくありません。
入居後に問題が発生すると、本人・保証人・施設の三者にとって大きなストレスになります。
実際に起こりやすいトラブル例
保証人に関する代表的なトラブルは以下の通りです。
- 費用の支払いを拒否される
入居者が滞納した際、保証人が「そんな責任があるとは聞いていない」と支払いを拒否するケースがあります。 - 保証人と連絡が取れなくなる
住所や電話番号が変わっていても、施設側に連絡がなければ対応に支障が出ます。 - 医療判断や身元引受に非協力的
緊急時に保証人が対応を拒否すると、入院や搬送がスムーズに進まない場合があります。
これらのトラブルは、入居前の確認不足や情報の行き違いから生まれることが多いです。
トラブルを防ぐための具体的な対策
事前にしっかり対策を取っておくことで、こうした問題はかなり防げます。
- 契約内容や保証人の責任範囲を明文化して共有する
口約束ではなく、具体的な資料を渡しながら説明することが大事です。 - 入居前に三者面談を行う
入居者・保証人・施設の三者で顔を合わせておくと、連携が取りやすくなります。 - 緊急連絡先や対応希望についても話し合っておく
万が一の医療措置や意思決定について、保証人の考えを事前に確認しておきましょう。
トラブルが起きてしまったときの対応
それでもトラブルが起きた場合は、次のような対応が求められます。
- 施設と保証人双方に事情を説明し、冷静に対応する
- 必要に応じて第三者(弁護士や福祉専門職)に相談する
- 新たな保証人を立てる、または制度・サービスの利用を検討する
保証人との信頼関係は、入居後の安心な生活を支える土台になります。
3.3 保証人に依頼する際のポイント
保証人を引き受けてもらうためには、単に「お願い!」と頼むだけではなく、誠実で具体的な説明が必要です。
依頼された側も不安や責任を感じるため、丁寧なコミュニケーションが欠かせません。
スムーズに了承を得るための準備
まずは以下の3点をきちんと整理してから話を持ちかけるようにしましょう。
- なぜ老人ホームに入居したいのか、その背景
- 保証人にどのような役割を求められるのか
- 万一トラブルが起きた際の対応方針
これらを説明することで、保証人としての責任や範囲を正しく理解してもらいやすくなります。
断られやすいパターンと回避法
保証人を頼むときにありがちな失敗例を3つご紹介します。
- 急に話を切り出してしまう
時間を取らずに「サインだけしてほしい」と頼むと、不信感を与えてしまいます。 - リスクや責任を曖昧に説明する
具体的な責任範囲を伝えずに依頼すると、あとからトラブルになることも。 - 保証人の経済状況を無視してお願いする
金銭的な不安を抱える人に依頼してしまうと、断られるだけでなく関係も悪化しかねません。
上手な伝え方とフォローのコツ
保証人の依頼をスムーズに進めるためには、以下のような工夫が有効です。
- 「責任範囲はここまで」と事前に書面で明示する
- 入居施設からの資料を同封して信頼性を高める
- 相手の不安や疑問には丁寧に答える姿勢を持つ
- 必要に応じて、第三者(福祉士やケアマネジャー)に同席してもらう
「お願いする側の誠実さ」が伝わるかどうかで、了承の可能性は大きく変わります。
4. 保証人に関するよくある質問
4.1 保証人は家族以外でも可能か
老人ホームの保証人は、家族以外でも認められる場合があります。
ただし、施設によって基準は異なるため、事前確認が必須です。
家族以外でも認められる条件
- 入居者と継続的な信頼関係がある
- 経済的に安定している
- 緊急連絡や意思決定に対応できる
- 身元の確認書類を提出できる
注意すべきポイント
- 責任範囲(金銭・身元)を明確にして説明する
- 施設によっては「家族限定」の場合もある
- 連絡が取れないと、契約が無効になることも
家族以外を保証人にする際は、信頼性と継続性がカギです。
4.2 保証人の人数や年齢制限について
保証人の条件には、人数や年齢に関する制限があることがあります。
これらは施設ごとに基準が異なるため、事前の確認が大切です。
人数に関するポイント
- 基本は「1名」で足りる施設が多い
- 一部の施設では「2名以上」求められることも
- 緊急連絡先とは別に保証人を立てるケースもある
年齢に関する制限
- 原則「20歳以上」であること
- 高齢すぎる(例:80代以上)と断られることも
- 判断能力や健康状態も審査の対象になる場合あり
注意点
- 夫婦で交互に保証人になるのは不可のことが多い
- 年齢制限が曖昧な場合は書面で確認しておくと安心
保証人の条件は「誰でもいい」というわけではないので、基準をよく確認しておきましょう。
4.3 保証人の責任範囲と解除方法
保証人になると、思っている以上に責任が重くなる場合があります。
そのため、役割と解除条件を事前に把握しておくことが重要です。
主な責任範囲
- 入居金・月額費用などの未納時の支払い義務
- 入院・退去時の手続き代行
- 死亡時の遺体引き取りや遺品整理の対応
よくある誤解
- 「署名だけで済む」と思って引き受ける
- 支払い責任の範囲が曖昧なまま契約する
- 家族間で責任のなすり合いになることも
解除の方法
- 施設に申し出て合意を得る
- 後任保証人を立てることで交代できる場合もある
- 契約書に「解除の条件」が明記されているかを確認
責任を理解しないまま引き受けると、後からトラブルになる可能性が高くなります。
5. 保証人問題を解決するための準備
5.1 早めの情報収集と相談の重要性
保証人がいない、頼みにくいという場合も、早い段階で情報収集と相談を始めることが解決のカギです。
情報収集のメリット
- 自分に合った施設や制度を見つけやすくなる
- 民間の保証サービスや後見制度の活用が検討できる
- 契約内容の理解不足によるトラブルを防げる
相談できる主な窓口
- 地域包括支援センター
- 自治体の高齢者福祉窓口
- 終活支援団体や介護専門の相談員
よくある遅れの原因
- 「まだ元気だから大丈夫」と先送りする
- 施設選びと保証人探しを同時に進めて混乱する
- 家族と意思共有せずに一人で悩む
「まだ先の話」と思わず、元気なうちから準備を進めておくことが安心への第一歩です。
5.2 契約前に確認すべきポイント
老人ホームの契約では、保証人に関する内容をしっかり確認しておくことが大切です。
見落とすと後々トラブルの原因になることもあります。
チェックすべき項目
- 保証人の責任範囲(費用、医療、死亡時対応など)
- 必要な保証人の人数と条件
- 保証人がいない場合の代替方法(サービスや制度)
よくある見落とし
- 契約書の細かい条項を読まずに署名してしまう
- 保証人の解除方法が明記されていない
- 緊急時対応の具体的な手順を確認していない
事前に準備したいこと
- 不明点は施設側に遠慮なく質問する
- できれば家族や第三者と一緒に説明を受ける
- 必要に応じて契約書を持ち帰り、専門家に確認してもらう
契約内容の理解不足は後悔のもと。納得できるまで確認することが重要です。
5.3 終活協議会のサポート内容
保証人探しに不安を感じている方には、終活協議会のサポートを活用するのがおすすめです。
入居支援や保証に関する幅広いサポートを提供しています。
提供されている主な支援内容
- 身元保証・緊急連絡・死後事務などの包括支援
- 老人ホーム探しや入居手続きの相談
- 成年後見制度や介護・医療の情報提供
終活協議会を活用するメリット
- 家族がいなくても入居の選択肢が広がる
- 契約や制度の不明点を専門家がサポート
- トラブルや孤立を防ぐ仕組みが整っている
安心して利用するために
- サービス内容と料金体系を事前に確認
- 契約前に不安点を相談し、納得してから利用
- 継続的なサポート体制の有無もチェック
終活協議会のような団体に相談すれば、一人でも安心して入居準備が進められます。
6. まとめ
ここまで紹介してきた内容をもとに、老人ホーム入居時の保証人に関する重要ポイントを整理しましょう。
保証人制度の基本
- 入居契約時に金銭面・緊急対応などの責任を負う存在
- 保証人と身元引受人は役割が異なるため要注意
- 家族以外でも条件を満たせば依頼可能
保証人がいない場合の対処法
- 成年後見制度や身元保証サービスの活用
- 保証人不要の施設を視野に入れる
- 終活支援団体に早めに相談することが大事
安心して入居するために
- 契約前に責任範囲や条件を丁寧に確認
- 保証人には誠意をもって丁寧に依頼する
- 不安があるときは第三者の力を借りる
「早めの準備と正しい情報」が、安心の入居を叶えるポイントです。
老人ホームの入居の不安は終活協議会にお任せください
保証人の確保や施設選び、契約内容の確認まで専門スタッフが丁寧にサポートします。
安心の終活を始めるなら、終活協議会の公式サイトをご覧ください。
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする