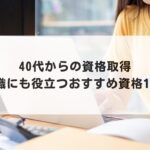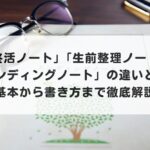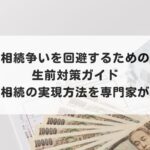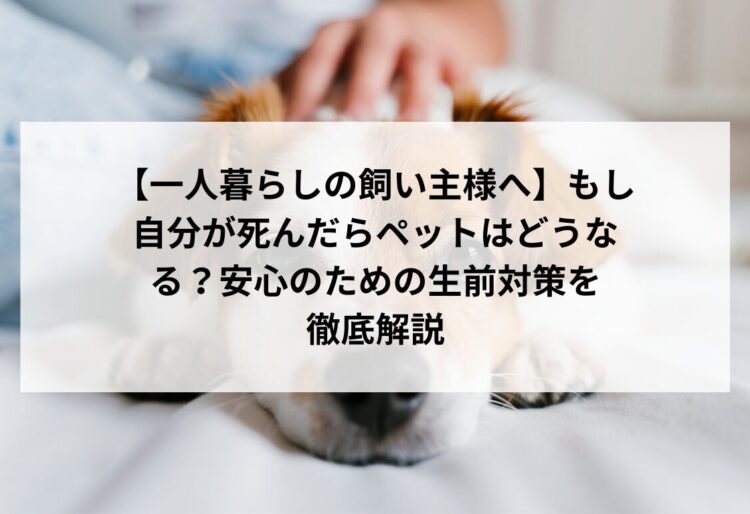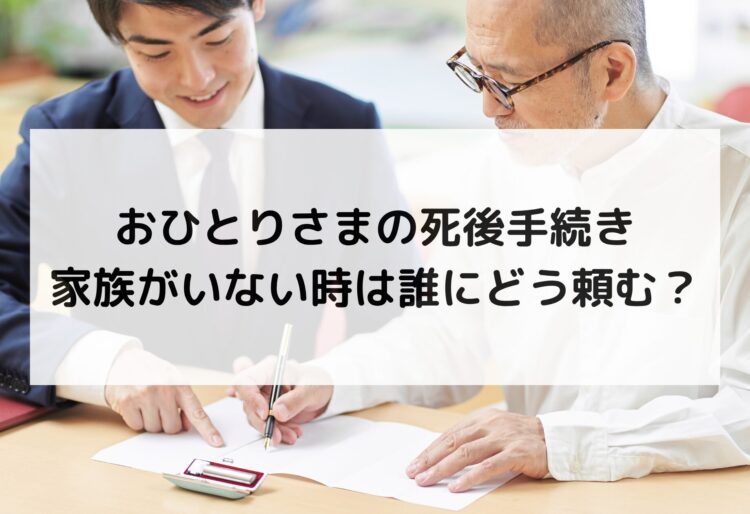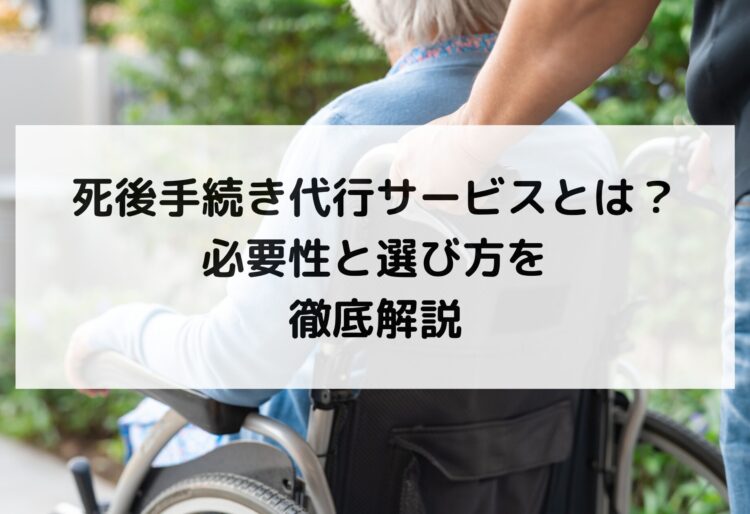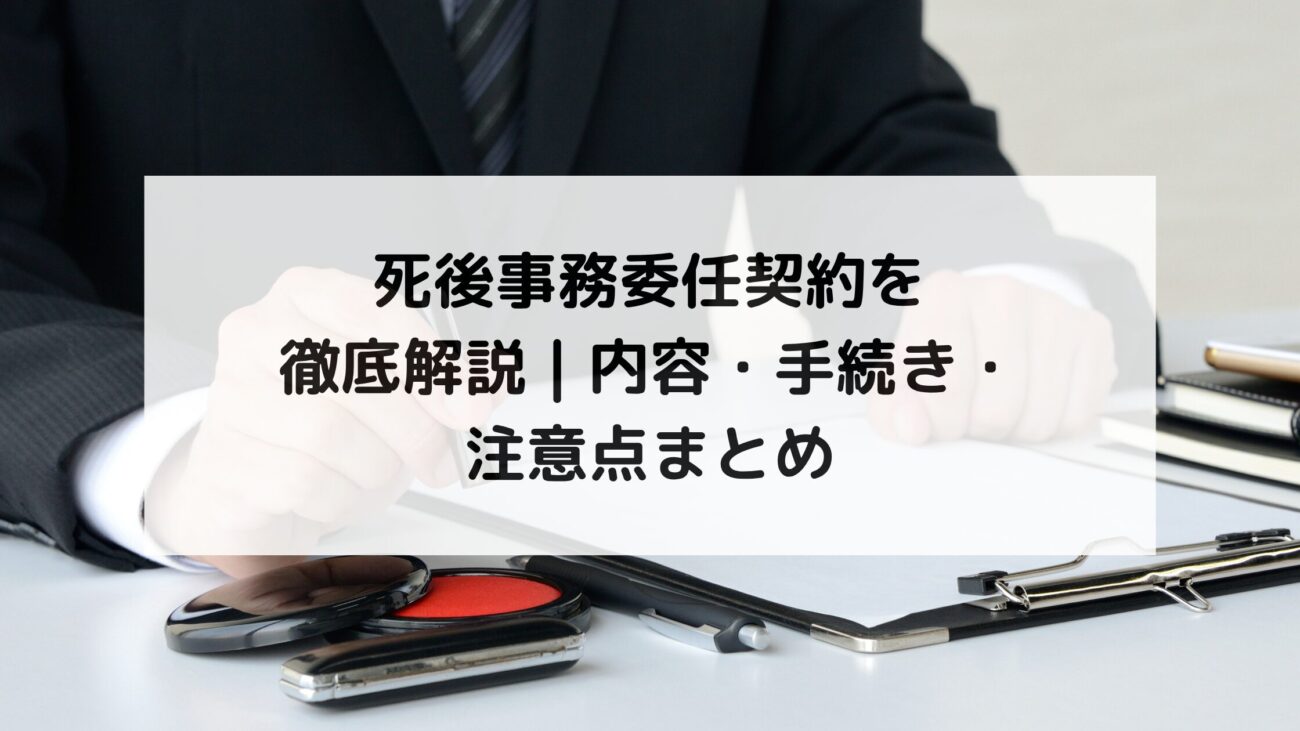
人が亡くなった後には、役所への届出や遺品整理、公共料金の解約など、さまざまな手続きが必要になります。
しかし、身近に頼れる家族がいない場合や、遺された家族に負担をかけたくないと考える場合、「誰がその手続きを行うのか」という不安が生まれます。
そこで注目されているのが「死後事務委任契約」です。
この記事では、死後事務委任契約の内容や手続きの流れ、利用する際の注意点までを徹底解説します。
- 死後事務委任契約の基本内容と委任できる手続き
- 死後事務委任契約と遺言・成年後見制度との違い
- 契約を結ぶ際の注意点
目次
1. 死後事務委任契約とは?基本内容をわかりやすく解説
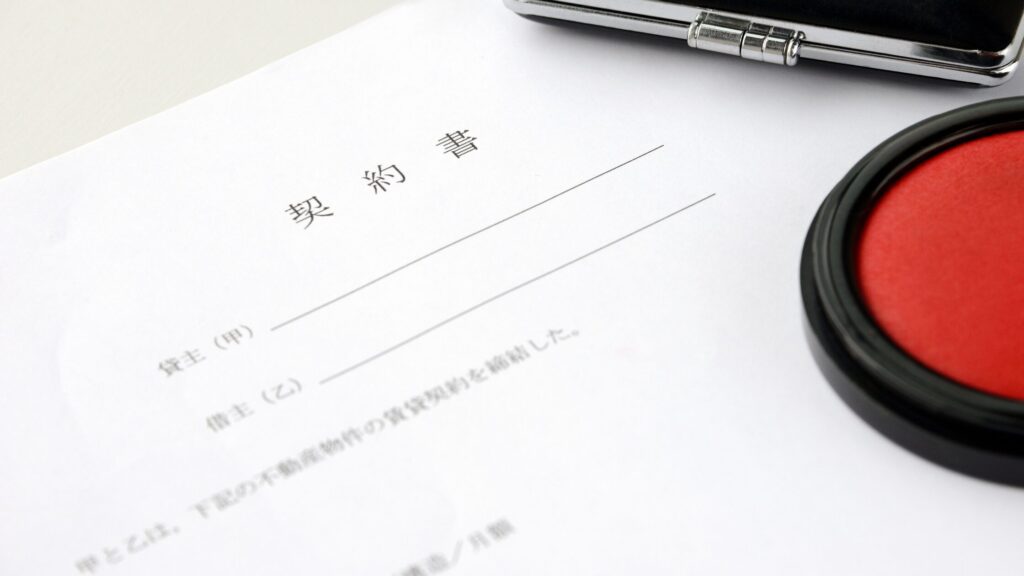
1.1 死後事務委任契約の概要とは
「死後事務委任契約」という言葉、聞いたことはあっても詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。
この契約は、自分が亡くなったあとに必要となる事務手続き全般を、信頼できる第三者に任せるための生前契約のひとつです。具体的には、葬儀の手配や家の片付け、公共料金の解約、役所への届け出などを本人に代わって行ってもらうための法的な取り決めを指します。
自分の死後に関する“現実的な手続き”を、事前に整えておくことで、家族や友人に負担をかけずに済むのが最大のメリットです。
死後事務委任契約は、口頭での約束では効力が弱いため、きちんと契約書にまとめておく必要があります。とくに「誰に、どんな事務を委任するか」「費用はどうするか」といったことを明確にし、必要に応じて公正証書で作成することが望ましいです。
死後の手続きを家族に頼める環境がある場合でも、以下のような理由から契約を結ぶ人が増えています。
- 身寄りがいない、もしくは家族に迷惑をかけたくない
- 終活をしっかり準備しておきたい
- 友人や支援者に依頼したいが法的に明確にしておきたい
たとえば一人暮らしの方や、高齢者施設で暮らしている方にとって、死後の準備を契約で明文化しておくことは、精神的な安心感にもつながります。
こうした契約は、弁護士や行政書士などの専門家に依頼することもありますが、最近では終活支援を専門とする団体や民間サービスでも対応が増えてきています。
1.2 委任できる具体的な事務内容
死後事務委任契約で委任できる内容は、亡くなったあとに必要になる各種の手続きや事務作業です。遺言とは異なり、相続や財産分与ではなく、「実務的な処理」を対象にしています。
たとえば、以下のような事務が含まれます。
主な委任内容の一例
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 火葬場の予約や葬儀社の手配などを含みます。
- 火葬場の予約や葬儀社の手配などを含みます。
- 役所への死亡届の提出
- 死亡届の提出や火葬許可証の取得といった公的手続きです。
- 死亡届の提出や火葬許可証の取得といった公的手続きです。
- 住居の明け渡し・遺品整理
- 賃貸住宅の解約や遺品の整理、不要品の処分など。
- 賃貸住宅の解約や遺品の整理、不要品の処分など。
- 公共料金や契約サービスの解約
- 電気・水道・ガス・インターネット・携帯電話などの解約。
- 電気・水道・ガス・インターネット・携帯電話などの解約。
- 医療費や未払い金の清算
- 最後にかかった医療費や、借りていたお金の返済など。
- 最後にかかった医療費や、借りていたお金の返済など。
- WEBサービスやSNS、サブスクの解約・削除
- FacebookやX(旧Twitter)などのアカウント削除も含まれます。
- FacebookやX(旧Twitter)などのアカウント削除も含まれます。
- ペットの引き取りや世話の依頼
- 飼っている動物の今後の対応についても記載可能です。
- 飼っている動物の今後の対応についても記載可能です。
このように、「誰かが確実にやらなければいけないこと」を事前に任せておくことで、死後の混乱を防ぐことができます。
よくある失敗例と注意点
ただし、内容を曖昧にしてしまうと、トラブルや手続きの遅れにつながることも。ありがちな失敗には次のようなものがあります。
- 項目の漏れがある
- 様々なWEBサービスやSNSアカウント、サブスクの削除など、現代ならではの項目を忘れがちです。
- 様々なWEBサービスやSNSアカウント、サブスクの削除など、現代ならではの項目を忘れがちです。
- 実際に委任できない内容を記載してしまう
- 財産分与や相続人の指定などは死後事務委任契約では行えず、遺言書でしか有効にできません。
- 財産分与や相続人の指定などは死後事務委任契約では行えず、遺言書でしか有効にできません。
- 実行者が実務に対応できない
- 遠方に住んでいたり、多忙な人に依頼すると実行が難しくなることも。
- 遠方に住んでいたり、多忙な人に依頼すると実行が難しくなることも。
こうした失敗を防ぐためには、次のような対策が有効です。
- 委任内容をチェックリスト化し、ひとつずつ確認する
- 専門家に一度内容を見てもらう
- 委任者と受任者で事前にしっかり話し合っておく
とくに、医療やインターネット関係の事務は忘れやすいため、漏れなく記載するのが大事です。
1.3 遺言や成年後見制度との違い
死後事務委任契約とよく混同されやすいのが、「遺言」と「成年後見制度」です。それぞれの目的や効力が異なるため、しっかり区別しておくことが大切です。
まず前提として、死後事務委任契約は“死後の実務手続き”に特化した契約です。
以下の表でそれぞれの違いを整理してみましょう。
| 項目 | 死後事務委任契約 | 遺言 | 成年後見制度 |
| 主な目的 | 死後の事務処理を委任 | 財産の分配や相続の意思表示 | 判断能力が低下した人の保護 |
| 効力が発生するタイミング | 死亡後 | 死亡後 | 判断能力が不十分になったとき |
| 委任できる内容 | 葬儀、契約解約、遺品整理など | 財産分与、相続人の指定など | 財産管理、介護サービス契約など |
| 形式 | 契約書(任意)・公正証書推奨 | 自筆、公正証書など形式が厳格 | 家庭裁判所の審判が必要 |
このように、それぞれの制度には役割の違いがあります。
よくある誤解と失敗パターン
実際に多い間違いとして、次のようなケースがあります。
- 死後の財産処理を死後事務委任契約で済ませようとする
- 財産の配分は遺言でしか指定できません。
- 財産の配分は遺言でしか指定できません。
- 後見人に死後の事務もお願いできると思っている
- 成年後見制度の効力は本人が生きている間だけです。
- 成年後見制度の効力は本人が生きている間だけです。
- 複数の制度を併用する必要性を知らない
- 終活には「遺言+死後事務委任契約+後見制度」の連携が重要な場合もあります。
- 終活には「遺言+死後事務委任契約+後見制度」の連携が重要な場合もあります。
たとえば、認知症などで判断力が落ちたときは後見制度、亡くなったあとの財産処理は遺言、葬儀や住居の処分などの事務は死後事務委任契約という形で、それぞれの制度をうまく使い分けることが理想的です。
「どれかひとつで全部対応できる」という考えは危険なので、目的に応じて使い分けましょう。
2. 死後事務委任契約が必要な理由と対象者
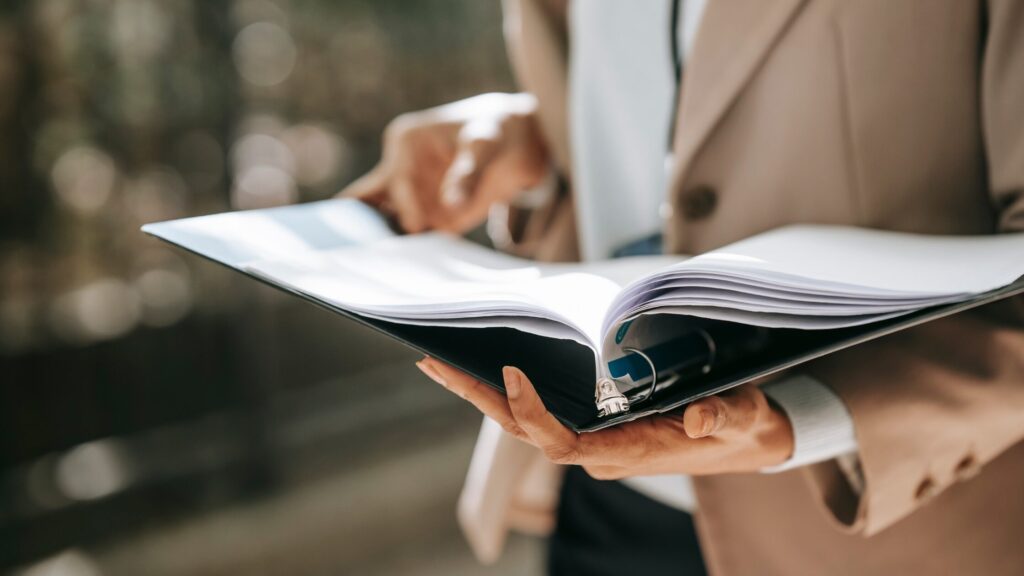
2.1 おすすめな人と理由
死後事務委任契約は、誰にとっても有効な仕組みですが、とくにおすすめなのは「死後の対応を誰かに頼みにくい状況」の人たちです。現代の多様なライフスタイルにおいて、こうした契約のニーズは年々高まっています。
以下のような状況にあてはまる方は、特に死後事務委任契約を検討しておきたいところです。
こんな方におすすめ
- 家族や親族がいない、または関係が疎遠な方
- 子どもに負担をかけたくない高齢者
- 一人暮らしの高齢者や中高年
- 同性パートナーと暮らしている方
- 親しい友人に死後の事務を任せたい方
誰かがやらなければならない“死後の雑務”を自分の意志で整理しておけることが、この契約の大きな価値です。
一般的なイメージ
たとえば、退職後に一人で静かに暮らしている方の場合、万が一のときに「誰に連絡してほしいか」「部屋の片付けはどうしてほしいか」などが曖昧だと、行政や関係者も対応に困ってしまいます。
実際、家族がいないことで死後の処理に時間がかかり、葬儀が予定通りに行えなかったり、遺品が長期間残されたままになるケースも珍しくありません。
契約をしておくことで得られるメリット
- 生前に自分の意思を明確にできる
- 周囲に迷惑をかけずに済む
- 残された人の精神的・物理的な負担を軽減できる
- 自分らしい最期を実現しやすくなる
たとえば、葬儀の形式や納骨方法、デジタル遺品の扱いまで希望がある場合、契約書に明記しておけば、確実に実行してもらえます。
「自分がいなくなった後のこと」こそ、今から準備することで安心が手に入ります。
2.2 ありがちなトラブルと回避策
死後事務委任契約は非常に有効な制度ですが、内容や運用方法を誤るとトラブルや実行不能のリスクが生じます。ここでは、よくある失敗例とその対策を詳しく見ていきます。
よくあるトラブル事例と原因
- 契約内容が曖昧で解釈にズレが生じる
- 依頼事項が抽象的すぎると、受任者がどう対応すべきか迷ってしまいます。
- 例:「適切に対応する」などの曖昧な表現は避けるべきです。
- 依頼事項が抽象的すぎると、受任者がどう対応すべきか迷ってしまいます。
- 受任者が契約内容を理解していない
- 形式的に契約だけしても、実際の内容や手続きに慣れていない人だと対応が難航します。
- とくに突然の連絡で驚いてしまい、動けないことも。
- 形式的に契約だけしても、実際の内容や手続きに慣れていない人だと対応が難航します。
- 関係者間で認識がずれてトラブルに発展
- 親族などに説明していなかった場合、「なぜこの人が手続きをしているのか」と疑問視されることもあります。
- 親族などに説明していなかった場合、「なぜこの人が手続きをしているのか」と疑問視されることもあります。
これらの失敗を防ぐには、契約書の内容を明確にし、事前に関係者としっかり意思疎通することがカギです。
トラブル回避のための対策
- 項目ごとに具体的に記載する
- 「〇〇の葬儀社に依頼」「携帯は〇〇名義で契約」など、できる限り明文化しましょう。
- 「〇〇の葬儀社に依頼」「携帯は〇〇名義で契約」など、できる限り明文化しましょう。
- 受任者と複数回にわたって打ち合わせをする
- 一度ではなく、複数回確認することで抜け漏れを防げます。
- 一度ではなく、複数回確認することで抜け漏れを防げます。
- 家族や近しい人にも契約の存在を伝えておく
- 形式的な書類だけでなく、実際の「共有」がスムーズな対応につながります。
- 形式的な書類だけでなく、実際の「共有」がスムーズな対応につながります。
- 信頼できる専門家に内容をチェックしてもらう
- 行政書士などに確認してもらうことで、法的にも安心できます。
- 行政書士などに確認してもらうことで、法的にも安心できます。
たとえば、最近では「死後事務の手続きに慣れた第三者」を受任者として選ぶ人も増えており、こうした専門知識を持つ支援先の活用も有効です。
「書いただけで安心」と思わず、実行できるかどうかまで見据えた準備が必要です。
2.3 死後事務委任契約によって得られる安心感とは
死後事務委任契約を結ぶことで得られる最大のメリットは、“自分がいなくなったあとの不安がなくなること”です。誰に何を任せるかを明確にしておくことで、精神的なゆとりが生まれ、より安心して日々を過ごせるようになります。
契約で得られる3つの安心
- 遺された人への配慮ができる
- 手続きや連絡を任せる人が決まっていれば、家族や知人が戸惑うことが減ります。
- たとえば「死亡届を誰が出すか」「病院からどこへ連絡が行くか」などを整理できます。
- 手続きや連絡を任せる人が決まっていれば、家族や知人が戸惑うことが減ります。
- “自分らしい最期”を叶えられる
- 葬儀の規模や方法、納骨先などに希望がある場合、それを文書にしておけば実行してもらいやすくなります。
- たとえば「家族葬にしてほしい」「お別れ会を開いてほしい」といった意向も書けます。
- 葬儀の規模や方法、納骨先などに希望がある場合、それを文書にしておけば実行してもらいやすくなります。
- 生きている今に集中できる
- 不安を先送りせず、「あとは任せた」と思えることで、日常生活にも前向きな気持ちが生まれます。
- 不安を先送りせず、「あとは任せた」と思えることで、日常生活にも前向きな気持ちが生まれます。
契約を交わすことは、“不安”を“準備”に変える行動です。
一般的な生活の中で感じる安心感
たとえば、一人暮らしの高齢者が「もし自分に何かあったらどうしよう」と感じているとします。死後事務委任契約を結んでおけば、万が一のときにも誰かが必要な手続きを進めてくれるという信頼が生まれ、不安が和らぎます。
また、家族との距離感がある方でも、契約によって「迷惑をかけないようにしよう」という想いを形にできるため、気持ちの整理にもつながります。
“安心して老後を過ごすための保険”として、この契約は非常に効果的です。
3. 死後事務委任契約の手続きの流れ

3.1 契約に必要な準備と書類
死後事務委任契約を結ぶには、いくつかの事前準備と必要書類の用意が欠かせません。ただ書面を交わすだけではなく、事前の情報整理や委任内容の明確化が大切です。
契約前に準備しておきたいこと
- 委任したい内容をリストアップする
- 例:葬儀の形式、役所手続き、デジタル遺品の整理、ペットの世話など。
- 例:葬儀の形式、役所手続き、デジタル遺品の整理、ペットの世話など。
- 信頼できる受任者を決める
- 家族・友人・支援団体・専門家などから選びます。
- 家族・友人・支援団体・専門家などから選びます。
- 費用の支払い方法を決めておく
- 手続きにかかる費用や報酬の出所をどうするかを明記する必要があります。
- 手続きにかかる費用や報酬の出所をどうするかを明記する必要があります。
この3点を明確にしておくだけでも、契約時のトラブルや手間を大きく減らせます。
必要となる主な書類一覧
契約書を作成するにあたり、以下の書類を準備することが一般的です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任契約書(内容を記載した書面)
- 実印および印鑑証明書(必要な場合あり)
- 支払いに関する資料(預金口座、信託契約など)
また、公正証書として契約書を作成する場合は、公証人との事前打ち合わせや予約も必要になります。その際は、原案のチェックや証人の手配も行っておくとスムーズです。
よくある準備不足とその対策
以下のような失敗も起こりやすいので注意しましょう。
- 内容の希望が曖昧なまま契約を進めてしまう
- 「細かく決めるのは後で」と先延ばしにせず、具体的に書き出しましょう。
- 「細かく決めるのは後で」と先延ばしにせず、具体的に書き出しましょう。
- 費用について委任者と受任者で認識がズレている
- 「実費はどこから出すのか」「報酬はあるのか」などは明確に話し合っておくべきです。
- 「実費はどこから出すのか」「報酬はあるのか」などは明確に話し合っておくべきです。
- 書類の不備で手続きが滞る
- 印鑑証明や証人の準備漏れなど、形式面も見落としがちです。
- 印鑑証明や証人の準備漏れなど、形式面も見落としがちです。
とくに、公正証書にする場合は正式な手続きが必要なため、書類の抜け漏れは手続き全体の遅れにつながります。
スムーズな契約には「事前準備」がすべてのカギになります。
3.2 公正証書化するメリットと注意点
死後事務委任契約は、書面で自由に作成することもできますが、より確実な執行を望むなら「公正証書」での作成がおすすめです。公正証書とは、公証役場で公証人が関与して作成する法的効力の高い文書のことです。
公正証書にするメリット
- 証拠力が高く、法的に強い効力を持つ
- 契約の存在や内容について争いが起きても、裁判で有効な証拠になります。
- 契約の存在や内容について争いが起きても、裁判で有効な証拠になります。
- 書類の原本が公証役場に保管される
- 紛失のリスクがなく、信頼性が高まります。
- 紛失のリスクがなく、信頼性が高まります。
- 執行がスムーズに進められる
- 金融機関や役所との手続きでも信頼性のある文書として認められやすくなります。
- 金融機関や役所との手続きでも信頼性のある文書として認められやすくなります。
「確実に実行してもらいたい」という人ほど、公正証書での作成が安心です。
公正証書化の手続きと費用
- 費用目安:2〜5万円程度(契約内容によって変動)
- 必要な書類:
- 委任契約の原案
- 委任者・受任者の本人確認書類
- 実印と印鑑証明書
- 委任契約の原案
- 所要時間:準備から作成までおよそ1〜2週間
- 証人2名が必要(公証人役場で手配も可能)
注意すべきポイント
- 内容に不備があると、公正証書でも執行が難しくなる
- 内容は具体的かつ明確に記述しないと、現場で混乱を招きます。
- 内容は具体的かつ明確に記述しないと、現場で混乱を招きます。
- 公証人との打ち合わせが必須
- 曖昧なまま提出すると、修正を求められ時間がかかります。
- 曖昧なまま提出すると、修正を求められ時間がかかります。
- 証人の準備が意外と手間になる
- 家族や知人に頼みにくい場合は、第三者機関に依頼する必要があります。
- 家族や知人に頼みにくい場合は、第三者機関に依頼する必要があります。
とくに注意したいのが、「公正証書=万能」ではないこと。
形式だけ整えても、内容が具体的でなければ意味を持ちません。
形式と中身の両方が整ってはじめて、“実行される契約”になります。
3.3 受任者を選ぶときのポイント
死後事務委任契約で最も重要な要素のひとつが、「誰に任せるか」という点です。契約内容をどれだけ整えても、実行する人が信頼できなければ意味がありません。
受任者の選定は、契約の成否を左右する最重要ステップです。
受任者に適している人とは?
基本的に、以下のような人物が望ましいとされています。
- 責任感があり、誠実な人
- 契約内容をしっかり理解してくれる人
- 自分の最期について信頼して任せられる人
- 必要な手続きを行う能力・時間がある人
たとえば、以下のような候補が一般的です。
- 親しい友人
- 家族や親族
- 終活支援団体の職員
- 専門家(行政書士、弁護士など)
「親しい=適任」とは限らない点にも注意が必要です。
よくある失敗例
- 気まずくて詳細を伝えないまま任せてしまう
- 事前に内容を共有しておかないと、当日に混乱が起きます。
- 事前に内容を共有しておかないと、当日に混乱が起きます。
- 高齢の家族を選んでしまう
- 自分よりも高齢な親族だと、実行が難しくなることもあります。
- 自分よりも高齢な親族だと、実行が難しくなることもあります。
- 多忙な人や遠方の人を選ぶ
- 忙しすぎる方や物理的に距離がある人だと、対応が遅れがちです。
- 忙しすぎる方や物理的に距離がある人だと、対応が遅れがちです。
安心して任せるためのチェックポイント
- 実行する内容を一緒に確認したことがあるか
- 自分の希望に共感してくれるか
- 責任を持って最期まで対応してくれる意志があるか
- 契約内容について納得しているか
最近では、死後事務を専門に引き受けてくれる民間団体も増えており、家族や友人に負担をかけたくない人は、こうした第三者機関を選ぶこともひとつの選択肢です。
「安心して任せられるかどうか」が、すべての判断基準になります。
4. 死後事務の具体的な内容と費用感
4.1 葬儀や納骨などの宗教的対応
死後事務委任契約の中でも、とくに希望や価値観が反映されやすいのが「葬儀や納骨に関する手続き」です。
どのようなかたちで最期を迎えたいのか、誰に見送ってほしいのか――そうした希望を、契約にしっかりと書き残すことで、安心して生きるための土台が整います。
とくに一人暮らしの方や、家族と離れて暮らしている方にとって、葬儀や納骨の手配は死後の大きな心配事。自分の意志が反映されない形で執り行われることを避けたい人にとって、この契約は大きな支えになります。
死後事務委任契約で委任できる主な宗教的手続き
- 葬儀の形式の指定(一般葬、家族葬、直葬など)
- 通夜・告別式の有無や簡素な形式の希望
- 葬儀会社の選定と連絡
- 宗教者(僧侶・神父など)の手配と読経・儀式の依頼
- お布施や香典返しの手続き
- 火葬手続きおよび火葬場の予約
- 骨壷や遺影の準備、会場の設営
- 納骨先の指定(寺院・霊園・散骨など)
- 菩提寺との対応(戒名の依頼、納骨時の読経依頼など)
このように、実際にはかなり多くの項目が含まれます。細かい部分まで明文化しておかないと、受任者が判断に迷ってしまうリスクもあるため、事前の準備と打ち合わせが重要です。
注意点と準備のポイント
- 抽象的な表現(「簡単に済ませてほしい」など)は避け、具体的に記載する
- 葬儀に関する費用の支払い方法や予算も合わせて明記する
- 寺院や霊園との関係性(檀家かどうか)を明記しておく
- 家族や関係者への連絡希望がある場合は連絡先もリスト化
こうした手続きを生前に委任しておけば、万が一のときも希望どおりの葬儀を行いやすくなります。残された人が迷わず動けるよう、詳細まで準備しておくのが安心への第一歩です。
4.2 行政・金融機関への手続き
人が亡くなると、葬儀や納骨以外にも多くの行政的・金融的な手続きが必要になります。こうした事務処理は、期限が決まっているものも多く、早めの対応が求められます。
死後事務委任契約でこれらの業務を任せておけば、遺された人に余計な負担をかけることなく、スムーズに各種手続きを進めることができます。
死後事務委任契約で委任できる主な行政手続き
- 死亡届の提出(通常は7日以内が期限)
- 火葬許可証の取得および提出
- 住民票の抹消手続き
- 健康保険・介護保険の資格喪失届の提出
- 年金(国民年金・厚生年金)の受給停止手続き
- 自治体への各種届出(マイナンバー返却、原付・車両の抹消など)
金融機関関連の主な事務手続き
- 銀行口座の解約や凍結手続き
- 公共料金(電気・水道・ガス)の解約および最終支払処理
- クレジットカードの停止・解約と未払金の清算
- 保険契約の解約・請求
- 携帯電話・インターネット回線の解約
- NHK・新聞・定期購読サービスの解約
これらの手続きは通常、死亡を証明する書類(死亡診断書や戸籍謄本など)を添えて行う必要があります。そのため、契約内容に加えて、必要書類の所在やコピーを受任者に伝えておくことも大切です。
注意すべきポイント
- 書類の準備が不十分だと手続きが長期化する
- 未払いが残ると、遺族に請求がいく場合がある
- 複数の契約・支払いが月をまたぐと二重請求の可能性も
- 受任者が複数機関をまわる必要があるため、優先順位の記載があるとスムーズ
行政や金融の手続きは、項目が多く煩雑になりがちですが、事前に委任内容を具体的にまとめておくことで、処理の負担を大きく軽減できます。終活を進めるうえで、必ず押さえておきたい領域のひとつです。
4.3 ペットやSNSなど現代的な対応項目
最近では、デジタル資産やペットの対応も死後事務に含めるケースが増えています。見落とされやすい分、事前の準備が大事です。
委任できる主な内容
- 飼っているペットの引き取り先への連絡・引き渡し
- SNSアカウント(Facebook、Xなど)の削除申請
- 動画・ブログ・クラウドデータの消去依頼
- サブスクリプションサービスの解約(動画配信、音楽など)
- ネット通販や会員登録サイトの退会処理
現代の生活に即した死後事務も、契約にきちんと含めておくことが安心に繋がります。
5. まとめ:死後事務委任契約で安心できる終活を
5.1 契約によって人生の最期を自分で整える
死後事務委任契約は、自分の意思で「最期のかたち」を決められる手段です。生き方と同じように、逝き方も自分で準備できます。
この契約で実現できること
- 葬儀や納骨の形式を自分の希望通りにできる
- 死後の手続きを信頼できる人に任せられる
- 遺された人の負担や混乱を減らせる
- 自分が望む「終活」の締めくくりになる
不安を準備に変えることで、“人生の最終章”に安心感を持てるようになります。
5.2 信頼できる支援先の選び方
死後事務は信頼できる人や団体に任せることが大切です。誰に相談すべきか、どんな点を見て選べばいいのかを押さえておきましょう。
支援先を選ぶ際のポイント
- 終活・死後事務に実績があるか
- 契約内容や費用を丁寧に説明してくれるか
- 公正証書や各種手続きに対応できるか
- 相談体制が充実しており、信頼できる対応をしているか
「ここなら安心して任せられる」と感じる支援先と出会えることが、終活成功のカギです。
身元保証・死後事務代行なら終活協議会へ。
専門スタッフが親身に対応し、必要なサポートをトータルでご提供。老後の「もしも」にしっかり備えられます。
終活協議会のサービス内容はこちらからチェックできます。
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 資格取得2025年10月4日40代からの資格取得|転職にも役立つおすすめ資格10選
資格取得2025年10月4日40代からの資格取得|転職にも役立つおすすめ資格10選 エンディングノート2025年10月4日終活ノート・生前整理ノート・エンディングノートの違いとは?基本から書き方まで徹底解説
エンディングノート2025年10月4日終活ノート・生前整理ノート・エンディングノートの違いとは?基本から書き方まで徹底解説 相続2025年10月3日相続争いを回避するための生前対策ガイド|円満相続の実現方法を専門家が解説
相続2025年10月3日相続争いを回避するための生前対策ガイド|円満相続の実現方法を専門家が解説 デジタル終活2025年10月3日終活でSNSアカウントはどうする?死後のリスクと主要4大SNSの手続きを解説
デジタル終活2025年10月3日終活でSNSアカウントはどうする?死後のリスクと主要4大SNSの手続きを解説
この記事をシェアする