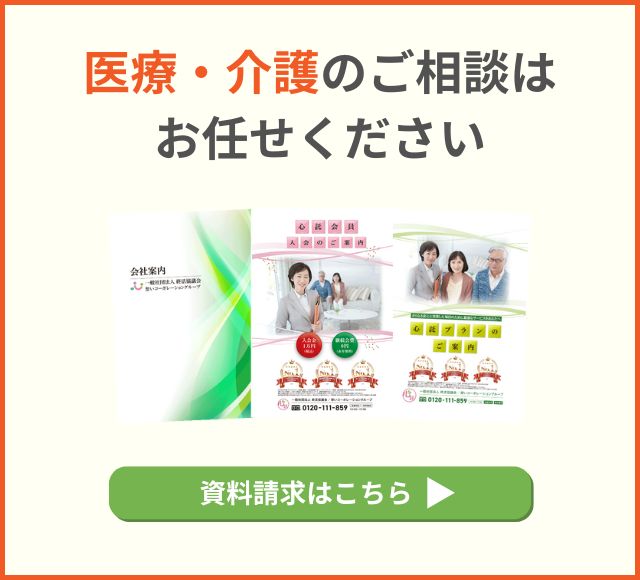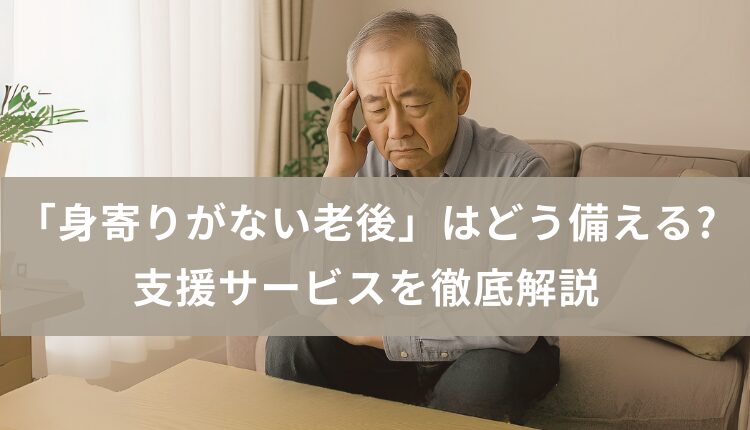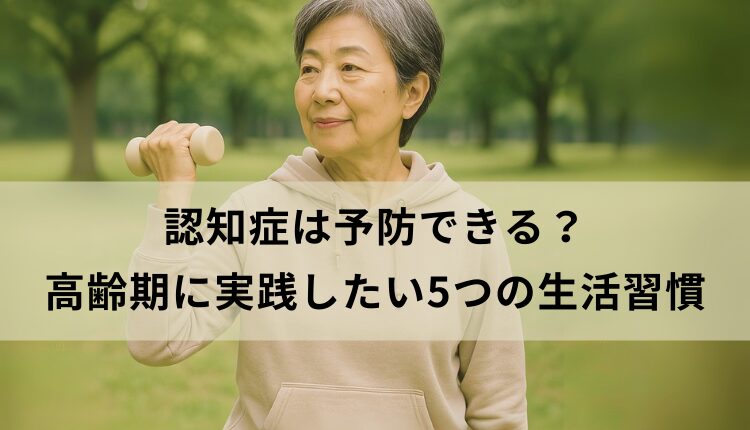
目次
要点まとめ
- 認知症は「完全に防ぐ」ことは難しいが、「リスクを減らす・発症を遅らせる」ことは可能
- 食事、運動、睡眠、人との交流、脳の刺激がカギとなる
- 予防だけでなく、将来を見据えた備えも重要
認知症は予防できる?医学的な見解と現実
日本では高齢化が進み、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるとも言われています。そんな中、「認知症は予防できるのか?」という疑問を抱く方も多いでしょう。
結論から言えば、完全に防ぐことは難しくても、生活習慣を整えることでリスクを減らしたり、発症を遅らせたりすることは可能です。
世界保健機関(WHO)は、認知症予防のための生活改善を公式に推奨しており、日本でも厚生労働省や地方自治体がその重要性を訴えています。
特に注目されているのは、糖尿病・高血圧・喫煙・運動不足・社会的孤立といったリスク要因。これらを適切にコントロールすることで、認知機能の維持に寄与できる可能性があるのです。
認知症予防に役立つ5つの生活習慣とは?
ここでは、日々の生活の中で取り入れやすい「認知症予防習慣」を5つにまとめてご紹介します。
- 栄養バランスのとれた食事
- 定期的な有酸素運動
- 良質な睡眠習慣
- 社会的つながりの維持
- 脳を刺激する活動
① 栄養バランスのとれた食事
地中海式食事(魚、野菜、オリーブオイル、ナッツ、果物など)を取り入れることで、認知症リスクを減らせるという研究結果もあります。
特にDHAやEPAなどのオメガ3脂肪酸を含む青魚は、脳の健康を保つ上で効果的とされます。
一方で、糖分や加工食品の多い食事は認知症のリスクを高めると言われています。
② 継続的な運動習慣
ウォーキングやラジオ体操、ストレッチなどの有酸素運動は、脳の血流を改善し、認知機能の低下を防ぐとされています。
1日30分、週に3〜5回の運動を継続するだけでも効果があります。可能であれば、人と会話しながらの運動(=デュアルタスク)もおすすめです。
③ 良質な睡眠
深い眠りの間に、脳内の老廃物(アミロイドベータなど)が除去されるという仕組みがあり、睡眠の質が認知症予防に直結することが分かってきています。
寝室の環境を整える、昼寝をしすぎない、寝る前にスマホを見ないなどの工夫も効果的です。
④ 人とのつながりを持つ
地域の活動や趣味のサークル、オンラインでも良いので定期的に誰かと会話することは、脳に大きな刺激を与えます。
孤独は認知症リスクの上昇に直結するため、「意識的に交流の場に出る」ことが大切です。コロナ禍以降、閉じこもりがちな方も多いため、意識的な対策が求められます。
⑤ 脳を刺激する習慣
クロスワードパズルや計算ドリル、読書や書道、編み物や楽器演奏など、「考える・工夫する」作業が脳に良いとされています。
新しいことを始めることも脳の活性化につながるため、「ちょっとやってみようかな」という好奇心を大切にしましょう。
不安を感じたらどこに相談すればいい?
「最近物忘れが増えた気がする」「家族がちょっとおかしいような…」と感じたら、早めに相談することが重要です。
相談先の例
- 地域包括支援センター(市区町村の高齢者総合相談窓口)
- かかりつけ医や認知症専門医
- 認知症初期集中支援チーム(自治体によって設置)
相談に早すぎるということはありません。
「気になる段階」での相談こそ、予防的支援につながるといわれています。
家族に迷惑をかけたくない…そんな時の備えとは?
「認知症になって、家族に迷惑をかけたらどうしよう…」「身寄りがないから、もしもの時が不安」という声を多く耳にします。
そんな不安を和らげる方法として、任意後見制度・家族信託・心託サービスなどの備えがあります。
特に、私たち終活協議会が提供する「心託サービス」は、
- 将来の認知症リスクを踏まえた生活サポート
- 緊急連絡先や身元保証
- 万一のときの病院・施設・亡くなられた後の事務手続き
まで一括して支援する体制を整えています。
ご家族やご親族が遠方にいる方、独り暮らしのご高齢者にとって大きな安心材料となっています。
「今からできること」から、始めてみましょう
認知症は誰にでも起こり得る身近な問題です。
だからこそ、「予防」と「備え」を両立することが、これからの終活の基本になります。
小さな工夫や行動の積み重ねが、将来の安心につながります。
「いつかやろう」ではなく、「今日からできること」をぜひ見つけてみてください。
📚 あわせて読みたい
📩認知症の不安、将来の備えに関するご相談はこちらから
終活協議会では、認知症や老後、死後の不安をお持ちの方に向けて、
「心託サービス」の資料を無料でお届けしています。
【フリーダイヤル】0120-111-859(年中無休10:00〜17:00)
【WEB】資料請求はコチラ
「将来が少し不安かも…」という段階でも大丈夫です。
どうぞお気軽にご相談ください。
📚 参考文献・出典
- WHO(世界保健機関)
認知機能低下と認知症のリスク軽減: WHO ガイドライン
https://www.who.int/publications/i/item/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia - The Lancet(世界五大医学雑誌の一つ)
認知症の予防、介入、およびケア: ランセットの2020年報告書
Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission – The Lancet - アメリカで実施された大規模臨床研究
アルツハイマー病協会国際会議 (AAIC), 2023年発表内容。
U.S. POINTER | Study Results | Alzheimer’s Association - J-MINT研究(日本多因子介入研究)
国立長寿医療研究センター「J-MINT:認知症予防を目指した介入研究」
多因子介入プログラムが、認知機能低下を抑制する可能性を示す(J-MINT研究) ―軽度認知障害を対象としたランダム化比較試験の結果よりー | 国立長寿医療研究センター - 日本耳鼻咽喉科学会会報
睡眠からアプローチする認知症予防
睡眠からアプローチする認知症予防 | CiNii Research - 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)発行『理学療法学Supplement』
運動による認知症予防
運動による認知症予防 | CiNii Research - 国立長寿医療研究センター「知的活動と認知症発症リスクの関連」
https://www.ncgg.go.jp/topics/20230704.html
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする