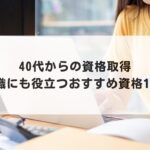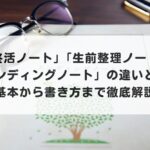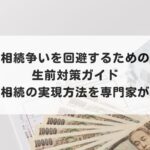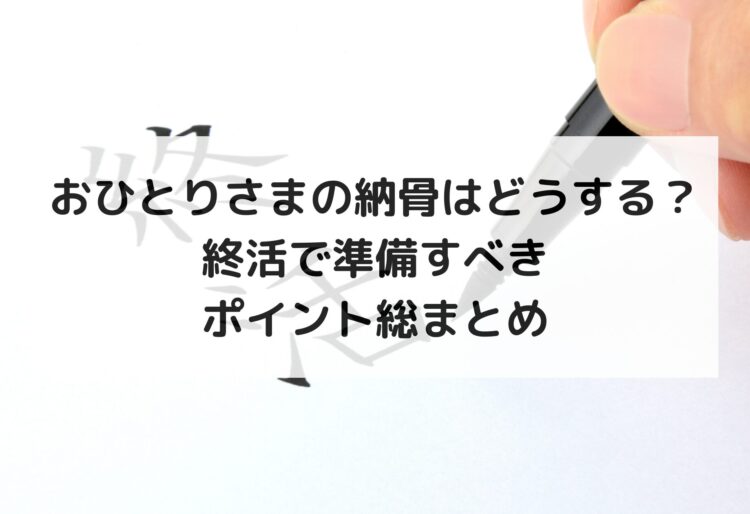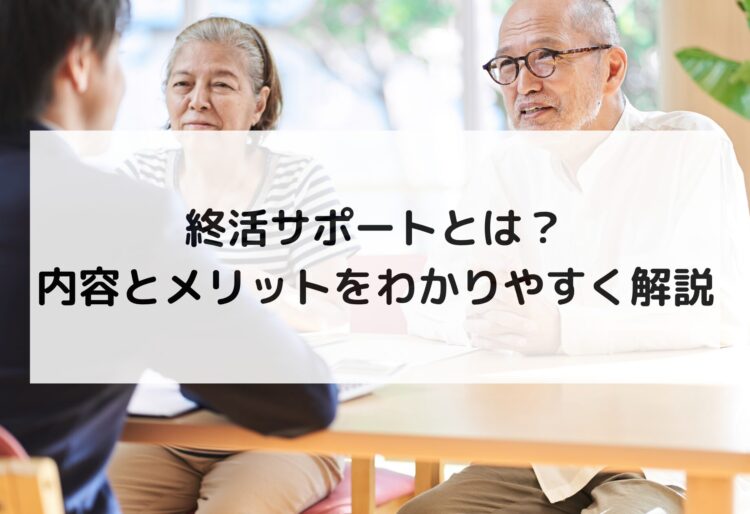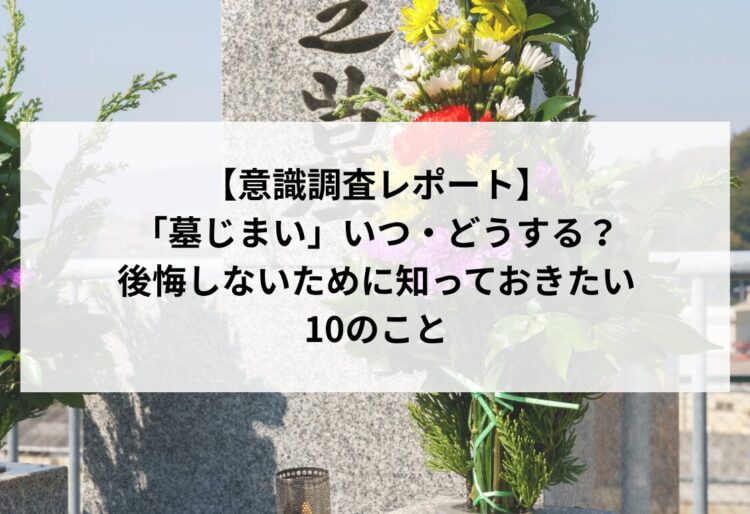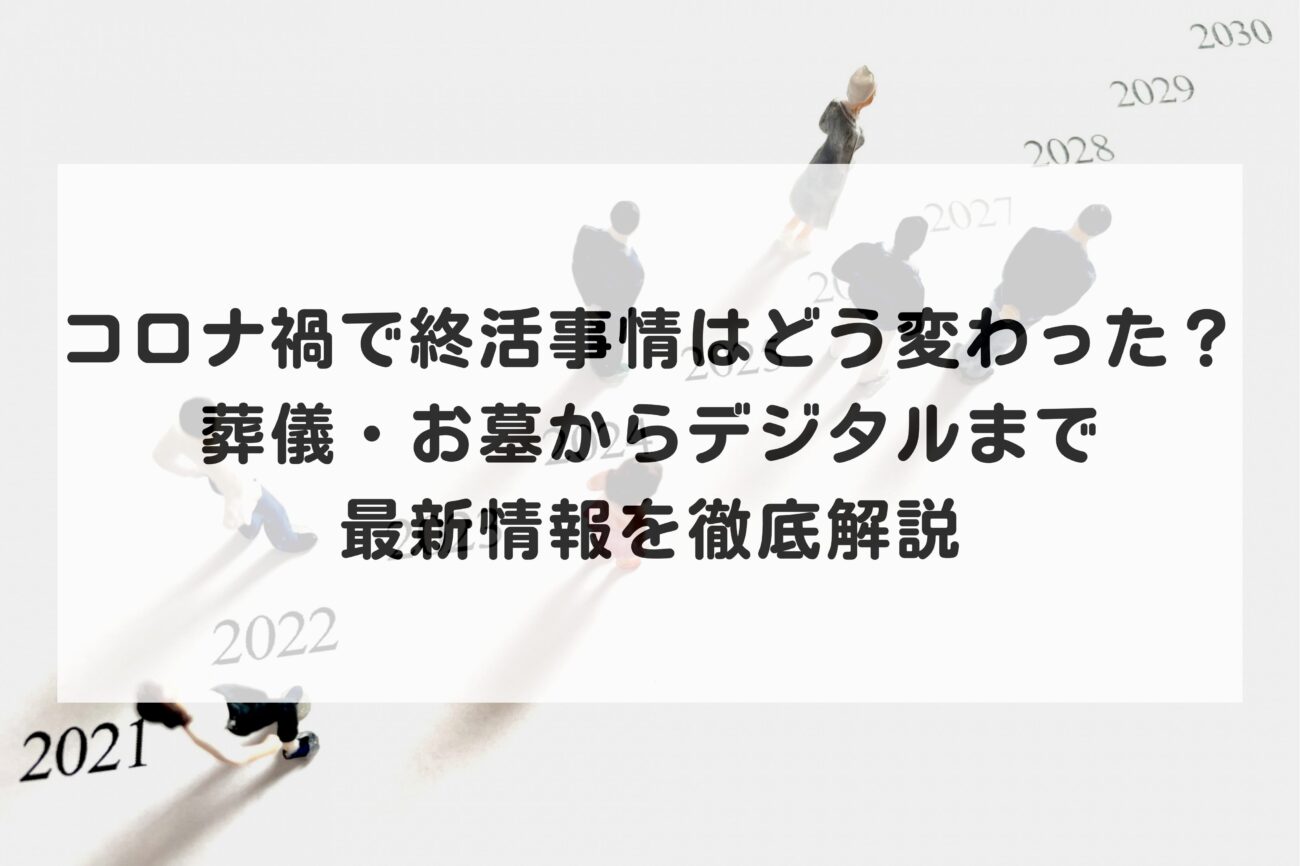
2020年から始まった新型コロナウイルスの拡大により、私たちの生活は大きな変化を余儀なくされました。
特に新型コロナに対するリスクが高い高齢者は、外出制限や面会制限などもあり、生活意識が変わった人も多かったようです。
この記事では、コロナ禍を経て日本の終活事情がどのように変化したのかを、意識、葬儀、お墓、そしてデジタル化という4つの側面から多角的に解説します。変わりゆく時代の中で、あなた自身や大切な家族にとって最適な「人生のしまい方」そして「これからの生き方」を見つけるための一助となれば幸いです。
- コロナによる終活事情の変化
- あたらしい葬儀・お墓の選択肢
- デジタル終活の重要性
目次
コロナ禍が私たちの「終活」に与えた根源的な変化
2020年から世界を一変させた新型コロナウイルスのパンデミック。
それは私たちの生活様式だけでなく、生命や死生観にも深く向き合うきっかけとなりました。
「もし自分や家族が…」という漠然とした不安は、「いつ何があるかわからない」という現実的な感覚へと変わり、多くの人にとって「死」がより身近なものとして意識されるようになりました。
この未曾有の事態は、人生の終わりを見据えた準備、すなわち「終活」のあり方にも根源的な変化をもたらしました。
それは単なるトレンドの変化ではありません。
家族のあり方、人との繋がり、そして自分自身の生き方そのものを見つめ直す動きへと繋がっています。
データで見る終活意識の変化
コロナ禍は、終活に対する人々の意識を大きく変えました。
これまで「終活は高齢になってから考えるもの」というイメージが強かったですが、パンデミックによる社会的な不安は、世代を問わず自らの人生の終わり方について考える機会を創出しました。
著名人の訃報に触れ、自分や家族のもしもを具体的に想像した方も少なくないはずです。
このような意識の変化は、終活を始めるタイミングや、終活そのものの捉え方にまで影響を及ぼしています。
それはもはや、ネガティブな「死への準備」ではなく、残りの人生をより豊かに、自分らしく生きるためのポジティブな活動として認識され始めているのです。
終活を始める年代が若齢化
コロナ禍がもたらした最も顕著な変化の一つが、終活を始める年代の「若齢化」です。
従来、終活は70代以上の高齢者が中心というイメージでしたが、現在は40代や50代といったミドル世代が積極的に関心を持ち、具体的な準備を始めるケースが急増しています。
この背景には、コロナ禍で自身の健康や親の介護、そして万が一の際の家族への影響を現実的に考えるようになったことがあります。
「自分が倒れたら、子供や配偶者に迷惑をかけたくない」
「親の終活をサポートする中で、自分自身の準備の必要性を感じた」
といった声は、この世代に共通する動機です。
彼らにとって終活は、単に死後の手続きを考えるだけでなく、住宅ローンや子供の教育費、自身の老後資金といったライフプラン全体を見直す一環として捉えられています。
エンディングノートの作成だけでなく、資産の整理や保険の見直し、デジタル遺品の管理方法の検討など、より実務的な側面から準備を進める傾向が強いのも特徴です。
40代・50代からの終活は、もはや特別なことではなく、未来への責任と自分らしい人生設計のための「新常識」となりつつあります。
ポジティブなライフプランニングとしての終活
コロナ禍を経て、終活の持つ意味合いも大きく変化しました。
かつての「死に支度」という言葉が持つ、どこか寂しくネガティブな響きは薄れ、代わりに「人生の棚卸し」という前向きな概念が浸透し始めています。
自宅で過ごす時間が増えたことで、多くの人が自身の持ち物、人間関係、そしてこれまでの人生の歩みを振り返る機会を得ました。
その過程で、
「本当に大切なものは何か」
「残りの人生で何を成し遂げたいか」
を自問自答し、未来の生き方を再設計する動きが活発化したのです。
これは、終活が「どう死ぬか」だけでなく、「どう生きるか」を考えるための重要なプロセスへと進化したことを意味します。
エンディングノートに記すのは、葬儀の希望や財産分与だけではありません。
家族への感謝の言葉、自分の趣味や生きがい、挑戦したいことのリストなど、未来に向けたポジティブなメッセージが盛り込まれるようになりました。
このように、終活は残された時間をより充実させるためのライフプランニングそのものとして捉え直されています。
この意識の変化こそが、コロナ禍がもたらした最も価値ある遺産の一つと言えるかもしれません。
【葬儀編】多様化するお葬式の最新事情
コロナ禍は、人が集まる儀式である「葬儀」のあり方を根本から見直す契機となりました。
感染症対策として「三密」を避ける必要性から、大規模な一般葬は減少し、代わりに近親者のみで故人を見送る小規模な葬儀が急速に普及しました。
この流れは、単なる一時的な対策に留まらず、人々の葬儀に対する価値観そのものを変え、コロナ収束後も新たなスタンダードとして定着しつつあります。
多くの人が、「本当に大切な人たちだけで、心ゆくまでお別れの時間を過ごしたい」「儀礼的な弔問客への対応に追われるより、故人を偲ぶことに集中したい」と考えるようになったのです。
その結果、「家族葬」が主流となり、さらに儀式を簡略化した「一日葬」や「直葬(火葬式)」といった選択肢も一般化しました。
また、遠方の親族や高齢で参列が難しい方のために「オンライン参列」という新しい形も登場し、葬儀の多様化はますます進んでいます。
主流になった「家族葬」
コロナ禍を経て、葬儀の主流となったのが「家族葬」です。
家族葬とは、その名の通り、家族やごく親しい親族、友人のみで執り行う小規模な葬儀形式を指します。
明確な定義はありませんが、一般的に参列者は30名以下であることが多いです。
最大のメリットは、故人とのお別れに集中できる時間と空間を確保できる点にあります。
義理での参列者がいないため、遺族は弔問客への挨拶や対応に追われることなく、心穏やかに故人を偲ぶことができます。
また、参列者が少ない分、会場費や返礼品、飲食接待費などを抑えられるため、一般的な葬儀に比べて費用が安くなる傾向があります。
費用相場は、地域や葬儀社のプランにもよりますが、おおよそ40万円から100万円程度が目安です。
一方で、デメリットも存在します。
故人と生前親交のあった方々へ訃報をどのタイミングで、どこまで知らせるかの判断が難しい点です。
葬儀後に訃報を知った方から「なぜ知らせてくれなかったのか」と思われたり、後日自宅へ弔問に訪れる方が相次ぎ、その対応に追われたりする可能性も考慮しておく必要があります。
事前に家族間で誰を呼ぶのか、そして呼ばない方への伝え方をしっかりと話し合っておくことが、トラブルを避ける鍵となります。
「一日葬」「直葬(火葬式)」の選択肢
葬儀の小規模化・簡素化の流れは家族葬だけに留まりません。
コロナ禍で感染リスクの低減や、高齢の参列者の身体的・精神的負担を軽減したいというニーズから、「一日葬」や「直葬(火葬式)」といった、さらにシンプルな形式を選択する人が増加しました。
これらの形式は、儀式の内容や時間を短縮することで、費用を抑えつつ、遺族の負担を軽くするという特徴があります。
かつては特別な事情がある場合に選ばれることが多かったこれらの形式ですが、現在では合理的な選択肢の一つとして広く認知されるようになりました。
「形式ばった儀式は望まない」「故人の遺志を尊重して、静かに見送りたい」と考える方々にとって、これらのシンプルな葬儀は非常に魅力的に映ります。
しかし、簡素化されているからこそ、注意すべき点も存在します。
例えば、菩提寺がある場合、事前に相談なく直葬を行うと、納骨を断られてしまうケースもあります。
また、親族の中には、伝統的な儀式を省略することに抵抗を感じる方がいるかもしれません。
これらの選択肢を検討する際は、費用や手軽さといったメリットだけでなく、宗教的な側面や親族の意向も十分に考慮し、後悔のないお別れができるよう慎重に判断することが重要です。
以下で、それぞれの形式について詳しく見ていきましょう。
一日葬
一日葬は、通夜を行わず、告別式から火葬までを一日で執り行う葬儀形式です。
通常の二日間の葬儀を一日 に短縮するため、遺族や遠方からの参列者の身体的・時間的な負担を大幅に軽減できるのが最大のメリットです。
費用相場は30万円から80万円程度で、通夜を行わない分、通夜振る舞いの飲食費や式場使用料(一日分)を削減できます。
流れとしては、ご逝去後、ご遺体を安置し、葬儀社と打ち合わせを行います。
葬儀当日に親族が集まり、告別式、最後の対面、出棺、火葬、そして収骨という手順で進みます。
この形式は、
「高齢の参列者が多く、二日間の日程は負担が大きい」
「費用を抑えたいが、告別式というお別れの儀式はきちんと行いたい」
「家族や親族だけで、ゆっくりと故人を偲びたい」
といった方に向いています。
ただし、通夜がないため、仕事の都合などで日中の告別式に参列できない弔問客が、お別れの機会を失ってしまう可能性がある点には配慮が必要です。
直葬(火葬式)
直葬(ちょくそう)、または火葬式は、通夜や告別式といった儀式を一切行わず、ごく限られた近親者のみで火葬場に集まり、火葬のみを執り行う最もシンプルな葬儀形式です。
費用相場は15万円から40万円程度と、他の形式に比べて最も安価です。
流れは、ご逝去後、法律で定められた24時間以上ご遺体を安置し、その後、直接火葬場へ搬送します。
火葬炉の前で僧侶による簡単な読経を行うこともありますが、基本的にはお別れの時間も短くなります。
この形式は、
「経済的な負担を最小限にしたい」
「故人が儀礼的なことを好まなかった」
「身寄りがなく、参列者がほとんどいない」
といった場合に選ばれることが多いです。
しかし、選ぶ前に知っておくべき注意点があります。
まず、菩提寺がある場合は必ず事前に相談が必要です。
儀式を行わないことで、納骨を拒否されるトラブルに発展する可能性があります。
また、親族の中には「あまりにも寂しいお別れだ」と反対する方もいるかもしれません。
費用面だけでなく、故人や遺族、親族の気持ちを総合的に考慮して判断することが極めて重要です。
葬儀形式の比較表
ここまで解説してきたように、葬儀の形式は多様化しており、それぞれにメリット・デメリット、そして費用感が異なります。
あなたやご家族にとってどの形式が最適なのかを判断するためには、これらの情報を客観的に比較検討することが不可欠です。
以下の表は、「一般葬」「家族葬」「一日葬」「直葬(火葬式)」の4つの主要な形式を、費用相場、参列者の範囲、儀式の内容、メリット・デメリットといった観点からまとめたものです。ご自身の価値観、予算、故人との関係性、そして親族の状況などを照らし合わせながら、後悔のないお別れの形を見つけるための参考にしてください。
| 形式 | 費用相場 | 参列者の範囲 | 儀式の内容 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般葬 | 120万~200万円 | 家族、親族、友人、知人、会社関係者など幅広く | 通夜、告別式、火葬 | ・多くの方に故人とお別れしてもらえる ・香典収入が見込める | ・費用が高額になりがち ・弔問客対応で遺族の負担が大きい |
| 家族葬 | 40万~100万円 | 家族、親族、ごく親しい友人など(~30名程度) | 通夜、告別式、火葬 | ・故人とゆっくりお別れできる ・費用を抑えられる | ・葬儀後の弔問客対応が必要になる場合がある ・誰を呼ぶかの線引きが難しい |
| 一日葬 | 30万~80万円 | 家族、親族など(家族葬と同様) | 告別式、火葬(通夜なし) | ・遺族や参列者の身体的・時間的負担が少ない ・費用を抑えられる | ・参列できない人が出てくる可能性がある ・比較的新しい形式で理解が得にくい場合も |
| 直葬(火葬式) | 15万~40万円 | ごく近親者のみ(数名~10名程度) | 火葬のみ(儀式なし) | ・費用を最も抑えられる ・遺族の負担が最小限 | ・お別れの時間が短い ・菩提寺や親族の理解が必要 ・納骨を断られるリスク |
オンライン参列や香典の新しいかたち
葬儀形式の変化に伴い、参列に関するマナーや慣習も新しい時代に対応する形で変化しています。
その象徴的な例が「オンライン参列」です。
コロナ禍で移動が制限される中、遠隔地に住む親族や、高齢・病気で外出が困難な方々が、葬儀の様子をライブ配信で視聴し、故人へと思いを馳せることができるようになりました。
この仕組みは、物理的な距離を超えて繋がれる手段として、今後も一定の需要が見込まれます。
また、香典の受け渡しも変化しています。
感染症対策として受付での現金のやり取りを避けるため、また遺族の負担を軽減するために、「香典辞退」の意向を明確に示す葬儀が増えました。
訃報連絡の際に「故人の遺志により、ご香典は固くご辞退申し上げます」といった一文を添えるのが一般的です。
さらに、キャッシュレス化の流れを受け、オンラインで香典を送れる「香典のオンライン決済サービス」も登場しています。
これにより、参列できない場合でも弔意をスマートに伝えることが可能になりました。
これらの新しいかたちは、伝統的なマナーを尊重しつつも、現代のライフスタイルや社会状況に合わせた、より合理的で思いやりのある選択肢として広がりを見せています。
【お墓編】継承を前提としない供養のかたち
葬儀と同様に、お墓や供養のあり方に対する価値観もコロナ禍を経て大きく変化しました。
少子高齢化や核家族化といった社会構造の変化が以前から進んでいましたが、パンデミックは人々に「家族」や「継承」という概念を改めて問い直す機会を与えました。
その結果、従来のような「〇〇家の墓」として代々受け継いでいくことを前提とした一般墓だけでなく、より個人のライフスタイルや価値観に合った多様な供養の形が求められるようになっています。
特に、「子供に墓守の負担をかけたくない」「自分らしい眠り方を選びたい」「費用を抑えたい」といったニーズが高まり、継承を前提としない新しいタイプのお墓が急速に需要を伸ばしています。
その代表格が、自然の中で眠る「樹木葬」「海洋散骨」や、屋内で天候に左右されずにお参りできる「納骨堂」です。これらの選択肢は、管理の手間が少なく、比較的費用も安価であることから、多くの人にとって現実的な選択肢となっています。また、こうした新しい供養の形へのシフトは、既存のお墓を整理する「墓じまい」の増加にも繋がっています。このセクションでは、変わりゆくお墓の最新事情を詳しく解説し、あなたに合った供養の形を見つけるためのヒントを提供します。
需要が急増した「自然葬」「納骨堂」とは?
継承を前提としない新しい供養のかたちとして、特に需要が急増しているのが「自然葬」と「納骨堂」です。
自然葬(しぜんそう)とは、墓石の代わりに樹木や草花を墓標としたり、遺骨を海や山に撒いたりして、遺骨を自然に還すという考え方に基づいた埋葬方法の総称です。
代表的なものに「樹木葬」や「海洋散骨」があります。
「自然に還りたい」という故人の希望を叶えられるだけでなく、多くの場合、管理費が不要であったり、宗旨・宗派を問われなかったりする点が支持されています。
墓石を建てる従来のお墓に比べて、費用を大幅に抑えられるのも大きな魅力です。
納骨堂(のうこつどう)とは、故人の遺骨を収蔵するための屋内施設のことです。
ロッカー型や仏壇型、最新のものではICカードをかざすと自動的に参拝スペースにご遺骨が運ばれてくる自動搬送型など、様々なタイプがあります。
多くは駅の近くなど交通の便が良い場所にあり、天候を気にせずお参りできる手軽さが特徴です。
こちらも永代供養が付いていることが多く、お墓の継承者がいない方でも安心して利用できます。
これらの選択肢は、現代人のライフスタイルや価値観の多様化に応えるものであり、お墓選びの新たなスタンダードとなりつつあります。
樹木葬
樹木葬は、墓石の代わりに樹木をシンボルとして遺骨を埋葬する方法です。
大きく分けて、里山のような広い敷地に埋葬する「公園型・里山型」と、庭園のように整備された霊園の一角で行う「ガーデニング型」があります。
費用相場:20万円~80万円程度。埋葬方法によって費用は大きく異なります。
- 合祀型:シンボルツリーの周りに、他の方の遺骨と一緒に埋葬する。最も費用が安い(20万円~)。
- 集合型:区画は分かれているが、シンボルツリーは共有する。
- 個別型:一本の木を一つの家族または個人で専有する。最も費用が高い(80万円~)。
選び方のポイント:
- 埋葬方法の確認:遺骨は骨壺のまま埋葬されるのか、布袋などに移して土に還るように埋葬されるのかを確認しましょう。
- 宗旨・宗派:多くは不問ですが、寺院が運営している場合は条件があることも。
- アクセスと環境:お参りに行くことを考え、自宅からのアクセスや現地の雰囲気が気に入るかどうかも重要です。
海洋散骨
海洋散骨は、粉末状にした遺骨を海に撒く供養方法です。
「雄大な自然に還りたい」「海が好きだった」という故人の想いを形にできます。
法律上の規制はありませんが、節度を守り、周辺環境や漁業関係者に配慮して行う必要があります。
そのため、専門の業者に依頼するのが一般的です。
費用相場:5万円~40万円程度。散骨の方法によって異なります。
- 合同散骨:複数の家族が同じ船に乗り合わせて行う。最も費用が安い(10万円前後)。
- 個人(貸切)散骨:一家族で船をチャーターして行う。プライベートな時間を過ごせる(20万円~)。
- 委託散骨:業者に遺骨を預け、散骨を代行してもらう。立ち会いはできないが最も手軽(5万円前後)。
選び方のポイント:
- 粉骨の必要性:散骨前には遺骨を2mm以下の粉末にする「粉骨」が必須です。費用に含まれているか確認しましょう。
- 散骨エリア:海水浴場や漁場の近くは避け、沖合で行うのがマナーです。業者がルールを遵守しているか確認が必要です。
- 証明書の発行:散骨した日時や緯度・経度を記録した「散骨証明書」を発行してくれる業者を選ぶと、後々の記念になります。
納骨堂
納骨堂は、屋内に設けられた納骨スペースに遺骨を安置する施設です。
天候に左右されず快適にお参りできる点や、セキュリティがしっかりしている点が魅力です。
費用相場:30万円~150万円程度。タイプや立地によって価格差が大きいです。
- ロッカー型:シンプルな棚に骨壺を安置する。比較的安価。
- 仏壇型:上段に仏壇、下段に納骨スペースがある。自宅に仏壇を置けない場合に人気。
- 自動搬送型:参拝ブースでカードをかざすと、バックヤードから遺骨が自動で運ばれてくる最新式。都心部に多い。
メリット:
- 駅近などアクセスが良い場所が多い。
- 天候や季節を問わずお参りできる。
- 掃除などの管理が不要。
注意点:
お参りの作法:火を使うお線香が禁止されているなど、施設ごとのルールがあります。
契約期間:多くは三十三回忌など一定期間後に合祀墓に移される「永代供養」です。個別に安置される期間を確認しましょう。
年間管理費:永代供養料とは別に、年間管理費が必要な場合があります。
「墓じまい」の増加とその背景
新しい供養の形が広まる一方で、「墓じまい」を選択する人も年々増加しています。
墓じまいとは、現在あるお墓を撤去・解体し、更地にして使用権を墓地の管理者に返還することです。
取り出した遺骨は、樹木葬や納骨堂、あるいは手元供養など、別の形で供養します。
墓じまいが増加している背景には、深刻な後継者不足があります。
「お墓が遠方にあり、墓参りに行くのが困難」
「子供がいない、あるいは娘だけで嫁いでしまったため、お墓を継ぐ人がいない」
「経済的な理由で、お墓の年間管理費を払い続けるのが難しい」
といった理由が挙げられます。
コロナ禍で帰省がままならず、お墓の管理ができない状況を経験したことで、決断した人も少なくありません。
墓じまいの費用は、墓石の撤去工事費、行政手続きの代行費用、離檀料(お寺の檀家をやめる際に支払うお布施)、そして新しい納骨先にかかる費用などを合わせて、総額で30万円から300万円程度と幅があります。
手続きとしては、まず現在の墓地管理者や親族に相談し、次に新しい遺骨の受け入れ先を確保します。
その後、自治体から「改葬許可証」を発行してもらい、墓石の撤去工事、遺骨の移動という流れになります。
複雑な手続きを伴うため、専門の業者に相談しながら進めるのが一般的です。
▼関連記事
墓じまいとは?平均費用や手続きの流れを解説!
【新潮流】デジタル終活
現代社会において、私たちの生活はスマートフォンやパソコン、インターネットと切り離すことはできません。
友人とのコミュニケーションはSNSで、資産管理はネットバンキングで、思い出はクラウド上の写真で。
生活がデジタル化するにつれて、私たちが亡くなった後に残される「デジタル遺品」の問題が、終活における新たな、そして避けては通れない重要課題として浮上しています。
コロナ禍は、このデジタル化の流れをさらに加速させました。
対面での接触が制限される中、人々はオンラインでのコミュニケーションやサービス利用を余儀なくされ、その結果、デジタル資産やアカウントの数はますます増加しました。
もし、あなたが突然亡くなった場合、家族はあなたのスマホのロックを解除できるでしょうか?
ネット銀行の口座や、契約しているサブスクリプションサービスを把握しているでしょうか?
これらのデジタル遺品を放置すると、家族が故人の大切なデータにアクセスできなかったり、不要なサービス料金が引き落とされ続けたりと、深刻なトラブルに発展する可能性があります。
同時に、終活そのものを進める手段としてもデジタル化は進んでいます。
遠隔地の専門家と繋がれるオンライン相談や、終活情報を一元管理できるアプリなど、便利なサービスが次々と登場しています。
見過ごせない「デジタル遺品」問題
デジタル遺品とは、故人が生前に使用していたパソコンやスマートフォン本体、そしてその中に保存されているデータや、オンライン上のアカウントなど、デジタル形式で残された遺産全般を指します。
具体的には、以下のようなものが含まれます。
- ハードウェア:パソコン、スマートフォン、タブレット、外付けハードディスクなど。
- データ:写真、動画、メール、文書ファイル、アドレス帳など。
- オンラインアカウント:
- 金融資産:ネット銀行、ネット証券、FX、暗号資産(仮想通貨)など。
- SNS:Facebook, X (旧Twitter), Instagram, LINEなど。
- Webサービス:ECサイト(Amazon, 楽天など)、サブスクリプション(Netflix, Spotifyなど)、クラウドストレージ(Google Drive, iCloudなど)。
これらのデジタル遺品で最も大きな問題となるのが、「IDとパスワードが本人にしか分からない」という点です。
家族がその存在すら知らず、ログインできなければ、資産を引き出したり、不要な契約を解除したりすることが非常に困難になります。
特にネット証券や暗号資産などは、遺族が気づかないまま放置され、価値が変動したり、最悪の場合失われたりするリスクがあります。
また、SNSアカウントを放置すると、乗っ取られて犯罪に利用される危険性もゼロではありません。
対策として、重要なアカウントのIDとパスワードをリスト化し、信頼できる家族にだけ保管場所を伝えておくことが不可欠です。
エンディングノートに直接書き込むのではなく、「パスワードは金庫の中のUSBメモリに保存」のように、間接的に場所を示す方法が安全です。
また、各SNSでは、死後にアカウントを追悼アカウントに移行したり、削除したりする設定が用意されている場合もあるため、生前に設定しておくことをお勧めします。
▼関連記事
デジタルデータをトラブルなく引き継ぐ。デジタル終活の進め方と注意点を業界関係者が解説
非対面で進める終活
コロナ禍で急速に普及したオンライン化の波は、終活の進め方にも大きな変化をもたらしました。
従来は葬儀社や石材店、士業の事務所などに直接足を運んで相談するのが一般的でしたが、現在ではZoomなどのビデオ会議システムを利用した「オンライン相談」が多くの事業者で導入されています。
これにより、自宅にいながら全国の専門家から話を聞き、複数のサービスを比較検討することが容易になりました。
特に、「近くに相談できる専門家がいない」「仕事や介護で家を空けられない」「まずは気軽に情報収集から始めたい」という方にとって、オンライン相談は非常に有効な手段です。
また、終活の基礎知識を学べる「オンラインセミナー」も頻繁に開催されており、無料で参加できるものも多いため、情報収集の第一歩として活用できます。
さらに近年では、より手軽に終活を進められる「終活アプリ」も登場しています。
AIロボットとの対話形式でエンディングノートを作成できたり、家族と情報を共有したり、アプリ経由で専門家に相談できたりと、多機能化が進んでいます。
これらのデジタルツールを賢く利用することで、時間や場所の制約なく、自分のペースで効率的に終活を進めることが可能です。
ただし、オンラインでのやり取りでは、相手の顔が見えにくい分、事業者の信頼性を慎重に見極めることがより一層重要になります。
今から始める終活の具体的なステップ
ここまで、コロナ禍を経て変化した終活の最新事情を、意識、葬儀、お墓、デジタルの各側面から見てきました。
葬儀やお墓の選択肢は多様化し、デジタル遺品という新たな課題も生まれました。
こうした変化の時代において、「終活の必要性は感じるけれど、何から手をつければいいのか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
実際に終活を検討する際に、具体的なプランニングで悩むのは自然なことです。
終活は、一度にすべてを完璧にやろうとすると、そのあまりの範囲の広さに圧倒されてしまいがちです。
大切なのは、焦らず、気負わず、自分のできるところから一歩ずつ始めてみることです。
それは、自分の人生を振り返る内面的な作業かもしれませんし、家族と将来について話すことかもしれません。あるいは、専門家から客観的な情報を得ることかもしれません。
この最後のセクションでは、これまでの情報を踏まえ、あなたが今日からでも始められる終活の具体的な3つのステップを提案します。
このステップに沿って進めることで、漠然とした不安を解消し、あなたらしい人生の締めくくりに向けた確かな道筋を描くことができるはずです。
ステップ1:まずは「人生の棚卸し」で自分の希望を明確にする
終活の第一歩は、専門家を探したり、商品を比較したりする前に、まず自分自身の内面と向き合うことから始まります。
これが「人生の棚卸し」です。
静かな時間を見つけて、これまでの人生を振り返り、自分の価値観や希望を明確にしてみましょう。
エンディングノートを用意し、以下のような項目について思いつくままに書き出してみるのがおすすめです。
- これまでの人生で嬉しかったこと、楽しかったこと
- 大切にしてきた価値観や信条
- 自分の財産(預貯金、不動産、有価証券、保険など)のリストアップ
- デジタル資産(アカウントやパスワード)のリストアップ
- 延命治療や介護についての希望
- 葬儀やお墓についての希望(誰に、どのように送ってほしいか)
- 大切な人たちへ伝えたい感謝の言葉やメッセージ
この作業の目的は、完璧なリストを作ることではありません。
自分の希望を可視化し、整理することで、自分が終活において何を優先したいのか、誰に何を伝えたいのかを客観的に把握することです。
この「自己分析」が、今後の具体的なステップを進める上での揺るぎない土台となります。
終活協議会では、資料請求で上記の内容を書き込める内容がそろったエンディングノートを無料でプレゼントしています。
書き方が分からない...という方のための説明動画に加え、お電話でのご相談も無料で受け付けております。
終活を始めるはじめの一歩として、お気軽にお申込みください。
ステップ2:家族と話し合う機会を持つ
自分の希望がある程度まとまったら、次のステップは、それを家族と共有することです。
多くの人が終活で悩むのは、「家族にどう切り出せばいいか分からない」「縁起でもないと思われないか」という点です。
しかし、あなたの希望を伝えておかなければ、いざという時に家族は大きな混乱と負担を抱えることになります。
話し合いは、深刻な雰囲気ではなく、例えば親の誕生日や結婚記念日、あるいは帰省のタイミングなど、家族が集まる機会に「これからのことを少し話しておきたくて」と、さりげなく切り出すのが良いでしょう。
伝えるべきことは、ステップ1でまとめた自分の希望です。
特に、延命治療の希望、葬儀やお墓の形式、そしてデジタル遺品の存在とアクセス方法については、明確に伝えておく必要があります。
同時に、家族の意向を確認することも重要です。
例えば、あなたが「直葬でいい」と思っていても、家族は「きちんとお別れの式をしたい」と考えているかもしれません。
終活は、あなた一人のものではなく、残される家族のものでもあります。
お互いの気持ちを尊重し、納得できる着地点を見つけるための対話が、円満な終活には不可欠です。
ステップ3:専門家への相談と情報収集
自分と家族の希望がある程度固まったら、最後のステップとして、具体的な情報を集め、専門家へ相談しましょう。
葬儀社、石材店、霊園、信託銀行、弁護士、司法書士など、終活に関わる専門家は多岐にわたります。
近年では、複数の分野にまたがる相談に対応してくれる終活の総合窓口サービスも増えています。オンライン相談などを活用し、複数の事業者から話を聞き、見積もりを取ることで、サービス内容や費用を客観的に比較検討できます。
その際、信頼できる専門家かどうかを見極めることが重要です。
また、法制度は時代と共に変化します。例えば、2020年7月には法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まり、遺言書作成のハードルが下がりました。
相続に関する法改正も行われています。
最新の情報を収集し、必要であれば法的な手続きについても専門家に相談することで、あなたの希望を法的に有効な形で確実に実現することができます。
情報収集と専門家への相談を通じて、あなたの終活プランをより具体的で確実なものにしていきましょう。
終活協議会はお客様に合わせた終活サービスを提供しています
新型コロナの影響により行動制限が掛けられた期間の中で、私たちの生活は様々な面で大きな影響を受けました。自分のこれからの人生を考える機会となった人も多かったようです。
人生100年時代を迎え、また、コロナ禍を経て、私たちの終活の在り方も変わってきています。
終活の重要性を知ることで、「老後をより幸せに過ごしたい」「残された遺族に苦労させたくない」といった理由から、終活に対する意識が高まっています。
一般社団法人 終活協議会は、終活サービスを始めて約20年、20,000人以上のお客様の終活をサポートした実績があり、多くのお客様からご好評の声をいただいております。
全国13カ所の拠点でサービスを展開し、各地に終活サービスにたずさわる専門家とのネットワークを構築しています。
追加費用やオプション費用は無く、「入会金と基本料金のみ」で、お客様一人ひとりに合わせた最適なプランをオーダーメイドで提供することが可能です。
終活ついてお悩み事や分からない事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
終活の専門知識が豊富なスタッフが、迅速かつ誠心誠意ご相談にお答え致します。
365日 (受付時間10:00~17:00) 対応していますので、お気軽にお電話ください。
また、会社やサービスについて資料請求をご希望の方は、下記のページより資料をご請求ください。
24時間365日受け付けております。
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 資格・セミナー2025年10月4日40代からの資格取得|転職にも役立つおすすめ資格10選
資格・セミナー2025年10月4日40代からの資格取得|転職にも役立つおすすめ資格10選 法律2025年10月4日終活ノート・生前整理ノート・エンディングノートの違いとは?基本から書き方まで徹底解説
法律2025年10月4日終活ノート・生前整理ノート・エンディングノートの違いとは?基本から書き方まで徹底解説 お金・相続2025年10月3日相続争いを回避するための生前対策ガイド|円満相続の実現方法を専門家が解説
お金・相続2025年10月3日相続争いを回避するための生前対策ガイド|円満相続の実現方法を専門家が解説 身の回り整理2025年10月3日終活でSNSアカウントはどうする?死後のリスクと主要4大SNSの手続きを解説
身の回り整理2025年10月3日終活でSNSアカウントはどうする?死後のリスクと主要4大SNSの手続きを解説
この記事をシェアする