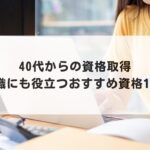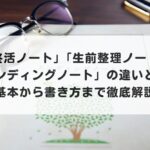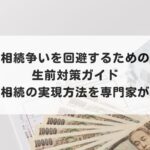「終活」とは、人生の終わりに向けて身の回りを整理し、家族や自分の未来に備える活動のことを指します。エンディングノートの記入や葬儀の準備、財産整理などが代表的ですが、意外と見落とされがちなのが「保険の整理」です。
今回、一般社団法人終活協議会では「保険と終活」に関する実態調査を実施し、多くの方が保険について何を重視し、どんな不安や悩みを抱えているのかが明らかになりました。本記事では、その調査結果をもとに、保険と終活の関係性や、今からできる準備について具体的に解説していきます。
「保険と終活」に関する実態調査については、こちらの記事をご覧ください。
【意識調査レポート】保険と終活に関する実態調査:加入率や課題、情報共有の実態が明らかに
目次
【1】終活世代が最も優先している保険とは?
今回の調査結果によると、最も優先して加入している保険として最も多かったのは「医療保険」(40.3%)でした。続いて「生命保険」(29.4%)、「がん保険」(7.1%)、「その他」(6.4%)という結果に。保険に加入していない人も16.7%おり、一定数の無保険層が存在することもわかります。
医療保険の人気は、終活世代にとって「入院」や「手術」などへの備えが最も現実的であり、かつ不安材料であることを反映しています。年齢とともに高まる医療リスクに備えたいという心理は非常に自然です。また、生命保険は家族への保障という観点から依然として重要視されています。
ここで注目すべきは、がん保険の割合が相対的に低い点です。近年ではがん治療の進化により、入院日数の短縮や通院治療の選択肢も増えています。そうした医療制度の変化に対応しきれていない方も多く、加入の優先度が下がっている可能性もあります。
また、無保険の人が一定数存在する背景には、「保険の必要性がわからない」「過去に保険に加入したものの解約した」など、様々なライフスタイルや価値観の違いがあると考えられます。終活世代にとっての保険は、単なる商品選びではなく、「これからの人生をどう生きるか」という価値観の反映でもあります。
【2】保険の見直しタイミング:実は「3年以上前」が2割以上
保険は一度加入したら終わり、ではありません。ライフステージや健康状態の変化に応じて、定期的な見直しが必要です。しかし、今回の調査では「最後に保険内容を見直したのはいつですか?」という問いに対し、「3年以上前」と回答した人が21.9%に上りました。「1年以内」が31.9%、「1〜3年以内」が27.7%であることを考えると、一定数の人が長期間見直しを行っていないことがわかります。
また、「保険に加入していない」と答えた人も18.6%おり、そのまま無対策で過ごしている可能性もあります。
保険の見直しにはさまざまなタイミングがあります。たとえば、定年退職、年金受給開始、子どもの独立、持病の発症など、ライフステージが変わったときは、保険の見直しを考える絶好の機会です。また、加入時にはなかった新しい保険商品が登場している可能性もあります。
見直しを怠ると、保険料が割高なままだったり、現在の自分のニーズに合わない内容になっていたりすることがあります。逆に言えば、定期的な見直しによってコストダウンや保障内容の最適化が可能になります。
終活においては、「これからの人生で本当に必要な保障は何か?」を見極めることが大切です。特に、医療費や介護費用、死後の整理費用など、自分の最期に必要なコストを見据えた保険設計が求められます。
【3】保険見直しの最大の理由は「保険料の負担」
調査の中で、「保険の見直しを行うとしたら、どの理由がもっとも大きいですか?」という問いに対して、最も多かった回答が「保険料の負担が大きい」(42.4%)でした。
やはり、終活世代にとって年金や貯蓄を頼りにした生活が中心となる中、月々の固定費としての保険料は見逃せない問題です。とくに、複数の保険に加入している人や、保障内容に比べて割高な保険を長年契約してきた人にとっては、保険料の見直しは家計の再編に直結します。
2番目に多かったのは「加齢や病気のリスクを感じて」(25.8%)という回答。年齢が上がることで、より具体的なリスク(たとえば心疾患や認知症など)を意識するようになるのは自然な流れです。こうしたリスク認識の高まりは、保障内容の見直しや、保障の重複・不足の再確認へとつながります。
一方で、「終活として情報を整理したい」(10.7%)、「家族に勧められた・提案された」(9.8%)といった回答もあり、終活が保険見直しの動機になるケースも見られます。その他(11.2%)の中には、「保険会社の担当者に促された」や「相続対策として再検討している」といった理由も含まれるでしょう。
【4】保険選びは「身近な人の意見」を参考にする人が最多
保険を選ぶ際、どのような情報源を頼りにしているのでしょうか。今回の調査によると、「家族や身近な人の意見を参考にしている」と答えた人が最も多く、全体の40.4%を占めました。
次いで「保険会社や担当者」(26.3%)、「ファイナンシャルプランナーなど専門家」(13.9%)、「自分自身のみ」(19.4%)という結果になりました。
この結果からわかるのは、多くの人が信頼できる他者の助言を重要視しているという点です。特に終活世代は「自分の選択に自信が持てない」「複雑な契約内容を理解するのが難しい」と感じることも少なくないため、信頼できる人の意見を参考にする傾向があります。
ただし、注意したいのは「情報の偏り」です。身近な人の経験や価値観がすべての人に当てはまるとは限りません。複数の視点から比較検討することが、より適切な保険選びには欠かせません。
専門家の意見もぜひ取り入れたいところです。近年では、無料の保険相談窓口や終活ガイド、ファイナンシャルプランナーによる個別相談なども充実しています。そうした第三者の視点を取り入れながら、自分の価値観と生活状況に合った保険を見つけていくことが重要です。

【5】約8割の人が「保険は終活の一部」と実感
調査によると、「保険が終活の一部として大切だと感じたことがあるか?」という問いに対し、「強く感じている」が36.9%、「なんとなく感じている」が41.2%と、合わせて約8割の人が「保険=終活の一部」と捉えていることが明らかになりました。
これは非常に注目すべき結果です。かつては「終活」といえば、主に葬儀の準備や遺言書の作成といったイメージが強く、保険の整理はそこまでフォーカスされてきませんでした。しかし近年では、終活の中でも「経済的な整理」に注目が集まり、保険の見直しや加入・解約の判断が重要な要素となっています。
実際に、終活を意識してエンディングノートを作成している方の中には、「現在加入している保険の一覧」「保障内容の要点」「保険金の受取人情報」などを記録するケースが増えています。これにより、いざというとき家族がスムーズに保険金を請求できるようになるだけでなく、残された家族に不安を残さないという安心感にもつながります。
また、保険が終活の一部であることを意識することは、自分自身の人生設計にもつながります。「万が一のとき、どのくらいの費用が必要なのか」「介護が必要になったとき、どのくらい自己負担があるのか」など、人生の後半を自分らしく生きるためには、保険の在り方が重要な要素になるのです。
【6】「死後に備える保険」加入者はまだ約3割
「葬儀費用や死後の手続きに備える保険に加入していますか?」という質問に対し、「加入している(終身保険など)」が35%、「加入していない」が34%、「これから検討したい」が31%という結果になりました。
これを見ると、死後に備える保険についての関心は一定程度あるものの、実際に加入している人はまだ3分の1程度にとどまっていることが分かります。
終活保険(いわゆる「死亡保障」や「葬儀費用に備える保険」)は、自分が亡くなったあとに遺族が受け取れる保険金を使って、葬儀や法要、納骨、遺品整理、相続税の支払いなどに充てることができます。つまり、「自分の死後にかかる費用を自分で用意しておく」という視点で、非常に終活的な性格を持っています。
それにもかかわらず、実際にはまだ加入者が少ない理由としては、以下のような要因が考えられます。
・加入時期を迷っている(高齢になると保険料が高くなるため)
・他の保険で代替できると考えている
・死後費用に関する正確な金額感がわからない
・「死後にかかる費用」を想像すること自体に心理的抵抗がある
今後、終活の情報提供が進むにつれて、このような終身保険の重要性がより認識され、加入率の増加につながっていくことが期待されます。
【7】「保険の共有」は約3人に1人が未実施
「保険について、どの程度家族に伝えていますか?」という問いでは、「内容も含めて共有している」が35.3%、「加入していることだけ話している」が29.6%、そして「まだまったく話していない」が35.3%という結果に。
つまり、約3人に1人が保険について家族とまったく話していないという現実が浮かび上がっています。
この結果にはさまざまな背景があると考えられます。
・そもそも伝える家族や親族がいない
・家族とのコミュニケーションが少ない
・死後の話題に触れることに抵抗がある
・保険の内容を理解していないため、説明が難しいと感じている
・共有の必要性を感じていない
しかし、保険は契約者が亡くなった後に活用される場面が多いため、受取人や手続きの方法を事前に伝えておくことが極めて重要です。保険の存在を知らないまま請求期限が過ぎてしまえば、せっかくの保障が無駄になってしまうこともあります。
終活ガイドの立場からは、「保険のことを伝えておくことは、残された方たちへのやさしさである」と伝えていくことが大切です。エンディングノートや保険情報一覧表を作成し、家族に預ける・話しておく・書き残しておくといった行動が推奨されます。

【8】保険証書の保管も「曖昧なまま」が約6割
「保険証書などの保管状況について、もっとも近いものを選んでください」という質問に対して、「エンディングノートなどにまとめている」は6%と少数派でした。「家族に伝えたうえで保管している」31%、「自分のみが把握している」32%、「整理できておらず不明確」31%と、約6割が保険の管理体制に不安を抱えている実態が明らかになりました。
この調査結果は、せっかく加入している保険の価値を、適切に活かせない可能性があることを示しています。
「証書が見つからない」「どの保険会社かわからない」「受取人の変更をしていない」などの理由で、保険金の請求ができずに終わるケースも少なくありません。
保険は契約して終わりではなく、いざというときに確実に活用できる状態にしておくことが肝心です。
具体的には
・保険証書をひとつのファイルにまとめる
・エンディングノートに加入内容を記載する
・家族に保管場所を伝える
契約内容の一覧をパソコンやクラウド上に保管し、共有設定しておくといった工夫が有効です。
【9】保険に関する「いまの悩み」とは?
「今のご自身の状況で、最も気になっている保険に関する課題は何ですか?」という設問においては、「加入内容が自分に合っているか不安」(28%)、「保険料の負担が大きい」(27%)が二大悩みとして挙げられました。
また、「本当に保険が必要かどうかわからない」(11%)、「家族にどう伝えるか」(3%)という回答も見られ、「特にない」が31%に達しました。
この結果からは、「加入してはいるけれど、本当にこれで良いのか不安」「そもそも今の自分に必要なのか?」といった漠然とした疑問が多くの人に共通していることがわかります。
これらの悩みを解決するためには、次のようなアクションが有効です。
・定期的に保険の内容を点検し、現状と照らし合わせる
・終活ガイドやFPの相談窓口を利用する
・保険の目的(医療・死亡保障・介護など)を明確化する
・自分や家族の生活スタイルに即した保障設計を考える
「何となく加入したまま」「昔のまま続けている」状態は、保険の本来の意味を失わせてしまいます。保険に対する今の悩みは、自分自身と向き合う絶好の機会とも言えるでしょう。
【10】終活ガイドとして提供すべき情報とは?
「終活ガイドの立場として、どのような保険情報が役に立つと感じますか?」という設問においては、「実例や体験談」(48%)が最多を占め、「専門家による情報提供」(28%)、「よくある質問形式の解説」(13%)と続きました。
これは、保険という専門性の高いテーマにおいて、「リアルな声」や「わかりやすい説明」が求められていることを示しています。
実際に保険を見直した人の体験談や、「こんな失敗があった」「保険金が下りずに困った」「家族が感謝してくれた」などの実例は、多くの人の共感を呼び、自分ごととして捉えるきっかけになります。
また、専門家の視点から「こういう人にはこのタイプの保険が向いている」「終活のタイミングではこう見直すべき」といった具体的なアドバイスも有効です。
さらに、Q&A形式や図解、チェックリストの活用など、「読みやすさ・使いやすさ」に配慮したコンテンツがあると、より多くの人に届く終活ガイドになります。
まとめ:保険は「未来の安心」を整える大切な終活項目
保険の整理・見直しは、将来の不安を軽減し、家族への思いやりを形にする行為でもあります。今回の調査からも、「なんとなく不安」「共有できていない」「整理しきれていない」という声が多く寄せられました。
終活を進めるうえで、保険に対する理解を深め、自分に合った保障を見極め、家族と共有すること。それは、安心して「その日」を迎えるための一歩でもあります。
あなたの終活にとって、「保険」はどんな存在ですか?
これからの人生に寄り添う保険の在り方を、ぜひ今一度見直してみてください。
一般社団法人 終活協議会では、どんな小さな悩みでも安心して相談できる『心託(しんたく)』サービスをご提供しています。
たとえば、保険に関するご相談も可能です。専門知識をもった信頼できるパートナーをご紹介し、あなたに合った選択を一緒に考えます。
「これって誰に聞けばいいの?」という時こそ、心託サービスをご活用ください。
終活のコンシェルジュとして、あなたに寄り添いながらサポートいたします。
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 資格取得2025年10月4日40代からの資格取得|転職にも役立つおすすめ資格10選
資格取得2025年10月4日40代からの資格取得|転職にも役立つおすすめ資格10選 エンディングノート2025年10月4日終活ノート・生前整理ノート・エンディングノートの違いとは?基本から書き方まで徹底解説
エンディングノート2025年10月4日終活ノート・生前整理ノート・エンディングノートの違いとは?基本から書き方まで徹底解説 相続2025年10月3日相続争いを回避するための生前対策ガイド|円満相続の実現方法を専門家が解説
相続2025年10月3日相続争いを回避するための生前対策ガイド|円満相続の実現方法を専門家が解説 デジタル終活2025年10月3日終活でSNSアカウントはどうする?死後のリスクと主要4大SNSの手続きを解説
デジタル終活2025年10月3日終活でSNSアカウントはどうする?死後のリスクと主要4大SNSの手続きを解説
この記事をシェアする