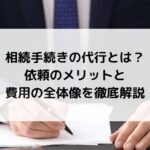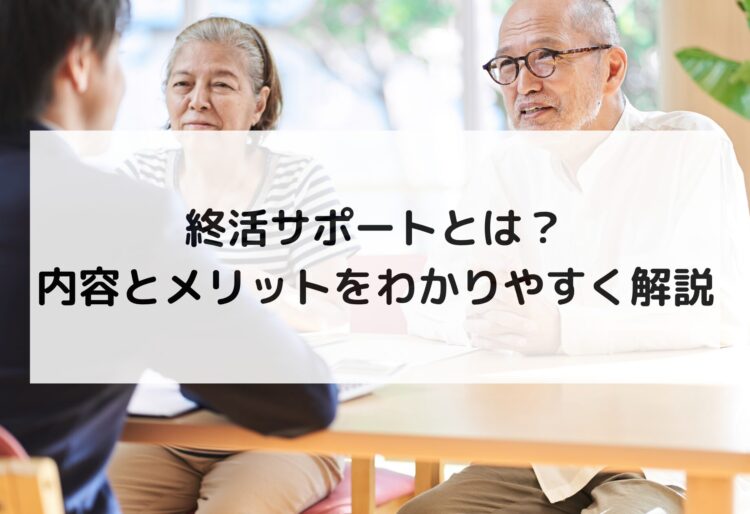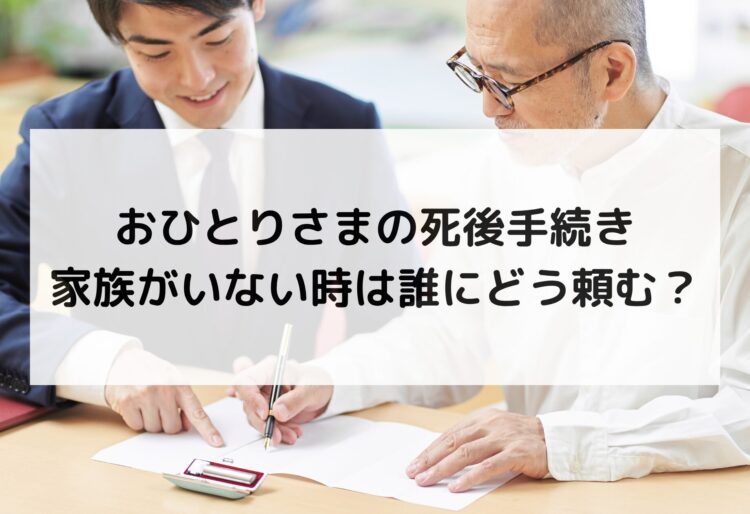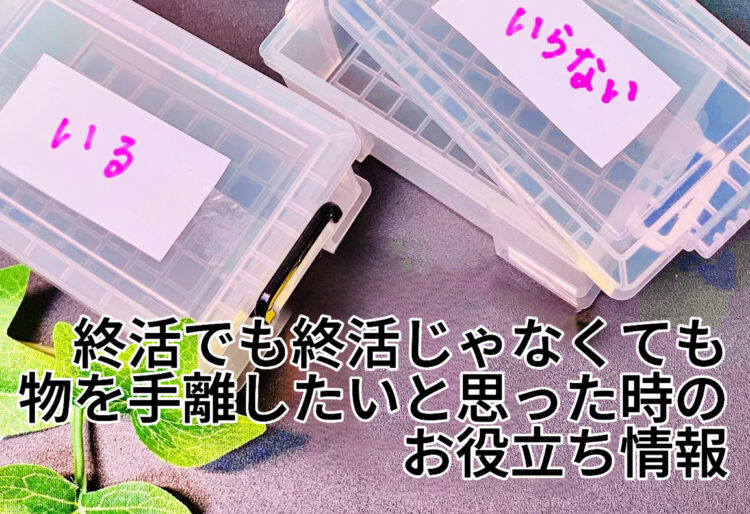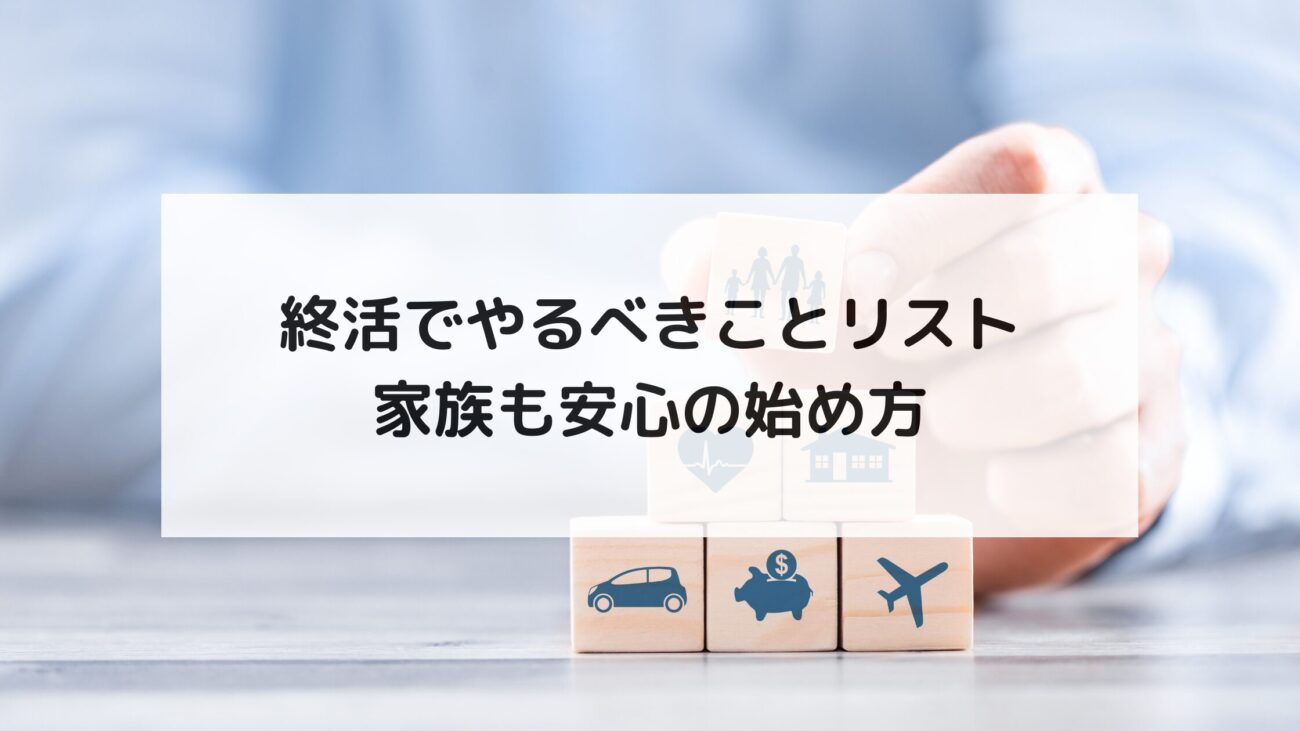
目次
1. 終活でやることとは?まず最初に知っておきたい基礎知識

1.1 終活と「やること」の意味とは
終活とは、「人生の終わり」に向けて必要な準備を自分自身で行うことを指します。
「終わりの活動」と書いて「終活」。最近ではシニア層だけでなく、40代・50代の現役世代にも広がりつつある考え方です。
では、「終活のやること」とは具体的に何を指すのでしょうか?
実は終活とひと口に言っても、その内容は多岐にわたります。財産や相続の整理だけでなく、医療や介護の希望、デジタルデータの管理、人間関係の見直しなど、人生全体の棚卸しとも言えるものです。
「やること」が幅広いため、全体像を知ることがとても大事です。
たとえばこんなことが含まれます:
- 銀行口座や保険などの財産整理
- 遺言書やエンディングノートの作成
- 葬儀やお墓に関する希望の整理
- 認知症や介護への備え
- 写真やSNSなどのデジタル情報の整理
- 家族に残したい想いやメッセージの整理
特に最近注目されているのが、デジタル終活です。スマートフォンやパソコンの中には、大切なデータや契約情報が数多く含まれています。何も準備しないままだと、家族がアクセスできず困るケースも増えています。
また、終活の「やること」を自分で整理しておくと、家族に負担をかけずに済むという安心感も得られます。
こんな失敗も多いです。
- 「何から手をつけていいか分からないまま放置」
- 「やろうと思っていたけど、体調を崩して進められなかった」
- 「家族に伝えていなかったことで、のちのちトラブルになった」
これを防ぐためには、全体像を早めに把握して、少しずつ着手していくのがポイントです。
当会が提供する「心託(しんたく)サービス」では、終活に関するあらゆるお困りごとを総合的にご支援いたします。ぜひ私たちにお任せください!
1.2 終活を始めるメリットと背景
終活という言葉が広く知られるようになったのは、ここ10年ほどのことです。高齢化社会が進む中で、「自分のことは自分で決めておきたい」という意識が高まり、多くの人が前向きに終活に取り組むようになっています。
では、終活を始めることでどんなメリットがあるのでしょうか?
主なメリットは次の3つです。
1. 家族の負担を大きく減らせる
亡くなったあとの手続きは、想像以上に多く、煩雑です。銀行口座の解約、相続の手続き、葬儀の手配…。何も情報がない状態だと、家族は膨大な時間と手間をかけることになります。
あらかじめ整理しておけば、そうした負担を軽減できます。
2. トラブルを防げる
相続や財産分与でよくあるのが、親族間のトラブルです。たとえば「誰が何を相続するか」が明確でないと、感情的な争いが起こることも。
終活で遺言書や希望を書き残しておけば、「あとで揉める」ことを回避できます。
3. 自分らしい最期を迎えられる
医療や介護、葬儀に対する希望を明確にしておくことで、「自分らしい人生の締めくくり」が実現できます。
特に、延命治療を受けるかどうか、介護施設に入るかどうかといった判断は、事前に希望を残しておくことがとても大切です。
こんな日常シーンがイメージしやすいかもしれません。
- 忙しい家族が、仕事と両立しながら葬儀の準備に追われてしまう
- 銀行口座がわからず、預金の手続きが数か月かかる
- 親が望んでいた介護の形を知らず、本人も家族も不安な時間を過ごす
こういった状況を防ぐためにも、終活は「いつか」ではなく「今」から取り組むべきテーマになってきています。
2. 終活でやるべき10のことをリストで紹介

2.1 財産・相続に関するやること
(資産整理、遺言書作成、相続税対策など)
終活の中でも、特に大きなテーマとなるのが「財産と相続」に関する準備です。
この分野は手続きも多く、何もせずに放置しておくと、家族の手間やトラブルの原因になりやすい部分でもあります。
財産と相続のやることには、主に次の3つがあります。
1. 銀行口座や金融資産の整理
複数の銀行口座を持っている人も多いですが、実際に使っているのは1〜2つということがよくあります。使っていない口座や古い通帳を整理し、どの口座に何があるかをリスト化しておくことが大事です。
また、株式や投資信託、保険商品なども契約内容を明確にしておきましょう。これにより、相続人がすぐに把握できるようになります。
2. 財産目録の作成
「何をどれだけ持っているのか」を一覧にまとめる作業です。これは相続の際に非常に役立ちます。
主な対象は以下の通りです:
- 現金・預金
- 株式・債券・投資信託などの有価証券
- 不動産(土地・建物)
- 貴金属や美術品などの資産価値があるもの
- 借入金や未払金などの負債
財産目録があると、遺産分割協議もスムーズに進めやすくなります。
3. 遺言書の作成
「誰に何をどのように渡すか」を明確にしておくのが遺言書です。
遺言書があるだけで、相続の手続きが大幅に簡略化されますし、法的トラブルも防げます。
ただし、手書きの「自筆証書遺言」には法律上のルールがあります。内容が不備だと無効になるケースもあるため、必要に応じて専門家に確認するのがおすすめです。
こんな失敗がよくあります:
- 複数の通帳が見つからず、相続手続きが止まってしまった
- 不動産の登記名義が古いままで、スムーズに移転できなかった
- 借金があることを家族が知らず、相続放棄の判断が遅れてしまった
こうした事態を防ぐには、元気なうちに「財産と相続」の全体像を整理しておくことが大切です。
2.2 生活・医療に関するやること
(医療・介護の希望、連絡先の整理、エンディングノートなど)
終活では、財産や相続の準備だけでなく、生活の質や医療に関する希望を明確にしておくことも大切です。
突然の病気や事故など、万が一のときに備えて「自分の意思をどう伝えるか」は、家族にとっても非常に重要な情報になります。
ここでは、生活・医療に関するやることを3つに分けて紹介します。
1. エンディングノートの作成
エンディングノートは、終活の土台とも言える存在です。
法的効力はありませんが、自分の考えや希望、連絡先などを自由に書き残すことができます。
記載しておくとよい内容には、次のようなものがあります:
- 医療・介護の希望(延命治療の有無など)
- 自分史や大切な思い出
- ペットの世話について
- 家族や友人へのメッセージ
- 緊急時の連絡先や保管している書類の場所
エンディングノートがあれば、家族も判断に迷わずにすみます。
2. 医療・介護についての希望整理
延命治療や認知症のリスクについて考えるのは、なかなか気が重いかもしれません。
でも、もし判断ができない状況になったとき、「事前に希望を伝えておくこと」は本人と家族双方の安心につながります。
よくある選択項目は:
- 延命治療を希望するかどうか
- 介護施設に入る希望の有無
- 自宅で最期を迎えたいか、病院を希望するか
- 医療行為に関して同意する人(代理人)の指名
判断が必要な局面で家族が迷わないよう、書面で残しておくと安心です。
3. 緊急時の連絡先や重要情報の整理
突然突然の入院や事故など、緊急時の備えも欠かせません。
こんな内容をまとめておくのがおすすめです。
- 主治医やかかりつけ病院の情報
- 健康保険証や医療保険の詳細
- 家族・親族の連絡先
- 通帳や保険証券など大切な書類の保管場所
とっさのとき、すぐに情報が取り出せるだけで家族の不安がぐっと減ります。
また、入院や手術の際に保証人がいない場合は注意が必要です。
保証人が立てられない場合でも、以下のような対処法があります。
- 医療ソーシャルワーカーへの相談
病院内にいる医療ソーシャルワーカーは、保証人に代わる制度や支援先についてアドバイスしてくれます。
生活保護や福祉サービスの活用も含め、行政との連携もサポートしてくれます。 - 身元保証サービスの利用
専門の身元保証会社に依頼することで、保証人がいない場合でも入院や手術が可能になるケースがあります。
費用や契約内容は事前にしっかり確認しましょう。 - 任意後見制度や公的な制度の活用
弁護士や司法書士に相談し、将来に備えて任意後見契約を結ぶ方法もあります。
信頼できる第三者に手続きを委ねることで、安心して医療を受けられる環境を整えられます。
失敗しやすいパターンはこちらです:
- 医療・介護の希望が家族に伝わっていなかった
- エンディングノートの存在を誰も知らず見つけられなかった
- 緊急時の連絡先が整理されておらず、必要な手続きが滞った
このような事態を避けるためにも、「もしも」に備えた情報整理を今のうちに進めておきましょう。
2.3 葬儀・人間関係・想いに関するやること
(葬儀・お墓の準備、人間関係の整理、やりたいことリストなど)
終活では「亡くなったあとのこと」や「大切な人とのつながり」も大きなテーマです。
葬儀やお墓の準備だけでなく、人間関係や感謝の気持ちを整理しておくことも、終活の大切なやることのひとつです。
ここでは、以下の3つの観点から詳しく紹介します。
1. 葬儀やお墓に関する希望の整理
葬儀の形式や埋葬方法は、実に多様化しています。
自分が望む形をあらかじめ明記しておくことで、家族の悩みや負担を大きく軽減できます。
たとえば以下の内容を考えておくとよいでしょう:
- 葬儀のスタイル(家族葬、一般葬、無宗教葬など)
- 参列者の範囲(家族のみか、友人・職場関係も含むか)
- お墓の場所(既にあるお墓か、樹木葬や納骨堂など)
- 費用の支払い方法や積立の有無
「自分の希望」を書き残すことで、家族が迷わず準備できます。
2. 人間関係の整理と連絡先リストの作成
長年の付き合いや疎遠になっている人間関係を整理することも、心の整理につながります。
終活をきっかけに、感謝の気持ちを伝えたり、関係を再構築したりすることもできます。
具体的にはこんな整理をおすすめします:
- 大切にしたい人・お世話になった人のリスト作成
- 自分が亡くなったときに連絡してほしい人のリスト
- 年賀状やメール、SNSのつながりの見直し
このリストは葬儀時の連絡にも役立つので、家族にもありがたい情報です。
3. やりたいことリストの作成(バケットリスト)
人生の終盤に向けて、「本当にやりたかったこと」に向き合うことも終活の大事な一歩です。
たとえば:
- 行ってみたかった場所に旅行する
- 親しい人に感謝の言葉を伝える
- 趣味にじっくり取り組む
- 未整理の写真や日記をまとめる
やりたいことをリストにして可視化することで、残りの時間をより充実させることができます。
よくある失敗も押さえておきましょう。
- 葬儀の希望を伝えていなかったため、家族が不安や後悔を抱いた
- 埋葬方法やお墓の場所が未定で、手続きが長引いた
- 親しい人に何も伝えられないまま最期を迎えてしまった
このような後悔を防ぐためにも、想いや希望はできるだけ言葉や文書にして残しておくことが大切です。
3. 終活でやることを始めるベストなタイミングとは

3.1 早めに始めるべき理由
終活というと、「もっと年を取ってから始めればいい」と思っていませんか?
実はそれ、大きな誤解です。
終活は「まだ元気なうち」に始めるのがベストタイミングなんです。
その理由は大きく3つあります。
1. 判断力と体力があるうちに進められる
終活では、財産の整理や医療の希望を決めるなど、たくさんの判断が必要になります。
判断力が衰えたり、体調が思わしくなくなってからでは、冷静に進めるのが難しくなってしまうんです。
たとえば、遺言書の内容を考えたり、資産をリストアップしたりする作業は、頭も手間も使います。
だからこそ、気力・体力ともに余裕のある時期に始めておくと、無理なく進められます。
2. 家族とのコミュニケーションがとりやすい
終活で大切なのは、家族と話し合っておくこと。
どんな介護を望むか、誰に何を相続させるかなど、家族にしっかり伝えておけば、トラブルを避けられます。
しかし、病気や高齢になると話し合う機会や時間が限られ、意思疎通が難しくなることも。
まだ元気なうちに「終活のやること」を共有しておけば、家族も安心できます。
3. 時間をかけて少しずつ進められる
終活は一気にやるものではありません。やることが多いため、時間をかけてコツコツと進めるのが理想です。
早めに始めておけば、忙しい日常の中でも少しずつ取り組めますし、「まだ間に合う」という安心感も生まれます。
3.2 年齢やライフイベント別の目安
終活を始めるタイミングは「何歳から」と決まっているわけではありません。
ですが、人生の節目やライフイベントをきっかけにスタートする人が多いのが特徴です。
ここでは、年齢層やライフイベント別に、終活を始めるおすすめの目安をご紹介します。
60代:退職を機に人生を見つめ直す時期
定年退職や仕事の区切りを迎えるタイミングは、終活にとって最適なスタートポイントです。
時間にも余裕ができ、生活環境も変わるので、落ち着いて取り組みやすいのがメリットです。
この時期にやっておきたいのは:
- エンディングノートの作成
- 財産目録の整理
- 医療や介護の希望をまとめる
退職金の受け取り後は資産の把握もしやすく、相続対策にも取りかかりやすいです。
50代:親の介護や相続を経験し、自分事として考え始める時期
この年代では、「親の介護」「親の相続」を通じて終活の大切さに気づく人が増えてきます。
自分自身の将来を意識するきっかけにもなりやすい時期です。
おすすめの取り組み:
- 自分が所有する不動産や口座の整理
- 家族との情報共有を開始
- 終活セミナーや相談窓口の利用
忙しい世代ではありますが、早めに準備しておくことで後々ラクになるというメリットがあります。
40代:まだ早いと思われがちでも、意識しておくと安心
40代で終活を考える人は少数派かもしれませんが、スマホやネットバンキングなどデジタル遺産が増える世代です。
突然の病気や事故に備えて、最低限の情報整理をしておくと安心です。
この時期におすすめの取り組み:
- パスワードや契約中のサブスクの一覧作成
- 家族や子どもへの伝えたいことの記録
- 医療や介護についての基本的な考えの整理
【ライフイベント別のきっかけ例】
| ライフイベント | 終活スタートのチャンス |
| 定年退職 | 時間と気持ちに余裕ができるため取り組みやすい |
| 子どもの独立 | 人生の第2章として見直すタイミング |
| 病気・入院の経験 | 自分の健康に向き合うことで意識が変わる |
| 親の介護や他界 | 相続・遺言・施設選びなどの現実的な問題に直面 |
| 住み替えや不動産整理 | 物理的な整理の延長として終活を考えやすい |
「まだ早い」と思ううちが、実は一番始めやすい時期です。
3.3 家族とタイミングを合わせるコツ
終活は家族と連携して進めることで、情報の行き違いやトラブルを防ぎやすくなります。自然な形で共有できる工夫が大切です。
話しやすくするコツ:
- 雑談の延長で話題を出す:「最近終活ってよく聞くね」とさりげなく
- 一緒に考える姿勢で伝える:「どう思う?」と相談スタイルに
- 書類やノートを見せながら共有:メモやノートを活用し見える化
家族と共有しておくと良い情報:
- 預金口座や保険などの保管場所
- 医療・介護・葬儀の希望内容
- 緊急連絡先や重要なパスワードの管理情報
小さなきっかけを逃さず、家族とこまめに共有するのが安心につながります。
4. 終活のやることを日常で自然に取り入れる工夫
4.1 忙しい朝や外出前のちょっとした時間活用
終活は、忙しい日々の中でも「1日5分」あれば少しずつ進められます。まとまった時間がなくても、スキマ時間を活用する工夫で着実に前進できます。
おすすめの取り組み:
- 朝のコーヒータイムにノート1項目だけ記入
- 通勤前に1つの書類をチェック・仕分け
- 寝る前にスマホのメモアプリで気づきを記録
活用しやすいツール・方法:
- エンディングノートやチェックリストを枕元や机に置いておく
- スマホのリマインダーで週1の終活タイムを設定
- 無理に完璧を目指さず「少しだけでもOK」と考えること
「少しずつ積み重ねる」が終活を続ける最大のコツです。
4.2 家族間で情報確認しながら進める場面
終活は家族に関わることが多いため、一緒に進めることが大切です。自然な会話や日常の行動に取り入れていくと、共有がスムーズになります。
情報共有に適したタイミング:
- 食事中の雑談で軽く話題を出す:「この前終活の話聞いたんだけど…」など
- 書類整理のついでに一緒に確認:通帳や保険証券の場所を見ながら説明
- LINEやメールで簡単に共有:ノートの写真やメモを送るだけでもOK
家族と確認しておきたい内容:
- 財産や保険の場所と内容
- 医療・介護の希望や対応者
- パスワードや重要情報の保管先
「話す」「見せる」「共有する」の3ステップが、終活成功のカギです。
4.3 行事や節目に合わせた取り組み
終活は、年中行事や人生の節目に合わせて行うと自然に進めやすくなります。時間の確保もしやすく、家族との話し合いのきっかけにもなります。
終活に適したタイミング例:
- 年末年始・お盆など家族が集まる時期
- 誕生日や退職などの人生の区切り
- 引っ越し・大掃除など物理的整理がしやすいとき
このタイミングでやるべきこと:
- エンディングノートや財産リストの記入・見直し
- 家族に希望や情報を共有する時間を持つ
- 書類の保管場所や不用品の仕分けをする
「この機会にやってみようかな」が、終活スタートの一歩です。
5. 終活のやることを効率よく進めるためのガイド
5.1 スケジュールの目安と優先順位
終活は、一度に全部やろうとせず、段階的にスケジュールを立てて進めるのがコツです。やることに優先順位をつけることで、効率よく進められます。
進め方の3ステップ:
- 準備期(1〜2か月):ノートを用意し、やることを書き出す
- 実行期(3〜6か月):財産整理・医療希望の記入・家族との共有
- 見直し期(年1回):情報の更新と家族への再確認
優先すべき項目トップ3:
- 財産と重要書類の整理
- エンディングノートの記入
- 医療・介護の希望の明文化
「優先度の高いことから、小さく始める」ことが成功の秘訣です。
5.2 チェックリスト形式での進捗管理法
終活のやることは多岐にわたるため、チェックリストを使って管理すると進み具合が明確になります。
進捗が「見える化」されることで、モチベーションも維持しやすくなります。
チェックリストの活用ポイント:
- 「完了」「未完了」を分けて一覧にする
- 優先度や予定時期も一緒に記入する
- 家族と共有できる形(コピーやデジタル)で作成
よく入れる項目例:
- 財産・通帳・保険の整理
- 医療・介護・葬儀の希望記入
- 遺言書やエンディングノートの完成
- 重要書類の保管場所と連絡先の確認
「やったこと」が見えると、終活がぐっと前に進みます。
5.3 家族や周囲を巻き込むコツ
終活はひとりで抱え込まず、家族や信頼できる人を巻き込んで進めることが安心への第一歩です。小さな共有から始めて、自然な形で協力を得ましょう。
巻き込みやすい工夫:
- 相談スタイルで話す:「ちょっと相談したいことがあるんだけど…」
- 情報を小分けにして共有:通帳の場所だけ、介護の希望だけなど
- ノートや一覧表を見せながら説明:視覚的に伝えると理解しやすい
協力をお願いしたい場面:
- 遺言書や財産リストの確認
- 医療・介護の希望についての話し合い
- 緊急連絡先や手続きの代理確認
「自分のため」だけでなく「家族のため」でもあると伝えると、協力が得やすくなります。
6. 終活のやることまとめ
終活にはさまざまな「やること」がありますが、大切なのは早めに少しずつ始めることです。
自分の意思を整理し、家族と共有することで、将来の不安がグッと減ります。
この記事で紹介した主なポイント:
- 財産・医療・葬儀などの情報を事前に整理しておくことが大切
- 家族と一緒に考え、タイミングを見て共有することが成功のコツ
- スキマ時間や行事の節目を活かして少しずつ進める
- チェックリストやノートを使って「見える化」すると継続しやすい
「やることリスト」を作って、小さな一歩から始めてみましょう。
終活の準備なら終活協議会にお任せください
終活に関する不安や悩みは、早めに専門家へ相談するのが安心です。エンディングノートや相続の進め方など幅広くサポートしています。
終活のプロに相談したい方は「終活協議会」のホームページをご覧ください。
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 エンディングノート2025年9月11日終活でやるべきことリスト|家族も安心の始め方
エンディングノート2025年9月11日終活でやるべきことリスト|家族も安心の始め方 エンディングノート2025年9月4日終活サポートとは?内容とメリットをわかりやすく解説
エンディングノート2025年9月4日終活サポートとは?内容とメリットをわかりやすく解説 遺言2025年8月28日遺言書作成は誰に依頼すべき?メリットと選び方を解説
遺言2025年8月28日遺言書作成は誰に依頼すべき?メリットと選び方を解説 相続2025年8月21日相続手続きの代行とは?依頼のメリットと費用の全体像を徹底解説
相続2025年8月21日相続手続きの代行とは?依頼のメリットと費用の全体像を徹底解説
この記事をシェアする