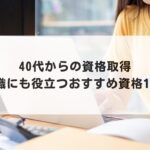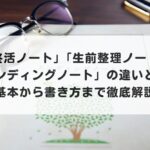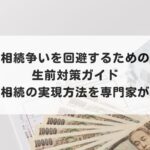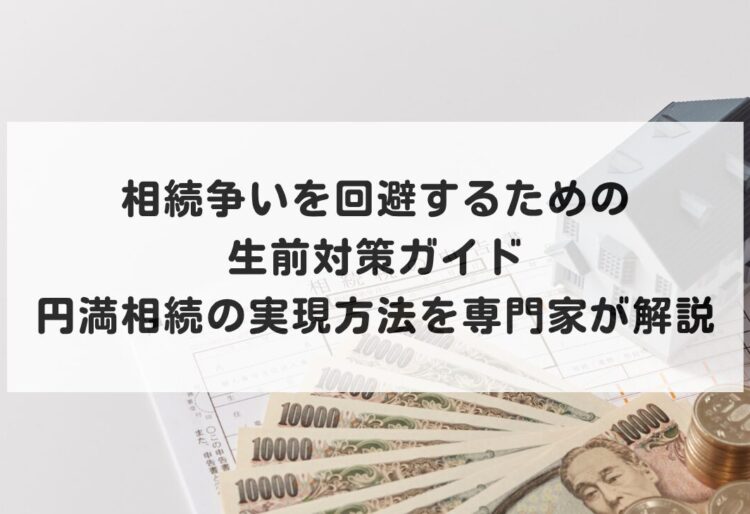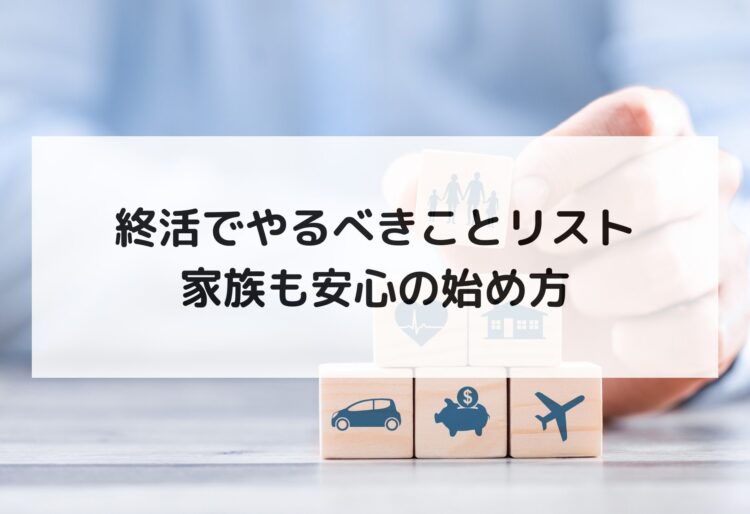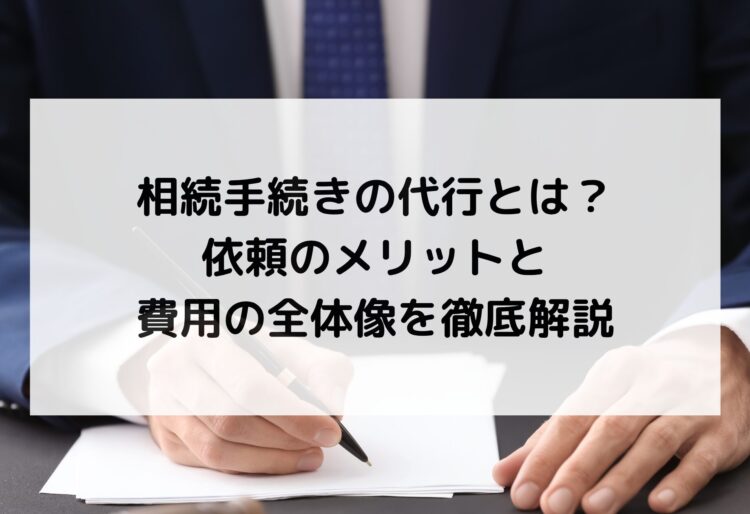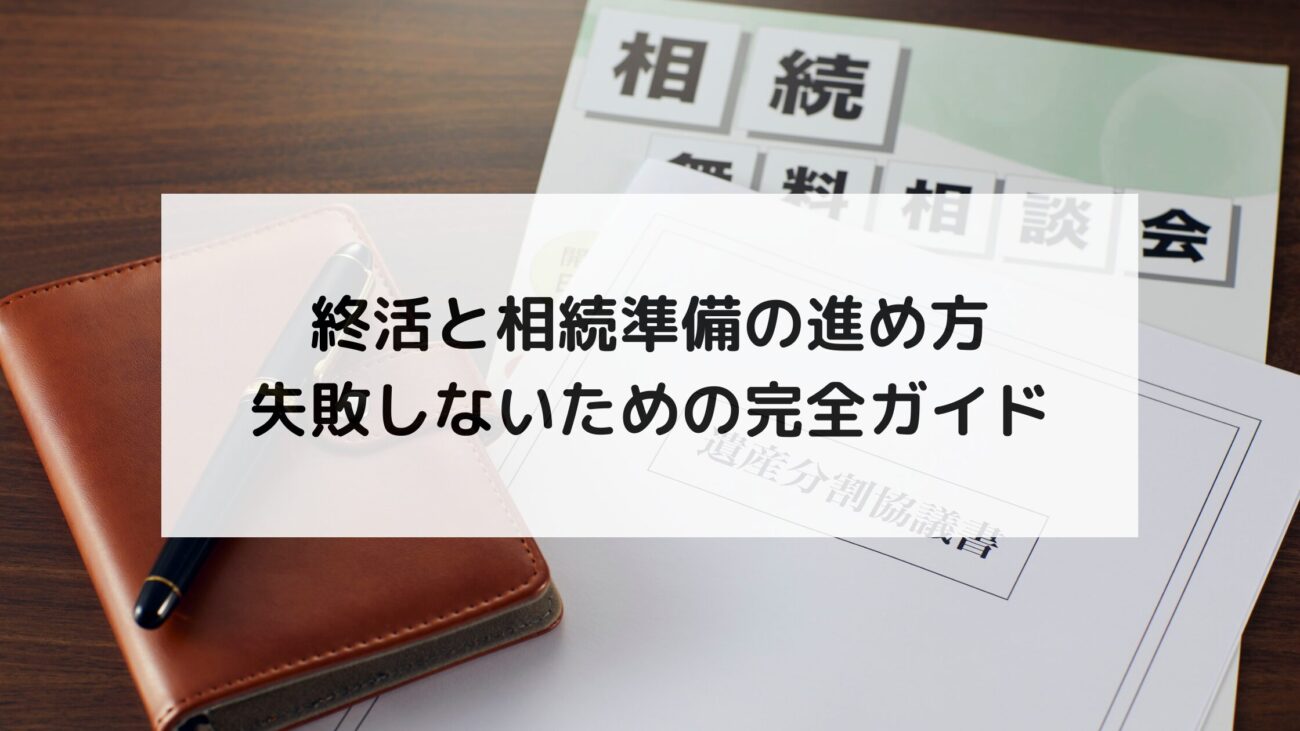
目次
1. 終活と相続準備の基本を知ろう

1.1 終活とは?今注目される理由
「終活」という言葉、最近よく耳にしませんか?
ニュースや雑誌でも取り上げられる機会が増え、関心を持つ人が年々増えています。
終活とは、「人生の終わりをより良く迎えるための準備」のこと。
財産や医療・介護のこと、葬儀の希望など、自分の思いを整理しておく活動です。
自分の意思を事前に整理しておくことで、家族にかかる負担を減らし、後悔のない最期を迎えやすくなります。
近年、終活が注目されている背景には以下のような社会的変化があります。
たとえばこんな理由があります:
- 高齢化の進行により、老後の生活や死後の手続きへの不安が増加している
- 家族構成の多様化により、「自分のことは自分で決めたい」という意識が強くなっている
- 遺された家族のトラブルや手続きの煩雑さを避けたいと考える人が増えている
また、こんなシーンを想像してみてください。
「毎日を元気に過ごしているけれど、ふとした瞬間に“もしものとき”のことが気になる」
「子どもたちには負担をかけたくないけど、どうやって準備を始めればいいのかわからない」
そんな不安を抱えた方が、エンディングノートを書いたり、専門家に相談することで安心感を得られるケースが増えています。
一方で、終活を始めるにあたってよくある誤解やつまずきポイントもあります。
よくある失敗はこちらです:
- 「まだ元気だから必要ない」と先延ばししてしまう
- 葬儀やお墓のことだけを終活だと思い込み、財産や医療のことを後回しにしてしまう
- 家族に何も伝えずに準備を進め、気持ちのズレが生じてしまう
こうした失敗を防ぐには、「終活=人生を前向きに見つめ直す機会」と捉えるのがポイント。
終活はネガティブなものではなく、自分らしく生きるための“前向きな整理”なのです。
1.2 相続準備とは?放置すると起こるトラブル
相続準備と聞くと、「お金持ちや資産家だけの話」と思っていませんか?
でも実は、不動産や預金が少しでもあれば、相続トラブルの火種になることもあるんです。
相続準備とは、亡くなった後に残された家族がスムーズに遺産を受け取れるよう、必要な手続きを整えておくこと。
具体的には、財産のリストアップ、分け方の希望、遺言書の作成、名義変更の準備などが含まれます。
準備を怠ると、こんな問題が起こりやすくなります。
よくあるトラブルはこちらです:
- 遺産分割でもめる
- 誰がどの財産を引き継ぐか決まらず手続きが長引く
- 税金や名義変更が期限内にできず、余計な費用が発生する
たとえば、現金よりも不動産が多いケースでは「誰が住むのか?どう分けるのか?」という問題が生じがち。
話し合いがまとまらず、何年も手続きが進まないという例も珍しくありません。
また、日常生活に追われて準備を後回しにしてしまうと、以下のような負担が家族にのしかかります。
- 必要な書類がどこにあるかわからない
- 故人の意向が不明で決断に迷う
- 相続税の申告期限に間に合わない
忙しい日々の中で、急にこれらの対応を求められるのは大きなストレスになります。
だからこそ、「まだ大丈夫」と思っている今こそが、相続準備のベストタイミングなんです。
ちなみに相続準備は、一度に完璧に整えなくてもOK。
少しずつ始めることで、気づけば家族に安心を残せる形が見えてきます。
1.3 終活と相続はどうつながっているのか
終活と相続は、別々のもののように感じられるかもしれません。
でも実は、この2つは切っても切れない深いつながりがあります。
終活は「人生の整理整頓」、相続は「その後の手続きをスムーズに進めるための橋渡し」です。
つまり、終活でやっておくことが、そのまま“相続準備”に直結していくのです。
たとえば、次のような終活のステップが、そのまま相続対策にもなります。
主な連動ポイントはこちらです:
- 財産をリスト化する → 相続人が財産内容を把握しやすくなる
- 遺言書を用意する → 財産分割のトラブルを未然に防げる
- エンディングノートで意志を伝える → 医療・介護・葬儀の希望が明確になり、家族の判断がラクになる
終活をしている人の多くは、「家族に迷惑をかけたくない」という気持ちから始めています。
そしてその思いが、結果として相続トラブルの予防や、家族関係の円満維持につながるんです。
こんな場面もあります。
「財産はたいしてないから準備はいらない」と思っていたけれど、実際には銀行口座や保険、不動産などが複雑に絡んでいた。
その情報が残されていなければ、家族は一から調べ直すことになり、大きな負担を抱えてしまいます。
逆に、きちんと終活を進めていた場合、相続手続きはスムーズで、わずか数週間で完了することもあります。
「終活=相続準備の第一歩」と考えると、今すぐ始める理由が見えてきます。
2. 終活でやっておきたい準備一覧
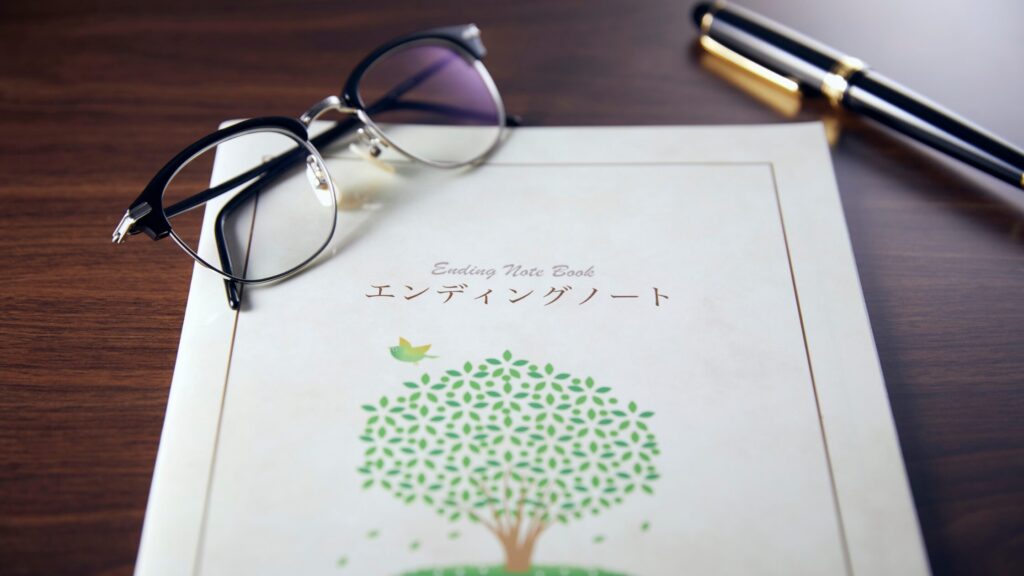
2.1 エンディングノートの活用方法
終活を始めるなら、まず手に取ってほしいのが「エンディングノート」です。
これは、自分の情報や希望を自由に書き込める“人生のまとめノート”のようなもの。
法的な効力はないものの、自分の思いを家族に伝えるための大切なツールとして、多くの人が利用しています。
エンディングノートに書ける主な内容は以下のとおりです。
たとえば、こんなことを書き込めます:
- 基本情報(氏名・生年月日・連絡先など)
- 医療や介護の希望(延命治療の有無、施設希望など)
- 財産の一覧(預金口座、不動産、保険、借入など)
- 葬儀やお墓に関する希望
- 相続に関する考え(遺言の有無、分け方の希望など)
- 感謝の言葉やメッセージ
このノートがあることで、家族が「何をどうすればいいか」が一目でわかるようになります。
とくに、葬儀の希望や財産の場所などが書かれていると、手続きが格段にスムーズになります。
一方で、書き始める際によくあるつまずきもあります。
こんな失敗に気をつけましょう:
- 項目が多くて途中で書くのをやめてしまう
- 書いたことに満足して、そのまま更新せず放置
- 家族にノートの存在を伝えず、結局活用されなかった
このような失敗を避けるためには、次のポイントを押さえておくと安心です。
エンディングノートを活かすコツ:
- 最初から完璧を目指さず、気になるページから少しずつ書く
- 年に1回は見直しをして、情報を更新する
- 書いたことを家族に伝えておく(保管場所も明確に)
たとえば、「通帳はどこにある?」「保険って入ってたの?」といった質問が、ノートひとつで一気に解決できるのは大きなメリット。
エンディングノートは、自分のためでもあり、家族への思いやりでもあるんです。
エンディングノートについては、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事:エンディングノートには何を書く?基本の11項目や遺言書との違いを解説
一般社団法人 終活協議会では、資料請求をしてくださった方限定で、エンディングノートを無料でプレゼントしています。
詳細は以下をご確認ください。
2.2 財産の整理と見える化
終活を進めるうえで欠かせないのが、財産の整理と見える化です。
これは「何をどれだけ持っているか」を明確にする作業で、相続準備の土台になります。
なぜこれが大事かというと、財産が“見えない”ことで家族が混乱したり、相続トラブルが起きる原因になるからです。
まず、整理すべき財産の種類を見てみましょう。
確認しておきたい主な財産の項目:
- 預貯金(銀行口座、定期預金など)
- 不動産(自宅、土地、賃貸物件など)
- 株式・投資信託・債券などの金融資産
- 生命保険や年金
- 借金やローン(マイナスの財産も含む)
- その他の資産(貴金属、骨董品など)
これらを一覧表にしておくと、全体像が見えてきます。
特に、複数の銀行口座を持っている場合は、使っていない口座の解約も検討しましょう。
一方で、財産の整理でつまずくポイントも多くあります。
よくあるつまずきポイント:
- 口座や保険の情報を把握しきれず、抜け漏れが出る
- ネットバンキングや電子マネーなどの存在を家族が知らず、手続きができない
- 借金やローンなどの「マイナスの財産」を伏せたままにしてしまう
こうしたリスクを減らすには、「一覧にして残す」「定期的に見直す」「家族と共有する」の3点がカギです。
たとえば、スマートフォンのメモアプリやスプレッドシートを使って、資産を記録しておくのも有効。
ただし、セキュリティ管理やパスワードの伝達方法は慎重に決める必要があります。
また、負債がある場合も正直に記載することが大切です。
万が一それが知られないまま相続されてしまうと、相続人に不利益が出るおそれもあります。
また、入院や手術の際に保証人がいない場合は、事前に対策を考えておくことが大切です。
病院の医療ソーシャルワーカーへの相談や、公的福祉制度・身元保証サービスの活用など、いくつかの選択肢があります。
急な入院時に慌てないよう、専門家に相談して準備しておくと安心です。
財産の「見える化」は、将来のトラブルを未然に防ぐ最大の武器になります。
2.3 医療・介護の希望を伝える準備
終活の中でも見落とされがちなのが、医療や介護に関する希望を明確にすることです。
自分が話せなくなったときに「どんな治療を受けたいか」「どこで介護を受けたいか」を家族に伝えておくと、判断の負担を大きく減らせます。
とくに重要なのが、延命治療や認知症の進行時の対応、入院・施設の希望などです。
書いておくと安心なポイントはこちらです:
- 延命治療の希望(人工呼吸器、心臓マッサージの可否など)
- 介護が必要になったときの住まい(自宅・施設など)
- 誰に決定を任せたいか(医療代理人の指定)
- 医療費や介護費の支払い方法(保険や預金の活用)
これらの意思表示がないと、家族は「本当はどうしてほしかったのか…」と悩むことになります。
たとえば、本人が望んでいなかった延命治療を行ってしまったことで、家族に後悔が残るケースも少なくありません。
また、準備が不十分なまま介護が必要になると、こんな困りごとが起きやすくなります。
よくある失敗や悩み:
- 誰が介護を担当するかでもめる
- 自宅か施設かで家族間の意見が分かれる
- 介護費用がいくら必要か分からず、不安が増す
こうしたトラブルを避けるためには、自分の考えを早めに整理し、それを家族に共有することが大切です。
最近では「事前指示書(リビングウィル)」や「尊厳死宣言書」といった書類を使って、医療や介護の意向を明文化する人も増えています。
また、エンディングノートに記載するだけでも、十分に意思を伝える手段になります。
家族で話し合うタイミングがなかなか見つからない場合は、「最近こういうことを考えていて…」という切り口で話を始めてみるとスムーズです。
自分の人生の最期を“自分らしく”するためには、医療・介護の希望をきちんと伝えておくことがとても大切です。
3. 相続準備で押さえるべき3つのポイント

3.1 遺言書の種類と選び方
相続トラブルを防ぐうえで、最も確実な対策が「遺言書の作成」です。
遺言書があるだけで、遺産分割の手続きがスムーズになり、相続人の混乱や争いを避けられます。
まず知っておきたいのが、遺言書にはいくつか種類があることです。
代表的な遺言書の種類:
- 自筆証書遺言
→ 全文を自分で手書きする。費用がかからないが、形式不備による無効リスクあり。 - 公正証書遺言
→ 公証人に作成してもらう。費用はかかるが、形式が整い確実に効力を発揮する。 - 秘密証書遺言
→ 内容は秘密にできるが、あまり一般的ではなく利用者は少ない。
もっとも使われているのは「公正証書遺言」です。
専門家と一緒に作ることで法的ミスが防げ、万が一のときでも確実に執行されます。
一方で、遺言書作成にまつわる失敗もよくあります。
こんなミスが多いです:
- 自筆証書で書いたものの、日付や署名が不完全で無効になった
- 書いた内容があいまいで、解釈をめぐって家族がもめた
- 遺言書があることを誰にも伝えず、結局発見されなかった
これらを避けるには、次のポイントを意識しましょう。
遺言書作成のコツ:
- 自筆証書なら形式(全文手書き・日付・署名・押印)を必ず確認する
- 複数の財産がある場合は、具体的な配分を書いておく(例:「長男にA銀行の口座全額」など)
- 作成後は、信頼できる人や専門家に保管や存在を伝えておく
また、法務局による「自筆証書遺言の保管制度」を利用すれば、安全に保管しつつ、紛失や未発見のリスクも減らせます。
遺言書は、将来の安心を“書面でカタチにする”最強の相続対策です。
3.2 相続トラブルを防ぐための事前対策
家族間の相続トラブルは、金額の大小に関係なく起こりがちです。特に話し合いや準備が不十分な場合、感情的な対立に発展することも。
主な原因:
- 財産の配分に不公平感がある
- 不動産しかなく、現金化できずもめる
- 誰が介護したかへの評価に差がある
トラブルを避けるための事前対策:
- 遺言書の作成:分配方針を明確にする
- 財産の見える化:何がどこにあるかをリストに
- 生前贈与の活用:タイミングを分けて相続負担を減らす
- 家族信託の検討:認知症や判断力低下への備えに
注意点:
- 「話さなくても伝わる」は危険
- 感情よりも“公平さ”を重視
- 書面で残すことで誤解を防ぐ
事前の一手間が、家族の関係を守るカギになります。
3.3 家族で話し合うときのコツと注意点
終活や相続準備では、家族との話し合いが欠かせません。
ですが、「重い話」として避けられがちです。
よくある失敗:
- 急に深刻な話を切り出し、家族が構えてしまう
- 一方的な意見になり、対立が生まれる
- 準備を進めていても、家族が内容を知らず混乱する
話し合いをスムーズにするコツ:
- きっかけは日常会話から:「最近こんなニュース見て…」など自然に話す
- 想いを伝える:「迷惑をかけたくない」気持ちを伝えると受け入れられやすい
- 段階的に共有:すべてを一度に伝える必要はなし
- 書類を見せながら説明:エンディングノートなどを活用すると理解が深まる
注意点:
- 感情ではなく、目的(安心・準備)を中心に
- 家族の意見にも耳を傾ける
話し合いは、“準備”と同じくらい大切な終活の一部です。
4. 終活・相続準備のよくある失敗と対策
4.1 書類の不備や放置によるトラブル
終活や相続準備をしていても、書類の不備や放置によってせっかくの準備が無駄になるケースが少なくありません。
よくある失敗:
- 遺言書に日付や署名がなく、無効扱いに
- 書類の保管場所が不明で、家族が探し回る
- エンディングノートの内容が古く、実態と合わない
対策のポイント:
- 遺言書の形式を確認:自筆なら全文手書き・日付・署名が必須
- 保管場所を明確に:家族または専門家に伝える
- 年1回の見直し:財産や状況に変化があれば更新
- 重要書類を一元管理:保険、不動産、通帳などを一か所にまとめる
注意点:
- 書いて満足せず、“使われる状態”にしておくことが大事
- 専門家の確認を受けると安心
書類管理は、終活準備の“基礎”です。
4.2 家族と話さないまま準備を進めた失敗
終活や相続準備を進めても、家族と共有していなければトラブルの原因になります。
よくある失敗:
- 遺言内容に家族が驚き、不信感が生まれる
- 葬儀や介護の方針を誰にも伝えておらず、現場で混乱
- 準備の存在自体を家族が知らず、活用されなかった
共有不足を防ぐための工夫:
- 想いの背景を伝える:「家族に迷惑をかけたくない」など本音を言葉に
- 信頼できる人から共有:全員で話すのが難しい場合は一人からスタート
- ノートや資料を活用:言葉で伝えにくい内容は、書面にして補足
- 日常会話に混ぜて話題に:自然なタイミングで切り出すと抵抗が少ない
注意点:
- 独りよがりな準備は、かえって混乱の元になる
- 対話は「伝える」より「共有する」姿勢で
準備は“家族との連携”があってこそ意味があります。
4.3 知識不足による制度の見落とし
終活や相続準備で意外と多いのが、制度や法律に関する知識不足からくる失敗です。知らなかったことで大きな不利益を受けるケースも。
よくある見落とし:
- 相続税の対象になるとは思わず、申告が遅れて加算税が発生
- 遺言書があればすべて自由になると勘違い(遺留分の存在を知らない)
- 認知症発症後に財産管理ができず、困った
事前に知っておきたい制度:
- 相続税の基礎控除:遺産総額によっては課税対象になる
- 遺留分制度:一定の相続人には取り分が保証されている
- 成年後見制度・家族信託:認知症などで判断力が低下したときの備え
対策方法:
- 専門家(行政書士・司法書士・税理士など)に相談
- 信頼できる情報サイトや書籍で学ぶ
- セミナーや相談会を活用して正確な知識を得る
制度を正しく理解すれば、準備の質がグッと上がります。
5. 専門家と一緒に進める安心の終活サポート
5.1 終活のプロに相談するメリット
終活や相続準備を一人で進めるのは不安がつきもの。
そんなときは、終活のプロに相談することで安心して進められます。
相談するメリット:
- 知識の不足をカバーできる:制度・法律・書類の基本がわかる
- 書類作成がスムーズに:エンディングノートや遺言書を具体的に整えられる
- 家族との話し合いをサポート:第三者の立場で対話を円滑に
- 漏れやミスを防げる:財産整理・相続税対策などを抜けなくチェック
よくある相談内容:
- 財産の分け方のアドバイス
- 遺言書の内容チェック
- 相続トラブルの回避方法
- 認知症対策としての家族信託や後見制度の検討
専門家に相談すると、迷いや不安が一気に軽くなります。
自分に合った進め方を一緒に見つけてもらえるのが大きな魅力です。
5.2 相続・遺言のプロとの連携でスムーズに
相続や遺言に関する手続きは専門性が高く、プロと連携することでスムーズに進められます。
主な専門家とその役割:
- 司法書士:不動産の名義変更や遺言書の作成支援
- 行政書士:遺言書・エンディングノート作成のアドバイス
- 税理士:相続税の計算・申告をサポート
- 弁護士:トラブル発生時の交渉や対応を担当
連携するメリット:
- 書類の不備や形式ミスを回避できる
- 節税や分割方法の最適化が可能
- 万一のもめごとにも備えられる
- 家族との意思疎通にもプロが介在しやすくなる
こんな人におすすめ:
- 不動産や金融資産を複数持っている
- 相続人が複数いて配分に悩んでいる
- 遺言書を正式に残したい
プロの知恵を借りることで、トラブルを最小限に抑えられます。
5.3 終活協議会のサービス紹介と活用方法
終活協議会では、終活や相続準備をサポートする多彩なサービスを提供しています。
不安や疑問を抱える方にとって、心強い味方になります。
主なサービス内容:
- エンディングノートの書き方講座
- 無料相談窓口(電話・オンライン対応)
- 相続・遺言の個別サポート
- 家族信託や後見制度の説明会
- 専門家とのマッチング支援
活用するメリット:
- 自分に合った準備方法が見つかる
- 専門家の話を無料で聞けるチャンスがある
- 家族と一緒に学べるセミナーが充実
- 地域やライフスタイルに合わせた情報提供が受けられる
こんな人におすすめ:
- 何から始めればいいかわからない
- 家族と終活を共有したい
- 具体的な準備を始めたいが一人では不安
終活協議会を活用すれば、迷わず一歩を踏み出せます。
一般社団法人 終活協議会では、全国各地に1,400名以上の専門家ネットワーク(弁護士、司法書士、行政書士、税理士)があります。
お住まいの地域で信頼できる専門家をご紹介することが可能です。
相続に関するお悩みごとは、私たちにお任せください。
6. まとめ:終活と相続の準備は「今」がベストタイミング
終活や相続の準備は、「まだ早い」と思っているうちにタイミングを逃しがちです。
元気な今だからこそ、冷静に準備を進められます。
早めに動くメリット:
- 気持ちや体力に余裕があるうちに判断できる
- 家族と穏やかに話し合える時間を確保できる
- 財産や希望を丁寧に整理できる
- 認知症や病気のリスクに備えられる
よくある後悔:
- 「体調を崩してからでは話す余裕がなかった」
- 「もっと早く相談すればよかった」
- 「準備不足で家族に迷惑をかけてしまった」
おすすめの行動タイミング:
- 60代に入ったら少しずつ意識する
- 年末や誕生日などの節目で見直しをする
- 家族イベントの前後で自然に話す機会をつくる
“今”の行動が、将来の家族の安心をつくります。
終活の準備なら終活協議会にお任せください。
エンディングノートの書き方から相続相談まで、終活の悩みを幅広くサポート。
専門家と一緒に、安心できる未来を形にしませんか?
→一般社団法人 終活協議会の「心託(しんたく)サービス」について
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 資格取得2025年10月4日40代からの資格取得|転職にも役立つおすすめ資格10選
資格取得2025年10月4日40代からの資格取得|転職にも役立つおすすめ資格10選 エンディングノート2025年10月4日終活ノート・生前整理ノート・エンディングノートの違いとは?基本から書き方まで徹底解説
エンディングノート2025年10月4日終活ノート・生前整理ノート・エンディングノートの違いとは?基本から書き方まで徹底解説 相続2025年10月3日相続争いを回避するための生前対策ガイド|円満相続の実現方法を専門家が解説
相続2025年10月3日相続争いを回避するための生前対策ガイド|円満相続の実現方法を専門家が解説 デジタル終活2025年10月3日終活でSNSアカウントはどうする?死後のリスクと主要4大SNSの手続きを解説
デジタル終活2025年10月3日終活でSNSアカウントはどうする?死後のリスクと主要4大SNSの手続きを解説
この記事をシェアする