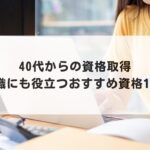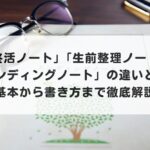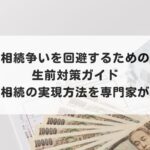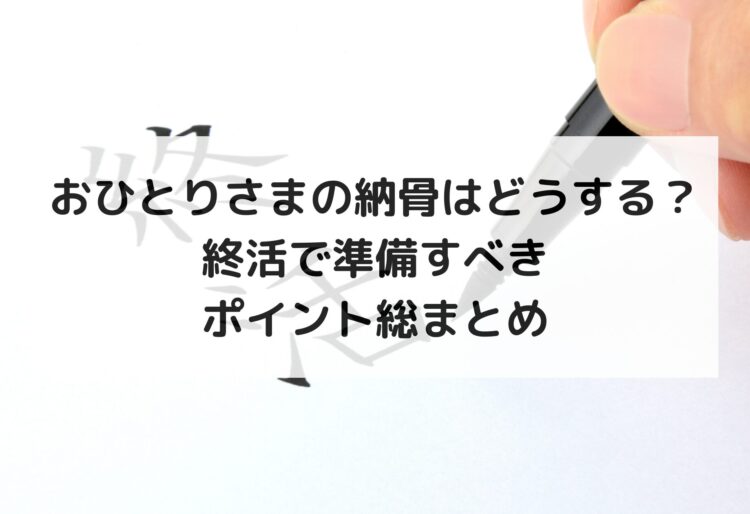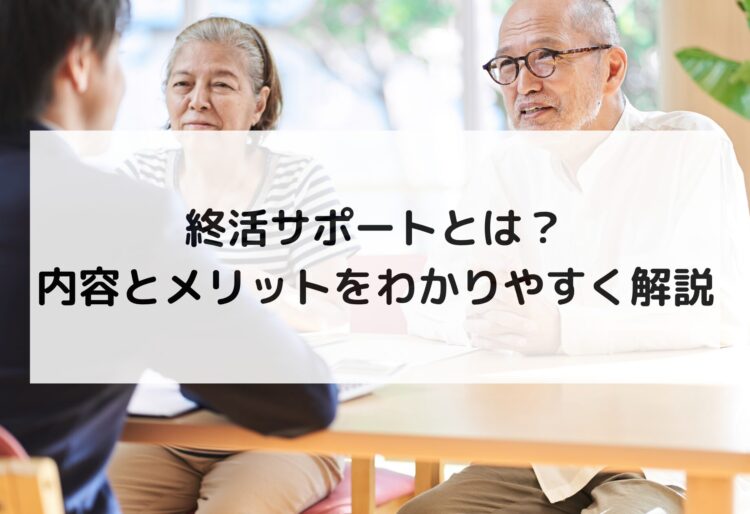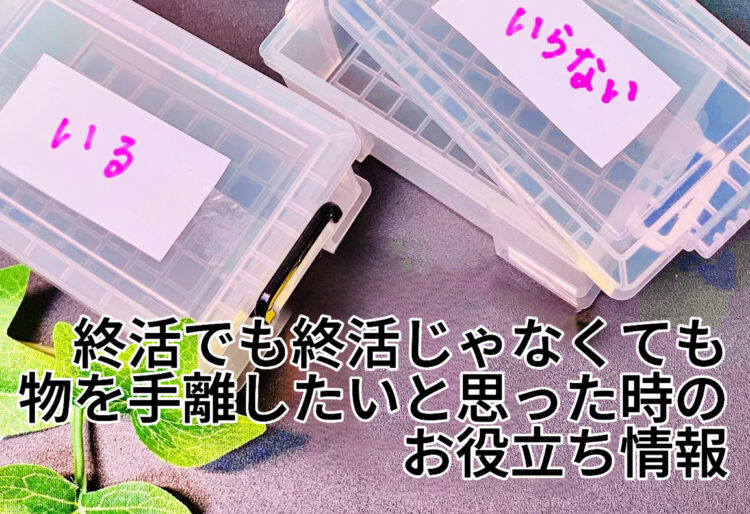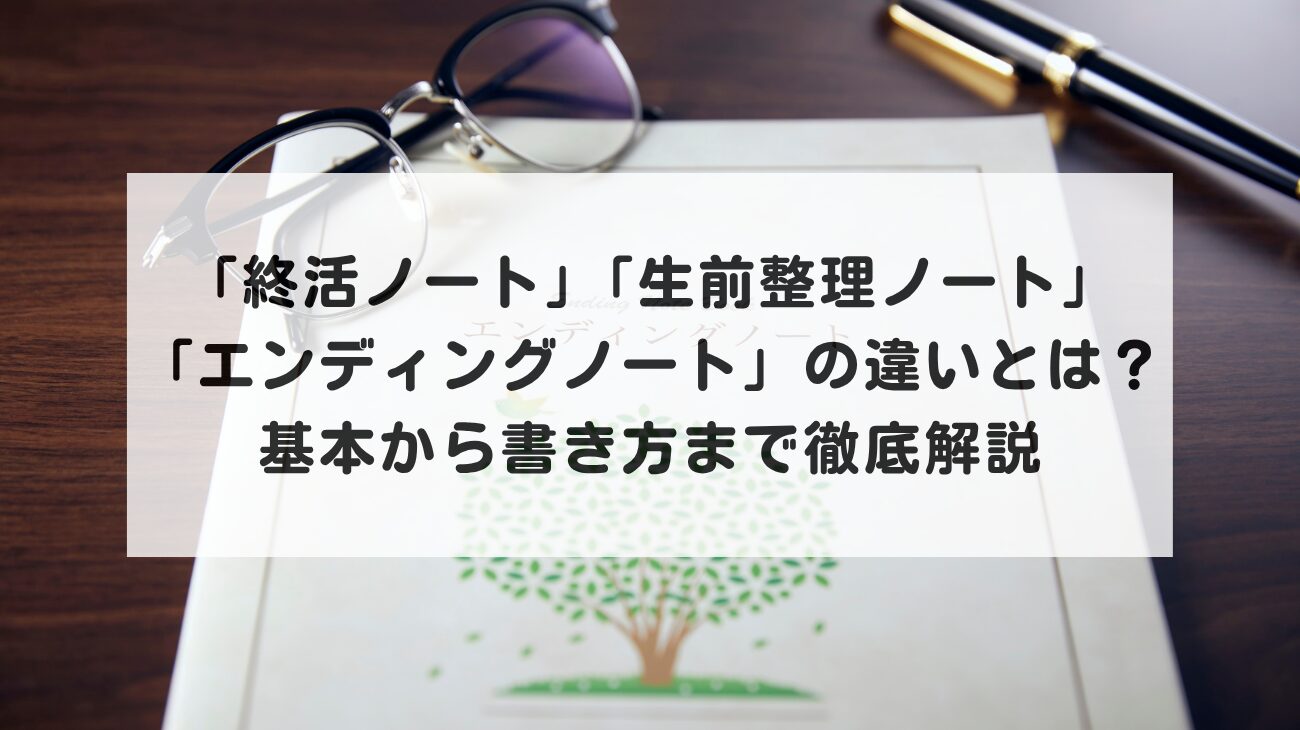
「そろそろ終活を…」と考え始めたとき、多くの方が「終活ノート」「生前整理ノート」「エンディングノート」といった言葉に出会うのではないでしょうか。
これらはよく似た言葉ですが、実はそれぞれ少しずつニュアンスや焦点が異なります。
それぞれの役割を理解すれば、ご自身に何が必要か、何から始めれば良いかが明確になります。
この記事では、それぞれのノートがどのようなものかを分かりやすく解説し、あなたの終活準備のスタートをサポートします。
終活協議会では、資料請求をした方にもれなくエンディングノートをプレゼント!
エンディングノートを受け取った方限定で、書き方を詳しく説明した動画も見ることができます。
分からない部分はお電話でのご相談も可能です。
少しでも終活に関するお悩みがあれば、まずは資料をご請求ください。
目次
「終活ノート」「生前整理ノート」「エンディングノート」とは?
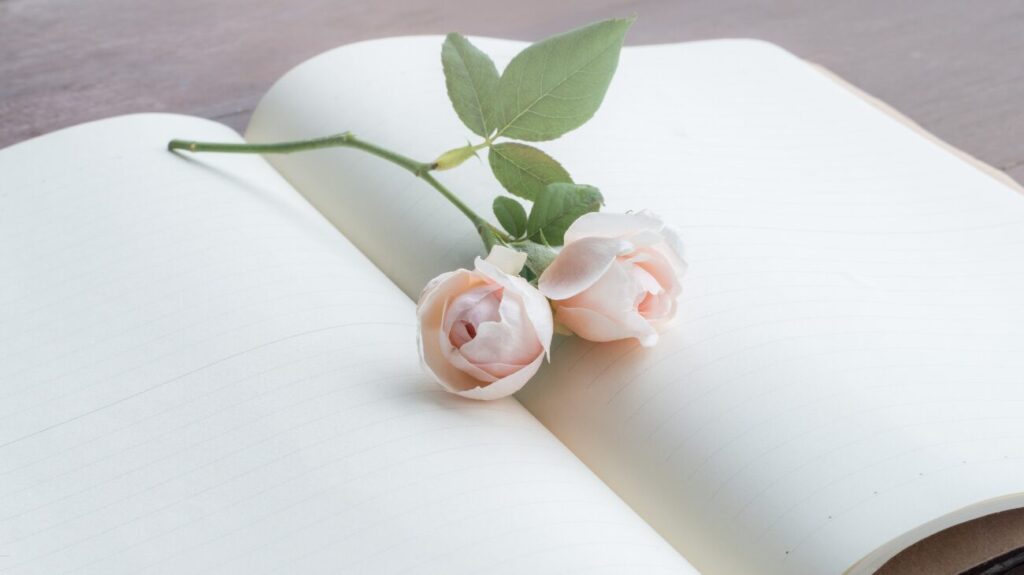
「終活ノート」:人生の終わりを考えるための広範なメモ
「終活ノート」は、その名の通り「終活」に関するあらゆる事柄を書き留めるための、最も広義なノートです。
特定の形式はなく、人生の終わりに向けて考えていること、準備しておきたいことなどを自由に記すための個人的なメモ帳と考えると分かりやすいでしょう。
例えば、理想の最期について、やりたいことリスト、お世話になった人への想い、財産の簡単なリストアップなど、頭に浮かんだことを整理するために使われます。
エンディングノートとほぼ同義で使われることも多いですが、「終活ノート」はより自分自身の思考整理や計画立案という側面に重きを置いた、自由度の高いノートと言えます。
「生前整理ノート」:モノや財産の整理に特化した記録
「生前整理ノート」は、終活の中でも特に「モノ」と「財産」の整理に特化したノートです。
自分が元気なうちに身の回りの品々を整理し、その記録を残すことを主な目的とします。
具体的には、家にある家具や衣類、骨董品などの処分方法の希望、誰に譲りたいか、また預貯金や不動産、有価証券といった財産の一覧などを記録します。
これにより、残された家族が遺品整理で困らないようにする、という実務的な側面に焦点が当てられています。
相続をスムーズに進めるための情報整理ノートとしての役割も大きく、物理的な片付けと並行して作成されることが多いのが特徴です。
家族の負担を具体的に減らしたいと考える方に適しています。
「エンディングノート」:想いや情報を家族に伝えるための総合ノート
「エンディングノート」は、これらの中で最も一般的で、総合的な内容を持つノートです。
最大の特徴は、「残される家族や大切な人へ、自分の想いや必要な情報を伝える」というコミュニケーションの側面に重きを置いている点です。
自分自身の基本情報から、財産リスト、医療や介護の希望、葬儀やお墓の希望、そして家族への感謝のメッセージまで、多岐にわたる項目が網羅的に用意されていることが多く、市販の製品も豊富です。
法的な効力はありませんが、万が一の時に家族が手続きや判断に困らないようにするための「引き継ぎ書」であり、感謝を伝える「最後の手紙」としての役割も果たします。
終活の全体像を把握し、バランスよく準備を進めたい方に最適な一冊と言えるでしょう。
「終活ノート」「生前整理ノート」「エンディングノート」の比較表
| 項目 | 終活ノート | 生前整理ノート | エンディングノート |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 人生の終わりを意識した自己の思考整理、計画立案 | モノや財産の物理的・情報的な整理、記録 | 家族への情報伝達、意思表示、想いを伝えること |
| 記載内容の焦点 | やりたいことリスト、自分史、漠然とした希望など自由 | 家財道具リスト、財産目録、処分方法の指定など実務的 | 医療・介護・葬儀の希望、連絡先、メッセージなど総合的 |
| 主な役割 | 自分自身のためのメモ・備忘録 | 遺品整理・相続を円滑にするための記録簿 | 家族のための引継ぎ書・手紙 |
| おすすめな人 | 何から始めるか考えたい、漠然とした不安を整理したい人 | 家の片付けや財産整理を具体的に進めたい人 | 家族に迷惑をかけたくない、想いをしっかり伝えたい人 |
3つのノートの目的・内容・使い方の違い

目的と役割の違い
比較表で示した通り、3つのノートは目的と役割に明確な違いがあります。
「終活ノート」は、いわば終活のスタート地点に立つための「自分との対話ノート」です。
これからどう生きたいか、何を準備すべきかを考えるためのもので、役割は自己完結的です。
一方、「生前整理ノート」は、より具体的なアクション、つまり「片付け」に連動した「記録ノート」です。
その役割は、物理的な整理をサポートし、家族が遺品整理に困らないようにすることにあります。
そして「エンディングノート」は、これらを含みつつも、最終的な目的を「家族への伝達」に置いた「引継ぎノート」です。
自分の意思を伝え、家族の精神的・実務的な負担を軽減するという、他者への配慮が最も強く意識されたノートと言えるでしょう。
主な記載内容の違い
記載内容の焦点も、それぞれの目的を反映しています。
「終活ノート」には、決まったフォーマットはなく、自分史や人生でやり残したことのリスト、大切な人への想いなど、内面的な事柄が多くなります。
「生前整理ノート」は非常に実務的で、家財のリスト、デジタル資産のID、銀行口座の一覧など、具体的な「モノ」と「カネ」に関する情報が中心です。
これに対し、「エンディングノート」は、これらの情報に加えて、延命治療の希望、葬儀で流してほしい音楽、ペットの世話のお願いといった、本人の「意思」や「希望」を伝える項目が充実しています。
つまり、情報(生前整理)と思考(終活)を統合し、そこに「想い」を加えて家族に伝えるのがエンディングノート、と整理することができます。
どのノートを選ぶべき?目的別おすすめガイド
「結局、自分はどれを選べばいいの?」と迷われるかもしれません。以下に、あなたの目的や状況に合わせたおすすめの選び方をご紹介します。
- 終活の第一歩として、まずは頭の中を整理したい方
→ まずは自由な「終活ノート」から始めてみましょう。普通の大学ノートに、気になること、不安なこと、やりたいことを書き出すだけで、考えがまとまりやすくなります。 - 家の片付けや、財産の整理を具体的に始めたい方
→ 「生前整理ノート」が最適です。整理したいモノのリストアップから始めることで、具体的な行動計画が立てやすくなります。 - 家族に迷惑をかけず、自分の想いをしっかり伝えたい方
→ 総合的な「エンディングノート」を選ぶのが最もおすすめです。市販のノートは項目が体系的に整理されているため、何を書けば良いか分かりやすく、抜け漏れなく情報を残せます。
多くの場合、「エンディングノート」は終活ノートや生前整理ノートの内容をカバーしているため、迷ったらまず「エンディングノート」を一冊手にとってみるのが良いでしょう。
書き進める中で、特に整理したい部分が見つかれば、その部分を深掘りしていくのが効率的な進め方です。
エンディングノートに書くべき必須項目リスト
エンディングノートを手に取っても、あまりに項目が多くてどこから書けば良いか戸惑ってしまうかもしれません。
しかし、すべてを一度に完璧に埋める必要はありません。
まずは書けるところから、少しずつ書き進めていくことが大切です。
ここでは、多くのエンディングノートに含まれている、特に重要性の高い必須項目をリストアップしてご紹介します。
ご自身のペースで、これらの項目を参考にしながら書き進めてみてください。
自分自身に関する基本情報
万が一の際、手続きを行う家族がまず必要とするのが、あなた自身の基本的な情報です。
意外と家族でも知らないことがあるため、正確にまとめておくと非常に助かります。
これはエンディングノートの基本の「き」と言える部分です。
- 氏名、生年月日、本籍地、マイナンバー
- 住所、連絡先(電話番号、メールアドレス)
- 血液型、持病、かかりつけ医、アレルギー情報
- 学歴、職歴、資格などの自分史
- 大切な人(家族、親戚、友人)の連絡先リスト
- 運転免許証、パスポート、健康保険証などの保管場所
資産・負債に関する情報(財産リスト)
お金に関する情報は、残された家族にとって最も重要かつデリケートな問題です。
どこに、何が、どれくらいあるのかを明確にしておくことで、手続きがスムーズに進み、相続に関するトラブルを未然に防ぐ助けになります。
ただし、暗証番号やパスワードそのものを直接書き込むのはセキュリティ上避け、別の方法で伝える工夫をしましょう。
- 預貯金(銀行名、支店名、口座番号、種類)
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 不動産(土地、建物)に関する情報
- 生命保険、損害保険などの保険契約情報
- 年金に関する情報(年金手帳の場所など)
- クレジットカード、各種ローンなどの負債情報
- 貸金庫の有無と場所
医療・介護に関する希望
もしもの時、あなたが自分の意思を伝えられなくなった場合、家族は非常に難しい判断を迫られます。
あなたの希望をあらかじめ書き記しておくことは、家族の精神的な負担を大きく和らげることにつながります。
これは、あなた自身の尊厳を守るためにも非常に重要な項目です。
- 延命治療の希望の有無(人工呼吸器、胃ろうなど)
- 病名や余命の告知を希望するかどうか
- 臓器提供(ドナーカードの有無)や献体の希望
- 希望する介護場所(自宅、施設など)
- 介護の方針に関する希望(大切にしてほしいことなど)
- かかりつけ医やケアマネージャーの連絡先
葬儀・お墓に関する希望
葬儀やお墓は、故人を偲ぶ大切な儀式ですが、残された家族にとっては費用面でも精神面でも大きな負担となりがちです。
あなたの希望を具体的に伝えておくことで、家族は迷わずに準備を進めることができます。
形式ばったものでなくても、「こんな風に見送ってほしい」という想いを伝えることが大切です。
- 希望する葬儀の形式(一般葬、家族葬、火葬のみなど)
- 希望する宗派や宗教
- 遺影に使ってほしい写真
- 葬儀に呼んでほしい人のリスト
- お墓に関する情報(場所、継承者など)
- 納骨や散骨など、遺骨の扱いに関する希望
- 葬儀社への連絡先や、互助会への加入状況
デジタル遺品(SNS・アカウント情報)の整理
現代において、パソコンやスマートフォンの中にあるデジタルデータは「デジタル遺品」と呼ばれ、その整理は非常に重要になっています。
オンラインサービスのアカウントやSNS、ネット銀行など、本人でなければ分からない情報も多く、放置するとトラブルの原因にもなりかねません。
IDやパスワードのありかを記し、死後に各アカウントをどうしてほしいか(解約、継続、追悼アカウント化など)を明記しておきましょう。
- パソコンやスマートフォンのログイン情報(ヒントなど)
- メールアドレスとパスワードの管理方法
- SNS(Facebook, X, Instagramなど)のアカウント情報と希望する対応
- ネット銀行やネット証券の口座情報
- 有料のサブスクリプションサービス一覧
- ブログやウェブサイトの管理情報
大切な人へのメッセージ
エンディングノートは、事務的な情報を伝えるだけでなく、あなたの「想い」を伝えるための大切なツールです。
普段は照れくさくて言えない感謝の言葉や、家族一人ひとりへのメッセージ、友人への想いなどを自分の言葉で綴りましょう。
このメッセージは、残された人々にとって何物にも代えがたい宝物となり、悲しみを乗り越える大きな力になるはずです。
遺言書には書けない、エンディングノートならではの最も温かい部分と言えるでしょう。
▼関連記事
エンディングノートには何を書く?基本の11項目や遺言書との違いを解説
最も重要な違い!エンディングノートと遺言書の法的効力
エンディングノートについて理解が深まると、次に必ず疑問に思うのが「遺言書とはどう違うのか?」という点です。
特に、財産に関する希望を書く上で、この二つの違いを正しく理解しておくことは非常に重要です。
結論から言うと、エンディングノートと遺言書を分ける最も決定的で重要な違いは、「法的効力」があるかないか、という一点に尽きます。
この違いが、それぞれの役割と書き方を大きく左右するのです。
法的効力とは?初心者にも分かりやすく解説
「法的効力」という言葉は、少し難しく聞こえるかもしれませんね。
簡単に言うと、「法律によってその内容の実現が強制される力」のことです。
例えば、法律で定められた形式に則って書かれた遺言書に「長男に自宅を相続させる」と記せば、それは法的な決定事項となり、他の相続人が反対してもその通りに手続きを進める義務が発生します。
これは遺言書が法律に守られた公的な力を持つ文書だからです。
一方で、エンディングノートに同じことを書いても、それはあくまで「お願い」や「希望」として扱われます。
家族がその想いを尊重してくれるかもしれませんが、法的に強制することはできません。
つまり、法的効力とは、あなたの意思を単なる「お願い」から、法律が後ろ盾となる「決定事項」へと変える力のことなのです。
目的・書ける内容・費用の比較表
| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |
|---|---|---|
| 法的効力 | なし(あくまでお願い・希望) | あり(財産の分け方などを法的に強制できる) |
| 目的 | 家族への想い、希望、情報伝達、負担軽減 | 相続財産の分配、相続トラブルの防止 |
| 書き方・形式 | 自由(市販ノート、自作、デジタルも可) | 法律で厳格に定められている(自筆証書、公正証書など) |
| 記載できる内容 | 制限なし(メッセージ、医療・介護の希望など自由) | 法律で定められた事項(相続、遺贈など)が中心 |
| 作成費用 | 無料~数千円程度 | 自筆なら安価。公正証書遺言は数万円~ |
| 保管・開封 | 家族が分かる場所に保管。いつでも開封可能。 | 厳重な保管が必要。死後に家庭裁判所の検認が必要な場合も。 |
おすすめは両方の併用!想いを確実に伝える方法
ここまで読んで、「自分にはどちらも必要かもしれない」と感じた方も多いのではないでしょうか。
その通りです。
エンディングノートと遺言書は、どちらか一方を選ぶべき対立関係にあるのではなく、それぞれの弱点を補い合うベストパートナーと言えます。
したがって、最も確実で安心な方法は「両方を併用する」ことです。
財産の分け方や相続人の指定など、法的な強制力を持たせたい重要な事柄は、厳格な形式で「遺言書」に記します。
そして、遺言書には書ききれない家族への感謝の気持ち、葬儀や介護に関する細かな希望、各種連絡先といった実務的な情報は、自由な形式の「エンディングノート」に綴るのです。
この二つを組み合わせることで、あなたの意思を法的な面と感情的な面の両方から、より確実に、そして温かく家族に伝えることができます。
遺言書の「付言事項」でエンディングノートの存在を知らせる
遺言書とエンディングノートを併用する際に、ぜひ知っておきたいテクニックがあります。
それは、遺言書の最後に「付言事項(ふげんじこう)」という項目を設け、そこにエンディングノートの存在と保管場所を書き記しておくことです。
付言事項自体に法的効力はありませんが、遺言書という法的な文書の中で、エンディングノートを読んでもらうよう促すことができます。
これにより、家族がエンディングノートを見つけ、あなたの想いを受け取ってくれる可能性が格段に高まります。
【書き方例】
「付言事項として、私の想いや葬儀の希望などをまとめたエンディングノートを、自宅書斎の机の引き出しに保管してあります。遺言と合わせて、ぜひ読んでください。」
いつから始める?終活とエンディングノート作成のタイミング
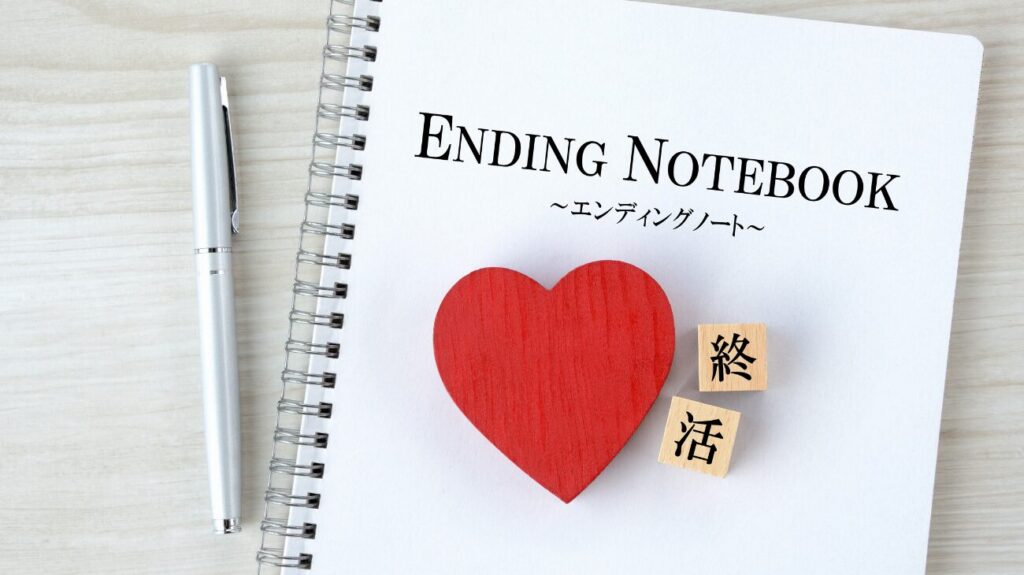
エンディングノートの重要性が分かっても、「一体いつから書き始めるのが良いのだろう?」とタイミングに迷う方も少なくありません。
終活というと、どうしても高齢になってからというイメージがあるかもしれませんが、実際には決まった年齢やタイミングはありません。
むしろ、心身ともに元気で、判断力がしっかりしているうちから始めることには多くのメリットがあります。
ここでは、エンディングノートを始めるきっかけとなる主なタイミングについてご紹介します。
思い立ったが吉日(きちじつ)!若いうちから始めるメリット
結論から言えば、エンディングノートを始めるのに「早すぎる」ということはありません。
「思い立ったが吉日(きちじつ)」という言葉の通り、気になったその時が最適なタイミングです。
特に、40代や50代といった比較的若い世代から始めることには、多くのメリットがあります。
まず、万が一の備えになるという点です。
病気や事故は、年齢に関係なく誰にでも起こり得ます。
若いうちから情報をまとめておけば、不測の事態が起きても家族が困ることはありません。
また、エンディングノートは死への準備だけでなく、「これからの人生をどう生きるか」を考えるためのツールでもあります。
自分の価値観ややりたいことを見つめ直すことで、残りの人生をより豊かに、前向きに過ごすための計画を立てるきっかけになるのです。
まずは自分史や資産リストなど、書きやすい部分から気軽に始めてみるのがおすすめです。
定年退職・還暦などの人生の節目
多くの方がエンディングノートを書き始めるきっかけとして、定年退職や還暦、子どもの独立といった人生の大きな節目が挙げられます。
これらのタイミングは、仕事や子育てが一段落し、自分の時間が増える時期です。
これまでの人生を振り返り、第二の人生をどう過ごすかを考える絶好の機会と言えるでしょう。
また、親の介護や死を経験したことをきっかけに、自身の終活を意識し始める方も少なくありません。残された家族の手続きの大変さや、意思表示がなかったことによる苦労を目の当たりにし、「自分の子どもたちには同じ思いをさせたくない」という気持ちから、エンディングノートの作成を決意するのです。
このように、具体的な必要性を感じた時も、作成を始める良いタイミングと言えます。
エンディングノートの選び方と注意点
さあ、いよいよエンディングノートを始めてみようと決めたら、次に考えるのは「どんなノートを選ぶか」ということです。
最近では様々な種類のエンディングノートがあり、それぞれに特徴があります。
また、作成したり保管したりする際には、いくつか知っておくべき注意点もあります。
ここでは、あなたに合ったノートの選び方と、安心して活用するためのポイントを解説します。
ノートの種類と特徴(市販・無料テンプレート・アプリ)
エンディングノートには、主に3つのタイプがあります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身が最も使いやすいと感じるものを選びましょう。
- 市販のノート
書店や文具店、通販などで購入できる専用ノートです。書くべき項目が網羅的に整理されているため、初心者でも迷わず書き進められるのが最大のメリットです。デザインも豊富で、自分好みのものを選べます。ただし、自分には不要な項目があったり、書きたい内容のためのスペースが足りなかったりする場合もあります。 - 無料テンプレート
インターネット上で配布されているテンプレートをダウンロードし、印刷して使うタイプです。費用がかからず、必要なページだけを選んで自分だけのオリジナルノートを作れるのが魅力です。パソコンで直接入力できるものもあります。ただし、印刷や製本の手間がかかる点がデメリットです。 - スマートフォンアプリ
スマートフォンやタブレットで管理できるデジタル版のエンディングノートです。いつでも手軽に情報を更新でき、写真や動画を保存できるものもあります。一方で、サービスの提供が終了してしまったり、スマートフォンの故障でデータが消えてしまったりするリスクも考慮する必要があります。
作成時・保管時の重要な注意点
エンディングノートを安心して活用するためには、作成時と保管時にいくつか注意すべき点があります。
以下のポイントを必ず押さえておきましょう。
- 重要すぎる情報は直接書かない
銀行の暗証番号やクレジットカードのパスワードなどをそのまま書き込むのは、紛失や盗難のリスクを考えると危険です。これらの情報は別の場所に保管し、ノートにはその保管場所を記すなどの工夫をしましょう。 - 存在と保管場所を伝えておく
せっかく心を込めて書いても、家族に見つけてもらえなければ意味がありません。信頼できる家族や友人に、エンディングノートを作成したことと、どこに保管してあるかを必ず伝えておきましょう。ただし、内容を無理に見せる必要はありません。 - 定期的に見直し、更新する
家族構成や資産状況、そしてあなた自身の気持ちも時間と共に変化します。年に一度、自分の誕生日などに見直す機会を設け、内容を最新の状態に保つことが大切です。 - 法的効力がないことを理解する
何度も繰り返しますが、エンディングノートには遺言書のような法的効力はありません。財産分与などで法的な拘束力を持たせたい場合は、必ず別途、法律に則った形式で遺言書を作成してください。
まずは一冊、自分に合ったノートから始めてみましょう
この記事では、「終活ノート」「生前整理ノート」「エンディングノート」のそれぞれの違いから、エンディングノートの具体的な書き方、遺言書との決定的な違い、そして作成のタイミングや注意点までを詳しく解説してきました。
たくさんの情報がありましたが、最も大切なことは、難しく考えすぎずに「まずは始めてみること」です。
エンディングノートは、残される家族のためだけのものではありません。
自分の人生を振り返り、大切な人への想いを再確認し、これからの人生をより良く生きるための、あなた自身への贈り物でもあります。
市販のノート、無料のテンプレート、どんな形でも構いません。
まずは一冊、あなたに合ったノートを手にとって、書けるところから少しずつ、あなたの言葉を綴ってみてはいかがでしょうか。
その一歩が、あなたとあなたの大切な人の未来にとって、かけがえのない安心につながるはずです。
終活に関するお悩みは終活協議会へ
終活協議会では、資料請求した方に無料でエンディングノートをプレゼントしております。
この記事で説明した項目を全て網羅したエンディングノートになっていますので、終活のはじめの一歩としてぜひ初めてみてはいかがでしょうか?
エンディングノートを書き進める中で、介護のこと、健康のこと、相続のこと…。
たくさんのお悩みが浮かび上がってくるかと思います。
終活協議会の『心託(しんたく)サービス』なら、終活に関するお悩みを一気通貫でサポート可能です。
ひとりひとりに合わせたプランで、これからの生活をまるっとサポートいたします。
全国47都道府県対応可能で、20,000人以上の方にご利用いただいております。
終活や老後に関するご不安がある方は、ぜひ資料をご請求ください。
まずは直接お話を聞いてみたい、という方はお電話での相談も受け付けております。
年中無休・全国対応可能なため、お悩みに合わせて終活のプロが対応いたします。
少しでも悩んでいる方は、お気軽にお電話ください。
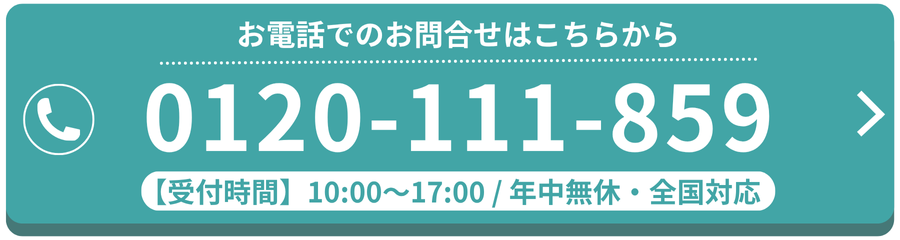
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 資格取得2025年10月4日40代からの資格取得|転職にも役立つおすすめ資格10選
資格取得2025年10月4日40代からの資格取得|転職にも役立つおすすめ資格10選 エンディングノート2025年10月4日終活ノート・生前整理ノート・エンディングノートの違いとは?基本から書き方まで徹底解説
エンディングノート2025年10月4日終活ノート・生前整理ノート・エンディングノートの違いとは?基本から書き方まで徹底解説 相続2025年10月3日相続争いを回避するための生前対策ガイド|円満相続の実現方法を専門家が解説
相続2025年10月3日相続争いを回避するための生前対策ガイド|円満相続の実現方法を専門家が解説 デジタル終活2025年10月3日終活でSNSアカウントはどうする?死後のリスクと主要4大SNSの手続きを解説
デジタル終活2025年10月3日終活でSNSアカウントはどうする?死後のリスクと主要4大SNSの手続きを解説
この記事をシェアする