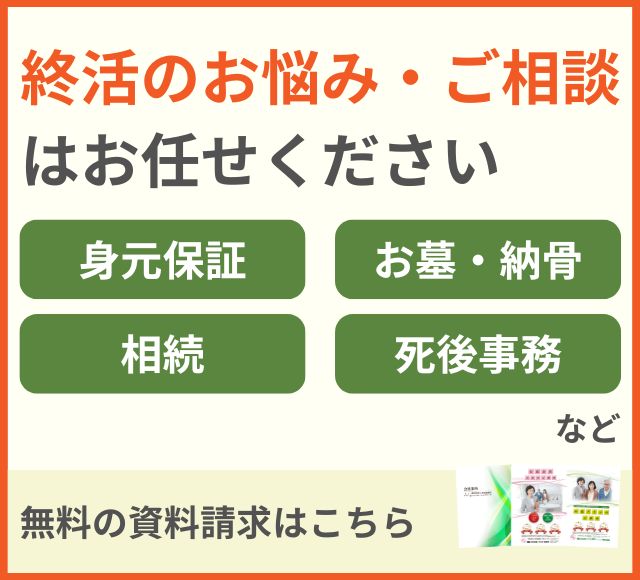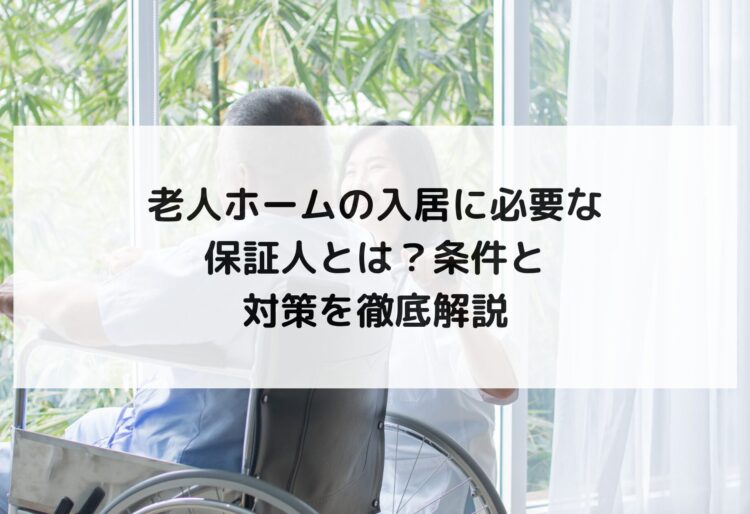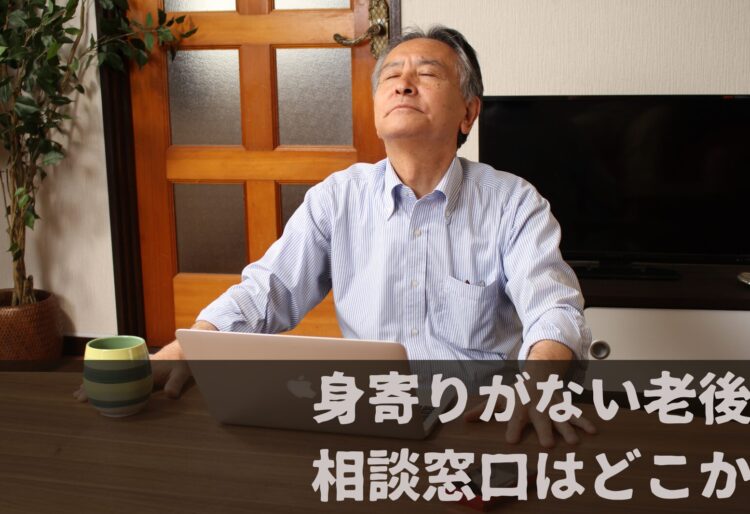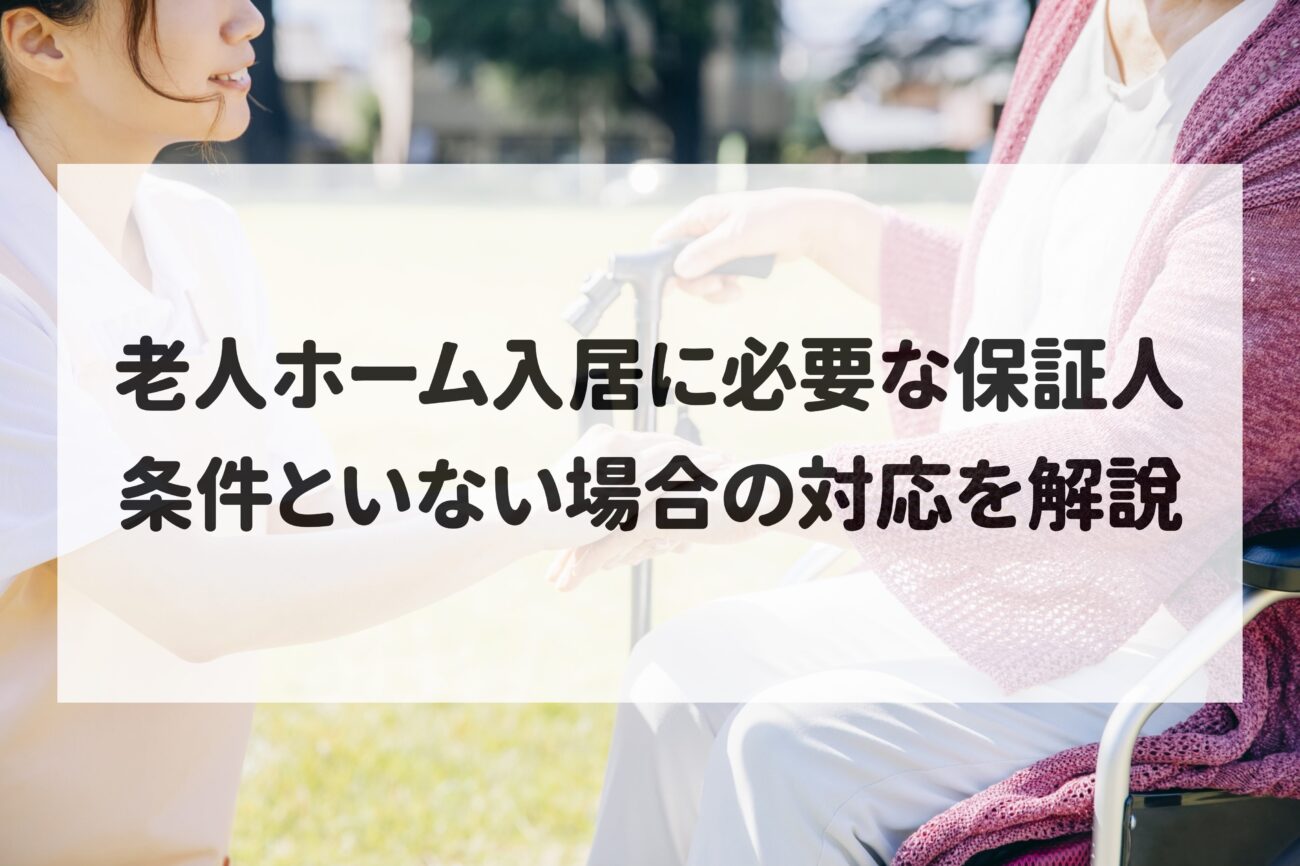
ご自身やご家族の老人ホーム入居を検討する中で、「保証人がいない」という壁に直面し、途方に暮れてはいませんか?頼れる親族がいない、あるいは親族が高齢で保証人をお願いできないなど、現代社会では決して珍しい問題ではありません。
多くの老人ホームでは、なぜ保証人が必要とされるのでしょうか。そして、もし保証人が見つからない場合、入居を諦めるしかないのでしょうか。答えは「いいえ」です。保証人がいなくても、老人ホームに入居するための具体的な解決策は存在します。
この記事では、老人ホームの入居に保証人が必要な根本的な理由から、保証人に求められる具体的な役割、そして保証人がいない場合の3つの対処法を、それぞれの費用、手続き、メリット・デメリットを含めて徹底的に解説します。
- 老人ホームの入居に保証人が必要な理由
- 保証人がいない場合の対処法
- おすすめの身元保証サービス
目次
老人ホームの入居に保証人が必要な理由とは?
そもそも、なぜ多くの老人ホームでは入居時に保証人を求めるのでしょうか。
これは、入居者が安心して生活を送るため、そして施設側が安定した運営を続けるための、双方にとって重要な仕組みだからです。
入居者は高齢であるため、将来的に健康状態や判断能力に変化が生じる可能性があります。そうした万が一の事態に備え、入居者を支え、施設との連携を円滑にするためのパートナーとして、保証人の存在が不可欠となるのです。
老人ホームに入居する高齢者は、突然の病気や認知症により、正確な判断能力を失う可能性があります。
施設側のリスク回避が主な理由
老人ホームが保証人を必要とする最も大きな理由は、施設運営に伴う様々なリスクを回避するためです。
入居者に万が一のことがあった場合、施設側だけでは対応しきれない問題が数多く発生します。例えば、月額利用料の支払いが滞ってしまった場合、認知症の進行などにより重要な医療判断が本人ではできなくなった場合、あるいは急な入院や逝去時の対応など、多岐にわたります。
これらの事態が発生した際に、迅速かつ適切に対応してくれる保証人がいなければ、費用の未回収リスクや、入居者の尊厳に関わる重要な決定が遅れるといった問題が生じかねません。保証人は、こうした施設側が抱える潜在的なリスクを引き受け、円滑な施設運営を支えるための重要な役割を担っているのです。
老人ホーム入居時の保証人に求められる4つの重要な役割
老人ホームにおける「保証人」は、単にお金の保証をするだけではありません。入居者の生活と尊厳を守るため、非常に多岐にわたる重要な役割を担います。施設や契約内容によって「身元保証人」や「身元引受人」といった名称が使われることもありますが、一般的に求められる役割は共通しています。
ここでは、保証人に求められる主な4つの役割を具体的に解説します。
1. 費用の支払い保証
保証人の最も基本的な役割が、費用の支払い保証です。
老人ホームでは、月額の利用料や食費、介護サービス費などが毎月発生します。入居者の預貯金が減少したり、年金の状況が変わったりして、万が一支払いが滞ってしまった場合、保証人が本人に代わって支払う責任を負います。これは「連帯保証人」としての側面が強く、施設側が安定した運営を続けるための重要な基盤となります。入居者が誤って施設内の備品を破損してしまった際の損害賠償なども、この責任範囲に含まれる場合があります。
2. 治療方針の決定や入院手続き
入居者の健康状態が変化し、医療的な判断が必要になった際の意思決定支援も、保証人の重要な役割です。
例えば、急な体調不良で入院が必要になった場合や、手術の同意、延命治療に関する意思表示など、本人が判断できない状況に陥った際に、家族として、あるいは本人から意思を託された者として、医師からの説明を受け、治療方針を決定します。老人ホームの職員には医療行為に関する同意権限はないため、保証人がこの役割を担うことで、入居者は迅速かつ適切な医療を受けることができます。
3. 緊急時の連絡窓口
保証人は、入居者の容態急変や怪我、災害発生時など、あらゆる緊急事態における第一連絡先(緊急連絡先)としての役割を担います。
高齢の入居者は、転倒による骨折や持病の悪化など、予期せぬ事態が起こりやすいものです。施設から連絡を受けた際には、状況を把握し、必要に応じて駆けつけたり、入院先の病院と連携したりと、迅速な対応が求められます。この連絡体制があることで、施設は安心して入居者のケアに専念でき、入居者本人も万が一の際に孤独になる不安が軽減されます。
4. 亡くなったときの身柄・遺品の引き取りと退去手続き
入居者が亡くなられた場合、その後の対応を行う「身元引受人」としての役割も保証人が担います。
具体的には、ご遺体の引き取り手配から始まり、居室に残された家財道具や私物(遺品)の整理・引き取り、そして未払いの利用料や原状回復費用などを精算し、退去手続きを完了させるまでの一連の責任を負います。身寄りのない方が増える中で、この逝去後の対応は施設にとって非常に大きな課題であり、保証人がこの役割を確実に果たすことが、契約上の重要な条件となっています。
保証人になるための条件
保証人は重大な責任を負うため、誰でもなれるわけではありません。施設側は、万が一の際に確実にその役割を果たせるかどうかを判断するため、いくつかの条件を設けています。これは施設によって異なりますが、一般的に共通する主な条件を3つご紹介します。
原則として親族であること
多くの施設では、保証人は配偶者、子、兄弟姉妹といった親族であることを条件としています。これは、法的な意思決定(特に医療同意など)や身柄の引き取りといった責任は、法的な関係性が強い親族でなければ対応が難しい場合が多いためです。ただし、近年はおひとりさまの増加といった社会状況の変化を背景に、事情を考慮して友人や知人、あるいは後述する保証会社などを認める施設も増えてきています。
資産や収入状況など支払能力に問題がないこと
保証人には、入居者に代わって費用を支払う金銭的な保証能力が求められます。そのため、安定した収入がある現役世代であることが望ましいとされています。入居契約時には、保証人の収入証明書(源泉徴収票など)や資産状況を示す書類の提出を求められることが一般的です。これにより、施設側は滞納リスクを評価し、保証人として適格かどうかを判断します。明確な年収基準はありませんが、継続的な支払い能力があることが重要です。
高齢ではないこと
保証人自身が、入居者本人と近い年齢であったり、すでに年金生活を送っていたりする場合、保証人として認められないケースがほとんどです。なぜなら、保証人自身が先に亡くなったり、病気や認知症で判断能力が低下したりして、保証人としての役割を果たせなくなるリスクが高いためです。多くの施設では、保証人の年齢に上限(例:65歳や70歳未満など)を設けており、入居者よりも若い世代であることが求められます。
保証人がいない場合の3つの具体的な対処法
「頼れる親族がいない」「親族はいるが高齢で保証人にはなれない」といった理由で保証人が見つからない場合でも、老人ホームへの入居を諦める必要はありません。現代では、保証人がいなくても入居できるための選択肢がいくつか用意されています。ここでは、代表的な3つの対処法について、その概要を解説します。
対処法1:保証人不要の老人ホームを探す
最も直接的な解決策は、初めから保証人を必要としない老人ホームを探すことです。数はまだ多くありませんが、社会的なニーズの高まりを受け、保証人がいなくても入居できる施設は少しずつ増えています。これらの施設は、独自の仕組みでリスクを管理しており、保証人がいない方でも安心して入居できる体制を整えています。ただし、選択肢が限られることや、特定の条件が付く場合があるため、その内容をよく理解することが重要です。
メリット・デメリットと注意点
メリット: 保証人不要の施設の最大のメリットは、保証人を探す手間や、親族に負担をかける心理的なストレスから解放されることです。保証会社など外部サービスを利用する必要がないため、追加の費用もかかりません。手続きがシンプルで、スピーディーに入居を進められる可能性もあります。
デメリット: 一方で、デメリットとしては、まず施設の選択肢が限られる点が挙げられます。特に、立地やサービス内容、費用面で希望に合う施設がなかなか見つからない可能性があります。また、「保証人不要」と謳っていても、実際には「緊急連絡先」の届け出が必須であったり、入居時にまとまった預託金(敷金より高額な場合も)を求められたり、あるいは提携の保証会社との契約が実質的な条件になっているケースもあります。契約前には、「保証人が不要」となる具体的な条件や、その代わりに求められるものは何かを細かく確認し、後々のトラブルを防ぐことが不可欠です。安易に「不要」という言葉だけで判断しないよう注意しましょう。
保証人不要施設の具体的な探し方と確認事項
保証人不要の施設を探すには、まずインターネットの老人ホーム検索サイトで「保証人不要」という条件で絞り込んで検索するのが効率的です。大手の介護情報ポータルサイトでは、こうした条件検索機能が充実しています。また、地域の地域包括支援センターや、ケアマネジャーに相談すれば、地域の施設情報に詳しいため、該当する施設を紹介してもらえる可能性があります。
施設が見つかったら、必ず以下の点を確認しましょう。
- 保証人不要の条件:預託金の金額、緊急連絡先の要否、提携保証会社との契約義務など、具体的な条件を確認します。
- 追加費用:保証人がいない代わりに、月額費用に管理費などが上乗せされていないかを確認します。
- 緊急時・逝去時の対応:誰が連絡を受け、誰が医療同意や身柄・遺品の引き取りを行うのか、具体的なフローを明確にしておきましょう。
- 契約書の内容:契約書の条文に、保証人不在時の取り決めがどのように記載されているかを隅々まで確認することが重要です。
対処法2:身元保証会社・法人を利用する
保証人が見つからない場合の、現在最も一般的な選択肢が「身元保証会社」や「身元保証サービスを提供する法人(NPO法人、一般社団法人など)」を利用することです。これらの会社や法人は、一定の費用を支払うことで、家族や親族に代わって老人ホーム入居時の保証人としての役割を包括的に代行してくれます。金銭的な保証から、緊急時の対応、逝去後の手続きまで、幅広いサービスを提供しているのが特徴です。
サービス内容と費用の目安
身元保証会社が提供するサービスは多岐にわたりますが、主に以下の内容が含まれます。
- 身元保証:老人ホーム入居時の保証人・身元引受人になります。
- 金銭保証:家賃などの滞納があった場合の連帯保証を行います。
- 生活サポート:定期的な訪問や買い物代行、通院の付き添いなど、入居後の生活を支援します。
- 緊急時対応:入院時の手続きや手術の同意などを代行します。
- 逝去後事務:葬儀・納骨の手配、行政手続き、遺品整理、部屋の明け渡しなどを代行します。
費用は、契約時に支払う初期費用(入会金や保証金など)と、月々の会費やサービス利用料で構成されるのが一般的です。国民生活センターの調査によると、契約時の平均金額は約100万円~200万円程度とされていますが、サービス内容によって大きく異なります。契約前には、どのサービスにどこまでの費用が含まれているのか、追加料金が発生するケースはないかなど、料金体系を詳細に確認することが極めて重要です。複数の会社から見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。
利用する際の手続きの流れ【ステップ解説】
身元保証会社を利用する際の一般的な手続きの流れは以下の通りです。実務家としてクライアントを支援する際にも、この流れを把握しておくとスムーズです。
- 情報収集と比較検討:インターネットや専門家からの紹介で複数の保証会社を探し、サービス内容、費用、実績などを比較します。資料請求や無料相談を活用し、疑問点を解消します。
- 無料相談・面談:担当者と面談し、本人の状況や希望を詳しく伝えます。サービス内容や契約に関する詳細な説明を受け、信頼できる会社かを見極めます。
- 審査・見積もり:申込書や必要書類(本人確認書類、収入証明など)を提出します。会社は本人の健康状態や資産状況などを基に審査を行い、具体的なプランと見積もりを提示します。
- 契約締結:提示された契約内容を十分に理解し、納得した上で契約を締結します。契約書は法的な効力を持つ重要な書類です。不明な点があれば、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
- 入居施設との連携:契約後、保証会社は入居予定の老人ホームと連絡を取り、保証人として必要な手続きを進めます。
信頼できる保証会社の選び方と契約時の注意点
身元保証会社は、長期間にわたって人生の重要な部分を委ねるパートナーです。そのため、慎重に選ぶ必要があります。信頼できる会社を選ぶためのチェックポイントは以下の通りです。
- 実績と運営歴:長年の運営実績があるか、多くの利用者をサポートしてきた実績があるかを確認します。
- 契約内容の透明性:サービス内容や料金体系が明確で、分かりやすく説明してくれるか。契約書に曖昧な点がないかを確認します。
- 財務状況の健全性:万が一の倒産リスクに備え、預託金の保全措置(信託銀行への預託など)が講じられているかを確認することは非常に重要です。
- NPO法人や社団法人か:営利を第一としない非営利法人は、比較的信頼性が高い傾向にありますが、法人格だけで判断せず、必ず中身を確認しましょう。
契約時には、特に「解約条件」と「倒産時の対応」について必ず確認してください。途中で解約した場合の返金額や、会社が倒産した場合に預けたお金がどうなるのかは、最大のリスク管理ポイントです。
対処法3:成年後見制度を活用する
本人の判断能力がすでに低下している、あるいは将来的な低下が懸念される場合には、「成年後見制度」の活用も選択肢の一つとなります。この制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人(親族、弁護士、司法書士など)が、本人に代わって財産管理や身上保護(介護サービスの契約など)を行うものです。ただし、保証人の役割を完全に代替できるわけではないため、その違いを正確に理解しておく必要があります。
成年後見人の役割と保証人との違い
成年後見人の主な役割は、本人の財産を守り、本人が不利益な契約を結ばないように法的に支援することです。具体的には、預貯金の管理、不動産の処分、介護サービス契約の締結、老人ホームの利用料の支払いなどを行います。この「財産管理」の面では、保証人の金銭保証に近い役割を果たせます。
しかし、決定的な違いが2つあります。第一に、成年後見人は本人の代理人に過ぎず、自身の財産から支払いを保証する「連帯保証人」にはなれません。あくまで本人の財産から支払いを行うだけです。第二に、手術の同意といった本人の一身専属権に関わる医療同意は行えません。また、亡くなった後の身柄や遺品の引き取りも、法的な権限外の行為とされています。このため、成年後見人がいても、別途「身元引受人」を求められるケースがほとんどです。
制度の種類(法定後見・任意後見)と申し立て手続き
成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります。
- 法定後見制度:本人の判断能力がすでに不十分な場合に、本人や親族などが家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらう制度です。本人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
- 任意後見制度:本人の判断能力がまだ十分なうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ自分で後見人(任意後見人)を選び、その人に任せる内容を公正証書で契約しておく制度です。
申し立て手続きは、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申立書のほか、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、医師の診断書など、多くの書類が必要となり、手続きは複雑で数ヶ月かかることもあります。司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。費用は、申し立てにかかる実費のほか、専門家への報酬、そして後見人が選任された後は、家庭裁判所が決定する後見人への報酬が継続的に発生します。
活用する上でのメリットと限界点
メリット: 成年後見制度の最大のメリットは、家庭裁判所の監督下で公的に本人の財産が保護される点です。これにより、悪質な契約から本人を守り、財産が不当に失われるのを防ぎます。施設側も、公的な立場である後見人が財産管理を行うため、費用の支払いについては一定の安心感を得られます。
限界点: 前述の通り、成年後見人は「連帯保証」や「医療同意」「身元引受」といった、保証人に求められる重要な役割を担うことができません。そのため、「成年後見人がいれば保証人は不要」とはならず、多くの施設では後見人に加えて身元引受人を別途立てるよう求められます。また、後見人への報酬が継続的に発生すること、財産の使用が家庭裁判所の監督下に置かれ、本人のため以外の支出(例えば家族への贈与など)が厳しく制限される点も理解しておく必要があります。
【包括的サポート】終活協議会の「心託サービス」という選択肢
ここまで3つの対処法を見てきましたが、「保証人不要施設は選択肢が少ない」「保証会社は費用や倒産リスクが心配」「成年後見制度は手続きが複雑で、役割に限界がある」といった、それぞれ一長一短な側面があることにお気づきかもしれません。
これらの課題や手続きの煩雑さを、一つの窓口で解決したいと考える方にとって、専門家による包括的なサポートサービスは非常に有効な選択肢となります。
3つの対処法の「面倒」を一本化するサービス内容
一般社団法人終活協議会が提供する「心託サービス」は、まさにこれまで解説してきた様々な「面倒」を一本化し、ワンストップで解決することを目指したサービスです。
具体的には、老人ホーム入居時の身元保証はもちろんのこと、入院時の保証人代行や手続き、日々の生活サポート(買い物同行など)、そして万が一の際の緊急時対応や逝去後の事務手続きまで、高齢期に直面するあらゆる不安を網羅的にカバーします。
保証会社が提供するサービスと似ていますが、終活の専門家集団として、単なる保証だけでなく、エンディングノートの作成支援や遺言の相談など、ご本人の意思を尊重したトータルライフサポートを提供している点が大きな特徴です。これにより、利用者は複数の業者と契約する手間なく、安心して老後の生活設計を任せることができます。
今なら資料請求をした方に無料でエンディングノートをプレゼントするキャンペーンを実施中!
少しでも迷いや不安がある方、身元保証サービスの利用を考えている方、終活を始める第一歩を踏み出したい方。ぜひ一度ご相談ください。
専門家によるワンストップ対応のメリット
専門家によるワンストップ対応の最大のメリットは、安心感と利便性です。保証人問題、財産管理、医療、介護、そして逝去後のことまで、それぞれの分野の専門家が連携して対応するため、利用者は個別に相談先を探す必要がありません。例えば、老人ホーム入居の手続きを進めながら、並行して任意後見契約の準備や遺言書の作成相談も同じ窓口で行うことができます。
また、一般社団法人のような非営利性の高い団体が運営している場合、利用者の利益を第一に考えた、中立的で公正なサポートが期待できるという点も大きなメリットです。保証人問題という入口から、その先の人生におけるあらゆる不安に寄り添い、継続的にサポートしてくれるパートナーがいることは、ご本人にとっても、そのご家族や支援者にとっても、計り知れない安心につながるでしょう。
どの方法が最適?状況別に見る選択肢の比較
ここまでご紹介した3つの対処法と包括的サポートサービス。どれが最適かは、ご本人の状況や何を最も重視するかによって異なります。ここでは、3つの典型的なケース別に、どの選択肢が適しているかを整理してみましょう。ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な方法を見つけるための参考にしてください。
費用を抑えたい場合の選択肢
初期費用や継続的なコストをできるだけ抑えたい場合は、まず「保証人不要の老人ホームを探す」ことが第一の選択肢となります。保証会社への支払いなどが不要なため、最も経済的な負担が少ない方法です。ただし、希望のエリアや条件に合う施設が見つからない可能性や、高額な預託金を求められる場合もあるため、根気強い情報収集が必要です。もし適切な施設が見つからない場合は、複数の身元保証会社から見積もりを取り、サービス内容と費用のバランスが最も良いところを選ぶのが次善の策となります。
手続きの手間を省きたい場合の選択肢
複雑な手続きや情報収集の手間をできるだけ省き、スムーズに入居を進めたい場合は、「身元保証会社・法人の利用」や「終活協議会の心託サービス」のような包括的サポートが最適です。これらのサービスは、保証人探しから施設との契約調整、入居後のサポートまで一貫して代行してくれるため、本人の負担を大幅に軽減できます。特に、身寄りがなく全てを一人で進めなければならない方や、仕事で忙しいご家族にとっては、時間と労力を節約できる大きなメリットがあります。
本人の判断能力に不安がある場合の選択肢
すでに認知症の症状が見られるなど、本人の判断能力に不安がある場合は、「成年後見制度の活用」が基本となります。家庭裁判所の監督のもとで財産が法的に保護されるため、安心して財産管理を任せることができます。ただし、前述の通り、成年後見人だけでは身元引受人にはなれないため、「成年後見制度」と「身元保証会社の身元引受サービス」を組み合わせて利用するのが最も確実な方法です。これにより、財産管理と身上保護の両面で、万全の体制を整えることができます。
事前に知っておきたい保証人に関するトラブルと回避策
保証人に関する問題は、金銭や法的な責任が絡むため、思わぬトラブルに発展することがあります。特に、個人間で保証人を依頼した場合や、保証会社との契約内容を十分に理解していなかった場合に問題が起こりがちです。ここでは、実際に起こりやすいトラブル事例と、それを未然に防ぐためのポイントを解説します。
実際に起こりやすいトラブル事例
- 保証人との関係悪化:親族に保証人を依頼したものの、費用の滞納が発生した際に支払いを巡って関係が悪化。あるいは、保証人が「こんなに責任が重いとは思わなかった」と後から辞退を申し出てくるケース。
- 保証会社の倒産:高額な預託金を支払って契約した身元保証会社が倒産し、預けたお金が戻ってこず、保証人も失ってしまう最悪のケース。
- 契約外の追加請求:保証会社の契約で「基本サービス」に含まれると思っていた内容が、実はオプション扱いで、入院の付き添いや手続きのたびに追加料金を請求されるケース。
- 保証人の名義貸し:入居者本人が「名前だけ貸してくれればいいから」と親族に頼み、保証人が責任範囲を理解しないまま契約し、後から高額な請求を受けて驚くケース。
トラブルを未然に防ぐためのチェックポイント
こうしたトラブルを避けるためには、事前の確認と準備が何よりも重要です。以下のチェックポイントを必ず押さえておきましょう。
- 責任範囲の書面化:個人に保証人を依頼する場合は、口約束で済ませず、保証する範囲(金銭保証の上限額、身元引受の具体的な内容など)を明確にした覚書などを交わしておくと、後の誤解を防げます。
- 保証会社の選定は慎重に:複数の会社を比較検討し、実績、評判、そして何より預託金の保全措置(信託保全など)がしっかりしているかを確認します。契約書は隅々まで読み込み、不明点は必ず質問しましょう。
- 契約内容の完全な理解:どこまでが基本料金で、何が追加料金になるのかをリストアップして確認します。「一式」「すべて込み」といった曖昧な言葉に惑わされず、具体的なサービス項目を確認することが肝心です。
- 専門家への相談:契約内容に少しでも不安があれば、契約前に弁護士や司法書士、地域の消費生活センターなどに相談しましょう。第三者の客観的な視点からアドバイスをもらうことで、リスクを回避できます。
まとめ:保証人問題は早めの準備と専門家への相談が鍵
老人ホーム入居における保証人問題は、多くの方が直面する可能性のある、重要かつ複雑な課題です。施設側が運営リスクを回避するために保証人を求めるのは当然の流れであり、保証人には金銭保証から緊急時対応、逝去後の手続きまで重い責任が伴います。
しかし、保証人がいないからといって入居を諦める必要は全くありません。「保証人不要の施設を探す」「身元保証会社を利用する」「成年後見制度を活用する」といった具体的な対処法が存在します。それぞれにメリット・デメリット、費用、手続きの複雑さが異なるため、ご自身の経済状況、健康状態、そして何を最も重視するかを基に、最適な選択肢を慎重に検討することが重要です。特に、各選択肢の限界点(例:成年後見人は身元引受人にはなれない)を正しく理解し、必要であれば複数のサービスを組み合わせる視点も求められます。
どの方法を選ぶにしても、最も大切なのは「早めに準備を始めること」です。いざ入居が必要になってから慌てて探し始めると、選択肢が限られたり、不利な条件で契約してしまったりするリスクが高まります。
少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まず、専門機関に相談することをお勧めします。専門家の知識とサポートを活用することが、安心して新しい生活をスタートさせるための最も確実な一歩となるでしょう。
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする