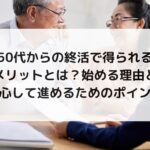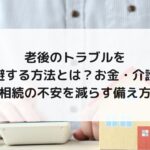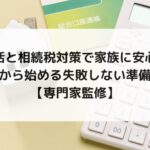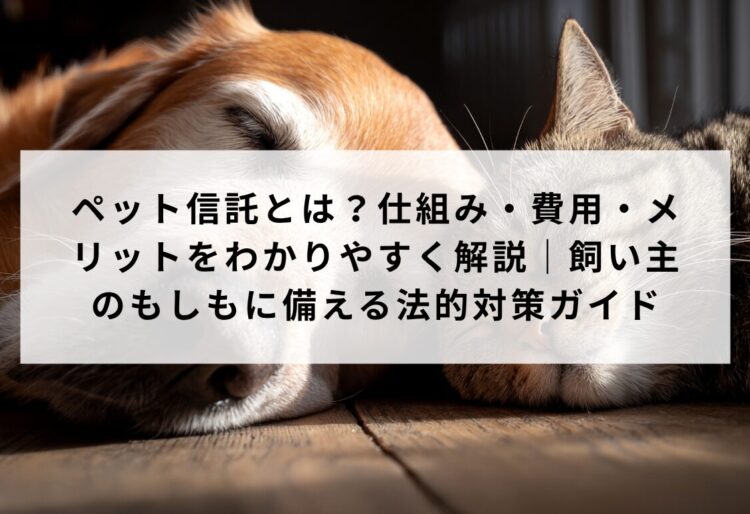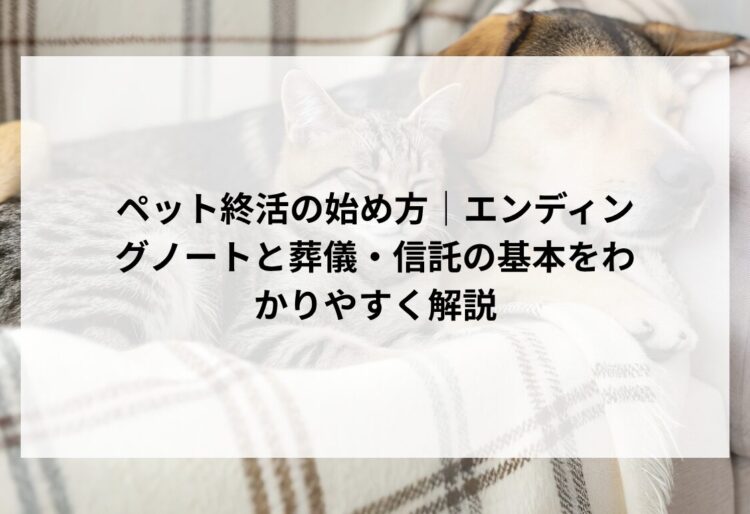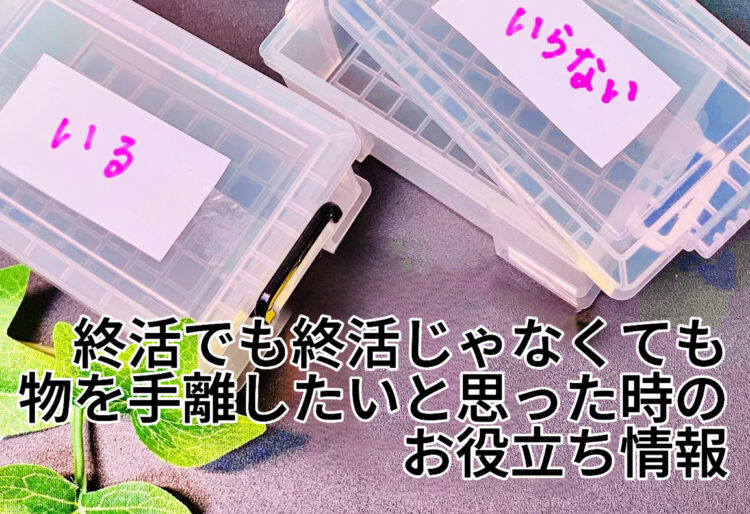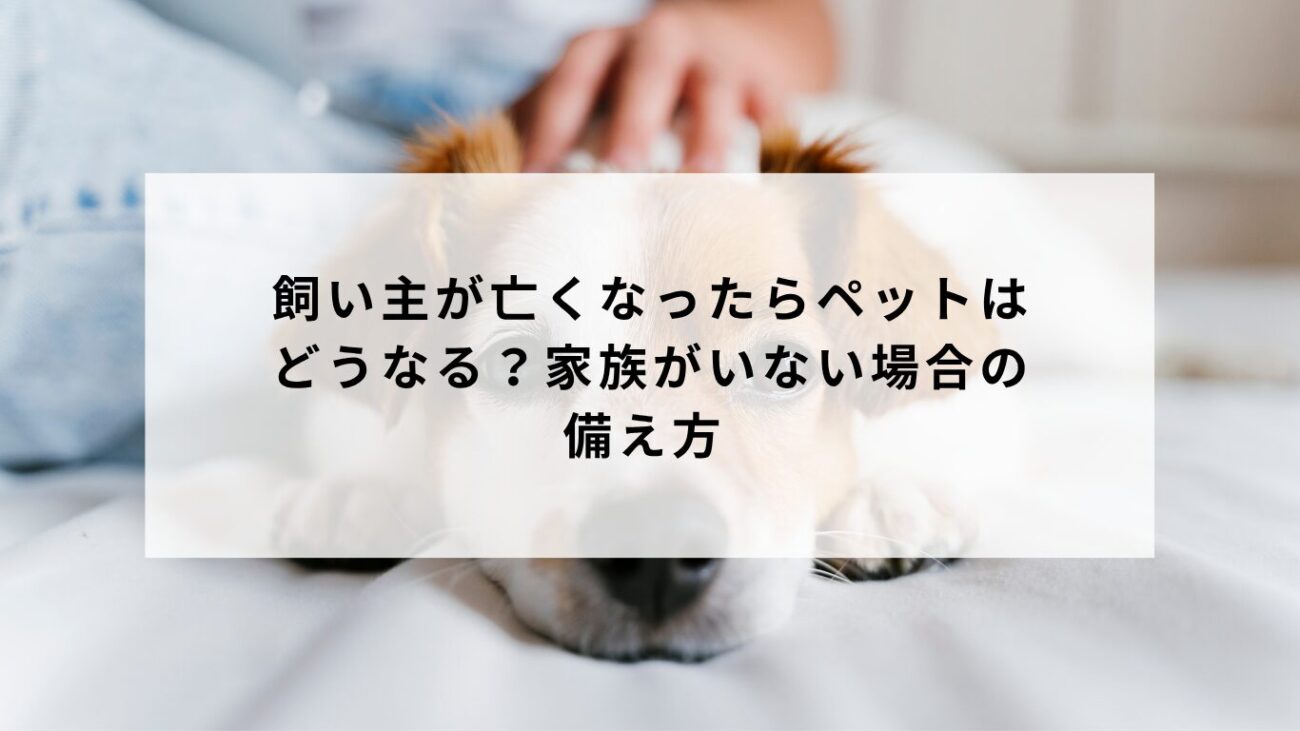
一人暮らし。ペットと二人きりの生活。
ふとした瞬間に頭をよぎる不安。「もし自分に何かあったら、この子はどうなるんだろう?」
孤独死のニュースを見るたび、胸が締め付けられる。他人事じゃない。明日は我が身かもしれない。
その不安は、ペットを深く愛しているからこそ生まれる感情です。逃げずに向き合うことが、大切な家族を守る第一歩になります。
目次
飼い主が死んだらペットはどうなる?現実を知る
引き取り手がいないと、どうなるのか
飼い主が亡くなった。身寄りがない。誰も引き取らない。
そんな時、ペットはどこへ行くのか?
まず警察や動物愛護センターに保護されます。でもそこから先が問題です。引き取り先が見つからなければ、一定期間を経て譲渡先を探す。それでも見つからない場合——。
殺処分。
可能性はゼロではありません。これが現実です。
一人暮らしの飼い主が直面するリスク
高齢の単身者。子どもが独立した世帯。「ペットと二人暮らし」という形は、年々増えています。
急な入院。突然の事故。自宅に戻れなくなる。
周囲がペットの存在に気づかなければ?食事も水も取れないまま、命の危険にさらされる。実際に起きている事態です。
だからこそ。
「自分が死んだ後どうするか」を考えるのは、ペットを守るための終活なんです。
ペットの未来を守る3つの備え方
漠然とした不安を、具体的な安心に変える。そのための方法を、順番に見ていきましょう。
① お金と契約で守る|ペット信託・遺言・委任契約
ペット信託とは?
飼い主が生前に信託契約を結ぶ。亡くなった後、指定した人(受託者)が信託財産からペットの飼育費用を使い、世話を続ける。法的に守られた仕組みです。
「お金を残しても、本当にペットのために使ってくれるのか?」
この不安を解消するのがペット信託。資金の使い道が明確に定められ、監督する仕組みもある。最も確実な方法の一つです。
負担付遺贈という選択肢
遺言書で「財産を渡す代わりに、ペットの世話をしてほしい」と指定する方法。シンプルで分かりやすい。
ただし注意点があります。相手の同意が必要なこと。本当に履行されるかの確認が難しいこと。
死後事務委任契約との組み合わせ
死後の手続きを専門家に委任する契約。葬儀の手配、ペットの引き渡し、供養まで包括的に任せられます。
ペット信託と組み合わせることで、より安心な体制を築けます。
② 引き取り先を探す|家族・友人・団体
まずは身近な人に相談
親族、信頼できる友人。「もしもの時、この子を引き取ってもらえますか?」
正直に話してみること。でも現実は厳しい。金銭的な負担、住環境、家族の事情。断られるケースも少なくありません。
動物愛護団体・NPO法人の活用
引き取り手が見つからない場合、次の選択肢があります。
- 老犬・老猫ホーム
- 譲渡支援制度を持つ団体
- 終生飼養契約(生前に費用を預ける仕組み)
一部の団体では、飼い主が元気なうちから契約を結び、万が一の時にペットを受け入れる体制を整えています。
③ 緊急時に備える|エンディングノート・連絡カード
ペットエンディングノートを作る
突然の入院。事故。そんな時、周囲の人がすぐに対応できるよう、情報をまとめておきましょう。
- ペットの名前、性格
- かかりつけの動物病院(連絡先)
- 普段の食事内容、回数
- 持病、投薬情報
- 好きなこと、苦手なこと
書き方は自由。大切なのは「誰が見ても分かる」こと。
緊急連絡カードを持ち歩く
財布やスマホケースに、小さなカードを入れておく。
「ペットが自宅にいます」 「緊急連絡先:〇〇」
これだけで救われる命があります。
どの方法が自分に合う?制度の比較表
| 制度名 | 内容 | メリット | 注意点 |
| ペット信託 | 信託財産で飼育費を管理、受託者が飼育 | 確実な運用、柔軟な設計が可能 | 費用がかかる、受託者選びが重要 |
| 負担付遺贈 | 遺言で財産を渡す代わりに世話を依頼 | 遺言書で簡単に指定できる | 相手の同意が必要、履行確認が難しい |
| 死後事務委任契約 | 死後の手続きを専門家に委任 | 包括的に任せられる | 委任範囲や費用に注意 |
それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合った方法を選びましょう。迷ったら、専門家に相談するのが確実です。
一人暮らしの飼い主が今日からできること
何から始めればいいか分からない。そんな方へ、今すぐできる4つのステップを紹介します。
1. ペット情報をノートやアプリにまとめる
名前、性格、医療履歴、食事内容、好き嫌い。思いつくままに書き出してみてください。完璧じゃなくていい。まずは始めることが大切です。
2. 信頼できる人に連絡先を共有する
親族、友人、近所の人、かかりつけの動物病院。「もしもの時はこの人に連絡してほしい」というリストを作り、共有しておく。
3. 緊急連絡カードを持ち歩く
財布に入れる。スマホケースに挟む。常に身につけておくことで、万が一の時にペットの存在を伝えられます。
4. 見守りサービスを活用する
定期的に安否確認を行う民間サービス。一人暮らしの方にとって、心強い味方になります。
まとめ|ペット終活は「今」を安心に変える
ペットは家族です。
「命のバトン」を次につなぐためには、飼い主が生前に備えるしかありません。
「まだ元気だから大丈夫」
そう思っていても、予期せぬ事故や病気は誰にでも起こります。
いざという時にペットが困らないよう、3つのことを意識してください。
- 信頼できる人との話し合い
- 契約やノートなどの記録
- 費用面の準備
これだけで、安心感は大きく変わります。
あなたの想いと、ペットの幸せを次につなぐために。今日から「ペット終活」を始めてみませんか。
終活協議会では、記入しながらペット終活を学べる「ペットの終活ガイドブック」を無料でプレゼントしています。ぜひご活用ください。
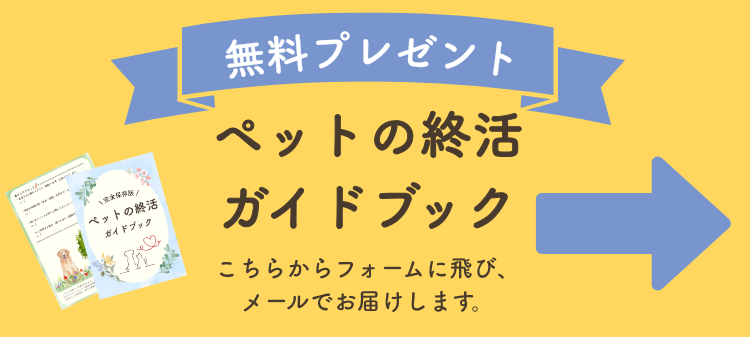
ペットの終活ガイドブックプレゼントはこちら!
こちらに必要項目を記入して頂き、「確認」ボタンを押してください。ご登録いただいたメールにお届けいたします。
確認ボタンを押すと、登録確認画面に遷移します。登録内容に間違えがなければ、「登録する」を押してください。
関連コラム
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 エンディングノート2025年12月5日50代からの終活で得られるメリットとは?始める理由と安心して進めるためのポイント
エンディングノート2025年12月5日50代からの終活で得られるメリットとは?始める理由と安心して進めるためのポイント お金・相続2025年11月28日老後のトラブルを回避する方法とは?お金・介護・相続の不安を減らす備え方
お金・相続2025年11月28日老後のトラブルを回避する方法とは?お金・介護・相続の不安を減らす備え方 お金・相続2025年11月24日終活と相続税対策で家族に安心を─今から始める失敗しない準備法【専門家監修】
お金・相続2025年11月24日終活と相続税対策で家族に安心を─今から始める失敗しない準備法【専門家監修】 身の回り整理2025年11月19日終活における人間関係の整理|後悔しない進め方とやることリスト
身の回り整理2025年11月19日終活における人間関係の整理|後悔しない進め方とやることリスト
この記事をシェアする