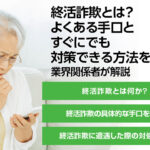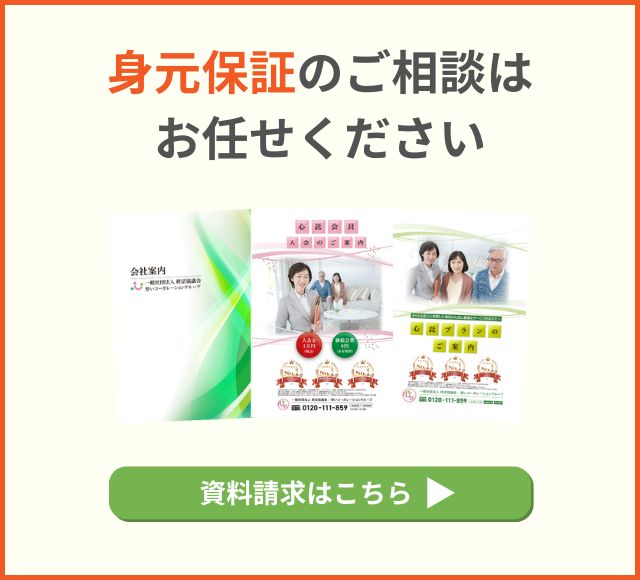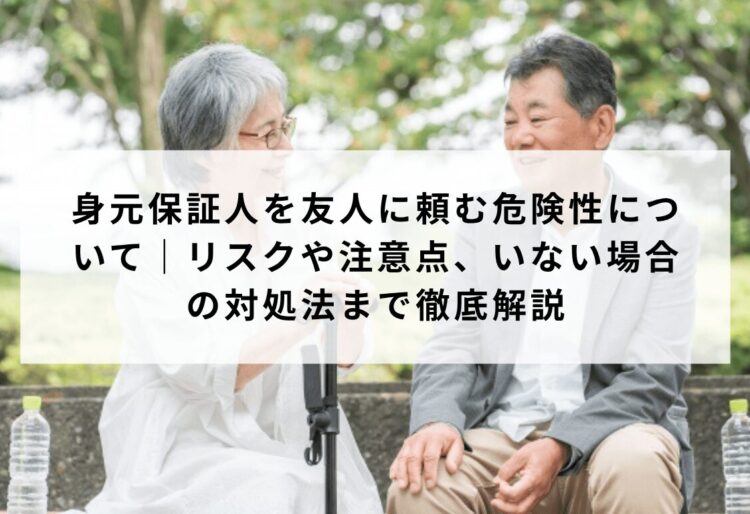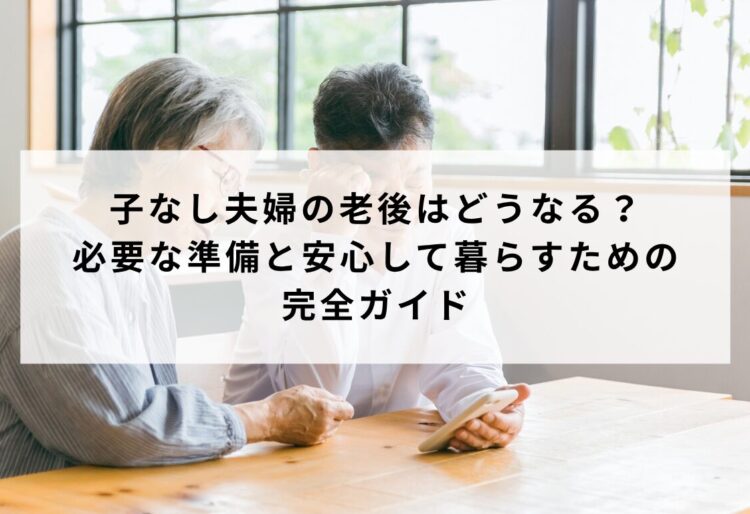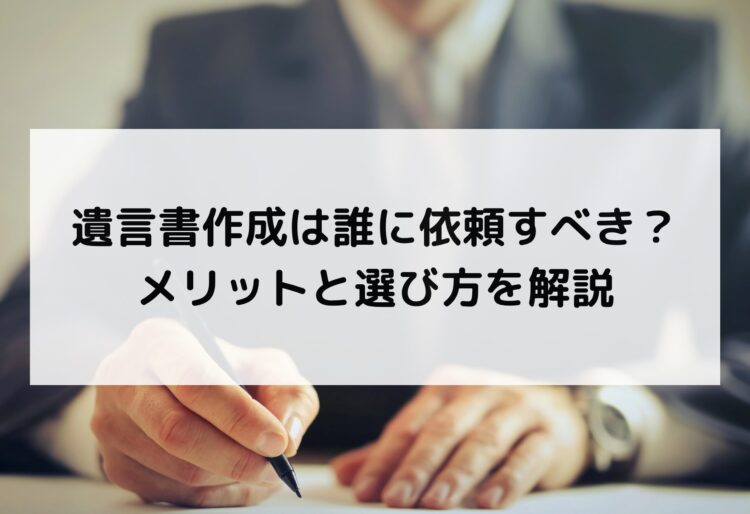就職や賃貸への引っ越し(賃貸契約)、病院への入院、介護施設への入所など重要なライフイベントの度に、身元(素性・素行)を証明する「身元保証人」が必要となります。手続きで身元保証人を求められたら「身元保証人の欄にサインしてもらったら終わり」と思っている方も多いです。
実は身元保証人に関することは、身元保証に関する法律でルールが決められています。知っておかないと不利益を被ることもあるので、今回は身元保証法についてなるべくわかりやすく解説していきます。
身元保証人が必要になった場合、この記事の内容を思い返していただければと思います。
身元保証法(身元保証に関する法律)とは?
身元保証法の正式名称は、「身元保証に関する法律」といい、昭和8年(1933年)に制定された古い法律です。本来は、雇用における身元保証契約に関する法律でした。
あらゆる場面で身元保証人が要求され、特にシニア世代にとって重要な存在に
法律が制定された当時は想定されていませんでしたが、現在ではシニア世代が病院に入院したり施設に入所したりする際にも身元保証人を設定することが要求されるケースが多くなってきています。
現行の身元保証法では厳密には雇用時以外の身元保証には対応していませんが、他に該当する法律がないため、身元保証法を一つの根拠法としています。
そもそも身元保証人って?
本人の身元を保証する人を一般的に「身元保証人」と呼びます。「身元引受人」と呼ぶケースもあり、責任の範囲もケースバイケースです。身元引受人と呼ぶ場合は、入院・入居していた方が死亡した時に遺体を引き取ったり、残された本人の所有物を処分したりする役割を担うケースが多いです。
また、一般的に本人が請求金額を支払えなかった際に、肩代わりして支払うことが求められます。つまり、身元保証人には十分な資力があることを求められます。身元保証契約を誰かと結ぶ際には、保証の範囲や金額を明確に理解しておくことが非常に重要です。
身元保証契約とは
身元保証契約とは、相手方(企業や病院、施設の運営など)と、身元保証人との間で締結する、身元保証の契約のことです。身元(素性・素行)に関する保証だけではなく「損害を加えた場合の賠償など本人に何かあった時に対応を求める」という契約となっています。
身元保証書とは
身元保証書とは、親族や友人などの第三者に身元を保証してもらう書類のことです。相手方は、ここにサインをした方(身元保証人)に対して、何かあった際の対応を求めます。
第三者に本人について保証してもらうことを目的としていますから、本人が身元保証書を代筆することは当然できません。必ず身元保証人を引き受けてくれる方に署名・捺印してもらう必要があります。
相手方にとっては、万が一の時の責任の所在について契約で定めるものですので「身元保証人が周りにいない」などと相談しても「郵送で対応できないか」「友人でもいいので頼めないか」などと、記入を求められます。
身元保証書は、一般的に以下の項目が盛り込まれています。
身元保証の有効期間
最長5年です。何も記載がないなら3年です。
損害賠償時の上限額(極度額)
万が一の際に、身元保証人が支払う損害賠償の金額は必ず上限額が記載されています。上限額が設定されていない場合、身元保証契約は無効となります。
連絡先
身元保証人の住所・氏名・電話番号・メールアドレスなどを記入してもらいます。
身元保証法は古くてわかりづらい…一体何が定められてるのか
「身元保証に関する法律」(通称「身元保証法」)は、全6条の短い法律です。表記方法が古くわかりにくいため、現代語の表記に直して、法律の内容をわかりやすく解説します。
身元保証法第一条「身元保証人には有効期間がある」
第一条の現代語訳
いわゆる身元保証契約を締結する際には、契約期間を定めていなければ契約期間は契約成立から3年間とみなします。ただし、商工業見習い者の身元保証契約については、5年間とみなします。
第一条の解説
雇用契約を結ぶ際には、もし被用者(労働者)が使用者(雇用主)に損害を与えたりした場合にその損害を賠償することを第三者が保証する契約を結べます。「商工業見習い者」は、現代における新卒採用者のことです。基本的には労働契約に関する規定ですが、入院や施設入居時の身元保証契約においても、期間の定めがない場合の契約期間は3年となります。
身元保証法第二条「有効期間は最大5年」
第二条の現代語訳
- 身元保証契約の期間は5年を超えることはできません。もし契約で5年を超える期間が定められていたとしても無効になり、5年間とみなされます。
- 身元保証契約は更新することができます。ただし、更新時も契約期間は5年を超えることはできません。
第二条の解説
身元保証契約の期間は最大で5年。更新時も同様に最大5年で、更新しなければ契約は自動的に失効することになります。
身元保証法第三条「身元保証人への通知」
第三条の現代語訳
使用者(雇用主)は以下のような場合、速やかに身元保証人に通知しなければなりません。
- 被用者(労働者)に業務上の適性や誠実さを欠いているような兆候があり、これによって身元保証人に責任が発生するような恐れがあることを知った時
- 被用者(労働者)の業務内容や勤務地が変更されて、これにより身元保証人の責任が重くなったり、または監督が困難になったりする時
第三条の解説
例えば、介護施設などへ入居する際の身元保証の場合、本人の身体状況が変化した時などは身元保証人に連絡しなければならないことになります。認知症が悪化して他人に危害を加える可能性が高まった場合などが該当すると考えて良いでしょう。
身元保証法第四条「身元保証人の解除(権)」
第四条の現代語訳
身元保証人が前条(第三条)の通知を受けた時は、将来身元保証契約の解除をすることができます。また、通知を受けなくても、身元保証人がみずから前条第一号や第二号の事実を知った場合でも同様です。
第四条の解説
例えば、施設入居後に素行の悪さが目立ち、施設に損害を与えるなど、身元保証人の責任が増加しそうな時は契約の解除が可能であると考えられます。
身元保証法第五条「身元保証人の事情を考慮する」
第五条の現代語訳
裁判所が身元保証人の損害賠償責任と賠償金額を定める際には、被用者を監督する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証を行うに至った理由と身元保証契約を結ぶ時にした注意の程度、被用者の任務内容や状況の変化などの様々な事情を考慮しなければなりません。
第五条の解説
身元保証契約を結んでいたからといって一方的に身元保証人が損害賠償を負わなければならないという訳ではありません。様々な事情を考慮したうえで、責任の程度や賠償金額が決定されます。
身元保証法第六条「身元保証人に不利になる契約は無効」
第六条の現代語訳
この法律の規定に反して、身元保証人に不利益になるような特別な契約を結んでもすべて無効です。
第六条の解説
身元保証契約を結ぶ場合、身元保証人が一方的に不利にならないように法律上の制限が加えられています。
民法改正で身元保証契約にも影響あり
民法の債券関係(契約関係)に関わる部分が2020年4月に一部改正され、保証について新しいルールが導入されました。
金融機関から融資を受ける際に、本人(主債務者)が返済できなくなった時やアパートの賃貸借契約で家賃を支払えなくなった時のために保証人をつけるのが保証契約です。アパートの保証人の場合は、借金の返済の保証などとは異なり債務の範囲が不特定なため、「根保証契約(ねほしょうけいやく)」と呼ばれています。今回の改正はこの根保証契約に適用されます。
例えばアパートの賃貸借契約の保証人となれば、借主の重過失によってアパートが全焼してしまった場合、保証人には多額の損害賠償の責任が発生します。今までは保証人は非常に大きなリスクを背負っていましたが、法律の改正により保証人の責任に制限が加えられました。
具体的には主に次の2点で変更があります。
上限額の定めがない個人根保証契約は無効
根保証契約(個人根保証契約)の場合、保証人の責任で支払う金額の上限額(極度額)を設定しなければなりません。もし、上限額なしで個人根保証契約を結んだ場合は無効となります。限度額は書面などで「〇〇円」と明確に定める必要があります。
特別な事情が生じると保証は終了
個人根保証契約は、保証人が破産した場合や本人(主債務者)、保証人が死亡した場合は、その時点で契約は打ち切りとなります。しかし保証人は、それ以前に発生した債務について、保証した内容の義務を負わなければなりません。
あなたは、この先も身元保証契約をしてくれる人が近くにいますか?
核家族化の進行に伴い、いざという時に頼れる人が近くにいない、身寄りのない方が増えています。あなたはいざという時に身元保証人を頼める方が周囲にいますか?
もし両親や兄弟、友人が近くにいたとしても、今後高齢になっていき、収入源が年金のみになると相手方に身元保証人に適さないと判断されるケースもあります。将来子供を授からず、自分より若い身内がいなければ、身元保証人になってくれる人が周りにいなくなってしまうという事態は容易に起こりえます。
いわゆる「保証人問題」であり、核家族化や少子化が進む時代においては決して他人事ではなく、真剣に向き合っていかなければなりません。
一般社団法人終活協議会ではこうした保証人問題を解決する身元保証の代行サービスをはじめとした、人生のお困りごとを相談・解決するサービス『心託』をご提供しています。サービス料金を明確に定め、公平な取引になり、お客様が安心して身元保証をお任せいただけるように誠心誠意努めており、全国で20,000名以上のご利用実績があります。
専門知識と経験豊富なスタッフが身元保証に関する疑問や悩みについて丁寧にお答えしておりますので、身元保証人の準備にお困りならぜひご連絡ください。
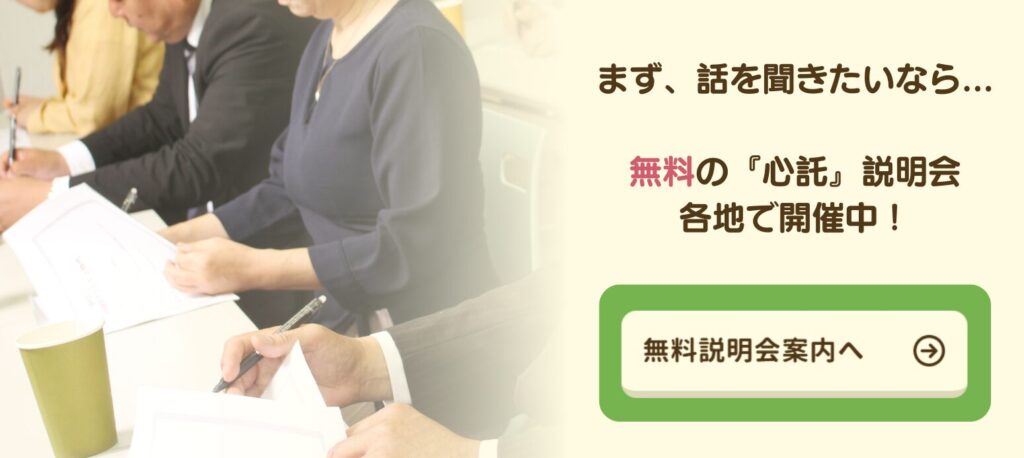
監修

- EMパートナーズ法律事務所 代表 一般社団法人 終活協議会 顧問弁護士
-
所属:東京弁護士会
◇経歴
日本大学法学部卒
明治大学法科大学院修了
2007年 弁護士登録・都内の法律事務所入所
2011年 「遠藤治法律事務所」開設
2021年 現事務所名へ名称変更
2022年 「一般社団法人 終活協議会」顧問弁護士就任
◇著書等
東京弁護士会編「労働事件実務マニュアル」改訂担当(共著)
東京弁護士会法友会東日本大震災復興支援特別委員会編「3・11震災法務Q&A」(共著)
東京弁護士会春秋会編「会社・経営のリーガル・ナビQ&A」(共著)
最新の投稿
 暮らし2023年9月11日終活詐欺とは?よくある手口とすぐにでも対策できる方法を業界関係者が解説
暮らし2023年9月11日終活詐欺とは?よくある手口とすぐにでも対策できる方法を業界関係者が解説 法律2022年11月8日法定後見制度とは?手続きの流れや費用・任意後見制度との違いを業界関係者が解説
法律2022年11月8日法定後見制度とは?手続きの流れや費用・任意後見制度との違いを業界関係者が解説 法律2022年9月2日身元保証法(身元保証に関する法律)とは?弁護士が解説
法律2022年9月2日身元保証法(身元保証に関する法律)とは?弁護士が解説
この記事をシェアする