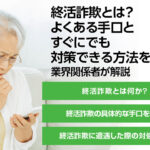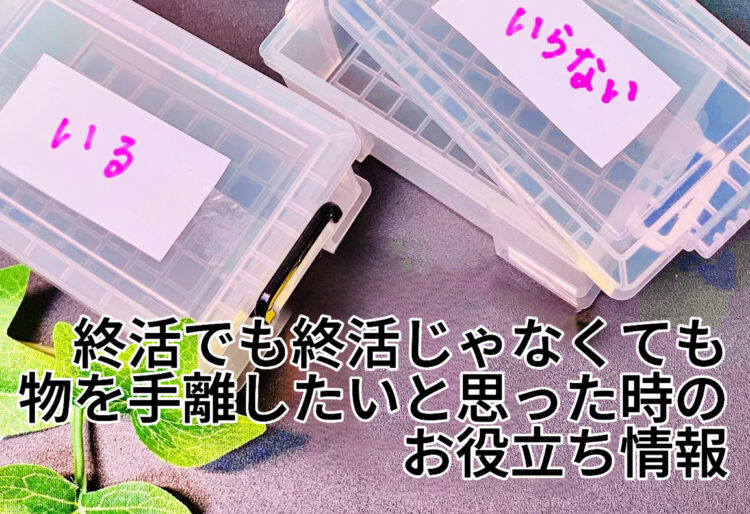厚生労働省(みんなのメンタルヘルス総合サイト)の情報によると、認知症患者は年々増加し、2025年には65歳以上の人口のうち、5.4人に1人が認知症患者になると予測されています。
認知症患者の増加に伴い、高齢者本人の判断能力がないことを悪用した犯罪が年々増えていますが、高齢者本人が正常な判断ができずに犯罪に巻き込まれた時の対策のひとつとして「法定後見制度」があり、高齢者本人を保護することができます。本記事では、法定後見制度とは何か、メリット・デメリット、実際に手続きを行う場合の流れなどについてわかりやすく解説します。
法定後見制度とは?
法定後見制度とは「成年後見制度」の一つです。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。そこで、「法定後見制度とは何か?」(修正理由は後述)「法定後見制度と任意後見制度は何が違うのか?」について解説します。
法定後見制度の役割
法定後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などで十分な判断能力がなくなってしまった人を法律的に保護する制度です。判断能力が不十分な状態では、日常生活に支障が出るだけでなく、重要な約束事や、契約の際に不安が生じます。例えば、老人ホームに入居しようとしてもどの老人ホームを選べばいいのか判断がつかなかったり、入居手続きに必要となる契約内容を理解できなかったりすることが考えられます。
また、本人の代わりに家族が銀行口座からお金を引き出そうとしても、銀行に対して本人に判断能力がないことを証明しないと、お金を引き出すことができません。法定後見制度は、そのような場合に各種契約や財産の処分・管理を本人に代わって行うことを法律的に保証する制度です。
法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見制度は、すでに判断能力が衰えてしまっている場合に、本人または四親等以内の親族からの申立てを受け、家庭裁判所の裁判官が後見人を選任する制度です。一方、任意後見制度は、将来的に判断能力が衰えた場合に備えて、本人の判断能力が十分なうちに、本人があらかじめ後見人を決めておく制度です。
「法定後見制度」では、本人が結んでしまった契約を後見人が代わりに取り消すことができるなど、大きな権限を有していることが特徴です。
法定後見制度の類型
法定後見制度には、高齢者本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」3つの類型(種類)があります。
後見について
後見は、高齢者本人の判断能力が全くなく、日常生活におけるささいな契約や手続きでさえままならないとみなされた場合に選任されます。後見人には、本人(被後見人)が行う全ての法律行為に対して代理権が付与されます。本人が結んだ契約でさえ、不必要であると考えられる場合は取り消すことが可能です。この権限を
「取消権」と言います。
なお、後見人が付くと本人は、公務員や医師、税理士などの職業には就けなくなります。
保佐について
保佐は、高齢者本人(被保佐人)の判断能力が著しく不十分で、簡単な判断は自分でできるものの、重要な契約や手続きについては難しいとみなされた場合に選任されます。保佐人は民法第13条1項に規定されている行為に関して「同意権」と「取消権」を有します。民法第13条1項で規定されている行為の中で主なものには以下のようなものがあります。
| ・預貯金口座からの払い戻し ・借金をすること、または借金の保証人になること ・不動産の売買 ・訴訟を行うこと ・家屋の新築・改築・増築 ・短期の場合を除く賃貸借 ・相続の承認、放棄、遺産の分割 ・贈与、和解、仲裁 |
上記の項目に該当するような行為をなお、後見の場合と同様に、被保佐人は公務員や医師などの職業には付けません。本人が自分の判断のみでできる行為には、遺言書の作成や結婚などがあります。
補助について
補助は、大抵のことは本人が問題なくできるけれども、複雑な契約等に関してサポートが必要であるとみなされた場合に選任されます。
補助人は保佐人と異なり、同意見および取消権は最初から付与されていませんが、裁判所の審判によって、民法13条1項の特定の行為について同意見および取消権が付与される場合があります。また、後見や保佐の場合と異なり、制度の適用によって就業や資格取得が禁止になる職業はありません。
法定後見制度のメリット
法定後見制度を利用するメリットには以下のようなものがあります。
1:後見人が本人に代わって財産を処分・管理できる
高齢者本人が認知症などで正常な判断ができなくなると、財産を処分したり、支払いを行う際にトラブルになることがあります。例えば銀行口座の解約をしようとしても、高齢者本人に判断能力がないと分かると、銀行から成年後見人を立てるように求められるケースがあります。後見人は本人に代わって財産に関して必要な手続きを行えるようになります。
2:本人に対して不利益な契約を取り消せる
高齢者本人が契約内容の不備に気づかなかったり、判断力が衰えているために一方的に押し切られてしまい、不利益な契約を組まされてしまった場合でも、後でその契約を取り消すことが可能です。
例えば、訪問販売などで必要もないのに大量の商品を買わされてしまった場合、後見人が妥当性を欠くと判断すれば契約自体を取り消すことができます。また、一般的な売買契約だけでなく、宗教団体への寄付でも、高齢者本人の生活に支障をきたすような多額の寄付であった場合は寄付行為の取り消しが可能です。
3:親族によるお金のトラブルを防げる
後見人が選任されると、本人の預貯金通帳は後見人が管理することになるため、本人に無断で家族が預貯金を引き出したりすることができなくなります。以前は家族が後見人に選任されるケースが多く、本人のためではなく、私的な理由でお金を不正に引き出すこともしばしばあったようです。その結果、家族間での金銭トラブルが起きる事もよくありました。
しかし、最近は家族による不正なお金の引き出しを防止するために、第三者が選任される
ケースが増えています。その結果、家族間による金銭関係のトラブルが起き辛くなったようです。
法定後見制度のデメリット
法定後見制度にはデメリットあります。代表的なものを、以下で2点解説します。
1:費用と手間がかかる
詳しい内容は後述しますが、法定後見の申立てには印紙代や医師の診断書などの作成に費用がかかります。さらに、申立てには煩雑な手続きが必要で、基本的には弁護士や司法書士などの専門家に依頼することになり、その費用が必要になります。
また、後見人に法律家や社会福祉士等の第三者が選任された場合には、報酬を支払わなければなりません。報酬は管理する財産の額によっても異なりますが、最低でも月に2万円、多額の財産がある場合はさらに高額の報酬が必要です。
2:簡単には申立ての取り下げが出来ない
成年後見制度は1度申立てをすると、簡単に取り下げることができません。通常は本人(被後見人)が亡くなるまで続きます。例えば、本人が所有する不動産を売却したり、定期預金を解約したりするために後見人を選任した場合、目的の不動産の売却や定期預金の解約が完了したからといって、後見人を解任することはできません。
また、後見人に報酬が発生している場合は、継続して支払い続ける必要があります。
法定後見制度を利用する際の流れ
法定後見人を選任してもらう際の手続きは、以下のような流れで進みます。
ステップ1:必要書類の準備
ステップ2:家庭裁判所への申立て
ステップ3:家庭裁判所による審判・手続き
ステップ4:後見の開始
上記4つのステップについて、順を追って解説します。
ステップ1:必要書類の準備
法定後見制度の審判の申立てには多くの書類が必要です。主なものを以下に挙げます。
| ・審判申立書 ・申立書附票(申立事情説明書) ・住民票・戸籍謄本 ・医師の診断書 ・本人情報シート ・成年後見等の登記がされていないことの証明書 ・本人の健康状態に関する資料 ・本人の財産等に関する資料 |
申立書附票とは、本人の状況や経歴、家族関係、申立てが必要な事情などを申立書よりさらに詳しく記入した書類です。裁判所によっては申立事情説明書と呼ぶ場合もあります。
ステップ2:家庭裁判所への申立て
裁判所への申立ては、誰でもできるわけではありません。申立てができる主な人は、本人、配偶者、4親等以内の親族及び市町村長です。4親等の親族は、イトコなどが該当します。
既に保佐や補助を受けていて、法定後見に変更する場合は、保佐人や補助人が申立てを行うことが可能です。申立てを行う裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ステップ3:家庭裁判所による審判・手続き
申立てを行うと裁判所で審判が始まり、以下のような流れで進みます。
| ・調査・審問 ・鑑定 ・審判 |
裁判所は申立書を受理すると、書類を精査したのちに本人や家族から事情を聞きます。後見人・保佐人・補助人の候補者がいる場合は、その人物の調査も行います。また、書類等で後見人をつけるべきかどうか判断しにくい場合、医師による鑑定が行われることもあります(ただし、実際に鑑定が行われるのは全体の5%程度です)。
調査および審問、場合によっては鑑定を実施したうえで後見を開始するかどうかの審判が下されます。審判結果は申立人に郵送で通知されます。
ステップ4:後見の開始
後見が決定されると、裁判所によって選任された後見人が財産の管理等を開始します。
後見が認められない場合や、後見開始の申立てを行ったにもかかわらず、保佐開始の決定がなされる場合もあります。審判の結果に異議がある場合、2週間以内であれば、不服申し立てが可能です。
法定後見制度にかかる費用
法定後見制度の利用にかかる費用について解説します。
審判申立てに必要な費用
法定後見制度の申立てに必要な費用を以下の表にまとめました。これらの費用は申立人が準備しなければなりません。
| 項目 | 金額 |
| 収入印紙 | 3,400円 |
| 送達・送付費用 | 3,000円代~4,000円代 |
| 医師の診断書の作成費用 | 5,000円~1万円程度 |
| 住民票・戸籍謄本 | 数百円/部 |
| 登記されていないことの証明書の発行手数料 | 300円程度 |
| 鑑定費用 | 5万円~10万円以上 |
| その他の費用 | – |
それぞれの項目について詳しく解説します。収入印紙
申立て手数料として800円、成年後見人登記手数料として2,600円、合計3,400円分の
収入印紙が必要です。また、保佐や補助の申立てで、代理権や同意権の付与申立てをする
場合は、さらにそれぞれ800円分の収入印紙を用意する必要があります。
送達・送付費用
審判書をはじめとする各種書類の送付等に必要な郵便切手の料金です。費用や切手の額面、枚数などについて細かい規定があり、さらに規定については各裁判所で異なるため、事前に管轄の裁判所にきちんと確認しておくことをおすすめします。例として東京家庭裁判所の場合、後見申立ての場合は3,270円、保佐および補助の申立ての場合は4,210円分の切手が必要です。
医師の診断書の作成費用
本人に判断能力がないことを明らかにするために医師の診断書が必要です。医療機関に
よって費用は異なりますが、概ね5,000円~1万円程度のことが多いです。
住民票・戸籍謄本
発行手数料は自治体によって異なりますが、概ね住民票は300~400円程度、戸籍謄本は450円程度です。
登記されていないことの証明書の発行手数料
本人が任意後見制度などを利用して既に後見を受けている場合は、新たな後見人の選任はできないため、後見登記がなされていないことの証明書の発行手数料が300円程度必要です。
鑑定費用
本人の判断能力がどの程度なのかを医師に鑑定してもらうための費用です。申立て時に用意する医師の診断書とは別のもので、裁判所が必要と判断した場合に鑑定が行われます。
鑑定が実施されるケースはそれほど多くありません。裁判所が公表している資料によると、2022年に鑑定が実施されたのは全体の4.9%、鑑定に要した費用は「5万円以下が、45.4%」「5万円~10万円が41.5%」でした。
その他の費用
場合によっては、所有する銀行口座の残高証明書や、不動産の登記事項全部証明書が必要になり、それらの発行についても手数料が必要となります。また、手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合は、少なくとも10万円程度の費用が掛かります。
法定後見人に支払う報酬
家族以外の第三者が法定後見人に選任された場合には、報酬を支払わなければいけません。
報酬額は裁判所が決定しますが、一般的には月額2万円程度が目安です。
管理する財産が高額である場合は、管理事務が煩雑になることから報酬も高くなる傾向があります。管理する財産額が1,000万円以上、5,000万円以下の場合の報酬は月額3~4万円、5,000万円を超える場合には月額5~6万円が目安です。
また上記の基本報酬の他に、特別困難な事情があった場合には、基本報酬の50%を上限に付加報酬をう必要が生じます。
特別困難な事情とは、多数の収益不動産があり管理が複雑である場合や、親族間で意見の相違があった場合に調停が必要な時だったり、成年後見人に不正があり、新しく選任された後見人がその処理をしなければならない時などが該当します。
法定後見制度についてお困りな方は気軽にご相談ください
法定後見制度の内容、メリット・デメリットや手続きの方法・費用について解説しました。法定後見制度は、認知症などで判断能力が衰えてしまった人を守る重要な制度です。しかし手続きは
複雑で、利用にあたって留意すべき事項も多数あります。
一般社団法人 終活協議会では、高齢者の終活に関する困りごとや悩みごとを解決する「心託」サービスを提供しています。
成年後見の手続きの代行、入院や施設の利用の際の身元保証、入院時の付き添いや日常生活におけるサポートサービスなどを提供する「安心プラン」、それに加えて、亡くなった後に必要な葬儀・納骨・各種行政手続きなどの終活にまつわる全てのサービスを提供する「完璧プラン」など、終活サービスを提供しています。
成年後見制度をはじめ、終活に関する困りごとがあれば、どんな些細なご相談でも受け付けております。専門知識を持つスタッフはもちろん、実績豊富な弁護士や司法書士が誠心誠意対応いたしますので、お気軽にお電話ください(受付時間は 10:00~17:00となります)。また、会社やサービスに関する資料請求をご希望の方は、下記のページからご連絡をお願いいたします。資料請求については24時間受け付けておりますので、いつでもご連絡くださいませ。
監修

- EMパートナーズ法律事務所 代表 一般社団法人 終活協議会 顧問弁護士
-
所属:東京弁護士会
◇経歴
日本大学法学部卒
明治大学法科大学院修了
2007年 弁護士登録・都内の法律事務所入所
2011年 「遠藤治法律事務所」開設
2021年 現事務所名へ名称変更
2022年 「一般社団法人 終活協議会」顧問弁護士就任
◇著書等
東京弁護士会編「労働事件実務マニュアル」改訂担当(共著)
東京弁護士会法友会東日本大震災復興支援特別委員会編「3・11震災法務Q&A」(共著)
東京弁護士会春秋会編「会社・経営のリーガル・ナビQ&A」(共著)
最新の投稿
 おひとりさま2023年9月11日終活詐欺とは?よくある手口とすぐにでも対策できる方法を業界関係者が解説
おひとりさま2023年9月11日終活詐欺とは?よくある手口とすぐにでも対策できる方法を業界関係者が解説 任意後見制度2022年11月8日法定後見制度とは?手続きの流れや費用・任意後見制度との違いを業界関係者が解説
任意後見制度2022年11月8日法定後見制度とは?手続きの流れや費用・任意後見制度との違いを業界関係者が解説 おひとりさま2022年9月2日身元保証法(身元保証に関する法律)とは?弁護士が解説
おひとりさま2022年9月2日身元保証法(身元保証に関する法律)とは?弁護士が解説
この記事をシェアする