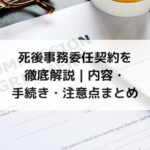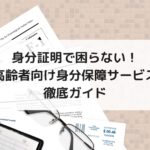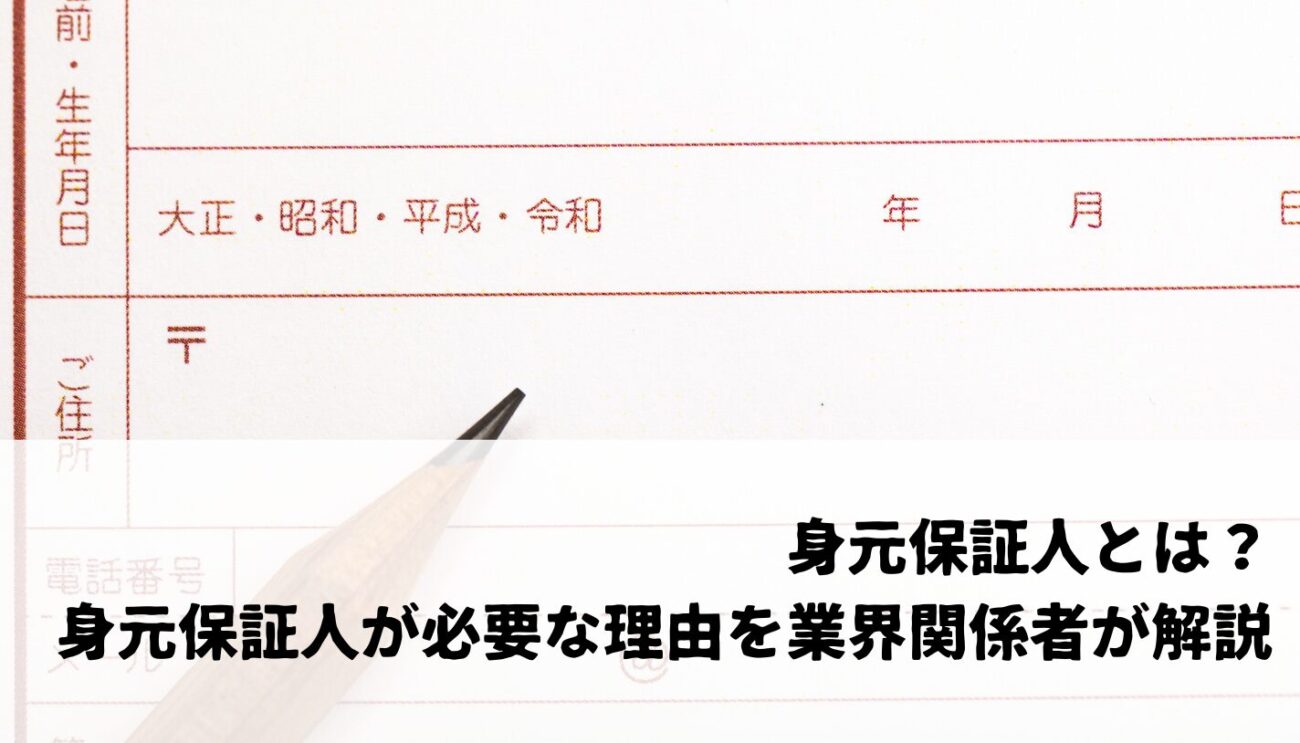
目次
身元保証人とは
身元保証人とは、その人の身元(素性)を保証し、何かあった時には本人の代わりに責任を負う人のことです。
例えば、身元保証人は就職や賃貸住宅の契約、病院への入院、高齢者施設への入所といった様々なライフイベントで必要となります。
最近では独り身で親族とも疎遠な方が増え、入院・入所の際に身元保証人を頼める人がいないことが社会問題となっています。
2019年に日本総研が発表したレポートでは「2040年には、高齢者世帯(単身世帯と夫婦のみの世帯)の約半数に当たる859万世帯、人数でおよそ1,000万人以上の高齢者が親族に身元保証を依頼できなくなる」と推測しています。
そんな今だからこそ、身元保証人について学んでおくことが重要です。
そこで今回は、身元保証人の重要性・役割や、身元保証人を選ぶ際のポイントについて解説していきます。
なぜ身元保証人が必要になる?その理由・目的とは
身元保証人の準備が必要なければ手続きがもっとスムーズに進むのにと思うかもしれません。
相手方から、身元保証人を求められる理由は、身元保証人がこれから紹介するような役割を持っているためです。
なお、身元保証人にどこまでしてもらうかは相手方によっても異なり、法律で定められているわけではありません。
それでは、なぜ身元保証人が必要になるかその理由を説明していきます。
本人の身元を確認するため
相手側が身元保証人を設ける目的は、本人の身元(素性)を明らかにして、本当に実在する人物であるかを、身元保証人となる方に証明してもらうためです。
ちなみに、就職時の身元保証人の場合、身元保証人を設けることで、本人の経歴や素行に問題がないことを会社に対して保証する目的もあります。
緊急時の連絡先を知っておきたいため
例えば本人が病院に運ばれた場合、本人に何かあった場合に相手方が誰に連絡していいかをはっきりさせるために身元保証人を設けます。
もしもの際に損害を補償してもらうため
器物の損害や支払いの遅滞など、本人が相手方に対して何らかの損害を発生させた場合、当然、相手方は損害の補償を求めてきます。
本人が支払いをしない(できない)場合に、身元保証人が代わりに支払う役割があります(金銭保証)。
ただし、契約時に「極度額」(上限額)を定めるので、無制限に責任を背負わされることはありません。
それに、保証することになったとしても、身元保証人は条件を満たせば解除権で身元保証人を辞めることもできます。
荷物などを引き取ってほしいため
介護施設や賃貸物件における身元保証人の場合ですが、本人が死亡するなどして退去となった場合に私物を撤去してもらう必要があります。
身元保証人にはこうした本人の荷物などを引き取る役割もあります。
身元引受人・連帯保証人・後見人とは?身元保証人との違い
身元保証人によく似た言葉に「身元引受人」「連帯保証人」「後見人」があります。
まずは、それらと身元保証人との違いについて説明します。
身元引受人との違い
身元保証人と身元引受人は、明確な区別なく使われることが多いです。
病院や施設によっては、身元保証人と同じ意味で身元引受人という用語を使っているケースもあります。
厳密には、身元引受人という場合、病院を退院したり施設を退所したりする際に本人を引き受ける人の意味になります。
また、本人が亡くなった時の遺体の引き取りや各種手続きについても、身元引受人が行います。
連帯保証人との違い
連帯保証人は法律上明確に定義されており、債務や弁済の責任を果たせなくなった本人の代わりに返済義務を負います。
保証人には債務者本人が債務を弁済できない場合に支払い義務が発生しますが、連帯保証人の場合は本人と全く同等の責任を持つことになります。
債務者本人に支払い能力があるにもかかわらず支払いを拒否した場合でも、連帯保証人は代わりに支払わなければなりません。
身元保証人も、本人が施設に損害を与えたり支払いが滞ったりした時に債務を弁済する義務がありますが、すべてを支払わなければならないわけではありません。
後見人との違い
後見人とは、認知症などで高齢者本人に判断能力がなくなった時に、本人に代わって財産管理および契約などの法律行為を行う人を指します。
後見人には「任意後見人」と「法定後見人」の2種類があり、「任意後見人」は判断能力が衰える前に選任し、「法定後見人」は判断能力が衰えた後に選任されるという違いがあります。
身元保証人と後見人は、入院・入所の手続きを代行する点などの一部の役割が同じですが、最も大きく異なるのは、後見人は債務の保証ができない点です。
後見人の役割は、高齢者本人の代理として契約や財産管理を行うことであるため、債務を保証することはできません。
また、通常は介護なども後見人の職務の対象外です。一方、身元保証人は、各種手続きや入院時の付き添いなど、身の回りのサポートなども担うのが一般的です。
身元保証人になるための条件とは
誰でも身元保証人になれるわけではありません。身元保証人になれる条件が大きく分けて2つあります。
本人と面識がある方
身元保証人は身元を保証しなければならないので、本人との面識がある必要があります。
ただし、必ずしも血縁関係でなければいけないといった決まりはありません。
本人との続柄は重視されず、直接の利害関係がない友人や知人、身元保証サービスを提供する会社であっても身元保証人になることは可能です。
関連記事:身元保証サービスとは?費用、注意点などを業界関係者が紹介
安定した収入がある方
身元保証人になることができる人は、資力を備えていることも必須条件となります。
そのため、一般的には、きちんとした仕事に就いていること、安定した収入を得ていること、一定以上の年収があること、資産状況が好ましいこと、年齢が18歳以上であること、などが確認できる書類を提出することが求められます。
それゆえ、身元保証人になることができない人もいます。
- 年金受給者
- 専業主婦・主夫
- 無職の人
- 高齢のご兄弟
- 高齢の配偶者
- 遠方の親戚
※条件は、場合ごとに、また契約内容によっても異なります。実際に各所の担当者に問い合わせて確認することをおすすめします。
なお、すでに後見人を務めている方は身元保証人になることはできません。
身元保証人になるリスクとは
前述の通り、身元保証人は本人がもし損害を与えた場合に、極度額(上限額)の範囲内で損害を補填する必要があります。
ゆえに、経済的な負担が生じるリスクはあります。
また、本人との関係が悪化するリスクもあります。本人に何かあった時に緊急連絡先としてトラブルの一次対応をしなければならないケースもあり、時間的・体力的な負担が生じるリスクもあります。
実際にはこうしたケースは少ないのですが、身元保証人にはある程度のリスクが伴うため、身元保証人を依頼する側と引き受ける側が、リスクについて認識しておく必要はあります。
ただし、身元保証人には「期限」(3年もしくは5年)がある
身元保証人の責任が重くなりすぎないように、「身元保証に関する法律」という法律で、身元保証人の期限が定められています。
相手方が期限を定めなかったときは3年、期限を定めても最長で5年です。
なお、期限後、身元保証人を更新する際には都度契約を締結しなおさなくてはならず、身元保証人の契約を自動で更新するといった、自動更新の制度を設けることはできません。
身元保証人には「解除権」が認められている
同じく「身元保証に関する法律」という法律で、身元保証人には条件付きで「解除権」が認められており、身元保証人が自ら辞める決断を下すことができます。
身元保証人の責任が重くなりすぎないように配慮されています。
身元保証書(身元保証契約書)とは?記入時の注意点
身元保証人になってもらう方には「身元保証書(身元保証契約書)」の記入(基本的には署名・捺印・身元保証人に関する情報の記入のみ)を求められることがあります。
身元保証人となることは一種の契約行為となるので、確かに身元保証人であることを書面に残しておくのは重要です。
それでは、身元保証書記入時の注意点をご紹介します。
身元保証人の保証内容(役割)をよく確認する
身元保証人の役割は、相手方によって大きく異なります。
単に身元を保証するだけの役割を担ってもらう場合もあれば、金銭保証からトラブル時の対応まで幅広い役割を担ってもらう場合もあります。
よく保証内容を読んだり、担当者に確認を取ったりして、どこまでの責任を負う必要があるのか確認しましょう。
必ず身元保証人になってもらう人に直筆で書いてもらう
身元を保証してもらわなくてはいけないので、身元保証人に書いてもらう必要があります。代筆は認められません。
署名や捺印に不備があると、身元保証書が無効になる可能性があるため注意が必要です。
提出期限を守れるように手配する
近年は核家族化により、家族が遠方に住むケースも増えてきました。「郵送」の必要がある場合、提出期限を見込んで、身元保証書を記入してもらうように手配しましょう。
高齢社会の今だからこそ知りたい!高齢者における身元保証人の重要な役割とは

みなさんが若ければ家族も元気で現役世代であることも多いと思われるので、身元保証人を父親や母親などの家族にお願いすることは比較的簡単です。
ただ、みなさんが高齢になるにつれて周りの家族も高齢になっていきます。亡くなってしまう家族も増えていきます。
そのため、高齢になってから身元保証人になってくれる人を探すのは大変です。
高齢の方はもちろん、自分がこの先誰に身元保証人を頼めそうか考えておくことが非常に重要となります。ここでは、高齢者にとって身元保証人はどのくらい重要な役割を担うのか解説します。
1:入院中・入所中のサポート
病院に入院したり、高齢者施設に入所する際には、多くの書類を作成しなければなりません。また、入院・入所時には生活用品や衣類の準備も必要です。
高齢になると書類の手続きや必要品の準備を一人で行うのは大変です。そこで身元保証人は、入院・入所時の煩雑な手続きのサポートや、生活用品の準備および購入といった生活支援を担うことが求められます。
2:入院計画・ケアプラン・医療行為へのサポート
入院時の計画書や入所時のケアプランは、高齢者にとってはわかりづらい内容です。
認知症でなくとも、年齢とともに判断能力は衰えてきます。身元保証人には、高齢者本人にわかりやすく計画書やケアプランについて説明し、かつ本人の代理として施設側と交渉をすることが求められます。
3:緊急時の対応
容態が急変したり、事故やトラブルなどがあった際は、病院や施設から対応を求める連絡が入ることがあります。身元保証人はそういった際の緊急連絡先として、連絡を受けて対処する必要があります。
4:退院・退所時のサポート
退院・退所する時も様々な手続きが必要です。手術で入院した場合、退院後の療養計画も把握しなければなりません。各種手続きの代行や、退院・退所時の同行も身元保証人が行う場合があります。
5:費用の支払い保証
もし入院・入所費用の支払いが滞った場合、身元保証人が代わりに支払わなければなりません。病院や施設が身元保証人を求める理由としては、この点がもっとも大きい割合を占めているでしょう。
金銭に関わる内容であるため、入院・入所時に身元保証人はサインする書類の内容を細かく確認することが重要です。
6:死亡時の対応
万が一高齢者本人が亡くなった場合の遺体や遺品の引き取りは、身元保証人に求められる大切な役割です。葬儀の手配や死後の事務手続きは、施設側と交わす身元保証契約の範囲には含まれませんが、身元保証サービスを利用する場合は手続きもサービスの一部として組み込まれている場合があります。
一般的に葬儀の手配や死後の事務手続きは身元引受人が担いますが、最近では身元保証人が包括して行うケースもあるようです。
高齢になってから身元保証人を必要とするシーンを考えておく
高齢の方はもちろん若い方でも、将来自分がどんなシーンで身元保証人が必要になるか考えておくことが非常に大切です。ここでは高齢になると、特にどんなシーンで身元保証人が必要になり、困りやすいのかご説明します。
「終の棲家(ついのすみか)」として、賃貸物件に入居するとき
高齢になると収入や同居人も限られてきますので、自分の身の丈に合い、生涯を終えるまで生活する場所、いわゆる「終の棲家(ついのすみか)」を自然と探すようになります。もし「この先は賃貸物件に住みたい」と思い立ったら、賃貸物件に入居する際に身元保証人が必要となります。
入院するとき
いつまでも健康でいたいものですが、高齢になるとどうしても病院にかかりきりになってします。医療機関は一般的に入院が必要になった時に身元保証人を求めます。厚労省によると6割を超える医療機関が身元保証人を必要としているそうです。
身元保証人がいないことを理由に入院することを拒むことはできませんが、身元保証人がいないことで入院手続きに遅れが出るなど、命にかかわる恐れがあります。なお、本人が寝たきりなどで意思疎通が取れない場合、身元保証人に対して本人の希望を確認することがあります(医療行為への同意は原則本人のみ)。
介護施設に入居するとき
自宅介護では限界で、介護施設に入居するとなった場合にも入居手続きで身元保証人が必要となります。こちらも身元保証人がいないことを理由に入居を拒否することはできません。しかし、高齢社会であるために介護施設は順番待ちになることも珍しくなく、身元保証人がいないことでスムーズに手続きが進まずになかなか介護施設に入居できないことも想定されます。
身元保証人がいない、身元保証人を頼めない高齢者は今後増加
今後、身元保証人を準備できないケースは増えていくと思われます。主に次の2つが増加の要因です。
一人暮らし世帯の増加
一人暮らし世帯の増加により、一人で暮らす高齢世帯(いわゆる「おひとりさま」)が増加の一途をたどっています。一般的には同居する家族に身元保証人を依頼する場合が多いのですが、一人暮らしだとそうした身寄りが少ない傾向にあることから、身元保証人を準備できない方が増えるようです。
身寄りがいるとしても身元保証人を頼みにくい
もし家族などの身寄りがいるとしても「自分のことで家族に面倒をかけたくない」「忙しい家族に頼むのは気が引ける」「喧嘩をして今ではすっかり話していない」などと心理的に頼みにくい方も少なくありません。こうした家族との心理的な距離の遠さも身元保証人を準備できない方が増える要因の一つです。
身元保証人がいない場合の対処法とは
もし身元保証人がいない場合は次の3つの方法をご検討ください。
身元保証人がいなくても手続きを進められるか聞いてみる
様々な手続きで身元保証人が必要となりますが、身元保証人をいないことを理由に拒むことは認められません。そのため、「頼れる家族がいない」などと事情を説明したうえで、身元保証人不要で手続きを進められないか一度確認してみましょう。
友人を頼る
身元保証人は家族である必要はありません。身元保証人の条件は面識があることと、十分な収入があることなので、その2つさえ満たしていれば友人でも構いません。もし親しい間柄の友人がいれば身元保証人を依頼してみてもいいでしょう。もともと務めていた会社の後輩で友人の方に身元保証人を依頼したというケースも聞いたことがあります。
身元保証サービスを利用する
身元保証会社が身元保証人を代行するサービスを提供しています。料金はかかりますが、身元保証人がいないなら身元保証サービスを利用するのが最も確実な対処法です。
身元保証人を頼める人が周りにいない場合は、以下のコラムを参照ください。
【終活】身元保証人がいない時はどうするのがおすすめか?その対策とは?
身元保証代行会社を選ぶ際のポイント
親族・知人に身元保証を頼める人がいない場合は、身元保証の代行サービスを提供している会社の利用を検討しましょう。
身元保証の代行サービスを行う会社は多く、サービスの内容もさまざまです。そのため、依頼する会社を選ぶ際は以下のポイントに留意して慎重に選定しましょう。
1:要望を明確にする
はじめに、なぜ身元保証人が必要なのかを明確にしなければなりません。入院費用の支払い保証だけが必要なのであれば、入院保証金や預託金を預けることで身元保証人を免除してもらえるケースもあります。生活のサポートや死後事務を委任するのであれば、それらのサービスを組み合わせたプランを提供している会社を選ばなければなりません。自分が困っていること・必要としていることを明確にし、どんな代行サービスが必要なのか見極めることが、失敗しない会社選びの第一歩です。
2:複数の会社を比較検討する
1社だけではなく複数の会社に相談して比較検討することをおすすめします。
1社に相談しただけで即決してしまうと、後でさらに理想的な会社が見つかった場合、後悔してしまう可能性があります。
また、複数の会社の料金やサービス内容を比較することにより、身元保証サービス全般の知識が深まり、当初に想定していた以上のサービスを受けることが可能になるかもしれません。
さらに、問い合わせをした各社の対応力を比較することで、会社ごとの長所・短所が見えてきます。
ただ、何社も比較検討していると、情報が多くなり判断が難しくなってきてしまうため、3社前後で比較するのがおすすめです。
3:契約内容を納得できるまで聞く
契約する際には細かい契約内容を理解しなければなりません。一度の説明だけで契約内容を理解できなかった場合は、納得できるまで何度でも相談しましょう。身元保証サービスだけでなく、様々な付帯サービスが含まれた高額なプランを契約させようとする悪質な会社もあります。そのため、必要なサービスが含まれているか、不要なサービスは含まれていないかをきちんと確認することが必要です。
対応が迅速で、なおかつ丁寧で分かりやすく契約内容を説明してくれる事業会社を見極めていきましょう。
4:支払い内容を理解する
料金について「一回限りの支払いか」「毎月・毎年の支払いが発生するか」を事前に認識しておくことも重要なポイントです。
「作業ごとに細かく料金が発生する」ような料金設定をしている会社もあるため、総計で掛かる金額を事前に聞くことをおすすめします。
また会社によっては、すぐに解約できないようにした上で、定期的に料金が発生したり、事あるごとに追加料金が発生したりする悪質な契約内容を締結させようとする会社もあります。
そのため、「一回限りの支払いでサービスを利用できる会社」がおすすめです。
ただし、契約内容を事前に確認しないと、自身が希望する身元保証サービスの内容と、会社の提供するサービス内容が合致せず、無意味な契約になってしまう可能性もあります。契約内容が自身に合っているか事前に確認しましょう。
5:事業会社の信頼性をチェックする
個人に身元保証人を依頼する場合、保証人が亡くなったり病気になったりして保証人を続けられなくなるケースも想定されます。
一方、法人に依頼する場合は、そのようなリスクは比較的小さくなります。しかし、会社は倒産する危険性があるほか、過去にトラブルを起こしつつも法人名を変えながらサービスを続けている悪質な会社も存在しているため、経営は安定しているか、実績がどの程度あるか、過去に大きなトラブルを起こしていないか、会社の所在地が明確であるか」といった、信用のおける会社であるかどうかを契約前にチェックしましょう。
条件に全てあてはまる会社を選ぶことは必須と言えます。
6:契約内容の変更・解約の条件を把握する
年齢を重ねるにつれて心身は変化します。契約当初は身の回りのことが自分でできたとしても、数年後にはできなくなるかもしれません。
そのため、新たにサービスを追加できるのか、その場合の費用はどうなるのかを事前によく確認しておくことをおすすめします。
場合によっては、サービスの削除や解約をしなければならないケースも考えられます。
契約内容の変更・解約ができるのか、その時の違約金や手続き方法についても事前に把握しておくことが大切です。
上記のことを考えると、一度料金をお支払いすれば身元保証サービス全ての内容に対応している事業会社を選ぶのが最良かと思います。
一般社団法人 終活協議会は身元保証でのお困りごとに全て対応
一般社団法人 終活協議会の「心託サービス」は、入院・入所時の身元保証だけでなく、
日常生活のサポートや緊急時の対応から亡くなった後の身元保証人が行う「全ての役割」に対応しているプランを用意しております。オプション費用や追加費用は一切なく「入会金と基本料金のみ」で提供しています。
⇒一般社団法人終活協議会の心託サービスについて
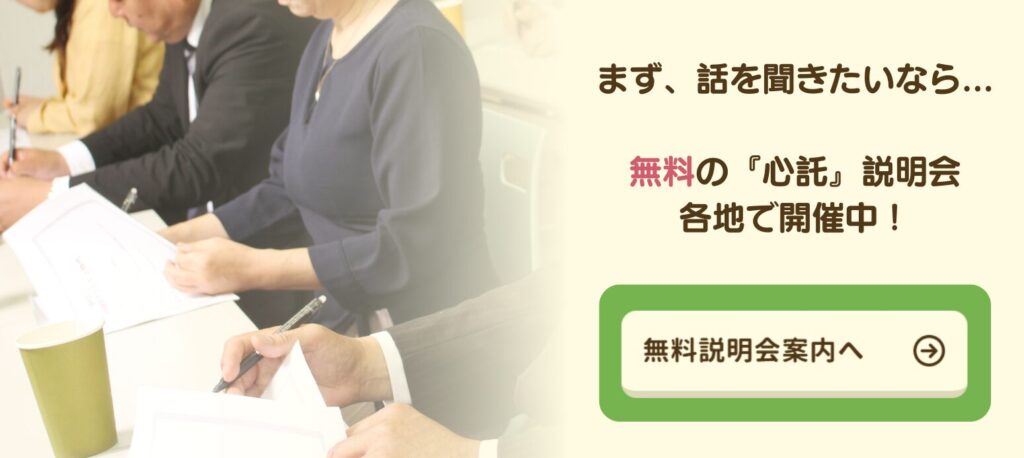
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 死後事務2025年7月3日死後事務委任契約を徹底解説|内容・手続き・注意点まとめ
死後事務2025年7月3日死後事務委任契約を徹底解説|内容・手続き・注意点まとめ 死後事務2025年7月3日死後手続き代行サービスとは?必要性と選び方を徹底解説
死後事務2025年7月3日死後手続き代行サービスとは?必要性と選び方を徹底解説 おひとりさま2025年7月3日老人ホームの入居に必要な保証人とは?条件と対策を徹底解説
おひとりさま2025年7月3日老人ホームの入居に必要な保証人とは?条件と対策を徹底解説 おひとりさま2025年7月3日身分証明で困らない!高齢者向け身分保障サービス徹底ガイド
おひとりさま2025年7月3日身分証明で困らない!高齢者向け身分保障サービス徹底ガイド
この記事をシェアする