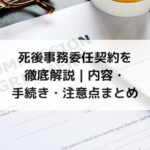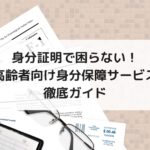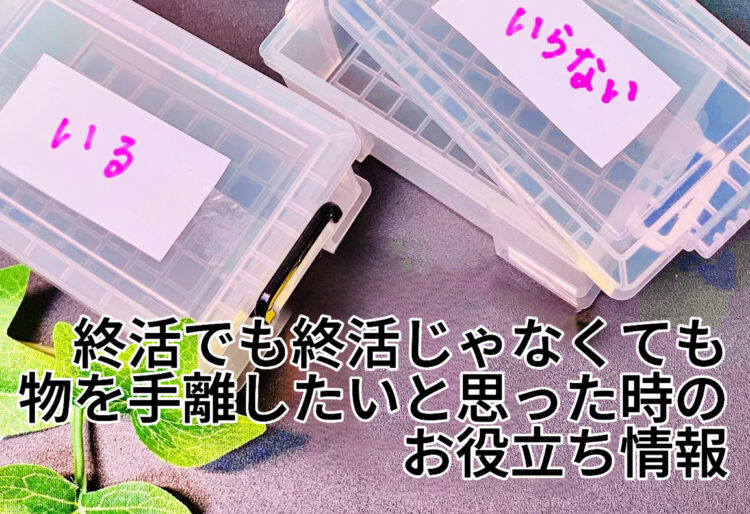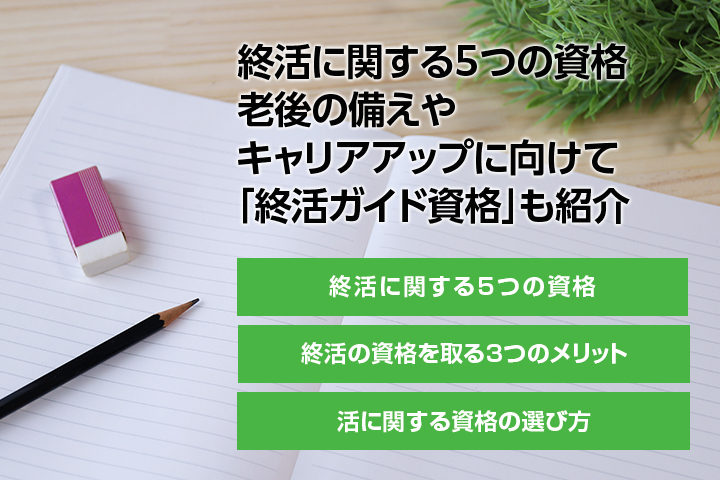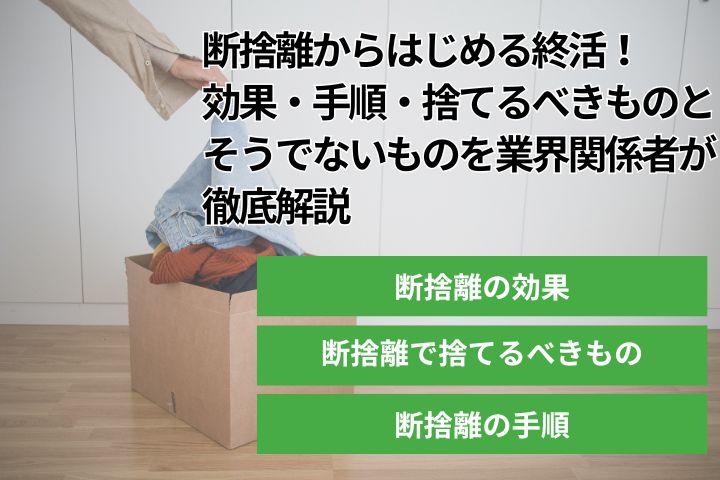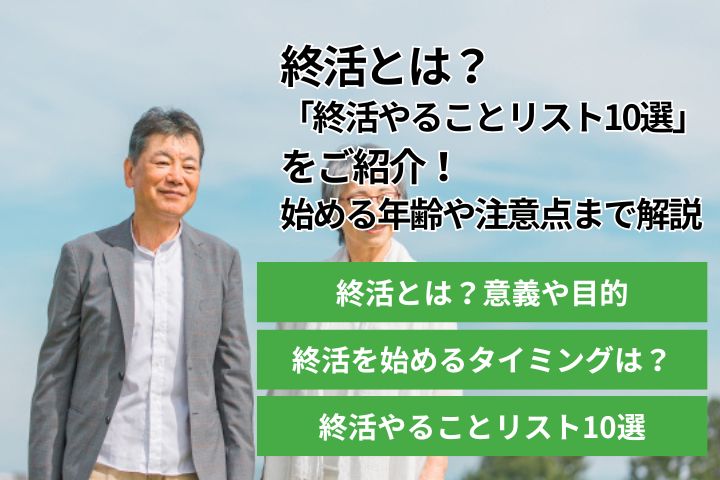
「終活」という言葉自体は広く使われるようになりましたが、具体的にどのようなことをすればよいのかイメージがつかない方もいるのではないでしょうか?
そこでこの記事では、終活を始めるおすすめのタイミングや、終活でやっておきたいことを紹介します。
終活の重要性を理解し、正しい順序で進めましょう。
目次
終活とは?意義や目的

終活とは、人生の最期をより良く迎えるため、事前に準備する活動のことです。終活の具体的な内容には、資産や所持品の整理、葬儀・お墓の検討、介護・医療の方針決めなどがあります。
終活という言葉が生まれた背景には、少子高齢化があります。
2008年頃から、社会保障制度の安定性と持続可能性の観点から、制度の見直しが必要な状況になり、老後の生活に不安を感じる方が増えました。
そこで老後の生活に備えた事前準備や家族の負担を軽減しようと考える方が増え、終活が定着したと考えられます。
終活には以下のような目的があります。
- 老後の生活を充実させる
- 死に対する不安を解消する
- 家族の負担を軽減する
- 介護や葬儀の希望を家族に伝える
それぞれの目的について、詳しく解説します。
老後の生活を充実させる
終活では、これまでの人生を振り返り、気持ちに整理をつけていきます。
この時間は、余生を考えるきっかけになるでしょう。
老後の生活を楽しめない理由のひとつに、漠然とした不安や恐怖が挙げられます。
しかし、なんとなく不安に感じていた悩みや問題が明確になると、対策が立てられます。
モヤモヤしていた気持ちが晴れやかになると、趣味を楽しむ余裕が生まれたり、新しいことに挑戦する活力が湧いたりするでしょう。
死に対する不安を解消する
「万が一の話をするのは縁起が悪い」という方もいますが、人間は誰しもいつかは終わりを迎えます。
終活を通じてさまざまな整理をすると、最期を迎える心の準備にもなるでしょう。
家族の負担を軽減する
人が亡くなると、葬儀や火葬の準備はもちろん、生命保険金や遺族年金の請求、各種サービスの解約手続きなど、様々な手続きや作業が遺族を待ち受けます。
しかし、事前に終活として断捨離や資産の整理をしておくと、遺された家族の手間は大幅に減り、ゆっくりと故人とお別れする時間を過ごせるかもしれません。
また、遺産相続や葬儀の形式についてのトラブルも防げるでしょう。
介護や葬儀の希望を家族に伝える
家族には、希望の最期を伝えておきましょう。
病気やケガのリスクは、歳を重ねるとともに高まるため、介護が必要になる可能性があります。
自分には関係ないと思わず、介護が必要になったときのことを考え、自宅介護を希望するのか、施設への入所を検討するのかについて家族と話し合いましょう。
理想の介護サービスを受けられる施設を探しておくと、いざという時にも慌てず対応できます。
また、葬儀やお墓など、亡くなったあとのことも家族に希望を伝えておきましょう。
最近では、葬儀やお墓の形式もさまざまで、多くの選択肢があります。
終活を始めるタイミングは?

終活を始める年齢やタイミングに、明確な決まりはありません。
しかし、終活でやるべきことは思いのほか多く、時間に追われる可能性があるため、早めに始めるのがおすすめです。
おすすめのタイミングは以下の通りです。
- 定年退職で余裕ができたとき
- 家庭環境に変化があったとき
- 親族や友人が亡くなったとき
- 自身の健康に不安を覚えるようになったとき
終活について考え始めたタイミングが、適切なタイミングといえるでしょう。
終活やることリスト10選

終活の意義や目的がわかったところで、実際に取り組むべきリストを紹介します。
どれも終活に欠かせない作業ですが、すべての人に当てはまるとは限りません。
自分の終活には必要ない、取り組みたくないと思われるのであれば、いったんリストから外してしておきましょう。
時間が経ち、再度気になり始めたとき、意欲が湧いたときに取り組んでも問題ありません。
老後にやりたいことをリストアップする
まずは、残りの人生をどのように送りたいか、自分の気持ちを整理しましょう。
そのうえで、やり残したこと、新たに挑戦したいことをリストアップします。
「都会暮らしから田舎暮らしにシフトしたい」「挫折した趣味や勉強を再開したい」「遠く離れた親戚と温泉旅行したい」など、さまざまな角度から考えてみましょう。
とくに、仕事が生きがいになっていた方は、退職によって生きる意味や目的を見失いがちです。やりたいことリストは、生きる意欲にもつながります。
エンディングノートを作成する
エンディングノートとは、家族や友人に向け、必要な情報や自分の想いを書き示したノートのことです。
介護や葬儀などの希望を書いたり、銀行口座や生命保険、各種パスワードなどを備忘録にしたりして利用します。
エンディングノートの書き方には、遺言書のような決まりはありません。
エンディングノート専用として構成されたノートを使うものいいでしょう。
以下の項目は、エンディングノートに記載する主な情報です。
- 自身の個人情報(生年月日、本籍、血液型など)
- 家族の情報(家族構成、それぞれの家族の生年月日や住所・勤務先など)
- 交友関係(親戚・友人・知人のリスト、葬儀で参列してほしい人のリストなど)
- 資産情報(銀行口座、保有不動産、株券、保険など)
- 葬儀に関する情報・希望(宗旨、菩提寺、葬儀の規模・形態の希望など)
- 埋葬に関する情報・希望(埋葬方法、先祖代々のお墓の情報など)
- 医療情報(かかりつけ医、既往歴、延命措置や終末医療に関する希望など)
- 遺言書に関する情報(遺言書の有無、保管場所、形式内容など)
- 遺品整理に関する情報(処分方法、価値のあるものなど)
- 家族に伝えたいこと(感謝の気持ちなど)
- 老後の計画内容(新たな目標、やりたいことなど)
ただし、あくまでも「故人の希望」を伝える手段のひとつで、遺言書のように法的な効力はありません。
⇒おすすめしたいエンディングノートの書き方を業界関係者が解説
身の回りを整理する
遺族にとってもっとも負担が大きいのは、遺品整理でしょう。
思い出のある遺品を処分するのは、精神的に大きな負担がかかります。
また価値の高いものが含まれている場合は、取捨選択に苦労するでしょう。
本人が元気なうちに整理し、処分できるものは処分しておくと、家族の負担を軽減できます。
どうしても捨てられないもの、死後に処分してほしいものがある場合は、エンディングノートの活用がおすすめです。
交友関係を整理しリストを作る
交友関係を整理してエンディングノートに連絡先を記載しておくと、葬儀の案内がスムーズになり、家族の負担軽減につながります。
自分の交友関係を振り返り、どのような方々とどのような関係を築いてきたか見直しましょう。
続いて、今後どのような関係を続けていきたいかを考えます。
「遠方に引っ越した友人に会いたい」「久しぶりに同窓会を開きたい」など、さらに具体的な計画に繋がると、充実した老後の生活を送ることができます。
資産を整理する
まずは、自分が持っている資産を一覧にして整理します。
不動産や預貯金、有価証券など、全ての資産を一覧にまとめましょう。
次に、それぞれの資産価値や状況を把握し、必要に応じて整理や見直しをします。
さらに、相続や贈与などの手続きを考え、将来の財産運用や相続税対策などについても検討しましょう。
資産の整理は大切な人に財産を残す準備にもなるでしょう。
医療・介護の方針を決める
医療・介護の方針決めは終活における重要な項目です。
まずは、将来の医療や介護に関する希望や考えを明確にしましょう。
病気や怪我になった場合の治療方針や入院・在宅療養の希望、介護が必要になった際の施設入所の意向などを考えます。
また、家族や信頼できる人と話し合い、自分の考えを共有し合意を得ることも大切です。
葬儀やお墓を検討する
自分が希望する葬儀の形式や場所、規模を考えましょう。
最近では、小規模でおこなう家族葬を選択する方が増えています。
新たにお墓を持つ場合は、お墓の形や場所、管理方法なども決める必要があります。
「お墓は家族代々受け継ぐもの」と認識している方も多いので、家族と意見が異なる場合は話し合い、合意を得ることが大切です。檀家に入っている場合は、僧侶との相談も欠かせません。
デジタルデータを整理する
デジタルデータとは、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などに残されたデータのことです。
クラウド上に保存されている写真や文書のデータ、各サイトへ登録している個人情報などが挙げられます。
デジタルデータは、目に見えにくいため見落としがちです。
定期購読や自動継続購入といったサブスクリプションサービスに加入している場合は、とくに注意が必要です。
サブスクリプションサービスを利用していると、亡くなった後も利用料金を請求されてしまいます。
家族が解約しようとしても、パスワードがわからず、時間や労力が膨大になる可能性があります。
使用しているサービスのアカウントやパスワード情報をまとめ、すぐに共有できる状態にしておきましょう。
⇒デジタルデータをトラブルなく引き継ぐ。デジタル終活の進め方と注意点を業界関係者が解説
遺言書を作成する
遺言書で大切な資産や遺志を明確にすることで、遺族間のトラブル防止に繋がります。
遺言書の作成方法は、大きく分けて2つあります。
ひとつは自分で手書きする「自筆証書遺言」、もうひとつは公証人に依頼する「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言はコストがかからず、気軽に思えますが注意が必要です。
なぜなら遺言書は、民法上の要件と自筆証書遺言書保管制度の要件、2つを満たす必要があるからです。
公正証書遺言はコストがかかりますが、専門家が作成するため、確実性があります。
不安な場合は、専門家に相談してみましょう。
参考:法務局(遺言書保管所)03 遺言書の様式等についての注意事項
老後を支えてくれる契約を確認する
判断力が低下すると、重要な契約が締結できなくなります。
独身で身寄りのない方、配偶者に先立たれている方、子どもが遠方にいてすぐに頼れない場合などは、老後をサポートしてくれる契約の利用を検討する必要があるでしょう。
具体的には、以下のような契約や制度があります。
- 成年後見制度
- 任意後見制度
- 財産管理委任契約
- 死後事務委任契約
⇒成年後見制度とは?メリットや手続き方法を業界関係者が分かりやすく解説
⇒死後事務委任契約とは?ご逝去の手続きで「親族に迷惑をかけたくない方・おひとりさまの方」でも安心
終活で注意したい3つのこと
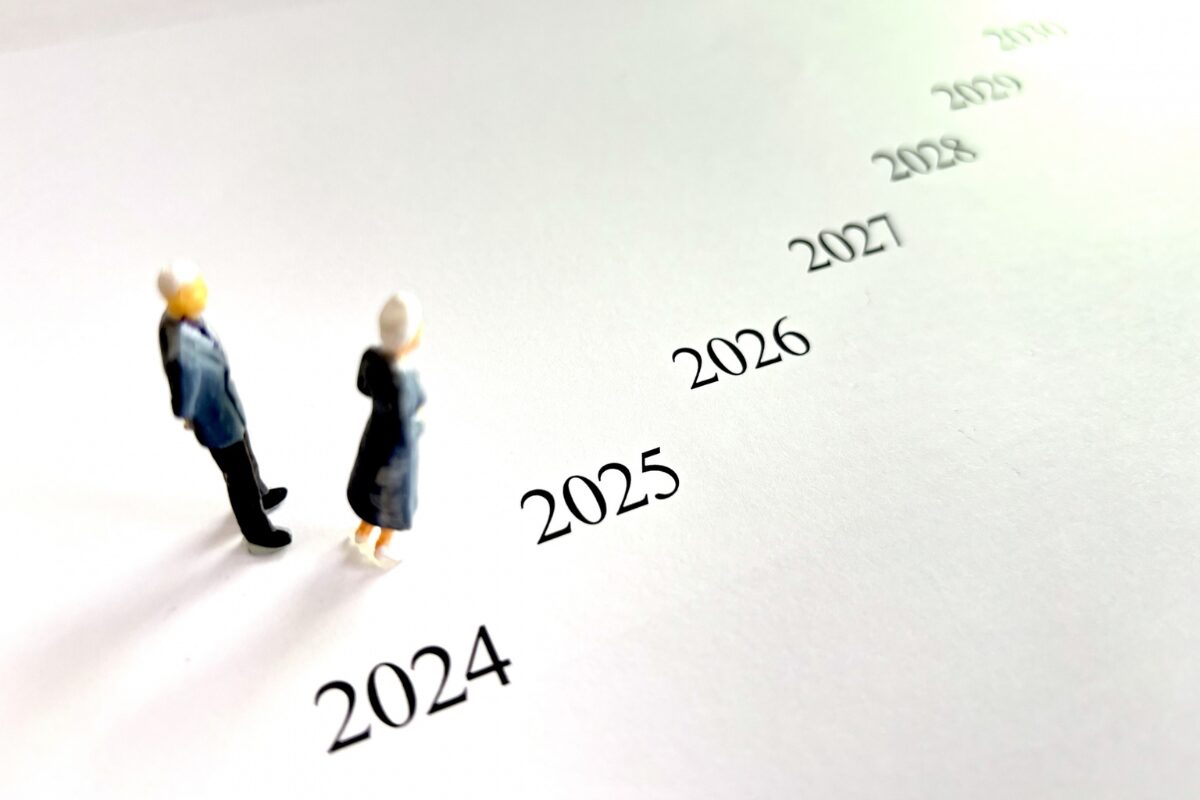
終活をおこなう際は、以下の3つに注意する必要があります。
- 自分のペースで進める
- 状況に応じて方針を見直す
- 家族との対話を忘れない
自分のペースで進める
前述したように、終活にはやるべきことがたくさんあります。
最初から張り切って進めると、途中で息切れをしてしまい、挫折につながります。
とくに断捨離は、過去と向き合い、決断しなくてはなりません。
精神力や体力が必要な作業ですので、計画的に進めましょう。
疲れを感じたときは、適度な休憩も大切です。
状況に応じて方針を見直す
事前の計画は大切ですが、予定通り進まないパターンも数多くあります。
たとえば、配偶者が亡くなったあとの生活です。
長年住み続けた自宅を離れたくないと思っていても、体力の衰えから、ひとり暮らしに不安を抱く可能性もあるでしょう。
高齢者施設への入居や、離れて暮らす家族との同居を検討するなど、柔軟な対応が求められます。
当初の計画に固執する必要はありません。終活の中で違和感があれば、計画変更も正しい判断です。
家族との対話を忘れない
終活の主な目的は、自分の希望を家族に伝え、理想の最期を迎えることです。
しかし、家族に迷惑をかけないのも終活の目的。
葬儀や埋葬方法の希望を一方的に押し付けるのではなく、家族の意見にも耳を傾ける姿勢が求められます。
また、遺言書の保管場所を共有しておくのも忘れずに。
相続手続きがすべて終わってから、遺言書が見つかるケースもまれにあります。
日ごろの会話を通してそれぞれの価値観を共有し、尊重し合う雰囲気づくりを目指しましょう。
専門家の助けを借りて満足度の高い終活を

終活は長い人生を振り返り、残りの人生をより良く過ごすための活動です。
これまでの人生に感謝したり、恩返しをしたりする前向きな時間ととらえましょう。
同時に、家族の負担を軽減する目的も果たす必要があります。
特に遺言書の作成や各種契約は、法的な問題に発展する可能性があります。
せっかく準備した遺言書が無効となってしまうと、家族に迷惑がかかるでしょう。
不安な方は、専門家の助けを借りてはいかがでしょうか。
一般社団法人 終活協議会では、終活にあたっての知識面のサポートから日常生活の支援、病院・介護施設利用時に必要な保証人代行まで、幅広いご支援が可能です。サービスについてより詳しく知りたい方は、下記のページより資料をご請求ください。
また、全国各地で無料相談会を開催していますので、終活についてお悩みの方はぜひお気軽にご参加ください。
下記のページからご予約が可能です。
⇒終活無料説明会申込ページ
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 死後事務2025年7月3日死後事務委任契約を徹底解説|内容・手続き・注意点まとめ
死後事務2025年7月3日死後事務委任契約を徹底解説|内容・手続き・注意点まとめ 死後事務2025年7月3日死後手続き代行サービスとは?必要性と選び方を徹底解説
死後事務2025年7月3日死後手続き代行サービスとは?必要性と選び方を徹底解説 おひとりさま2025年7月3日老人ホームの入居に必要な保証人とは?条件と対策を徹底解説
おひとりさま2025年7月3日老人ホームの入居に必要な保証人とは?条件と対策を徹底解説 おひとりさま2025年7月3日身分証明で困らない!高齢者向け身分保障サービス徹底ガイド
おひとりさま2025年7月3日身分証明で困らない!高齢者向け身分保障サービス徹底ガイド
この記事をシェアする