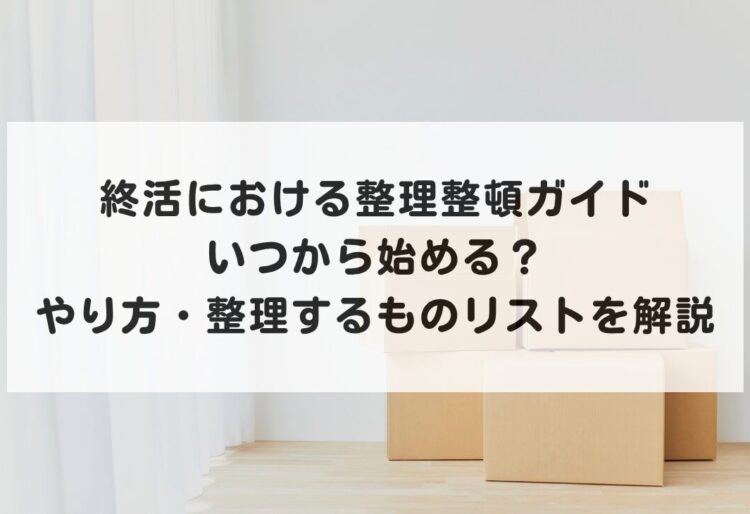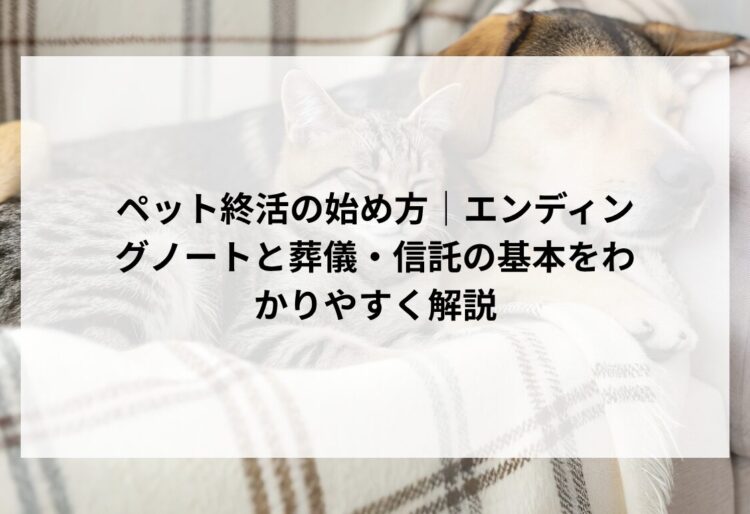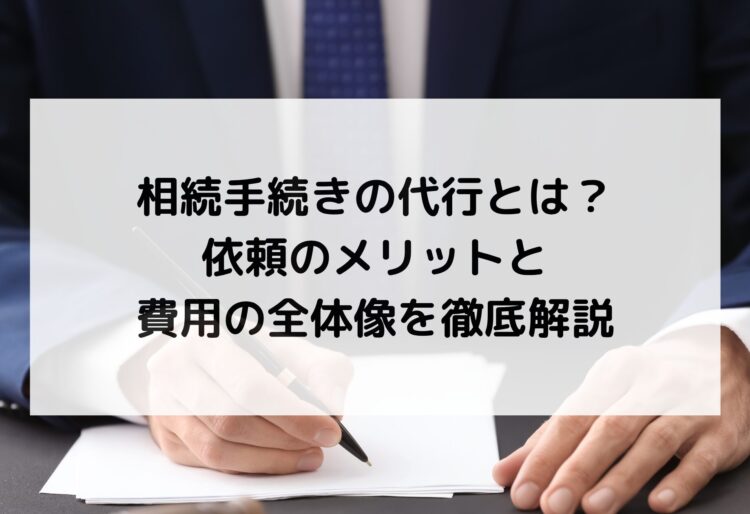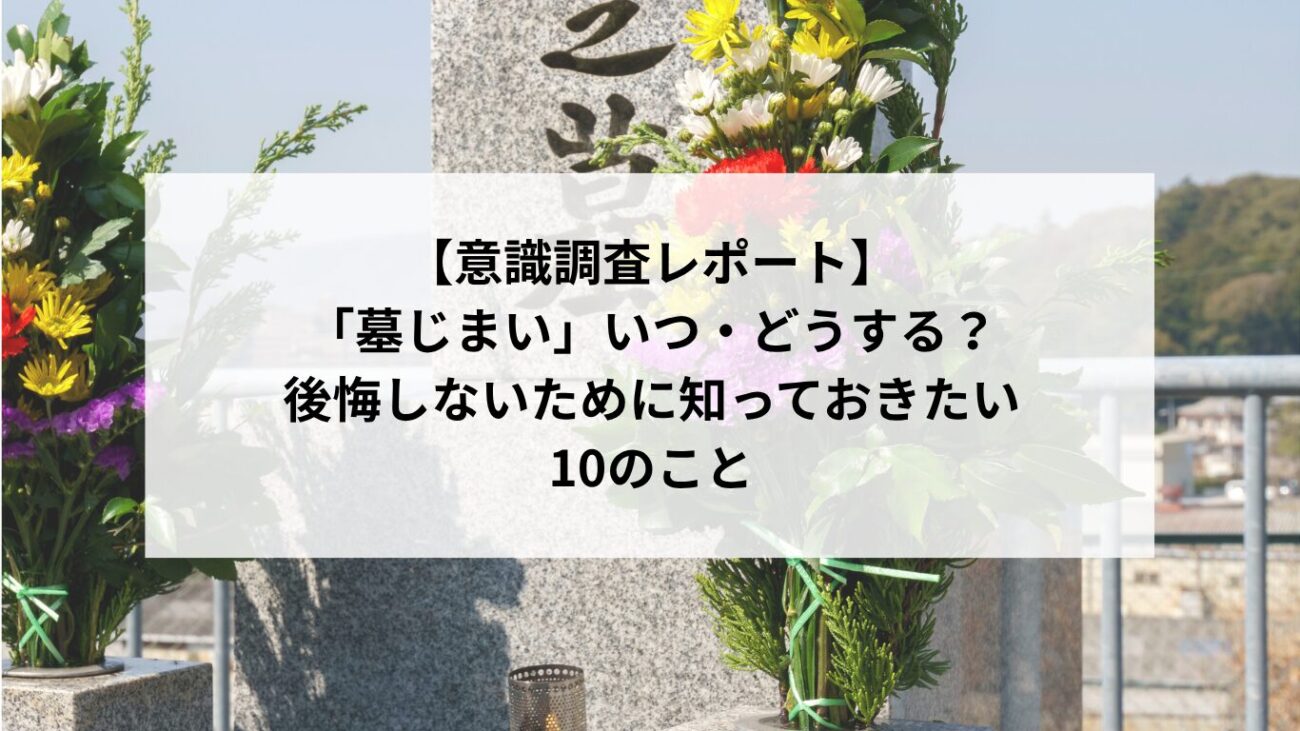
「墓じまい」とは、お墓を撤去し、遺骨を別の場所へ移すことで、今あるお墓の管理を終了する手続きのことを指します。少子化や核家族化が進むなかで、お墓の継承が難しくなり、「墓じまい」を検討する方が年々増えています。
しかしながら、「菩提寺との関係」「費用の相場」「親族との話し合い」など、実際に墓じまいを進めるには多くの不安や悩みがつきまとうものです。
今回、一般社団法人終活協議会では、「墓じまい」に関する意識や実態を把握するためのアンケート調査を実施しました。その結果から、多くの方がどのような理由で墓じまいを考え、どのような供養のかたちを選び、どんな後悔や課題を感じているのかが見えてきました。
本記事では、その調査結果をもとに、「墓じまいとは何か」「費用や手続きの実際」「供養方法の選び方」「後悔しないための準備」などを10の視点から詳しく解説します。
「墓じまい」に関する実態調査については、こちらの記事をご覧ください。
【2025年最新調査】墓じまいを考える理由1位は「後継ぎがいない」 |終活ガイド資格者390人に聞いた意識調査
また、終活協議会では、墓じまいについて詳しく学べるガイドブックを無料でプレゼントしております。是非、ご活用ください。
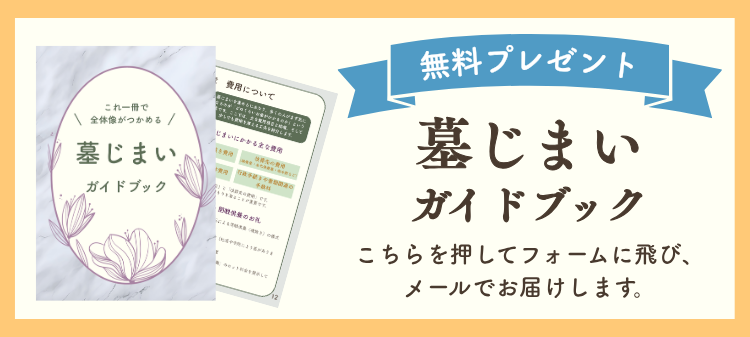
目次
- 【1】「墓じまい」とは?言葉の意味と最近の関心の高まり
- 【2】実家?遠方?お墓の場所が「将来の負担」に変わる瞬間
- 【3】誰が管理してる?「お墓の維持者」がいなくなるリスク
- 【4】墓じまいを考える人はどれくらいいる? 突然訪れるきっかけに備えて
- 【5】なぜ墓じまいするのか?多くの人が直面する事情
- 【6】永代供養、樹木葬、散骨…供養の選択肢とその違いとは?
- 【7】墓じまいの費用はいくら?「知っているつもり」が一番危ない
- 【8】墓じまいの最大のハードルはここにある
- 【9】「もっと早くやっておけば…」墓じまい経験者のリアルな声
- 【10】気持ちの整理、家族との対話…墓じまいがもたらすもの
- 関連コラム・リリース
- 「墓じまいガイドブック」無料プレゼントはこちら
【1】「墓じまい」とは?言葉の意味と最近の関心の高まり
「墓じまい」という言葉を、最近よく耳にするようになったという方も多いのではないでしょうか。少子高齢化やライフスタイルの変化を背景に、従来の先祖代々のお墓を守るという価値観が変わりつつあります。
では、そもそも「墓じまい」とは何か。簡単に言えば、現在あるお墓を撤去し、遺骨を別の場所へ移すことを指します。改葬先としては、永代供養墓や樹木葬、納骨堂、散骨などがあり、費用や宗教的な配慮、家族の事情によって選択肢が分かれます。
「墓じまい」という言葉の認知度は?
一般社団法人終活協議会が実施した「墓じまいに関する実態調査」によると、「墓じまい」という言葉を「よく知っている」人は35.2%、「聞いたことがある」が50.7%と、合わせて約86%の人が何らかの形で言葉を知っていることが分かりました。一方で、「知らなかった」と回答した人も14.1%おり、言葉としての認知は広がってきてはいるものの、まだ内容までは十分に理解されていない可能性があります。
【墓じまいの認知度】
・よく知っている:35.2%
・聞いたことがある:50.7%
・知らなかった:14.1%
このように「墓じまい」は、少しずつ世間に浸透してきた言葉である一方で、その実態や手続き、費用などに関してはまだ曖昧なままという人が多いのが現実です。特に、いざ検討しようとしたときに「どこに相談すればよいのかわからない」「親族とどう話し合えばいいか悩む」という声も多く聞かれます。
墓じまいは「自分ごと化」されてきている
これまで「墓の問題=親や祖父母の代の話」と捉えがちだった人も、実際に自分や配偶者が将来継ぐ可能性のあるお墓の所在や管理者を考える中で、少しずつ自分事として捉えはじめている傾向も見られます。
- お墓の場所について「実家近く」と答えた人は55.5%と最も多く、次いで「現住所から遠方」が35.9%と、約4割の人がアクセスに不便を感じている現実も浮き彫りになっています。
- また、現在のお墓の管理者は「両親や親戚」が58%と最多ですが、「自分が管理している」という人も15.1%存在し、少しずつ管理の担い手が若い世代へ移りつつあることも伺えます。
これらの背景から、墓じまいはもはや「年配の人の問題」ではなく、「将来を見据えて、今のうちに準備を始めるべきこと」として認識されはじめているのです。
もし、墓じまいに関することでご相談がございましたらこちらからお気軽にご相談ください。
【2】実家?遠方?お墓の場所が「将来の負担」に変わる瞬間
お墓の場所は、管理しやすさを大きく左右する
お墓は家族の思い出や先祖への感謝をつなぐ大切な場所です。しかし、その場所がどこにあるかによって、日々の供養や管理にかかる負担は大きく変わってきます。
終活協議会の調査によると、家族のお墓が「実家の近くにある」と答えた人は55.5%で過半数を占めました。これは比較的管理やお参りがしやすい状況にある人たちといえるでしょう。
一方で「現住所から遠方にある」と答えた人は35.9%。距離があることで、年に数回のお参りや掃除すら難しくなり、次第に「維持が負担」と感じるきっかけにもなりやすいのです。
さらに、「お墓の場所が不明」と回答した人が1.8%、「お墓が特にない」とした人も6.8%いました。これは、親世代が管理していたものの、場所の共有がされていなかったり、もともと墓地を持たない家庭であるケースと考えられます。
墓じまいを考える前に確認したい、お墓の所在
今はまだ遠方のお墓に足を運べていても、自分の年齢や健康状態、家族構成の変化によって、管理が難しくなるタイミングは突然やってきます。そのときにどうしようと後悔するよりも、あらかじめ場所や管理方法を見直しておくことが、家族にとっても大きな安心につながります。
また、子どもや孫の世代がすでに地元を離れている場合は、将来的に誰もお墓を見られなくなるリスクもあります。お墓の場所を「そのままにしておく」ことが、将来の家族への負担につながる可能性があるという視点は、今後ますます重要になっていくでしょう。
【3】誰が管理してる?「お墓の維持者」がいなくなるリスク
墓の維持には、継続的な労力と費用がかかる
お墓は建てたあとも、管理し続ける必要があるものです。掃除や草むしり、法要の準備、寺院や管理会社との連絡など、継続的な手間と費用がかかります。しかし、こうした維持の役割が不明確だったり、担い手がいなかったりすると、思わぬトラブルや放置の原因になってしまいます。
終活協議会の調査によると、現在お墓を管理・維持している人として最も多かったのは「両親・親戚」で58%でした。次いで「自分」が15.1%、「寺院・管理会社」が14.4%となっており、多くの家庭ではまだ高齢の親世代が管理を担っていることがわかります。
一方で、「誰も管理していない」と答えた人が4.2%、「分からない」と答えた人も8.4%おり、約1割以上の人が、お墓の維持状況について把握できていない実態が明らかになりました。
管理者がいないことで起きるトラブルとその予防
この結果から見えてくるのは、現在の管理者が高齢であるケースや、そもそも継承について話し合われていない家庭が少なくないということです。両親や親戚に任せきりになっていると、いざという時に「どこに連絡すればいいのかわからない」「管理費が未納だった」「お墓が荒れていた」といった問題が起きかねません。
特に近年は、子ども世代が実家から遠く離れて暮らしている家庭も多く、物理的にお墓の管理を引き継ぐことが難しい場合もあります。そうした現実を前にして、墓じまいを選ぶ家庭が少しずつ増えてきているのです。
お墓は一度建てたら終わりではなく、世代を超えて守り続けていくものです。しかし、守る人がいなければ、それは家族の負担や心残りにつながる可能性もあります。まずは今、お墓を誰がどのように管理しているのかを明確にすることが、将来のトラブルを防ぐ第一歩になります。
【4】墓じまいを考える人はどれくらいいる? 突然訪れるきっかけに備えて
多くの人が「まだ話していない」という現実
墓じまいは、家族の事情やライフスタイルの変化に応じて、誰にとっても起こり得る選択肢の一つです。しかし実際には、どれくらいの人が具体的に墓じまいを考えたり、相談を始めているのでしょうか。
終活協議会の調査では、「墓じまいを検討・相談した経験がある」と答えた人は12.5%、「現在検討中」と答えた人が11.5%でした。これに対し、「特に考えたことがない」と回答した人は66.7%、「話す予定もない」と答えた人も9.4%にのぼりました。
つまり、8割近い人がまだ墓じまいについて家族と話したことがない、あるいはその予定もないということになります。
きっかけは突然訪れることもある
今は考えていないとしても、両親の高齢化や相続、急な体調の変化など、ある日突然「お墓のことを考えなければならない」場面に直面する可能性があります。そのときに慌てずに済むよう、事前に家族と少しずつ話し合っておくことが、将来の安心につながります。
墓じまいは決して簡単な話題ではありませんが、だからこそ、元気なうちに一度話題にしてみることが重要です。いざというときに家族が困らないように、今のうちから意識を向けておくことが、現代の終活において欠かせない準備の一つといえるでしょう。

【5】なぜ墓じまいするのか?多くの人が直面する事情
墓じまいを考える理由は、現代ならではの課題にあった
墓じまいを検討する人が増えている背景には、現代の家族構成や生活スタイルの変化があります。終活協議会の調査では、墓じまいを考える理由として最も多く挙げられたのは「跡継ぎがいない」で、35.7%にのぼりました。
少子化や単身世帯の増加により、お墓を守る人がいなくなるケースが増えており、この現実が墓じまいという選択につながっています。
次に多かったのは、「特に理由はない/考えていない」が33.9%と、かなりの割合を占めました。これは、今はまだ明確な理由がないけれど、将来的な選択肢として頭の片隅にあるという層が多いことを示しています。
他にも「遠方で通うのが難しい」(15.1%)、「掃除や管理が負担」(11.4%)、「墓地や維持費が高額」(3.4%)、「宗教・宗派の問題」(0.5%)など、それぞれの立場や生活環境に応じた悩みがあることがわかります。
墓じまいは、家族の未来への配慮でもある
墓じまいを考えることは、単なる後始末ではなく、今後の家族の負担を減らすという思いやりの一つでもあります。将来、自分の子や孫に管理の手間や費用を負わせたくないという気持ちから、事前に整理をしておこうと考える人も増えてきました。
中には、「自分の代で終わらせたい」「墓のあり方にこだわらない」といった新しい価値観を持つ人もいます。墓じまいの背景には、世代間の考え方の違いや、生活の多様化が反映されているのです。
検討にあたっては、自分自身の思いや事情だけでなく、家族の状況や将来像も踏まえて、柔軟に考えることが大切です。
【6】永代供養、樹木葬、散骨…供養の選択肢とその違いとは?
墓じまいのあと、どう供養するかを決める
墓じまいを行ったあとは、遺骨をどう供養するかという選択が必要になります。現代では、かつてのように「家のお墓に入る」だけでなく、さまざまな供養方法が選べるようになってきました。
終活協議会の調査では、墓じまいをした場合に検討したい供養方法として最も多かったのは「永代供養」で、32.3%が選択しています。永代供養とは、寺院や霊園が遺骨を一定期間、または永続的に管理・供養してくれる方法で、後継ぎがいない人でも安心して利用できる点が特徴です。
次いで多かったのは「特に決めていない」が36.2%。墓じまいの方向性を考えていても、供養方法まではまだ検討が進んでいないという人が多いことが分かります。
その他の供養方法としては、「散骨」9.5%、「納骨堂」9.3%、「樹木葬」6.6%、「合祀」3.4%、「その他」2.6%という結果となりました。
それぞれの供養方法の特徴と選び方
供養方法は、それぞれの価値観や宗教観、家族構成に応じて選ぶことが大切です。
- 永代供養は、手間をかけずに一定の供養を望む人向き
- 樹木葬は、自然の中で眠りたいという希望をもつ人に人気
- 納骨堂は、都市部でアクセスの良さを重視する人に選ばれやすい
- 散骨は、お墓という形にとらわれず自由な供養を望む人向け
- 合祀は、費用を抑えながら供養を続けたい人に適している
どの方法にもメリット・デメリットがあるため、自分や家族にとって納得できる形を選ぶことが大切です。
今はまだ決められないという人も、将来的に困らないように、どのような供養方法があるのかだけでも情報を集めておくと安心です。
また、終活協議会では、墓じまいについて詳しく学べるガイドブックを無料でプレゼントしております。是非、ご活用ください。
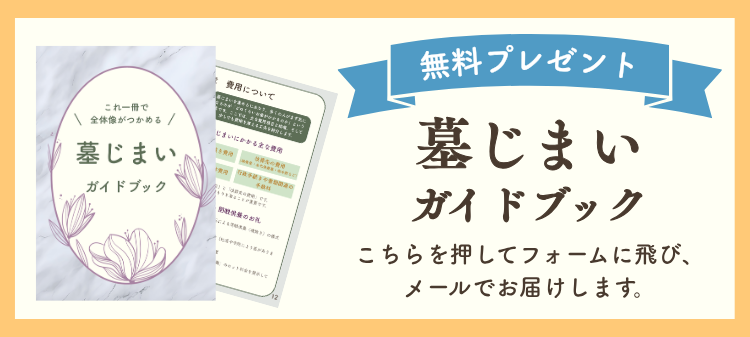
【7】墓じまいの費用はいくら?「知っているつもり」が一番危ない
墓じまいの費用感、どれだけ把握していますか?
墓じまいを考える際に、多くの人が気になるのが「費用」のことです。しかし、実際にはどれくらいの人が費用相場を把握しているのでしょうか。
終活協議会の調査によると、墓じまいにかかる費用について「知っている」と答えた人はわずか10.1%。「だいたい知っている」が19.8%で、合わせても3割程度にとどまり、70.1%は「知らない」と回答しました。
つまり、7割以上の人が「墓じまいの費用について何も分からないまま」不安や疑問を抱えていることが明らかになりました。
墓じまいにかかる費用の内訳とは
墓じまいにかかる費用は、単に「お墓を片づけるだけ」ではなく、いくつかの項目が重なって発生します。主な費用の内訳は以下のとおりです。
- 墓石の撤去・整地費用
- 遺骨の取り出し・新たな供養先への移送
- 改葬許可申請などの行政手続き費用
- 新たな供養方法にかかる費用(永代供養料や納骨堂の使用料など)
- 菩提寺などへの離檀料(必要な場合)
これらの費用は、地域や寺院、墓地の規模などによっても大きく異なりますが、一般的には20万円〜50万円程度が目安と言われています。加えて、新たな納骨先の費用も必要になるため、総額で数十万円〜100万円程度になるケースも珍しくありません。
「知らなかった」では済まされない費用の壁
費用の情報を正しく知っていないと、いざ墓じまいを進めようとしたときに「こんなにかかるなんて思わなかった」と戸惑うことにもなりかねません。
また、事前に見積もりを取って比較したり、補助金制度の有無を確認することも、賢い選択には不可欠です。
「お金のことを後回しにしがち」なのは自然なことですが、だからこそ、今のうちから費用感を知り、自分に合った準備を進めておくことが大切です。
【8】墓じまいの最大のハードルはここにある
手続きより難しい話し合いの壁
墓じまいを進める上で、多くの人が直面するのが人間関係の問題です。実際に手続きや費用のこと以上に、家族や親族との意見の違いが障壁になるケースは少なくありません。
終活協議会の調査でも、墓じまいに対して今一番の不安やハードルに感じていることとして、最も多かったのは書類・手続きの不安(27%)でしたが、それに次いで親族と意見が合わない(18.4%)という回答が続いています。さらに、菩提寺との関係や許可も13.9%を占めており、墓じまいは自分の意志だけで進められるものではないことが浮き彫りになっています。
墓じまいは自分ひとりでは決められない
たとえ墓じまいの必要性を感じていても、親や兄弟、親戚が反対していれば話が進まないというのはよくあることです。代々守ってきたお墓を自分の代で終わらせるのは気が引ける、遠方に住んでいる親族にどう説明すればいいか分からない、など感情面での葛藤も少なくありません。
また、菩提寺※がある場合は、離檀や改葬の相談が必要となり、寺院側との関係性によっては時間や手間がかかることもあります。
※菩提寺(ぼだいじ)・・・先祖代々の供養をお願いしているお寺のことを指します。家族のお墓があるお寺であり、法要や葬儀などの際にも関わる、いわば「家の宗教的な拠りどころ」となる存在です。
一番大切なのは対話と共有
墓じまいを円滑に進めるには、まずは家族や関係者との対話から始めることが重要です。感情的な議論ではなく、なぜ墓じまいを考えているのか、将来の不安をどう解消したいのかなど、自分の気持ちや考えを丁寧に伝えることがカギになります。
また、同じ立場に立っている人の声を参考にするのも良い方法です。調査では、墓じまいを経験した人の中に家族との対話が深まった(2.7%)という前向きな変化を感じた人もいました。
墓じまいは、ただお墓を処分する作業ではなく、家族や親族との関係を見つめ直し、未来をどう共に考えていくかという人生の分岐点でもあります。

【9】「もっと早くやっておけば…」墓じまい経験者のリアルな声
墓じまい経験者の約4人に1人が、何らかの後悔を感じている
墓じまいを終えた人の中には、「もっと早く準備しておけばよかった」と後悔するケースも少なくありません。実際、調査では全体の約23%が何らかの後悔を抱えていることが明らかになりました。
親族との話し合いは元気なうちに
最も多かったのは、「親族と元気なうちに話しておけばよかった」(9.3%)という声です。墓じまいには家族や親戚との合意形成が欠かせず、関係者が高齢になる前に話し合っておくことが重要です。話すタイミングを逃すと、意見が食い違ったり、物理的に集まることが難しくなったりすることもあります。
費用や手続き、相談も早めがカギ
次に多かったのは、「費用を早めに調べておけばよかった」(7.7%)。墓じまいにかかる費用は内容や地域によって差があるため、早い段階での情報収集が費用面での不安解消につながります。
その他にも、「自分が動けるうちに済ませておけばよかった」(2.4%)、「菩提寺や霊園と早めに相談しておけばよかった」(2.4%)、「改葬先を早く探しておけばよかった」(1.1%)など、体力的・時間的な余裕があるうちに準備を始めておくべきだったという声も見られました。
後悔しないために、できることを一つずつ
一方、「特に後悔はない/まだ経験していない」と答えた人は77.1%と多数を占めています。これは、まだ墓じまいを行っていない層が多いことを反映していると考えられますが、すでに経験した人の声には、今後の参考になるヒントが詰まっています。
後悔を減らすためには、早めの準備と周囲との対話が何より大切です。
【10】気持ちの整理、家族との対話…墓じまいがもたらすもの
墓じまいを終えた人のリアルな声とは
実際に墓じまいを経験した人の声からは、さまざまな気持ちの変化や課題が見えてきます。調査によると、「まだ経験していない/検討していない」と答えた人が84.8%と大多数を占めている一方で、経験者からは貴重な意見が寄せられました。
「気持ちの整理がついた」(6.1%)、「家族との対話が深まった」(2.7%)といったポジティブな声がある一方で、「手続きや費用が大変だった」(1.3%)、「心残りや後悔がある」(1.3%)、「話し合いが難航している」(3.7%)という現実的な課題も挙げられています。
墓じまいは精神的にもエネルギーが必要
「気持ちの整理がついた」「家族との対話が深まった」と感じる人が一定数いる一方で、思った以上に「大変だった」と感じた人も多く、墓じまいには体力や時間だけでなく、精神的な準備も必要だということが分かります。
特に、家族や親族との話し合いがスムーズにいかなかったという声は少なくなく、感情のもつれや世代間の価値観の違いが障壁になることもあります。
墓じまいは経験者の声を参考にして
これから墓じまいを検討する方にとって、実際の経験者の声はとても参考になります。成功体験だけでなく、苦労した点や後悔したことも含めて耳を傾けることで、自分に合った進め方が見えてくるはずです。
時間に余裕のあるうちに、そして家族が元気なうちに、少しずつ情報を集め、話し合いを始めていくことが何よりの準備になります。
まとめ:墓じまいは「家族への思いやり」から始まる終活の一歩
今回の調査から、墓じまいという言葉を知っていても、実際に行動に移している人はまだ一部にとどまり、多くの方が「気になってはいるけれど、どうすればいいか分からない」という状態にあることが分かりました。
跡継ぎの不在や距離的な問題、費用の不安、親族や菩提寺との調整など、墓じまいには避けて通れない課題があります。その一方で、実際に取り組んだ人の中には、「気持ちの整理がついた」「家族との対話が深まった」といった前向きな変化を感じている人も少なくありません。
特に多かった後悔の声が、「もっと早く話しておけばよかった」「自分が元気なうちに準備すべきだった」というもの。これは、墓じまいが“未来の誰かのため”だけでなく、“今の自分の安心”にもつながることを示しています。
供養の形は、永代供養や樹木葬、納骨堂、合祀など多様化しており、自分や家族の価値観に合った選択肢を選べる時代になりました。大切なのは「選べるうちに、話し合っておくこと」です。
「まだ元気だから」「うちは大丈夫」と思っている今こそ、動き出すベストタイミングかもしれません。
一般社団法人 終活協議会では、どんなに小さな不安や疑問でも安心してご相談いただける『心託(しんたく)』サービスをご提供しています。
墓じまいに関するお悩みも、もちろんご相談可能です。費用や手続き、菩提寺とのやりとり、供養方法の選び方など、それぞれの状況に合った進め方を一緒に考え、信頼できる専門家をご紹介します。
「誰に相談すればいいのかわからない」そんなときこそ、心託サービスを活用してください。
終活のコンシェルジュとして、あなたとご家族の心に寄り添いながら、後悔のない選択をサポートいたします。
関連コラム・リリース
「墓じまいガイドブック」無料プレゼントはこちら
こちらに必要項目を記入して頂き、「確認」ボタンを押してください。ご登録いただいたメールにお届けいたします。
確認ボタンを押すと、登録確認画面に遷移します。登録内容に間違えがなければ、「確認する」を押してください。
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする