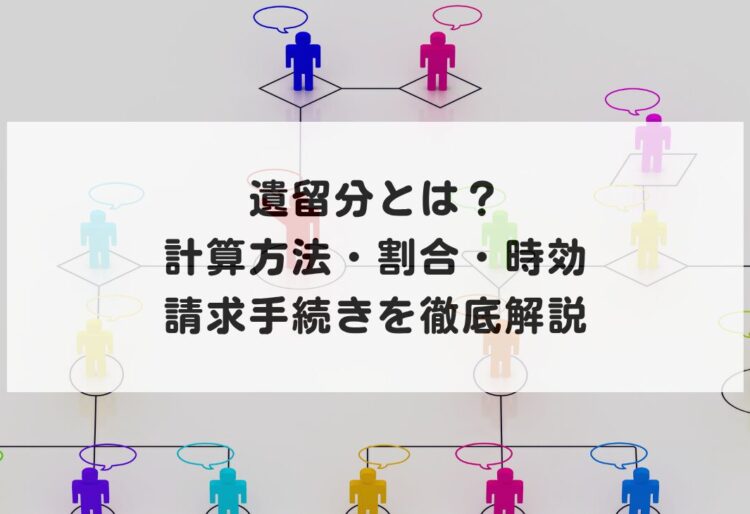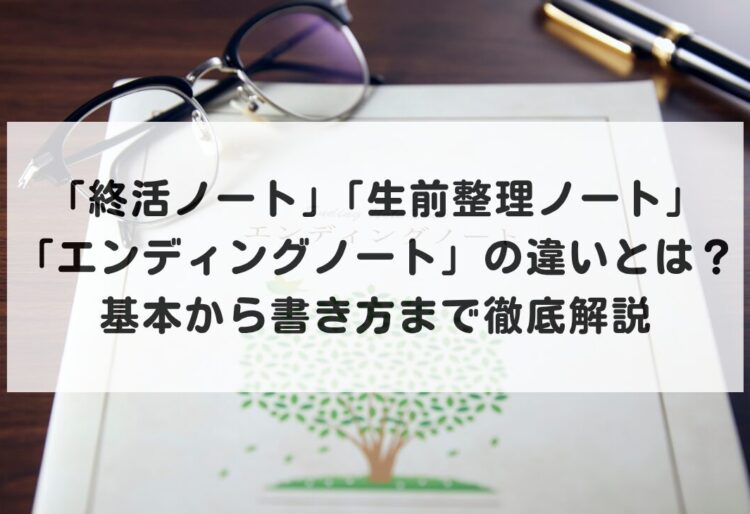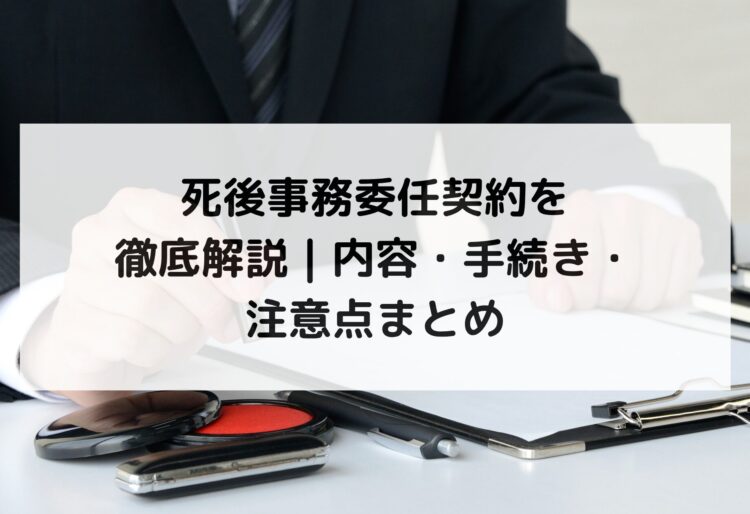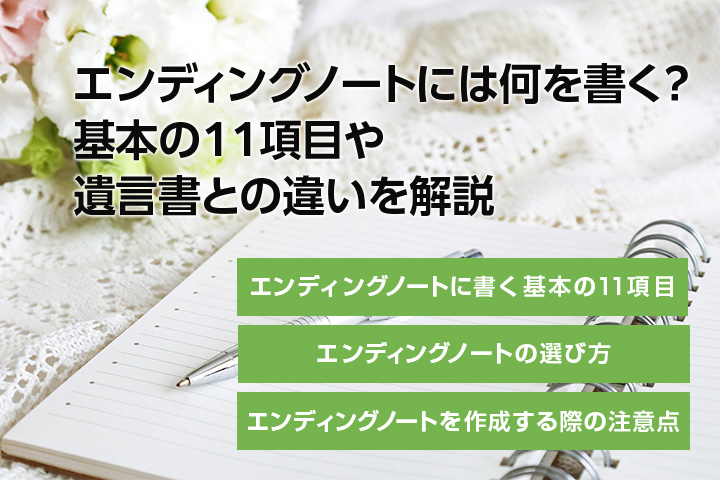
「エンディングノートは大事だよ」と方々で聞くようになりましたね。ところが「エンディングノート」という言葉だけが独り歩きしており、「実際にどのようなものなのか」「何を書けばよいのか」までは知らない方も少なくありません。
そこで本記事では、終活の専門家が、エンディングノートの役割や入手方法、エンディングノートに記載する基本の11項目(書き方)などをわかりやすく解説します。遺言書との違いやよくある質問もご紹介しますので、少しでもエンディングノートに興味がある方の参考となるかと思います。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。
- エンディングノートの項目別の書き方
- エンディングノートのメリット・デメリット
- エンディングノートを書く際の注意点
なお、一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループでは、資料請求をしてくださった方限定で、エンディングノートを無料でプレゼントしています。詳細は以下をご確認ください。
目次
エンディングノートとは

エンディングノートとは、自分にもしもの事があったときに備えて、家族や友人に伝えたい情報や希望を書き留めておくためのノートです。
エンディングノートに特に形式はないため大学ノートに記入したり、市販のエンディングノートを使用したりするなど、入手方法はさまざまです。まずはエンディングノートの役割や記載内容についてご紹介します。
エンディングノートの役割・記載内容
自分にもしもの事があり、急に家族と話ができなくなったらどうしますか?そんな時に備え、家族に宛てたメモや指示書をこっそり残す方は多いかもしれませんね。エンディングノートもそれに似ていて、家族にどうしてほしいか、自分の希望を伝言してくれる役割があります。
例えば「財産内容・医療情報・葬儀・遺品整理に関する希望」や「家族に対する想い、気持ち」などを自由に書き残しておきます。
「遺書」や「遺言書」と何が違う?
エンディングノートは幕引きを意識して書き残す書面として、遺書や遺言書と勘違いされることが多いです。しかし、遺書や遺言書とは、明確に異なります。
遺書とエンディングノートの違い
遺書は亡くなることを覚悟した方が、主に家族に対して自分の気持ちを伝える書面(手紙)のことです。誰かに気持ちを伝えるという意味では、エンディングノートも似たような意味を持ちますが、主に次の3つの違いがあります。
- エンディングノートには、残された家族や友人などにどうしてほしいか「希望」(さらには実現手段)が示してある
- エンディングノートは家族に行動してもらうことが重要なので具体性があり、記入項目がある程度決まっていて、ボリュームもある
- エンディングノートは「希望を残す」というポジティブな意味合いが強い
遺書よりはエンディングノートを残した方が明るい幕引きとなるでしょう。
遺言書とエンディングノートの違い
遺言書は、亡くなった後の財産の配分について書き残す法的な書面のことです。遺言書でも「付言事項」に家族への気持ちなどを書き残すことができます。
最大の違いは、遺言書は主に財産の配分について決めておくという目的で使用される、という点です。遺言書には財産の配分に関する法的効力があり、法律で定められた書式で財産の配分について書き残すことで、相続人(親族など)は原則、その配分通りに相続する必要性が生じます。
理想は、エンディングノートと遺言書を併用すること。どちらも用意しておくことで、より現実的な終活の準備ができるでしょう。
エンディングノートの発祥・歴史
余談ですが、エンディングノートは1990年代にとある葬祭関連事業者が作成したものがルーツとされています。それ以降は他の事業者も書籍として販売したり、自治体が無料配布したりするなどして、全国で広く認知されるようになりました。
2011年にはエンディングノートを題材とした映画「エンディングノート」(砂田麻美監督)が公開されています。
エンディングノートを作るメリット・デメリット
エンディングノートはなぜここまで認知されたのでしょうか。その背景には、エンディングノートのメリットがあります。
エンディングノートを書き残すメリット
エンディングノートを書き残すメリットには、次のようなものがあります。
直接口では伝えにくいこともメッセージとして残せる
家族への感謝の言葉は、普段から伝えておくのがベストです。しかしながら、小恥ずかしくて口頭では伝えにくいのではないでしょうか。また、亡くなった後のことも口頭で伝えようと思うと少し気が引けるかもしれません。直接伝えにくいメッセージでも、文面ならなんとか伝えられますよね。
エンディングノートは、直接家族に伝えづらいことを代わりに伝えてくれる「伝言板」のような意味合いもあります。
家族の負担を減らすことができる
例えば、葬儀の場面で「忙しすぎて誰かを惜しむ間もない」という思いをされたことはありませんか?どのような葬儀にしたらいいのか、宗派はどこなのか、葬儀に誰を呼べばいいのか、どのくらいの規模にしたらいいのか、などを決める必要があり、残された家族にとっては負担が大きいです。
エンディングノートで事前に葬儀や介護、延命治療、持ち物の処分などについて、どうしてほしいのか、どうすればいいのか示しておけば、家族はスムーズに対応することができます。
不安を解消し、安心して楽しい余生を過ごせる
老後は、自分の病気や介護のこと、収入のこと、お墓の管理のことなど、さまざまな不安を感じると思います。どこかに不安を感じていては楽しい余生を過ごせませんよね。「備えあれば患いなし」といいますが、不安を解消するために必要なのはやはり「準備」です。
入院時や介護、お墓の希望を決めたり、財産を整理して資産状況を把握するなど、エンディングノートを書き進めるには、さまざまな準備(終活)が伴います。エンディングノートを作成し、老後の不安を解消していきましょう。
現状を把握できる
エンディングノートを記入していくために、資産状況や介護の希望などを把握する必要があります。財産がいくらあるのか現状を把握しておけば、生活費、娯楽や交際費にどのくらい割り振るのかを考え直すこともできます。
また、情報の整理のために、いったんメモなどに様々な情報を書き出す過程があると思いますが、その過程を通して自分がやりたいこと(やり残したこと)もはっきりとしてくると思います。
逆にエンディングノートに「デメリット」はある?
エンディングノートを作ることはメリットが大きいです。「死を意識してしまう」と忌避される方もいますが、作成しておくことでかえって死への不安が和らぎます。基本的にエンディングノートの作成にデメリットはありませんが、これから紹介するように扱い方を誤るとデメリットが生じる可能性があります。
管理の仕方次第では、個人情報流出の恐れがある
エンディングノートは必ず金庫やシークレットボックスなどセキュリティ性の高いところで管理しなければなりません。なぜならエンディングノートにはスマホのパスワードや資産状況、通帳の保管場所など、重要な個人情報を記載するためです。
管理の仕方に気を付けていないと、個人情報流出の恐れがあるのがデメリットといえます。
抽象的すぎる内容だとかえって混乱をまねく
家族に何をしていいのかある程度具体的に記載しなければなりません。例えば「葬儀は小規模で良い」とだけ記載されていても、結局誰どの程度の付き合いの人を呼べばいいのか、どのくらいの費用感が小規模なのかは伝わりません。
抽象的な内容だと家族がかえって混乱してしまうので、何をどうしたらいいのか具体的に記載する必要があります。
財産の相続に関することは、遺言書を作る必要がある
財産の相続に関することをエンディングノートに記載できないわけではありません。遺言書ではないので、記載しても法的な効力はないというだけです。財産の相続に関することを決めておきたいなら、エンディングノートとは別に遺言書を作る必要があり、二度手間になってしまいます。
遺言書の作成は専門家に代行することもできるので、面倒なら任せてしまうのも一つの手です。
エンディングノートの扱い方に注意すればデメリットはありません!
エンディングノートのデメリットを紹介しましたが、保管場所と家族に実施してほしい内容が記載されていて、遺言書との使い分けができていればデメリットはありません。後程、エンディングノートの注意点として解説するので「恩恵の方が大きくて、気を付けておけば大丈夫」とだけ覚えておいてください。
エンディングノートはどこで入手するのがおすすめか

市販されているエンディングノートにはさまざまな形式があります。自分が書きたい内容に合わせて、最適なものを選びましょう。
エンディングノートを入手する方法は次の3つです。
- 無料配布のエンディングノート(テンプレート)を入手する
- 市販のエンディングノートを購入する
- 自分でエンディングノートを作成する
この記事では書き方も紹介するので、まずはいずれかの入手方法で、エンディングノートを手に入れてみてください。
無料配布のエンディングノート(テンプレート)を入手する
老後の負担軽減などを目的とした福祉施策として、全国でエンディングノートを無料配布している自治体がいくつかあります。例えば以下の自治体です。
- 東京都新宿区「わたしのノート」
- 大阪府大阪市都島区「もしもの時に伝えたいこと」
- 愛知県北名古屋市「エンディング(終活)サポートノート」
- 福岡県福岡市「わたしが伝えたい大切なこと」
これらはPDFデータで無料配布されているので、お手持ちのパソコンやスマホでダウンロードし、プリンターで印刷して使用します。お住まいの自治体のエンディングノートを使用する必要はないので、ネット上で好きなデザインのものを見つけてみてください。
なお、エンディングノートはパソコンの文章作成ソフトで作っても良いのですが、情報は紙にペンで書き出した方が思考を整理しやすいので、できれば紙のエンディングノートをおすすめします。
市販のエンディングノートを購入する
行政刊行物は堅苦しく、デザイン性に乏しいものも珍しくありません。それゆえ、無料配布のエンディングノートの中からは、自分好みのものを見つけづらいと思います。
エンディングノートは家族に対して見せるものなので、見た目もこだわりたいのであれば市販のエンディングノートを購入されるのがおすすめです。文房具屋や書店で売っていることもありますが、見つからない場合はWEBで「エンディングノート」と検索し、気に入ったものを購入しても良いかもしれません。
ただし、数千円かかるものもあるので少し高いという印象を受けます。
市販のエンディングノートの選び方
たとえば、写真や手紙などの思い出の品を一緒に保管できるタイプや、デジタル形式で作成できるものもあります。また、自分史の記録に重点を置いたものや、財産や相続に関する情報を詳細に記入できるものなど、目的に応じて選択肢は多岐にわたります。
エンディングノートの書き方に不安を感じる方は、書き方の解説つきのものを選ぶとよいでしょう。初めての方でも、手順に沿って簡単に作成できます。自分に合ったエンディングノートを選ぶことで、残したい想いを的確に伝えられます。大切な人へのメッセージを残すために、じっくりと選んでみてください。
自分でエンディングノートを作成する
冒頭で説明したようにエンディングノートには特に決まった形式はなく、大学ノートなどに記入しても問題はありません。自分で作るので挿絵や図表を追加するなどオリジナリティを出せますし、費用もノート代くらいでできます。
ただし、市販のエンディングノートのように、記載項目(ガイド)がないので、次章を参考に何を書けばいいのか事前に頭に入れておきつつ、作成する必要があります。
エンディングノートに書く基本の11項目

エンディングノートは書きたいことを自由に書いていただいて構いませんが、基本的な11項目を押さえておくことで、ご家族のためになる内容になります。ここからはエンディングノートに書くべき11項目をご紹介します。
1.本人の基本情報
残念ですが、ご家族は思っている以上にみなさんのことを知りません。そのため、エンディングノートの最初の方のページには、以下のような自分自身の基本情報を記入しておきます。
- 氏名
- 生年月日
- 現住所
- 固定電話番号
- 携帯電話番号
- 本籍地
- 個人番号(マイナンバー)
- 家族構成
- 学歴
- 職歴
- 資格・免許
これらの情報は、もしものときの手続きに必要不可欠です。また、家族構成なども記しておくと、相続手続きの際に役立ちます。学歴や職歴、資格・免許といった項目は一見必要ないかもしれませんが、老後資金の補填のためにシニア求人に応募する場合などにこうした情報を整理しておくと、履歴書の作成がスムーズになります。
2.本人の医療情報
病気になったときに備えて、現在の健康状態や緊急時にどのように対応するのかといったことを整理しておくと、受診先や救急隊へ情報をスムーズに引き継ぐことができます。以下のような情報をエンディングノートに書き留めておくとよいでしょう。
- 身長・体重・血圧・血液型など
- かかりつけ医
- 持病、既往歴、常用薬、アレルギー
- 健康保険証の情報
- 介護保険証の情報
- 臓器提供の意思表示
3.財産の情報
エンディングノートには、預貯金や不動産、金融商品、保険、年金など、自分の財産に関する詳細な情報を記録します。口座番号や保管場所なども明記しておきましょう。ネットバンクをお持ちなら、記載漏れの内容に注意してください。
また、借金やローンといった負債についても漏れなく記載し、返済方法や処理方針を明確にしておくことで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。遺族に負担をかけないためにも、財産情報の記録は欠かせません。
4.医療・介護の希望
医療や介護に関する希望は、判断力が衰えないうちに家族と十分に話し合い、その内容をエンディングノートに記録しておくことが大切です。
- 認知症やその他の疾患などで判断能力が低下した場合の対応
- 「誰に介護してほしいか」「施設入所の是非」といった介護の希望
- 終末期の介護や医療の意向
これらの内容を考慮して記載しておきましょう。特に、不治の病の告知や終末期の延命治療についての意思は、家族との共有が不可欠です。なぜなら、治療の意思決定ができるのは原則本人だけであるためです。寝たきりなどになった場合、家族が代わりに希望を伝えることができても、意思決定までは代理できません。
これらをエンディングノートに明記することで、自分の意思を確実に伝え、家族の負担を軽減できます。
5.葬儀・お墓の希望
近年は葬儀や納骨の形態が多様化しています。ごく身近な人達だけでおこなう家族葬や樹木葬、海洋散骨などを選ぶ人も増加しています。また先祖代々のお墓を撤去し、「墓じまい」をする方も増えてきました。自身の葬儀や供養の方法に関して希望があれば、エンディングノートに記載しましょう。
- 信仰する宗教・宗派
- 菩提寺の情報
- 葬儀の形式・規模
- 葬儀に呼ぶ人・呼ばない人
- 遺影に使う写真
- 納骨の方法
- 墓地の情報
また、葬儀の準備で慌ただしいなか、遺影写真を選ぶのは遺族にとって負担になります。あらかじめ本人が気に入った写真を選んでおき、その保管場所をエンディングノートに記しておくと安心です。
6.相続・遺言書について
エンディングノートには法的拘束力がないため、遺産分割の方法を記載しても効力はありません。しかし、遺言書の有無や詳細情報を記録しておくことは非常に重要です。
遺言書を作成している場合は、以下について記載しておきましょう。
- 形式(自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれか)
- 保管場所
- 専門家に依頼した場合はその連絡先
これにより、遺族が遺言書を適切に見つけ出し、相続手続きをスムーズに進められます。遺言書がない場合でも、その旨を記載しておくことで、遺族の混乱を防げます。
7.死後のさまざまな手続きについて
人が亡くなったあとは、役所での手続き以外にも、家族が忘れがちなさまざまな契約やサービスの解約・変更が必要です。具体的には以下のようなものがあります。
- クレジットカード
- 携帯電話
- サブスクリプションサービス(動画配信、通販の定期利用など)
- オンラインアカウント
- SNSアカウント
これらを放置すると、料金の引き落としが継続したり、大切なデータが失われたりする可能性があります。特に、仮想通貨などの金融資産は、解約や換金の手続きが複雑で、相続税の対象にもなるため注意が必要です。
エンディングノートには、現在契約中のサービスを全てリストアップし、解約方法やデータのバックアップ方法、換金方法などを詳細に記録しておくことをおすすめします。
8.ペットについて
一人暮らしでペットを飼っている人は、自身が亡くなったあとペットがどうなってしまうのかは、大変気になる問題です。エンディングノートにはペットの引き取り先に加え、性格や好物、病歴、かかりつけの獣医、保険などの情報を記載しておきましょう。これにより、新しい飼い主がペットを適切に世話できるようになります。
ペットの終活について、こちらのガイドブックで詳しく説明しております。無料で配布しておりますので、是非ご活用ください。
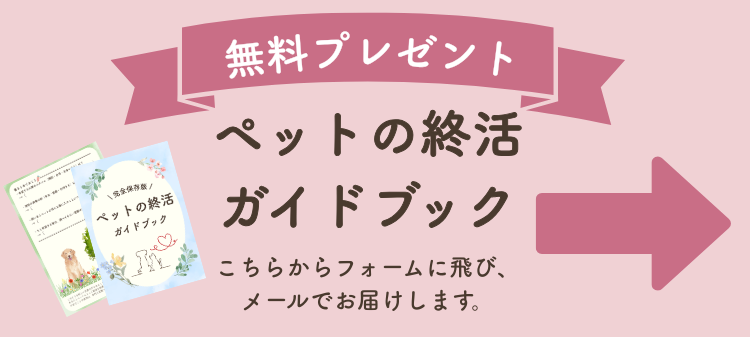
9.家族・親族、友人、お世話になった方へのメッセージ
エンディングノートの作成は、普段なかなか伝えられない感謝や想いを残す絶好の機会です。家族や親族はもちろん、友人やお世話になった方々に対しても、心からのメッセージを綴ります。
- 子供や孫に対しては小さかった頃のエピソードを
- 親友には共に過ごした思い出を
- お世話になった上司や同僚には感謝の言葉を
それぞれの関係性に応じた温かいメッセージは、遺された人々にとって大切な思い出となり、心の支えになることでしょう。率直な気持ちを込めて、あなたらしいメッセージを残してください。
10.過去の記録・思い出
市販されているエンディングノートの大半は、自分史の作成に多くのページが割かれています。家族や友人との旅行や、その他の楽しかった思い出やエピソードを中心に当時の気持ちや想いを綴ることで、これまでの人生を振り返り、残りの人生をより充実させられます。
可能であれば、関連する写真を貼付することで、より鮮明に記憶を呼び起こすことができるでしょう。
11.これからの計画・やりたい事
エンディングノートを書く過程でこれまでの人生を振り返ると、まだやり残していることや新たな目標が見えてくるかもしれません。終活は、死後の準備だけでなく、残りの人生をどのように充実させるかを考える機会でもあります。
行きたかった旅行先や長年連絡を取っていない友人との再会など、思い浮かぶ「これからの計画・やりたいこと」をエンディングノートに自由に書き留めてみましょう。
これらの目標を明確にすることで、前向きに人生を歩むためのモチベーションにもなります。あなたの夢や希望を大切に、充実した人生を送るための指針としてエンディングノートを活用してください。
エンディングノートを作成する際の注意点
エンディングノートを買ったものの、いざ書こうとするとなかなか筆が進まないこともあるでしょう。ここでは、エンディングノートを作成する際の注意点として、次の5つがあります。
- 一度で完成させず、書ける項目から書く
- 定期的に見直す
- 内容によっては、家族と相談する
- 保管場所を明確にし、家族と共有する
- 財産の配分に関しては遺言書を作成する
ひとつずつ見ていきましょう。
一度で完成させず、書ける項目から書く
エンディングノートは一度で完成させるものではありません!エンディングノートには多くの項目があり、全てを一度に埋めるのは大変です。そのため、まずは書きやすい項目から始めましょう。順番にこだわる必要はなく、気軽な気持ちで最初の一歩を踏み出すことが大切です。
まずは「書きたい内容が思い浮かんだら書いてみる」程度の気持ちで始めるのがおすすめです。また、考えが変わったり情報の更新が必要になることもあるため、鉛筆や消せるボールペンを使うとよいでしょう。
定期的に見直す
エンディングノートは一度作成して終わりではありません。時間の経過とともに、記載内容の修正や追加が必要になることがあります。情報が古くなると、いざというときに役立たなくなる可能性があるため、定期的に見直しましょう。
1〜3ヵ月に一度、大まかな内容確認をおこない、明らかに更新が必要な情報をチェックします。さらに、3〜6ヵ月に一度はより詳細な見直しをおすすめします。
内容によっては、家族と相談する
例えば、家族のためを思って「お墓は管理が面倒だろうし、墓じまいをする」と決め、墓じまいをした結果、家族側は「これからもお墓を守っていきたい」と考えていてトラブルに発展したケースもあります。「お墓はどうしていきたいと考えている?」などと家族と相談して意見をすり合わせてから、エンディングノートを書き残すことをおすすめします。
保管場所を明確にし、家族と共有する
エンディングノートの作成後は、その保管場所を家族と共有しましょう。せっかくノートを作成しても、自身の死後に誰にも読まれなければ意味がありません。
ただし、重要な金融情報や個人情報が含まれているため、保管場所の選択には注意してください。簡単に見つかる場所は避け、家族だけが知っている安全な場所に保管します。
たとえば、金庫や鍵のかかる引き出し、または家族しか知らない収納スペースなどが適しています。保管場所を決めたら、必ず家族に伝え、緊急時にすぐに取り出せるようにしておきましょう。
財産の配分に関しては遺言書を作成する
繰り返しとなりますが「財産はこの人が引き継いでほしい」という希望はエンディングノートに残しても、遺言書のように法的な効力はありません。財産の配分に関する希望があれば遺言書を作成しましょう。
エンディングノートに関するよくある質問
ここでは、エンディングノートに関するよくある質問のうち、以下の2点について解説します。
- 何歳から始めるべきか
- どこで買えるのか
ひとつずつ見ていきましょう。
何歳から・いつから書き始めるべき?
エンディングノートを書き始める年齢に決まりはありません。大切なのは自分の人生や家族のことを考え始めたときに着手することです。
- 親の介護を考え始めたとき
- 子育てが一段落したとき
- 定年退職したとき
このように人生の節目でエンディングノートを書き始める方は多いでしょう。ただし、若いうちから書き始めることも決して早すぎることはありません。
むしろ、人生の早い段階から自分の人生設計や家族への想いを整理することで、より充実した人生を送ることにつながる可能性があります。思い立ったときが、エンディングノートを書き始める最適なタイミングだといえます。
どこで買えるの?
書店やインターネットで簡単に購入できます。ただし、無料や低価格で入手できる方法もたくさんあるため、必ずしも高価なものを買う必要はありません。
100円ショップでも購入でき、地域によっては役所で無料配布しているケースもあります。また、Excel形式のテンプレートを無料でダウンロードできるWebサイトや、若い世代向けに開発されたスマートフォンアプリも登場しています。
どの方法を選ぶか迷った場合は、まずは無料や低価格のものから試してみるのがおすすめです。自分に合ったスタイルを見つけてから、必要に応じて市販のものを購入するのもよいでしょう。まずは始めることが大切です。
エンディングノートを作ることから終活を始めてみよう

一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループでは、資料請求をしてくださった方限定で、エンディングノートを無料でプレゼントしています。このノートは、以下の項目について記載できるようになっています。
- 自分のこと
- パソコン・スマートフォン・日記など
- ホームページ・ブログなど
- 現在の身体について
- 医療について
- 介護について
- ペットについて
- 葬儀について
- お墓について
- 私の家系図
- 生命保険について
- 建物の保険と年金について
- 財産について
- 友達やお世話になった人の連絡先
- 行ったことのある印象深い場所や国
- 日本で行ったところで想い出深い場所
- 楽しかった想い出や挑戦してみたいこと
終活に興味はあるけど一歩を踏み出せない方は、まずは資料請求し、エンディングノートを書いてみることから始めてみるのはいかがでしょうか。
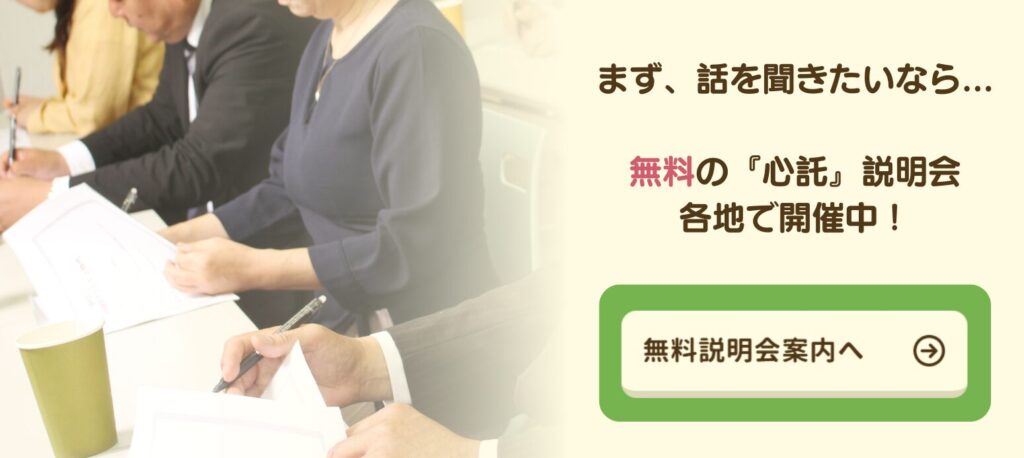
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする