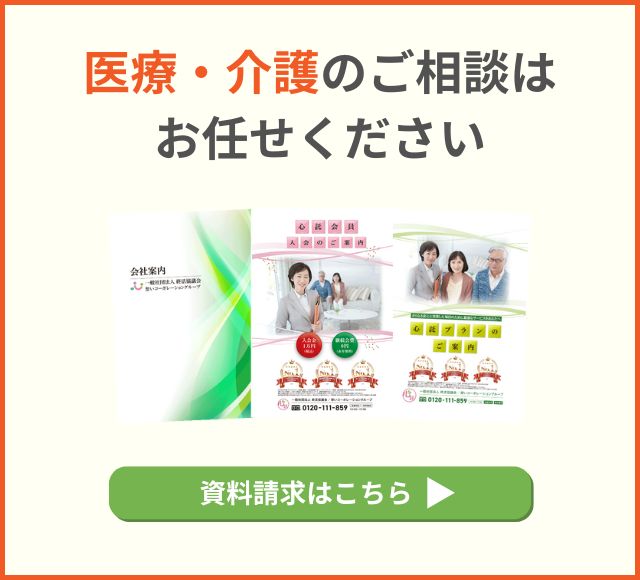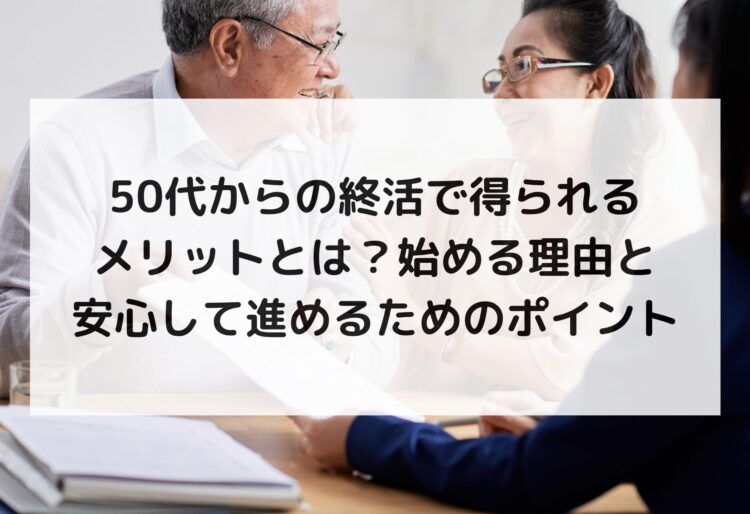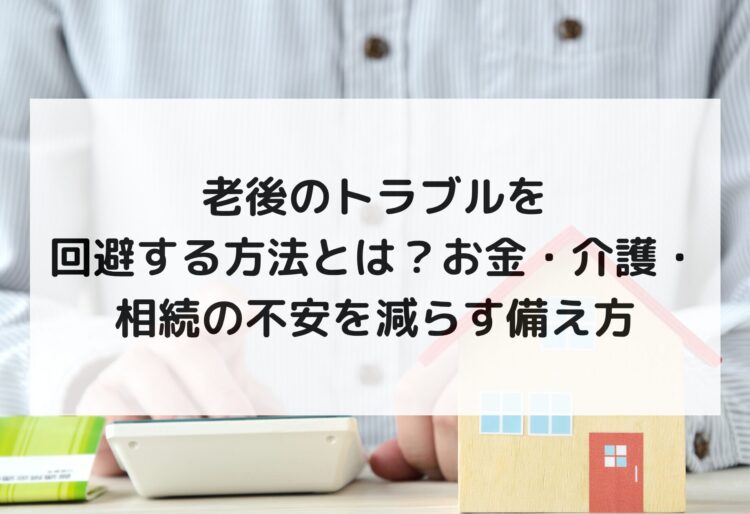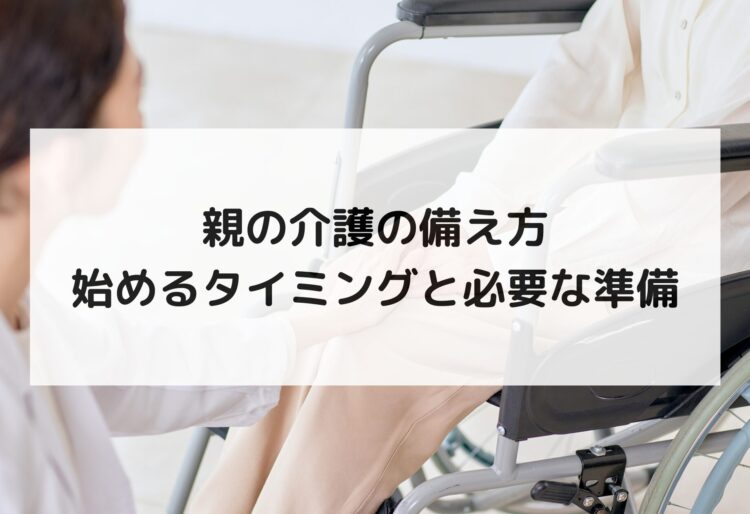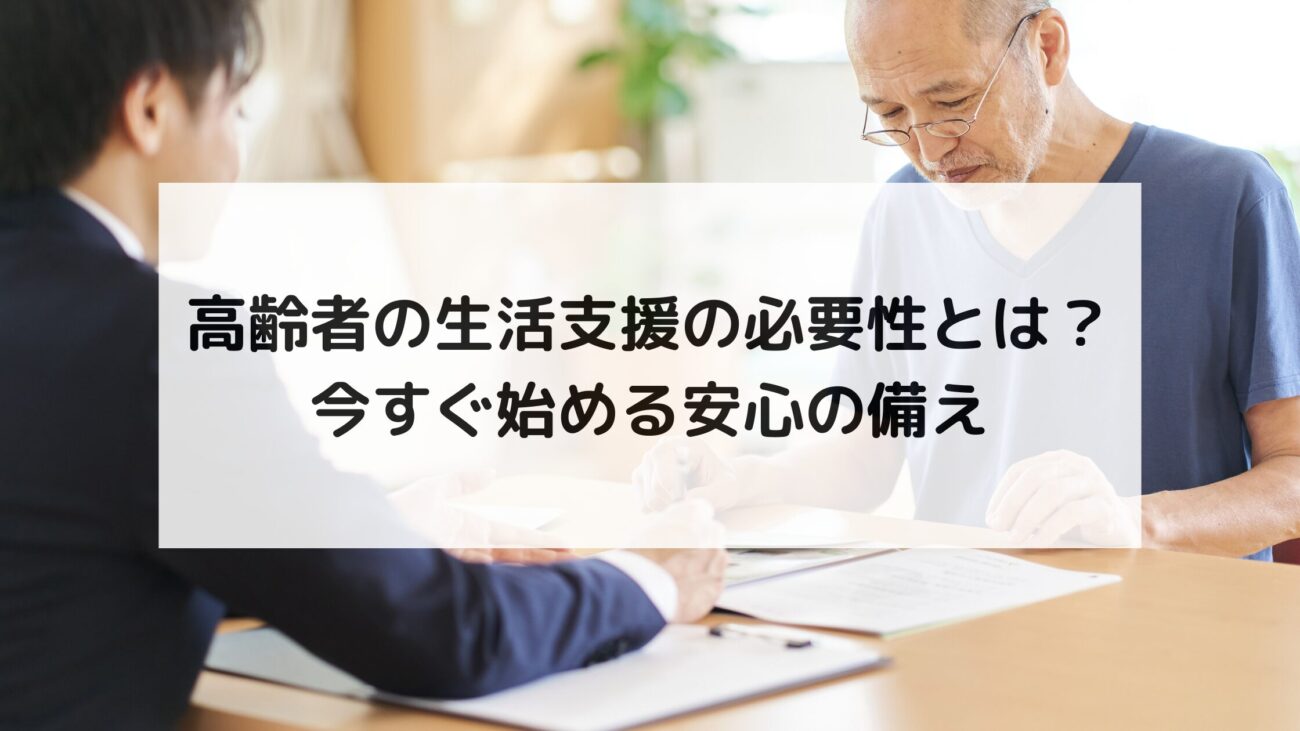
- 高齢者の生活支援が必要な理由とは
- 高齢者の生活支援でよくある失敗と対策
- 生活支援サービスを選ぶときのポイント
目次
1. 高齢者にとっての生活支援の必要性とは

1.1 高齢化社会が進む中で求められる支援の変化
内閣府が公表したデータによると、日本はすでに高齢化率が29%を超える超高齢社会に突入しています(※)。
※令和7年版 高齢社会白書(内閣府)
これは、3人に1人が65歳以上という計算です。こうした中、従来のように家族や親族が支え合う生活スタイルでは、十分に対応できなくなってきています。
昔は「家族が面倒を見るのが当たり前」という価値観が根強くありましたが、今では共働きや単身世帯が増え、家族だけで支援を担うのは現実的に難しい時代になりました。
高齢者の生活を支えるためには、公的制度や民間サービスを組み合わせた「新しい支援のかたち」が必要になってきています。
1.2 一人暮らし・家族に頼れない高齢者の実情
高齢者の生活スタイルは多様化しており、特に増えているのが「おひとりさま高齢者」です。厚生労働省「2024(令和6)年国民生活基礎調査」によれば、65歳以上の者のいる世帯のうち、単独世帯は903万1千世帯にのぼり、全高齢者世帯の52.5%を占めています。これは一般的に、高齢者が一人で暮らす世帯が増えていることを示しており、年々その割合は高まっています。
以下のような理由で、支援を受けにくい高齢者も少なくありません。
- 家族が遠方に住んでいて、すぐには頼れない
- 子どもや親族に迷惑をかけたくないと考えている
- 周囲との人間関係が希薄で、頼る人がいない
こうした状況下では、本人が困っていても声を上げにくくなる傾向があります。たとえば、ちょっとした不調や買い物の困難、家事の負担なども我慢してしまいがちです。
「誰かに頼るのは迷惑になる」と感じる方が多いため、生活支援の必要性が高まっているにも関わらず、利用までつながらないケースも多いです。
1.3 日常生活に潜む「困りごと」が支援につながる
生活支援が必要なのは、介護状態になったときだけではありません。「介護の手前」段階でも支援が重要です。
たとえば以下のような日常の中に、支援のヒントが隠れています。
- 掃除や洗濯がしんどくて、家の中が散らかる
- 買い物が重くて外出するのが億劫になる
- 食事が偏りがちになり、体力が落ちてしまう
このような日常の積み重ねが、健康リスクや孤立、介護状態への進行に直結することがあります。
ですが逆に言えば、こうした困りごとに早めに対応できれば、「介護にならない支援=生活支援」で生活の質を高く保つことができます。
高齢者にとって生活支援は「困ってから受けるもの」ではなく、「困らないために備えるもの」という意識がこれからは大事になります。
2. 高齢者の生活支援が必要とされる理由

2.1 孤立・認知症・体力低下がもたらす生活リスク
高齢になると、自然と生活範囲が狭まり、他者との関わりも減っていきます。この「孤立」が多くのリスクの引き金になります。
たとえば、こんな問題が起こりやすくなります:
- 誰とも会話しない日が続き、精神的に不安定になる
- 外出しなくなり、筋力が低下して転倒のリスクが高まる
- 服薬ミスやゴミ出し忘れが頻発し、生活環境が悪化する
さらに、認知症の初期症状は「物忘れ」や「段取りのミス」など一見軽微に見えるため、気づかないまま生活が破綻してしまうことも。
特に判断力の低下による火の不始末や金銭トラブルは、周囲に迷惑をかけるだけでなく、本人の安全にも直結する深刻な問題です。
生活支援は、こうしたリスクを早期に察知し、防ぐための「予防策」でもあるという視点が必要です。
2.2 家族・地域のサポートだけでは限界がある
昔ながらの「地域や家族で支える」スタイルには、すでに限界がきています。
具体的にはこんな状況が多く見られます:
- 子ども世代が遠方に住んでいて、すぐに対応できない
- 高齢者夫婦のみの世帯で、互いに支え合うことが難しい
- 町内会や自治会などの地域機能が弱体化している
たとえ近くに家族がいたとしても、仕事や育児に追われる日々の中で、十分なサポートを続けるのは簡単ではありません。
また、地域ボランティアや見守りサービスなども、人手不足や高齢化の影響で十分に機能していないことも多いです。
そのため、専門的な知識と体制を持った外部の生活支援サービスが、これからの時代には欠かせない存在となってきます。
2.3 支援によって「できること」が増える理由
生活支援の目的は、「できなくなったことを代わりにやる」だけではありません。
むしろ、「できることを続ける」「新しいことに挑戦できる環境を整える」ことが支援の本質です。
たとえば、
- 買い物に同行することで、歩く機会が増えて筋力低下を防げる
- 食事の準備をサポートすることで、栄養バランスが改善する
- 何気ない会話を通じて、心の張りや生活のリズムが生まれる
こうした支援の積み重ねによって、「本人のやる気」や「自分らしい暮らし」を維持しやすくなります。
生活支援とは、「奪う」のではなく「引き出す」サポート。本人の可能性を広げるためにも、早めの支援がとても大切です。
3. 高齢者の生活支援でよくある失敗とその対策

3.1 行政サービスだけに頼りすぎてしまう
「生活支援」と聞くと、真っ先に思い浮かぶのが行政の介護保険サービスや福祉制度かもしれません。確かにこれらは非常に重要ですが、すべてのニーズに対応できるわけではないのが実情です。
よくある失敗のひとつが、以下のようなケースです:
- 要介護認定を受けたものの、ヘルパーの派遣枠が足りない
- 利用申請に時間がかかり、すぐに支援が受けられない
- 支援内容が限定されており、柔軟な対応が難しい
たとえば、日常の「ちょっとした困りごと」――買い物への付き添いや、ゴミ出しの手伝い、病院への送迎などは介護保険の対象外となることが多いです。
行政サービスをベースにしつつ、民間サービスや地域の支援と組み合わせる視点が必要です。
「頼れる選択肢を複数持つ」ことが、安心できる生活支援の第一歩です。
3.2 支援の相談が遅れてトラブルに発展
「まだ自分は大丈夫だから」「誰にも迷惑をかけたくないから」といった思いから、支援の依頼や相談を後回しにする人は少なくありません。
しかし、以下のような結果を招きやすいので注意が必要です。
- 急な入院や転倒後に慌てて支援を探すことになり、空きがない
- 生活環境がすでに悪化しており、支援開始が手遅れに
- ご近所トラブルや衛生問題など、周囲に影響が及ぶ
こうなると、本来であれば予防できた問題が深刻化し、結果的に本人だけでなく家族や地域にも負担がかかってしまいます。
早めの相談は「おおげさ」でも「恥ずかしい」ことではありません。まだ元気なうちに準備を始めることが、支援を受ける上での最大のコツです。
3.3 「どこに相談していいかわからない」問題
もうひとつ大きなハードルが、「最初の相談窓口がわからない」という点です。
高齢者本人だけでなく、家族もこんな悩みを抱えることがあります:
- 介護保険の窓口?ケアマネージャー?民間業者?誰に聞けばいいの?
- 病院では教えてくれなかった
- インターネットで調べても情報がバラバラで混乱する
実際に支援が必要になったとき、相談先がわからないまま時間だけが過ぎてしまうケースがとても多いです。
このようなときに役立つのが、「終活ガイド」や「生活支援専門窓口」など、幅広い情報を一元的に整理して案内してくれるサービスです。
「情報が届く人」と「届かない人」で支援の質に差が出る」という現実もあります。だからこそ、普段から頼れる窓口を確保しておくことが大切です。
4. 高齢者の生活支援サービスの種類と選び方
4.1 家事・買い物・見守りなど日常支援の具体例
高齢者の生活支援サービスと聞くと、介護を連想しがちですが、実は「介護ではない支援」こそニーズが高まっています。
たとえば以下のような日常的なサービスがあります:
- 掃除、洗濯、食事の準備などの家事代行
- 食材や日用品の買い物代行や同行支援
- 外出時の付き添いや病院への送迎サポート
- 定期的に連絡を取り安全を確認する見守りサービス
これらは、介護認定が出ていなくても利用できるものが多く、「まだ元気だけどちょっとだけ不便」な時期から活用するのにぴったりです。
とくに見守りサービスは、一人暮らしの方にとって大きな安心感につながります。週1回の電話確認だけでも、異変の早期発見に役立つケースがあります。
日常支援は「自立した生活を守るためのサポート」という視点で捉えるのが大切です。
4.2 医療・介護との連携が安心につながる理由
日常支援に加えて重要なのが、医療・介護とのスムーズな連携です。
高齢者の体調は変化しやすく、突然の入院や介護が必要になることもあります。そのため、支援体制は以下のように「つながっていること」が重要です。
- 医療機関との連携により、通院や服薬管理もカバーできる
- ケアマネージャーと協力して介護保険サービスと併用できる
- 緊急時の対応ルート(救急搬送や連絡体制)が整っている
また、病院や施設の入退院時には「身元保証人」が求められることがありますが、それに対応した生活支援サービスも増えています。
こうした医療・介護との接続ができる支援は、単なる便利さ以上に「安心」そのものです。
生活支援は“切り離されたサービス”ではなく、“生活の中に溶け込む支援”として選ぶことが大切です。
【関連コラム】
身元保証人とは?身元保証人が必要な理由を業界関係者が解説
4.3 終活や身元保証まで対応できる支援とは
最近注目されているのが、「終活」や「身元保証」まで対応できる生活支援です。これは単に今の生活をサポートするだけでなく、将来の不安に備える支援でもあります。
代表的なサポート内容には以下があります:
- 施設入所や入院時の身元保証代行サービス
- 死後事務(遺品整理、役所手続き、供養など)のサポート
- 財産管理や意思表示の支援(エンディングノート作成など)
- 葬儀やお墓に関する事前相談や契約サポート
特に「おひとりさま」の高齢者にとっては、誰が代わりに動いてくれるのかが明確になること自体が安心感に直結します。
最近では、生活支援と終活サポートを一体化したサービスが増えており、「何をどこに相談すればいいかわからない」という悩みを一挙に解決できる体制が整ってきました。
生活支援は、いずれ来る“その時”に備える重要な準備でもあるという意識が、今後ますます大切になります。

5. 高齢者の生活支援を叶える「想いコーポレーショングループ」の取り組み
5.1 心託サービスで得られる「家族の代わり」の安心
「心託サービス」は、身元保証・死後事務・生活支援までを一括して引き受ける総合型の終活支援サービスです。
とくに注目されているのが、以下のような特徴です:
- 入院や施設入所時の身元保証(保証人代行)
- 見守りサービス・健康相談・通院付き添いなどの日常生活支援
- ご逝去後の葬儀・納骨・遺品整理・相続・手続き代行(死後事務)
こうした“家族がやってくれるはずだったこと”を、すべて任せられるのが心託サービスの最大の魅力です。
しかも、利用者一人ひとりに専任コンシェルジュがつき、窓口が一本化。財産開示も不要で、プライバシーに配慮されているほか、月額・年会費は一切不要(入会金1万円のみ)という安心設計も人気の理由です。
「何かあったとき、もう迷わなくていい」そんな安心を提供するサービスです。
詳細は以下をご確認ください。
5.2 全国47都道府県に支部を展開、365日サポート
想いコーポレーショングループが他と一線を画すのは、全国47都道府県に支部を持つ圧倒的なネットワークです。
これにより、どこに住んでいても同じクオリティの支援が受けられる体制が整っています。
さらに、
- 年中無休・10:00〜17:00までの無料相談ダイヤル
- 全国各地で開催される無料説明会・資料請求特典(エンディングノート)
- 地域の支援者と連携した迅速かつ柔軟な対応
など、支援のハードルをぐっと下げてくれる仕組みが豊富です。
心託会員数も20,000名を超えており、安心して任せられる実績が広がり続けています。
どこにいても、どんな状態でも「安心できる場所がある」――それが想いコーポレーショングループの魅力です。
6. まとめ:支援は「今から考える」時代へ
6.1 支援を受けることは「自立」の一歩
「支援を受ける」というと、自分でできないから仕方なく…というマイナスな印象を持たれる方もいます。
でも本当は逆なんです。
生活支援を上手に活用することは、自分らしく暮らし続けるための前向きな選択肢。
たとえば、
- 無理せず安全に暮らすための環境整備
- 心の余裕を生み出すサポート体制
- 家族や周囲との関係を良好に保つ工夫
これらを整えることで、できることを無理なく続けながら、自分の生活を自分でコントロールする力が育ちます。
「支援=依存」ではなく、「支援=自立のためのツール」という考え方が、これからの時代には必要です。
6.2 不安を抱えたままにしない環境づくり
高齢になるにつれて、不安が増えていくのは当然のことです。
ただし、その不安を「抱え込まない」「早めに誰かに相談する」ことが、安心な暮らしへの第一歩になります。
たとえば、こんな不安が多く聞かれます:
- ひとり暮らしで倒れたらどうしよう
- 入院や施設入所のときに保証人がいない
- 死後の手続きを誰にも頼めない
これらの不安は、支援制度やサービスを活用すればきちんと解決できるものばかりです。
しかし、知らないままだと不安は膨らむ一方です。
「情報」と「行動」の差が、未来の安心に直結する時代です。
自分のため、家族のために、少しでも早く支援を選ぶ準備を始めておくことが大切です。
6.3 無理なく始める生活支援の第一歩とは
「じゃあ、何から始めたらいいの?」と迷う方も多いですよね。
無理なく始めるなら、以下のような方法がおすすめです:
- 気軽に参加できる終活説明会に行ってみる
- 無料相談窓口に問い合わせて情報収集する
- エンディングノートを使って、将来の希望を書き出してみる
どれも費用も手間もかからず、今すぐに始められる小さな一歩です。
想いコーポレーショングループでは、無料資料請求でエンディングノートがもらえたり、365日対応の相談ダイヤルがあるなど、初めての方でも安心して始められる環境が整っています。
「いざという時のため」ではなく、「今の安心のため」に、支援とのつながりを持つことが何より大事です。
高齢者の生活支援なら想いコーポレーショングループへ
高齢者の生活支援は、困ってからではなく「今から備える」ことが大切です。
想いコーポレーショングループでは、身元保証・日常支援・死後事務までをサポートする【心託サービス】を全国47都道府県で展開中。
専任コンシェルジュが一人ひとりに寄り添い、年中無休で安心を届けています。
まずは無料資料請求から、安心の第一歩を始めてみませんか?
詳細は以下をご確認ください。
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする