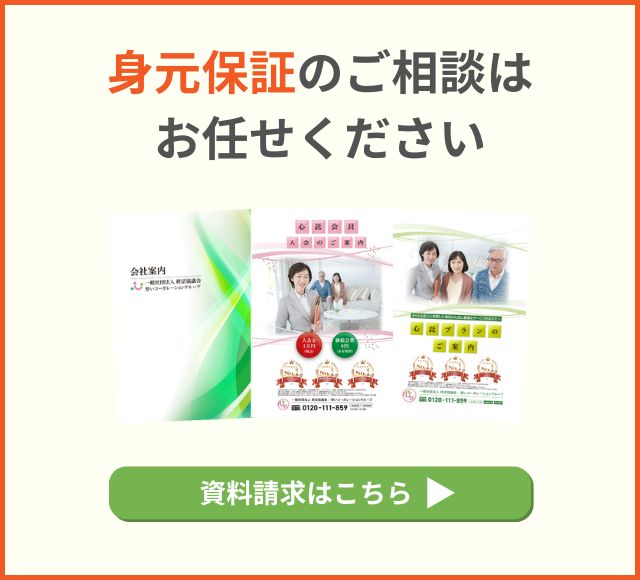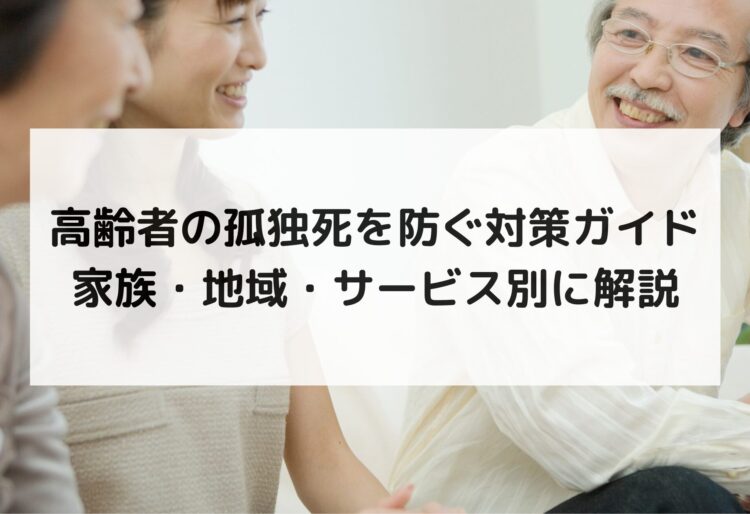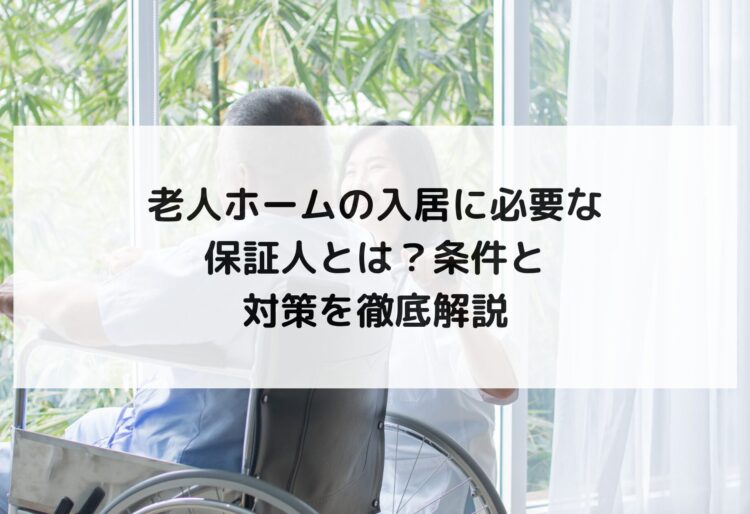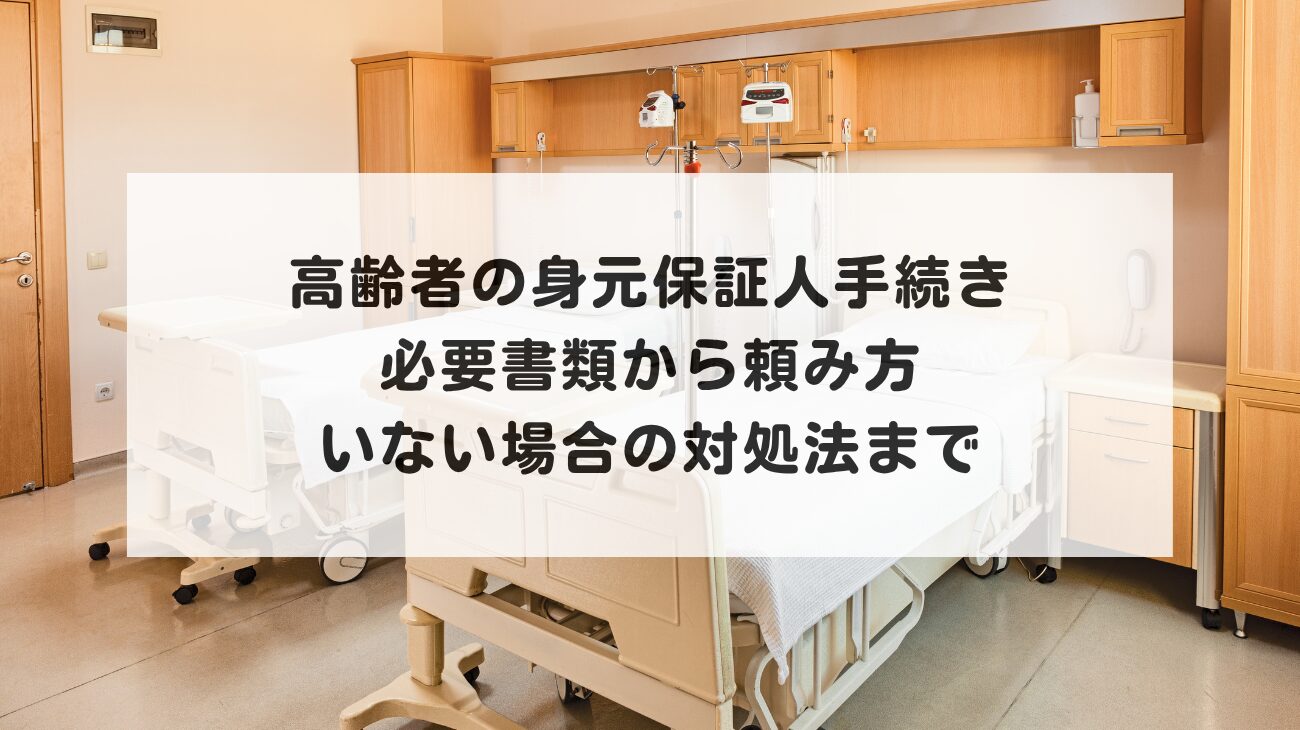
「入院の際に身元保証人を頼まれた」
「親の施設入居で必要になった」
など、高齢者の身元保証人の手続きは、私たちの生活の様々な場面で関わってきます。
しかし、その言葉の響きから「借金の連帯保証人のようなもの?」「何かあったら全責任を負わされるのでは?」と、漠然とした不安を感じる方も少なくないでしょう。
特に、親しい間柄だからこそ、安易に引き受けて後悔する事態は避けたいものです。
この記事では、高齢者の身元保証人になることを検討している方や、将来に備えて知識を深めたいと考えている方のために、身元保証人の具体的な役割から法的な責任範囲、そして万が一の時のための対処法までを、専門的な視点からわかりやすく解説します。
- 高齢者の身元保証人になるために必要なこと
- 身元保証人になるための手続きの流れ
「高齢者の身元保証人を頼める人がいない」「身元保証人になってくれるひとを急いで探している」という方はぜひ終活協議会にご相談ください。
年中無休・全国対応で身元保証サービスを提供しております。
お急ぎの方はお電話でご相談ください。ご相談は何度でも無料です。
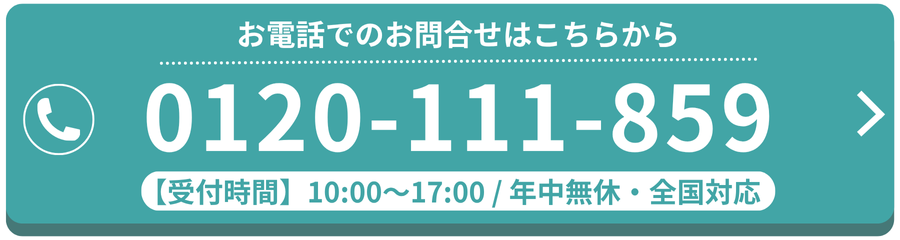
目次
身元保証人とは?安易に引き受ける前に知るべき役割と責任

身元保証人とは、簡単に言えば「本人の身元が確かであることを保証し、万が一、本人が病院や施設などに損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任を負う人」のことです。
しかし、その責任は無制限ではありません。
法律によって保証される範囲や期間が定められており、契約内容をしっかり確認することが何よりも重要になります。
この機会に、漠然とした不安を解消し、自信を持って手続きに臨めるよう準備を整えましょう。
高齢者の身元保証人の主な3つの役割
高齢者の身元保証人に求められる役割は、主に以下の3つに大別されます。
契約によって詳細は異なりますが、これらの基本的な役割を理解しておくことが重要です。
- 本人の人物保証
これが最も基本的な役割です。「この人物は信頼できる人間です」と、その人となりを保証します。施設入居や賃貸契約において、施設や病院が「素性のわからない人物ではないか」というリスクを軽減するために求められます。 - 損害賠償責任
本人が故意または重大な過失によって施設や病院に損害を与え、本人だけでは賠償しきれない場合に、その損害を賠償する責任を負います。ただし、後述するように、この責任は法律によって上限が定められています。 - 緊急連絡先としての役割
特に高齢者の入院や施設入居の場面で重要視される役割です。本人の体調が急変した場合や、緊急の判断が必要になった際の連絡先となります。また、本人が亡くなった際の遺体や遺品の引き取り(身元引受)を兼ねる場合も多くあります。
法的責任の範囲はどこまで?民法改正による変更点
身元保証人と聞くと、「本人が起こした損害をすべて肩代わりさせられるのでは?」という金銭的なリスクが最も気になる点でしょう。
しかし、その心配は過去のものとなりつつあります。2020年4月1日に施行された改正民法により、保証人を過度に保護する仕組みが強化され、責任範囲が明確化されました。
最も重要な変更点は、「極度額(きょくどがく)」の設定が義務化されたことです。
極度額とは、保証人が負う可能性のある損害賠償責任の「上限金額」を指します。
この極度額が契約書に明記されていない身元保証契約は、法律上、無効となります。
つまり、「上限なく青天井で責任を負う」という事態は、現在の法律ではあり得ません。
身元保証人になることを依頼された際は、必ず契約書に「極度額」が具体的な金額で記載されているかを確認してください。
例えば、「上限50万円」といった形です。
この金額が、万が一の際にあなたが負う最大の責任範囲となります。
この法改正により、保証人は予見できないほどの高額な請求をされるリスクから守られるようになったのです。
安易に判を押す前に、契約書の内容を隅々まで確認する習慣をつけましょう。
高齢者の身元保証人の手続きが必要になる場面
では、具体的にどのような場面で高齢者の身元保証人の手続きが必要になるのでしょうか。
私たちの生活において、主に2つの代表的なケースが挙げられます。
それぞれの場面で求められる役割や保証の性質が少しずつ異なりますので、違いを理解しておきましょう。
これらの場面は、ご自身が本人として保証人を依頼する側になることもあれば、親族や友人から保証人になることを頼まれる側になる可能性もあります。
いざという時に慌てないよう、それぞれのケースについて基本的な知識を備えておくことが大切です。
病院への入院時
病院へ入院する際には、多くのケースで身元保証人(または身元引受人)が求められます。
その主な役割は、入院費用の支払いを保証することです。
万が一、本人が支払えなくなった場合に、保証人がその責任を負います。
また、それだけではありません。
手術や治療方針に関する同意の判断を求められたり、緊急時の連絡先となったり、退院時の手続きや身柄の引き受けを行ったりと、医療的な側面での重要な役割も担います。
特に意識がない場合など、本人の意思確認ができない状況では、保証人の判断が極めて重要になることがあります。
介護施設への入居時
特別養護老人ホームなどの介護施設へ入居する際には、ほとんどの場合で身元保証人(または身元引受人)が求められます。
ここでの役割は、金銭的な保証(入院費や利用料の支払い)だけでなく、緊急時の連絡、そして万が一の際の遺体や遺品の引き取りといった「身元引受」の側面が非常に強くなります。
高齢化社会が進む中で、このケースでの身元保証の重要性はますます高まっています。
【実践】高齢者の身元保証手続き完全ステップガイド
高齢者の身元保証人の役割や必要となる場面を理解したところで、ここからは実際の手続きの流れを具体的に解説していきます。
いざ手続きを進めるとなると、「誰に頼めばいいのか?」「どんな書類が必要なのか?」「保証書には何を書けばいいのか?」など、次々と疑問が湧いてくるものです。
このセクションでは、身元保証人を探すところから、書類の準備、そして契約書の記入までを3つのステップに分けて、誰にでもわかるように丁寧にガイドします。
特に、保証人を依頼する際のマナーや、契約書で必ず確認すべきポイントは、後々のトラブルを避けるためにも非常に重要です。
ご自身の状況と照らし合わせながら、一つひとつのステップを確実に進めていきましょう。
ステップ1:高齢者の身元保証人になれる人の条件を確認する
まず最初に、誰が身元保証人になれるのか、その条件を確認する必要があります。
法律で厳密に定められているわけではありませんが、一般的に病院、施設側が設定する主な条件は以下の通りです。
- 安定した収入があること:万が一の損害賠償能力を証明するため、定職に就いており、一定の収入があることが求められます。パートやアルバイトでは認められない場合もあります。
- 成人であり、責任能力があること:未成年者は身元保証人にはなれません。
- 本人とは別の生計を立てていること:保証能力の観点から、本人と生計を共にしている人(同居の配偶者など)は認められないケースがあります。
- 国内に在住していること:緊急時の連絡や手続きの観点から、日本国内に住んでいることが条件となるのが一般的です。
多くの場合、両親や兄弟姉妹、配偶者(別生計の場合)といった三親等以内の親族に依頼することが推奨されます。
友人や知人でも可能ですが、その場合は関係性や保証能力をより詳しく確認されることがあります。
ステップ2:身元保証人を依頼する際の流れと注意点
身元保証人になってくれる人が見つかったら、次は依頼の手続きに進みます。
身元保証は相手に一定の責任を負ってもらう重要な依頼です。
軽々しくお願いするのではなく、誠意をもって丁寧に進めることが、良好な関係を維持する上で不可欠です。
依頼の流れ
- 事前相談:まず、電話や直接会って、身元保証人になってほしい旨を伝えます。この時、なぜ保証人が必要なのか(入院、施設入居など)、どのような責任が生じるのかを自分の言葉で誠実に説明しましょう。
- 書類の送付・持参:相手の承諾を得られたら、身元保証書などの必要書類を渡します。郵送する場合は、記入例や返送用封筒を同封するなど、相手の手間をできるだけ省く配慮をしましょう。
- 署名・捺印の依頼:相手に書類の内容を十分に確認してもらった上で、署名と捺印をしてもらいます。実印と印鑑証明書が必要な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
- お礼:手続きが完了したら、必ずお礼を伝えます。菓子折りを持参するなど、感謝の気持ちを形にすることも大切です。
注意点:
最も重要なのは、リスクを隠さずに正直に伝えることです。
「迷惑はかけないから」と安易に言うのではなく、契約書に書かれている責任範囲や極度額を一緒に確認し、納得してもらった上で引き受けてもらうことが、信頼関係の基本です。
ステップ3:身元保証書の書き方と必要書類
依頼が完了したら、最終ステップとして身元保証書を完成させます。
この書類は、あなたと保証人、そして提出先(施設や病院)との間の契約を証明する重要なものです。
不備があると再提出を求められることもあるため、慎重に作成しましょう。
必要書類は提出先によって異なりますが、ここでは一般的な記載項目と、ケース別の必要書類リストをご紹介します。
身元保証書に記載すべき必須項目
身元保証書のフォーマットは提出先から指定されることがほとんどですが、一般的に以下の項目が含まれています。
記入漏れがないか、必ず確認しましょう。
- 被保証人(本人)の情報:氏名、住所、生年月日、連絡先
- 身元保証人の情報:氏名、住所、生年月日、連絡先、本人との続柄、勤務先、年収
- 保証内容:本人の身元を保証し、損害を与えた場合に賠償する旨の文言
- 極度額(上限金額):保証人が負う損害賠償責任の上限額。この記載がない契約は無効です。
- 保証期間:通常、3年または5年と定められています。期間の定めのない契約は原則3年となります。
- 日付:契約を締結した年月日
- 署名・捺印:本人と身元保証人、双方の自筆での署名と捺印が必要です。
【ケース別】必要書類一覧(本人・保証人)
身元保証書とあわせて、本人確認や収入証明のための書類提出を求められます。
【本人(入居者など)が必要な書類の一例】
- 住民票(マイナンバー記載なし、世帯全員分など指定を確認)
- 健康保険証、介護保険被保険者証の写し
- 収入を証明するもの(年金振込通知書、課税証明書など)
- 健康診断書(施設から指定された項目)
- 認印
【身元保証人が必要な書類の一例】
- 住民票
- 印鑑証明書
- 実印
- 収入を証明するもの(源泉徴収票、課税証明書など)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、パスポートなど)
これらのリストはあくまで一例です。
必ず事前に提出先に確認し、不備のないように準備を進めてください。
身元保証人がいない…そんな時の具体的な対処法

ここまで高齢者の身元保証人の手続きについて解説してきましたが、現代社会では「頼れる親族がいない」「親族には負担をかけたくない」「友人に迷惑はかけられない」といった理由で、身元保証人が見つからずに困ってしまうケースが深刻な問題となっています。
少子高齢化や核家族化、人間関係の希薄化などを背景に、これは誰にでも起こりうる状況です。
しかし、身元保証人がいないからといって、入居を諦める必要はありません。
近年、こうした社会的なニーズに応えるための様々な選択肢が登場しています。
特に、専門の「身元保証サービス」は有効な解決策の一つです。そのメリットや選び方、具体的な利用手続きの流れまで、一歩踏み込んでご紹介します。
親族や友人に頼めない場合の選択肢
身近な人に身元保証を頼むのが難しい場合、いくつかの代替策が考えられます。
まずはこれらの選択肢を検討してみましょう。
- 保証人が不要な病院を探す:数は多くありませんが、入院時の身元保証人を不要としている病院もあります。
- 成年後見制度を利用する(高齢者・障がい者の場合):判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が選んだ後見人が財産管理や身上保護を行う制度です。ただし、手続きが複雑で、あくまで本人の保護が目的のため、すべての身元保証の代わりになるわけではありません。
- 身元保証サービスを利用する:NPO法人や一般社団法人、株式会社などが提供する、身元保証人の役割を代行してくれるサービスです。これが最も包括的な解決策となることが多いです。
身元保証サービスを利用するメリットと選び方
身元保証サービスは、単に書類にサインをするだけでなく、緊急時の対応や金銭管理、場合によっては亡くなった後の事務手続き(死後事務)まで、幅広いサポートを提供してくれるのが大きなメリットです。
特に身寄りのない高齢者にとっては、心強い存在となるでしょう。
【主なメリット】
- 親族や友人に気兼ねすることなく、保証を依頼できる。
- 法人として契約するため、個人の保証人よりも信頼性が高いと判断される場合がある。
- 緊急連絡先、入院・入居手続きの代行、死後事務など、包括的なサポートを受けられる。
【サービスの選び方】
一方で、サービス提供事業者は数多く存在し、中には高額な費用を請求する悪質な業者もいるため、選定は慎重に行う必要があります。
- 実績と信頼性:運営歴が長く、NPO法人や一般社団法人など、非営利性・公益性の高い団体を選ぶと安心です。
- 料金体系の明確さ:契約前に、すべての費用(契約金、月額費用、追加料金など)が明記された見積書を提示してくれるか確認しましょう。
- 契約内容の範囲:どこまでのサービスをカバーしてくれるのか、契約書の内容を隅々まで確認し、不明点は納得できるまで質問しましょう。
- 無料相談の活用:多くの事業者が無料相談を実施しています。複数の事業者から話を聞き、比較検討することが重要です。
一般社団法人 終活協議会では、身元保証に関するご相談を年中無休で受け付けております。
全国47都道府県どこでも対応可能です。
身元保証人がいない、家族には迷惑をかけたくない...そんなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
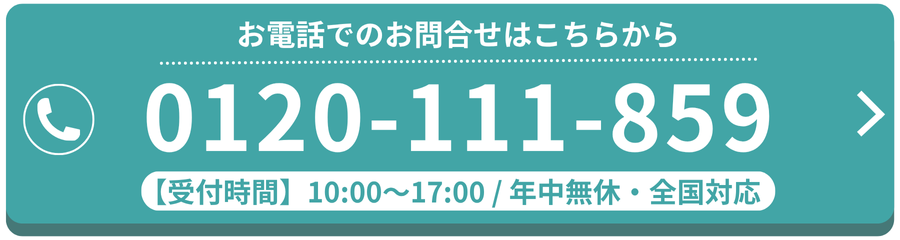
身元保証サービス利用時の手続きの流れ(一例)
では、実際に身元保証サービスを利用する場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
ここでは、相談から契約、そして実際の保証履行までの具体的な流れを解説します。
事業者によって詳細は異なりますが、全体像を掴むことで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
サービス利用には、施設や病院との契約の前に、まずサービス事業者との間で契約を締結する必要があるため、時間に余裕を持って行動することが大切です。
相談から契約までのステップ
身元保証サービス事業者との契約は、人生の重要な局面を任せるための大切な手続きです。
以下のステップを経て、慎重に進められます。
- 無料相談・面談:まずは電話や対面で、現在の状況や希望するサポート内容を相談します。ここで事業者の対応や信頼性を見極めます。本人の意思確認が非常に重要視されます。
- 基本契約の締結:提供されるサービス内容全体に関する基本契約を結びます。
- 各種契約書の作成:次に、具体的なサポート内容に応じた個別の契約書を作成します。
- 身元保証契約の締結:すべての準備が整った後、最終的に身元保証契約を締結します。この契約をもって、事業者が正式にあなたの身元保証人となります。
主な契約内容の解説(財産管理・死後事務など)
身元保証サービスは、単なる保証人代行にとどまらず、利用者の生活を包括的に支えるための様々な契約を組み合わせることが一般的です。
以下はその代表例です。
- 財産管理等委任契約:日常的な金銭管理や行政手続きなどを代行してもらうための契約です。元気なうちから利用できます。
- 任意後見契約:将来、認知症などで判断能力が低下した際に、あらかじめ指定しておいた後見人(事業者)に財産管理などを任せるための契約です。
- 死後事務委任契約:亡くなった後の葬儀、納骨、役所への届け出、遺品整理など、死後の手続き一切を委任する契約です。残された人に迷惑をかけたくないというニーズに応えます。
- 公正証書遺言:遺産の分配方法などを法的に有効な形で残すものです。葬儀費用などを遺産からスムーズに支払うために作成します。
- 預託金に関する契約:死後の手続き費用などを事前に預けておくための契約です。本人の死後、銀行口座が凍結されても手続きが滞りなく進むように備えます。
これらの契約を組み合わせることで、身元保証だけでなく、終末期、そして死後まで、切れ目のないサポートを受けることが可能になります。

まとめ:高齢者の身元保証の手続きは正しい知識で冷静な判断を
高齢者の身元保証人の手続きは、人生の節目で必要となる重要なプロセスです。
かつては漠然とした不安や重い責任が伴うイメージがありましたが、正しい知識を持つことで、不当なリスクを恐れる必要はありません。
もしあなたが保証人を頼まれたなら、契約書をしっかり確認し、納得した上で判断することが何よりも大切です。
一方で、保証人が見つからずに困っているなら、終活協議会の身元保証サービスなど、解決策は存在します。
いずれの立場であっても、冷静に情報を集め、ご自身の状況に合った最善の選択をすることが重要です。
高齢者の身元保証に関してのご相談は年中無休で受け付けております。
ご相談は何度でも無料です。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする