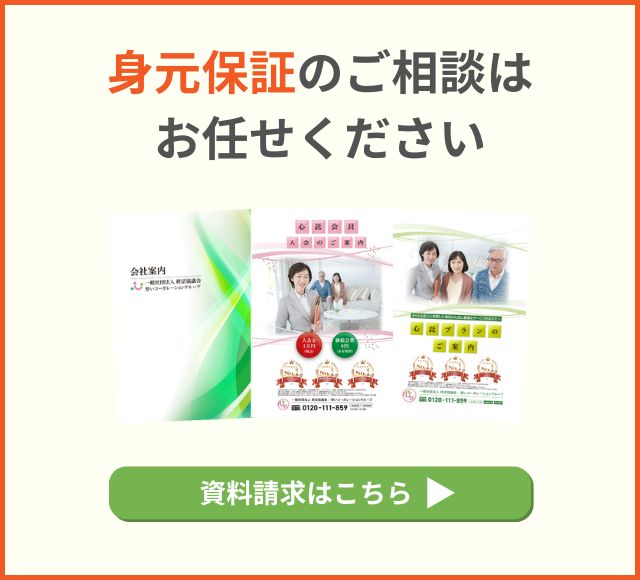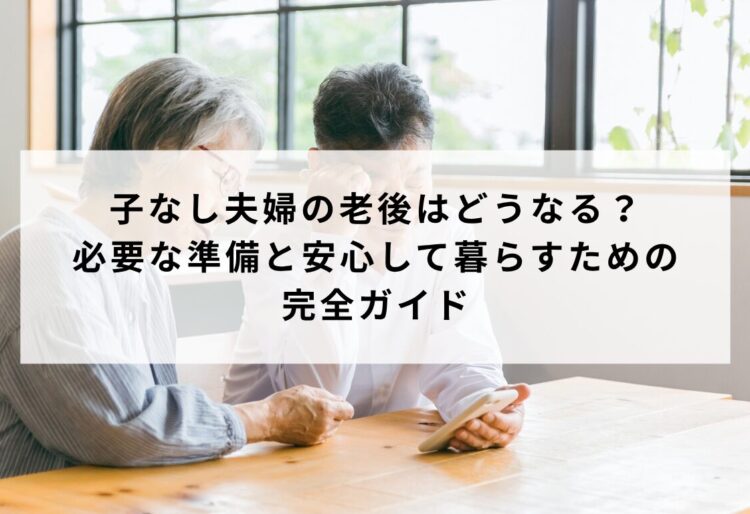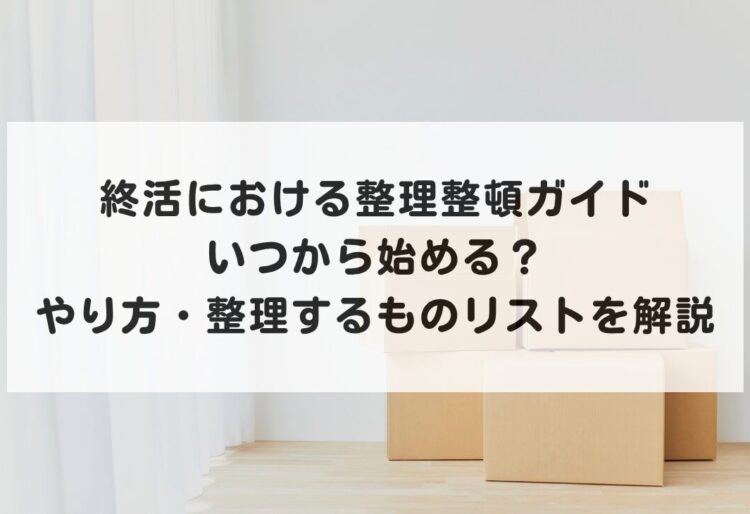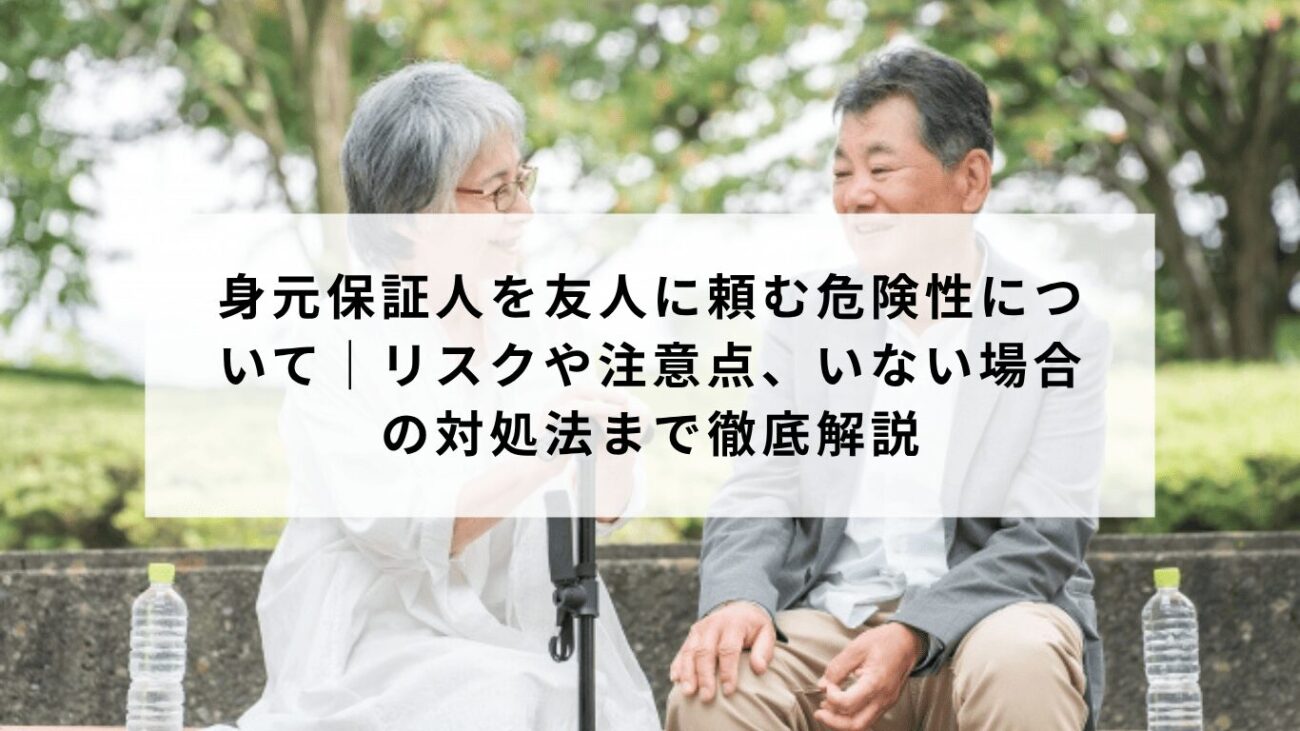
目次
友人に身元保証人を頼むのが難しい理由と潜むリスク
入院や施設への入居、賃貸契約など、人生の様々な場面で必要となる「身元保証人」。
頼れる親族がいない場合、まず思い浮かぶのは親しい友人かもしれません。
しかし、大切な友人だからこそ、身元保証人をお願いするのは慎重になるべきです。
安易にお願いしてしまうと、友情にひびが入るだけでなく、友人を大きなトラブルに巻き込んでしまう可能性があります。
要注意!友人の身元保証人になる・頼むことの3大リスク
身元保証人は、単なる「緊急連絡先」ではありません。
契約者が亡くなった際の遺品整理や、場合によっては金銭的な責任まで負う可能性のある、非常に重い役割を担います。
その責任の重さを十分に理解しないままお願いしてしまうと、後々「こんなはずではなかった」と、双方にとって辛い結果を招きかねません。
リスク1:金銭的な負担をかけてしまう可能性
最も直接的で深刻なリスクが、金銭的な負担です。
身元保証人は、本人が会社に与えた損害や、滞納した入院費などの支払いを求められる可能性があります。
2020年の民法改正で、個人が保証人になる契約では保証の上限額(極度額)を定めることが義務付けられましたが、その上限額の範囲内では支払い義務が発生します。たとえば、上限額が100万円と設定されていれば、その範囲内で友人があなたの代わりに支払わなければならない状況があり得るのです。
友情を信じて引き受けた結果、友人が自身の生活を切り詰めてお金を工面する…そんな最悪の事態もゼロではないことを忘れてはいけません。
リスク2:友人関係が悪化・崩壊する恐れ
次に考えられるリスクは精神的・時間的な負担です。
身元保証人になった友人は、「何かトラブルを起こさないだろうか」「もしもの時は自分が責任を負うのか」といった精神的なプレッシャーを常に感じることになります。また、入院中に容体が急変したときなど、緊急の対応を求められることが考えられます。
あなたにとっては些細なことでも、友人にとっては心配の種になるかもしれません。こうした見えない負担が積み重なり、徐々に関係に溝が生まれることがあります。
リスク3:法的な責任によるプレッシャー
最後に考えられるリスクは法的な責任によるプレッシャーです。
身元保証契約は、口約束ではなく法的な拘束力を持つ契約です。一度署名・捺印(なついん)すれば、「友達だから」という理由は通用しません。契約書に定められた責任を法的に負うことになります。この「法的な責任」という重圧は、想像以上に大きいものです。頼まれた側は、常にあなたの行動を気にかけ、心配し続けることになります。この精神的なプレッシャーが、友人にとって大きなストレスとなることが考えられます。
関連記事:
身元保証人とは?身元保証人が必要な理由を業界関係者が解説 | 一般社団法人終活協議会
身元保証人がいない!誰にどうやって頼めばいいのか
身元保証人を頼める人がいない…そんな時の具体的な解決策
親族や友人に頼めず、身元保証人が見つからないと、入院や入居を諦めなければならないのかと不安になりますよね。しかし、個人に依頼する以外にも、問題を解決するための具体的な方法が存在します。
身元保証サービスを利用する
近年、個人に代わって法人(会社)が身元保証人になってくれる「身元保証サービス」が普及しています。
これは、一定の料金を支払うことで、身元保証に関する様々な役割を代行してくれるサービスです。友人や親族に精神的な負担をかけることなく、問題を解決できるため、多くの方が利用しています。
関連記事:
身元保証サービスとは?費用、注意点などを業界関係者が紹介
身元保証サービスに関する「厚生労働省」の情報をわかりやすくまとめました | 一般社団法人終活協議会
身元保証人がいなくても手続きを進められるか聞いてみる
様々な手続きで身元保証人が必要となりますが、身元保証人をいないことを理由に拒むことは認められません。
そのため、「頼れる家族がいない」などと事情を説明したうえで、身元保証人不要で手続きを進められないか一度確認してみましょう。
一般社団法人 終活協議会は身元保証でのお困りごとに全て対応
一般社団法人 終活協議会の「心託サービス」は、入院・入所時の身元保証だけでなく、
日常生活のサポートや緊急時の対応から亡くなった後の身元保証人が行う「全ての役割」に対応しているプランを用意しております。オプション費用や追加費用は一切なく「入会金と基本料金のみ」で提供しています。
⇒一般社団法人終活協議会の心託サービスについて
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする