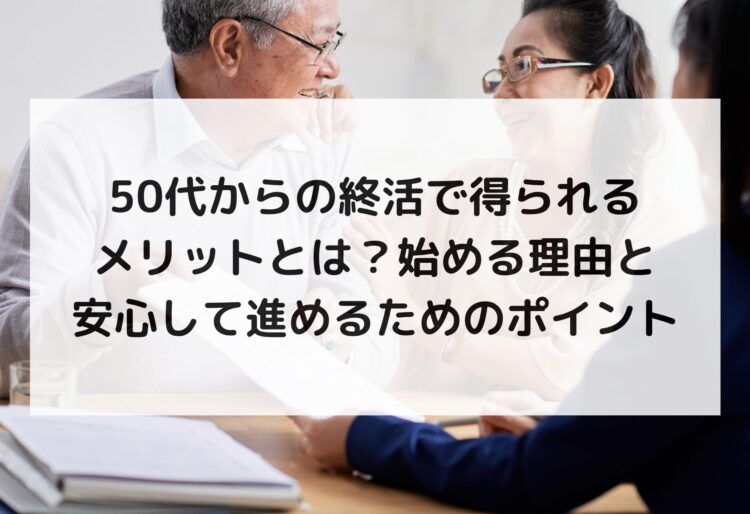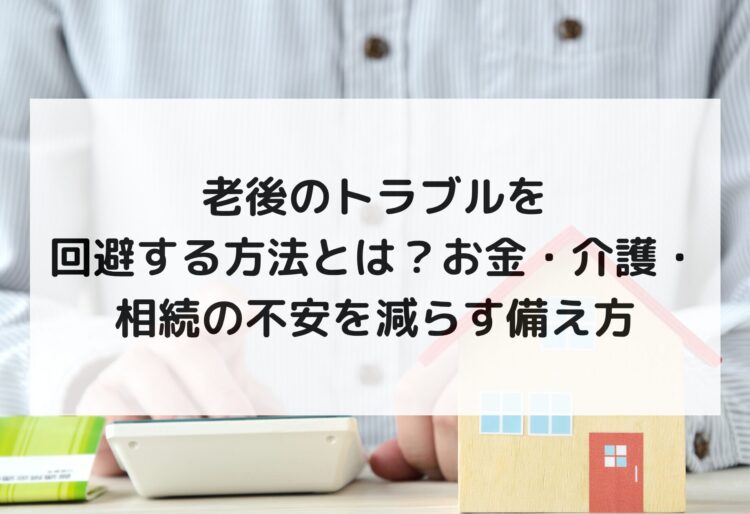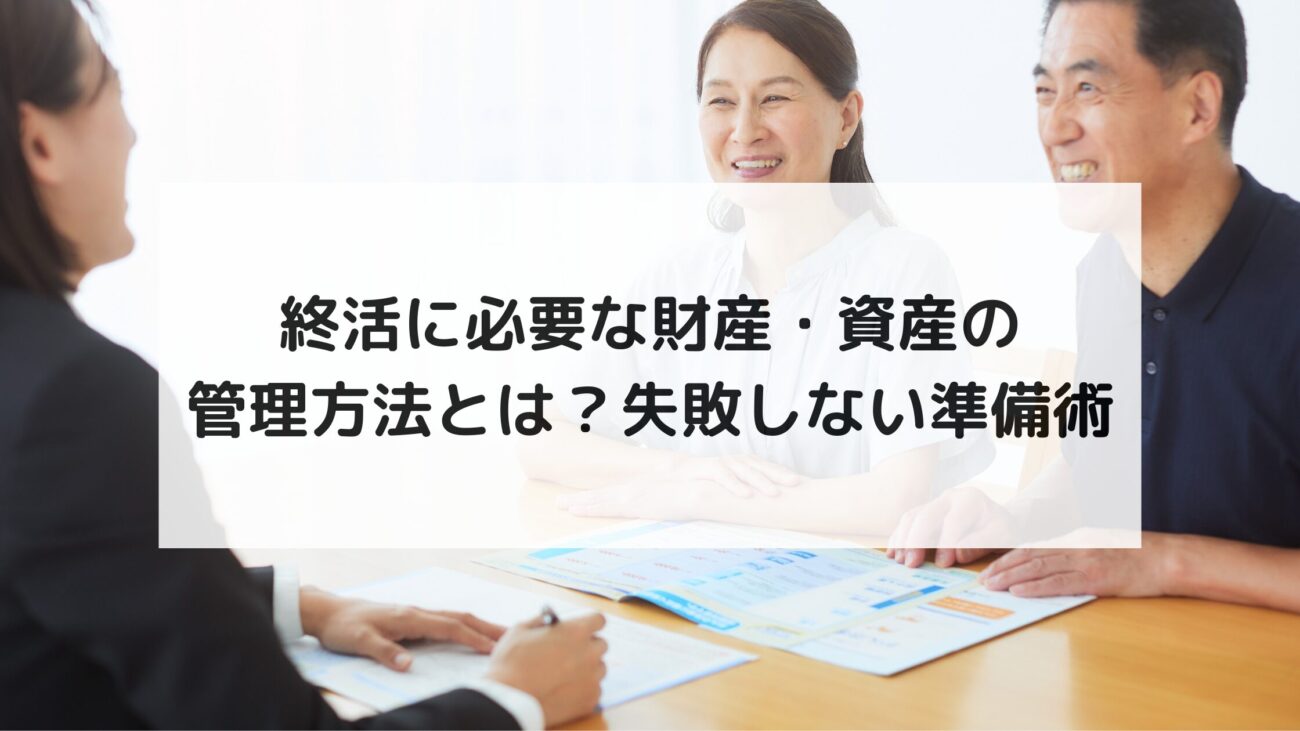
- 終活で財産・資産管理が重要な理由とは
- 終活での財産整理でよくある失敗と対策法
- 管理を依頼できるおすすめサービス
目次
1. 終活における財産と資産管理の重要性
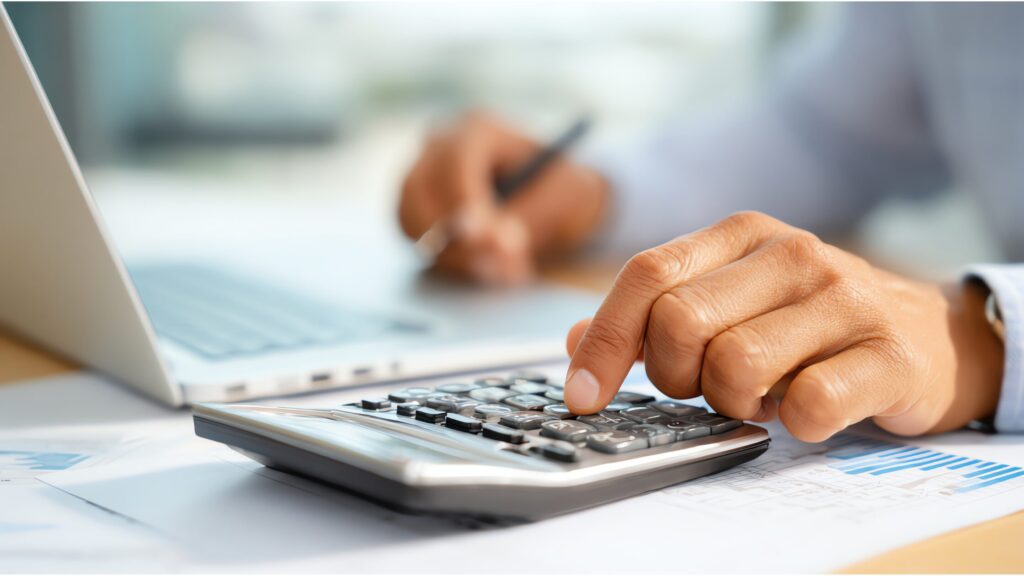
1.1 終活で財産・資産を整理する理由
「終活」という言葉を耳にする機会が増えてきましたが、その中でも特に重要なのが財産や資産の整理です。
ではなぜ、多くの人が終活の中で財産管理に力を入れるのでしょうか?
主な理由は次の3つです。
- 死後のトラブルを未然に防ぐため
- 家族への負担を減らすため
- 自分の意志を反映した資産の使い方を実現するため
たとえば、相続人が複数いる場合、何も準備をしていないと財産分与でもめることがあります。実際、家庭裁判所で扱われる遺産分割調停の件数は年々増加傾向にあります。
また、金融資産や不動産などがどこにどれだけあるのかを把握していないと、家族が探し出すのに膨大な時間と手間がかかってしまいます。
財産を整理しておけば、「何を」「誰に」「どのように」渡すかを自分の意思で明確にでき、死後のトラブルを防ぐことができます。
普段の生活ではあまり意識しないかもしれませんが、日々の支払いで使っている口座、名義だけ残っている不動産、保険契約など、放置しておくと後々厄介になるものは意外と多いんです。
1.2 財産整理を怠ると起こりやすいトラブル
終活における財産管理を後回しにしてしまうと、さまざまなトラブルにつながります。代表的なものを3つ紹介します。
① 相続トラブルで家族が対立
遺言書がなく、資産内容が不明瞭なまま亡くなった場合、相続人同士で争いが起こることがあります。
特に不動産が絡むと、「売る」「残す」「分ける」で意見が割れがちです。
② 預貯金が引き出せず生活費に困る
本人が亡くなった直後、銀行口座が凍結されることがあります。
遺産分割協議が終わるまで引き出せないため、葬儀費用や生活費の準備ができず困るケースが少なくありません。
③ 名義変更や解約手続きに膨大な時間がかかる
使っていない口座や契約が多いと、解約や名義変更に必要な書類を集めるだけでもかなりの手間になります。
しかも、どこに何の資産があるのか本人以外がわからないと、手続きが進まず放置される可能性も。
こうした問題を回避するには、生前のうちにきちんと財産を整理しておくことがとても大切です。
2. 終活で実践すべき財産管理のステップ

2.1 保有資産のリストアップと見える化
終活における第一歩は、自分の財産をしっかり「見える化」することです。
どこに、どれだけ、どんな財産があるのかを把握しておかないと、適切な管理や相続ができません。
たとえば、次のような資産が挙げられます。
- 銀行口座(普通・定期など)
- 株式、投資信託、外貨預金などの金融資産
- 不動産(自宅・賃貸物件・土地など)
- 保険契約(生命保険・医療保険・がん保険など)
- 自動車や貴金属、骨董品などの動産
- 借金や住宅ローン、カードローンなどの負債
よくある失敗としては、以下のようなケースがあります。
- ① 使っていない口座が放置されている
- ② 株式や投資の明細を紛失している
- ③ 不動産の名義が古いままになっている
これを防ぐには、通帳・契約書・証券などを一箇所に集め、資産目録として一覧化することが有効です。
一覧にすることで、どの資産をどう整理するかの方針も立てやすくなります。
2.2 死後を見据えた財産の使い分け
整理した財産は、「どのタイミングで使うか」を考えることが大切です。
特に次の3つの視点で使い道を分けておくと、終活がぐっと具体的になります。
- 老後の生活費として使うお金
- 病気や介護に備えるための費用
- 死後に備える(葬儀・お墓・相続)の費用
こうした分類をしておくことで、無駄なく、目的に応じた使い方ができます。
また、終活保険や信託サービスを活用することで、自分が望むタイミング・相手に資金を届ける仕組みも作れます。
生きている間に「お金の出口」を想定しておくことが、安心した老後とスムーズな相続のカギです。
2.3 不要な口座・契約・物品の整理方法
次に取り組みたいのが、不要な契約や物品の整理です。
「これはもう使わない」と思うものをそのままにしておくと、死後に家族が処理に困ってしまいます。
よくある整理対象はこちらです。
- 使っていない銀行口座
- 解約していない保険やサブスク契約
- すでに利用していないクレジットカード
- 使っていない車や家電、家具など
- 古い書類や郵便物
具体的には、次のような失敗例が目立ちます。
- ① 口座が複数あり、どれがメインかわからない
- ② 毎月の引き落としが続き、不要な出費が続いている
- ③ 保険の契約内容を把握していない
こうした無駄を見直すことで、月々の支出を削減できるだけでなく、死後の手続きもシンプルにできます。
また、不動産や高価な動産は早めに売却・譲渡・名義変更を検討すると、相続税や維持管理のトラブルを防げます。
2.4 情報共有の仕方とエンディングノート活用法
最後に重要なのが、「情報をきちんと家族や信頼できる人に共有すること」です。
せっかく財産を整理しても、それが他の人に伝わっていなければ意味がありません。
しかし、よくある悩みはこんなところです。
- ① どの情報をどこまで共有するか悩む
- ② パスワードや契約先がわからなくなる
- ③ 家族にどう伝えたらいいか迷ってしまう
そこで活用したいのが、エンディングノートです。
このノートには、以下のような情報を整理して書くことができます。
| 項目 | 内容 |
| 財産目録 | 預金、保険、不動産などの一覧 |
| 医療・介護の希望 | 延命措置の可否、希望する施設 |
| 葬儀・お墓の希望 | 宗教形式、墓の種類や場所 |
| 家族・親戚への連絡先 | 緊急時の連絡先リスト |
| デジタル遺品の管理 | SNS、ネット銀行、暗証番号など |
このノートがあるだけで、残された家族は「何をどうすればいいか」が一目で分かります。
なお、情報漏洩が心配な方は、信頼できる第三者や専門サービスに管理を委ねるという選択肢もあります。
終活協議会では、ご逝去後の手続きや整理などの死後事務にも対応しており、安心して任せられる体制が整っています。
さらに、資料請求をされた方には、終活の第一歩として役立つエンディングノートをプレゼントしています。
3. 終活における財産整理でよくある失敗とその対策

3.1 口座・保険・不動産がバラバラになっている
財産整理でよくある失敗のひとつが、保有する資産がバラバラに管理されていることです。
銀行口座が複数あり、保険証券も点在。不動産の書類はどこにあるか不明…。
こうした状態では、いざというときに家族が何から手をつければいいのか分かりません。
特に多い問題がこちらです。
- ① 銀行口座を使い分けているうちに管理が複雑化
- ② 複数の保険会社で契約しており、内容が重複
- ③ 不動産の登記情報が更新されておらず相続時に混乱
このようなケースでは、資産一覧表を作成することが有効です。
銀行名、支店名、口座番号、保険の種類と契約内容、不動産の所在地や評価額などを一枚の表にまとめるだけで、全体像が見えてきます。
資産を集約し、「誰に何を引き継ぐか」を見える化することで、家族の負担は大きく減らせます。
3.2 親族との連携が不十分
終活に関する準備は、自分だけで完結するものではありません。
特に財産に関わる部分は、親族との連携がとても重要です。
ところが現実には、以下のようなコミュニケーション不足によるトラブルが多く見られます。
- ① 遺言がないため、相続人同士でトラブルに
- ② 資産の存在を誰にも伝えておらず、発見が遅れる
- ③ 生前贈与や財産の偏りが原因で関係が悪化
こうした問題を防ぐには、定期的な話し合いや共有の場を設けることが大切です。
一度にすべてを話す必要はありません。
「銀行口座はどこにあるか」「どんな保険に入っているか」など、少しずつでも共有しておくことで信頼関係が深まります。
また、遺言書の作成や信託サービスの利用も、家族間の摩擦を防ぐ有効な手段です。
3.3 書類の管理や保管場所が不明確
財産整理で見落としがちなのが、「重要書類の保管場所」です。
書類自体はそろっていても、「どこにあるか分からない」「鍵が見つからない」となると、相続や手続きに大きな支障が出ます。
とくに注意が必要なのは次のような書類です。
- 預金通帳、キャッシュカード
- 保険証券、年金関係の書類
- 不動産の登記簿謄本、権利証
- 遺言書、エンディングノート
よくある失敗は以下のとおりです。
- ① 複数の引き出しや箱に分散してしまっている
- ② そもそも整理しておらず、不要な書類と混在している
- ③ 火災・盗難対策をしていない場所に保管している
解決策としては、「重要書類ファイル」や「終活用ボックス」にまとめて保管する方法が有効です。
さらに、その保管場所を信頼できる家族に伝えておくことで、いざというときの手続きがスムーズになります。
3.4 自分だけが把握している情報の危険性
意外と多いのが、財産や契約情報を「自分しか知らない」状態で抱えていることです。
その理由としては「誰にも迷惑をかけたくない」「プライバシーを守りたい」といった思いがあるかもしれません。
しかし、これは次のようなリスクにつながります。
- ① 死後、資産が発見されないまま放置される
- ② 電子マネーやネット口座の存在に気づかれない
- ③ 暗証番号やIDが分からず、手続きできない
特に近年は、ネットバンキングや仮想通貨など「デジタル資産」が増えており、紙の書類がない場合は気づかれにくい傾向があります。
このリスクを回避するには、必要最低限の情報だけでも、信頼できる第三者または専門サービスに託すことが大切です。
たとえば、パスワード管理リストを作成し、封筒に入れて保管する方法や、心託サービスのようなサポートを活用するのもおすすめです。
「自分だけが知っている状態」は、残された人を困らせる可能性が高いことを意識しておきましょう。
4. 資産管理を支えるサポートサービスの選び方
4.1 家族に頼れない時代の資産管理
かつては、終活における資産管理を家族に任せることが一般的でした。
しかし、現代は価値観も家族構成も大きく変わりつつあります。
特に以下のような状況が増えています。
- 子どもが遠方に住んでいてすぐに頼れない
- 単身世帯やおひとりさまが増加
- 家族との関係が希薄で相談しにくい
- 子どもに負担をかけたくないと考える人が増えている
このような背景から、資産管理や終活におけるサポートを「家族以外」に求める人が増えています。
具体的には次のような行動が取られています。
- 財産管理や死後の手続きについて、専門サービスを検討する
- 身元保証や生活支援を、第三者に任せる
- 財産情報をエンディングノートではなく専門機関に預ける
「家族に頼らない」という選択肢を前提にした資産管理が、今後ますます主流になっていく傾向です。
4.2 専門家や第三者に依頼するメリット
資産管理を第三者に任せると聞くと、「本当に大丈夫?」と不安に感じるかもしれません。
しかし、信頼できる専門家やサービスに依頼することで、以下のような明確なメリットがあります。
メリット①:手続きがスムーズになる
専門家は財産管理や相続の仕組みに詳しいため、複雑な手続きでも適切に対応できます。
たとえば、複数の口座や不動産の名義変更、保険金の請求など、個人で対応するよりも圧倒的にスピーディです。
メリット②:客観的・中立的な対応ができる
家族間では感情が絡みやすい場面でも、第三者なら冷静に判断できます。
遺産分割や財産の配分を巡ってトラブルが起きそうなときにも、専門家が間に入ることで公平性を保てます。
メリット③:必要な情報を一元管理できる
複数の契約や書類を分散して保管するのではなく、専門サービスに一括で預けられるため、管理がとてもラクになります。
また、365日対応の窓口があるサービスなら、いつでも相談できる安心感もあります。
これらの理由から、近年は「心託サービス」や信託会社、終活支援団体などに資産管理を託す人が増えているのです。
4.3 信頼できる支援を選ぶためのチェックポイント
では、実際に資産管理をサポートしてくれるサービスを選ぶときは、どんな点をチェックすればよいのでしょうか?
以下に、信頼性の高いサービスを選ぶためのポイントをまとめました。
チェックポイント①:料金体系が明確であるか
後から追加料金が発生しないよう、入会金・月額費・手数料などがはっきり明記されているかを確認しましょう。
入会金のみ・年会費不要のサービスは、コスト面でも安心です。
チェックポイント②:対応エリアが全国かどうか
特に高齢者施設や病院とのやりとりが必要になる場合、全国に対応できる支部やネットワークがあると安心です。
チェックポイント③:365日対応のサポート体制があるか
平日昼間しか対応していないと、急なトラブルのときに困ります。
365日・年中無休で相談できる体制があるサービスを選ぶと、いざというときにも頼れます。
チェックポイント④:担当者の質と一貫対応があるか
専任のコンシェルジュがつくサービスなら、窓口が一本化されてスムーズに連携が取れます。
複数の担当者とやりとりする必要がなくなるため、情報の伝達漏れも防げます。
チェックポイント⑤:プライバシー保護への配慮があるか
財産情報を預ける以上、個人情報の取り扱いには慎重であるべきです。
財産の開示が不要で、必要最小限の情報でサポートが受けられる体制が整っているかをチェックしましょう。
サポートサービスを選ぶ際は、価格・対応力・安心感をしっかり比較して、自分に合ったものを見つけることが大切です。
5. 心託サービスで実現する安心の終活と資産管理
5.1 人生の備えに役立つ「心託サービス」
終活を考えるとき、財産や資産の整理と並んで大切なのが、身元保証や死後の手続きといった「もしも」に備えることです。そうしたニーズに応えてくれるのが、「心託サービス」です。
心託サービスは、入院時や介護施設入居時に必要な保証人の代行や生活サポート、葬儀や納骨、遺品整理、相続手続きまでを一括で支援する終活サポートです。全国47都道府県に展開しており、地域に関係なくサービスを受けられるのが大きな魅力です。
主なポイントは以下の通りです:
- 専任コンシェルジュが一貫対応し、窓口が一本化されて安心
- 財産開示は不要でプライバシーが守られる
- 入会金1万円のみで、月額・年会費不要
- 365日対応の相談ダイヤルがあり、困ったときにすぐに連絡できる
- 3つのプラン(安心・万全・完璧)から自分に合った内容を選べる
「これで老後が安心できた」と感じている利用者が多数おり、実績も信頼性も高いサービスです。
心託(しんたく)サービスの詳細はこちら心託(しんたく)サービスの詳細はこちら
5.2 まずは無料で始められる資料請求・説明会
いきなり申し込みをするのは不安という方に向けて、無料資料請求や全国各地での無料説明会も用意されています。
- 資料請求では、終活に役立つ「エンディングノート」が無料でプレゼントされる
- 無料説明会では、サービス内容やプランの違い、実際の利用例などを詳しく確認できる
- 通話無料の相談ダイヤル(0120-111-859)では、どんな小さな不安にもスタッフが丁寧に対応
全国対応・年中無休で利用できる体制が整っているため、誰でも気軽に始められます。
これからの人生を安心して過ごすための第一歩として、心託サービスを上手に活用してみてください。
6. まとめ:自分らしい終活の第一歩を踏み出そう
6.1 早めの準備がもたらす安心
終活というと、年齢を重ねてから始めるものだと思われがちですが、実は早めに準備を始めることで得られる安心感は想像以上です。
- 「もしもの時」に慌てない
- 大切な人に負担をかけない
- 自分らしい人生の終わり方を選べる
こういったメリットがあるからこそ、終活は「年齢」ではなく「タイミング」が大切です。
実際、早めに準備を始めた人ほど、「心にゆとりができた」「不安がなくなった」と感じる傾向があります。
特に財産や資産の整理は、思っている以上に手間がかかるため、時間に余裕のあるうちに少しずつ進めるのがおすすめです。
6.2 今すぐ始められることからスタート
終活は一度にすべてを完了する必要はありません。
できることから、少しずつ取り組むことが何より大切です。
たとえば、次のようなことは今日からでも始められます。
- 家にある通帳や保険証券を一箇所にまとめておく
- 財産一覧をノートに書き出してみる
- 不要な口座や契約を整理してみる
- エンディングノートを手に入れて、書き始めてみる
- 心託サービスや終活ガイド資格の資料を請求してみる
どれも、1日30分程度の作業で進められる内容ばかりです。
大切なのは、「まだ早い」と思わず、自分の人生を自分で整える時間を持つことです。
今この瞬間が、終活を始めるベストなタイミングかもしれません。
家族に頼らない終活と資産管理なら心託サービスを
「財産や資産をどう管理するか」「死後の手続きで家族に負担をかけたくない」──そんな悩みに寄り添うのが、一般社団法人 終活協議会の心託サービスです。
専任コンシェルジュによる一貫対応で、身元保証から死後事務までサポート。全国47都道府県で対応、年会費不要の安心体制も整っています。
自分らしい終活の第一歩として、まずは無料資料請求から始めてみませんか?
以下から無料で資料請求ができます。
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする