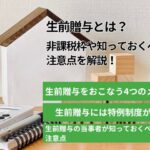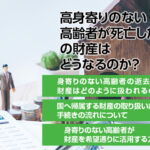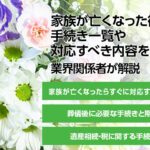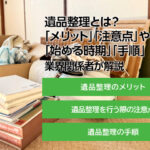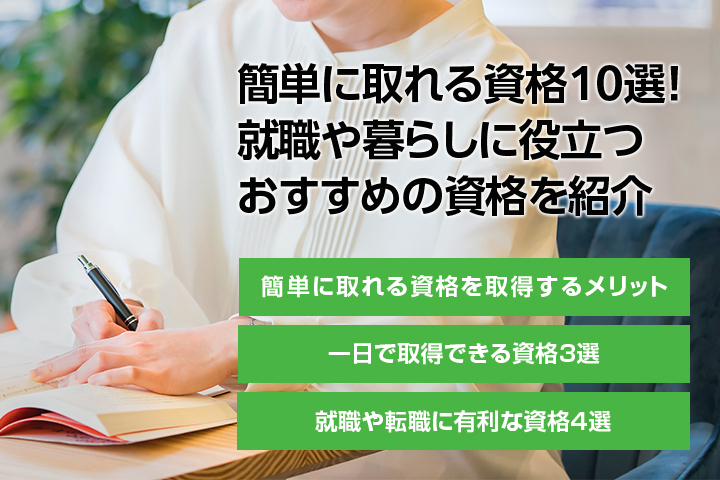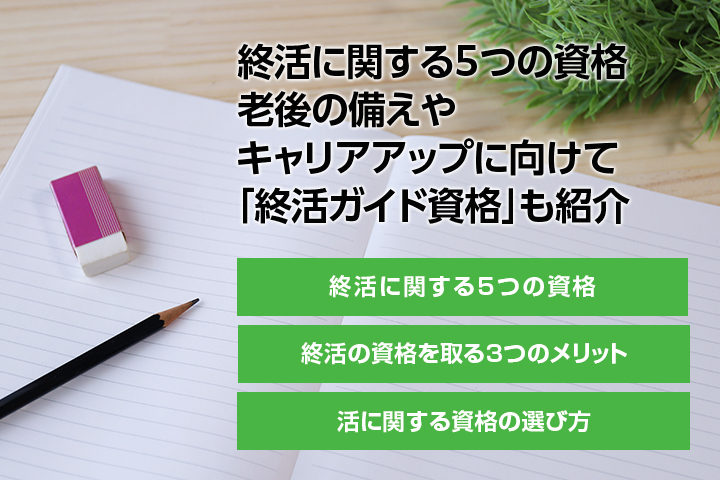任意後見制度とは、将来認知症などで判断能力が衰えた時に備えて、予めサポートしてくれる人やサポート内容を決めておく制度です。おひとりさまにとっては老後の不安解消に
繋がるとても重要な仕組みです。
しかし、一人暮らしの高齢者が増えているにもかかわらず、利用者が少ない現状にあります。そこで今回は、任意後見制度の役割やメリット・デメリットなどについて解説します。
認知症などで判断能力が衰えた時のことが心配な方は、ぜひ参考にしてください。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分となった人の権利保護を目的とした
制度です。任意後見制度では、被後見人(高齢者本人)の意思を尊重しながら、任意後見人が必要な法的手続きや、日常生活のサポートを提供します。任意後見人は被後見人との信頼関係を築きながら、財産管理や医療・介護の決定などを代行します。また、任意後見人は法的責任を負い、裁判所の監督下に置かれます。
被後見人の意思を尊重しつつも、保護を行うための柔軟性を持ち、被後見人の尊厳を
損なわずに支援する重要な枠組みが任意後見制度です。この制度を活用することで、
被後見人の権利が適切に保護されて、生活の質を向上させることが期待されます。
任意後見人の役割
任意後見人の主な役割は次の2つです。
| ・身上監護(しんじょうかんご) ・財産管理 |
身上監護とは、被後見人の生活や健康の維持、介護等を管理する制度です。
例えば、介護サービス契約の締結や病院の入退院の手続き、家屋の維持管理・修繕契約の
締結などが該当します。
また、財産管理とは、身上監護で必要となる費用の支払いや預金通帳・実印等の保管、
各種公共料金の支払い等を管理することです。
逆に、以下の業務は任意後見人の役割の対象外となります。
| ・直接的な介護(食事の介助や家事のサポート) ・病院等への付き添い ・医療行為への同意 ・株式投資等の資産の運用 ・身元引受人・身元保証人になること |
手術や延命治療などの医療行為に関する判断は、任意後見人が判断することはできません。しかし、任意後見制度の利用促進の為、制限付きで医療行為への同意を可能にするかという議論が現在進んでいるようです。
また、被後見人が介護施設への入居や入院をする際には、任意後見人は身元引受人や身元保証人になることができません。身元保証人になることは、被後見人の債務を保証することになるため、利益相反関係になるという考えから基本的には認められていません。
任意後見制度の種類
任意後見制度には、「即効型契約・将来型契約・移行型契約」の3つの種類があります。
即効型契約
即効型契約は、契約と同時に任意後見が開始します。被後見人が、すでに軽度の認知症等で、判断能力に少し不安がある場合に利用されます。契約締結後、すぐに家庭裁判所へ
任意後見監督人の選任申し立てを行い、任意後見監督人が選任されると後見業務が始まります。
軽度の認知症で時々家事に失敗したり、少し前に買ったばかりの商品をまた買ってしまったりすることがある場合等に利用を検討しましょう。
将来型契約
将来型契約は、まだ判断能力に問題がない状態の中で、将来、被後見人の判断能力が低下した時に備えて結ぶ契約です。判断能力を有する状態で締結する為、契約内容を十分に検討し、被後見人の望むサポートを受けることができます。
しかし、実際の後見業務が始まる前に被後見人が急死した場合や、契約締結をしてから長期間が
経過して、契約自体の存在を忘れてしまうようなリスクも想定しなければなりません。
その為、将来型契約を締結する際には、「見守り契約」を同時に結ぶことをおすすめします。
移行型契約
移行型契約は、被後見人の判断能力が十分なうちは任意代理契約を締結して、判断能力が
衰えてきた時に任意後見契約に切り替える契約です。実際の任意後見制度では、移行型契約の利用が最も多いとされているようです。
法定後見制度との違い
任意後見制度は「成年後見制度の中にある一つの制度」ですが、その中に任意後見制度ともう一つの制度として「法定後見制度」があります。そこで、任意後見制度と法定後見制度の違いについて解説します。
法定後見制度は、被後見人の判断能力が衰えた状態で後見人等を選ぶ仕組みになります。
一方、任意後見制度はまだ被後見人の判断能力に問題がないうちに、将来判断能力が衰えた場合に備えて後見人を選びます。任意後見制度は法定後見制度に比べて、「任意後見人を誰にするか、契約内容をどうする
か」について被後見人の意思を尊重することが可能です。
利用されている成年後見制度の多くは法定後見制度
2022年8月に厚生労働省が発表した調査結果(「成年後見制度の現状」)では、利用されている成年後見制度のほとんどは法定後見制度で、そのうちの3/4近くが成年後見、保佐が2割弱、補助の割合は6%未満です。任意後見制度の申立て件数の割合はわずか1%程度に留まっています。
法定後見制度の問題点
法定後見制度は被後見人の意思に関わらず法定後見人を選任する為、トラブルが生じることも多い様です。被後見人とは全く無関係の第三者が法定後見人に選任された結果、被後見人や家族の実情を考慮しないことが問題となっています。
法定後見人が自分の利益を少しでも多く獲得する為に理不尽なことを言って、老後の生活を苦しめてくるような後見人がいます。TV番組などでも、成年後見制度の問題が取り上げられており、大きな話題になっています。
法定後見人の報酬は、被後見人の預貯金額に比例します。その為、被後見人の預金を使わせない様に旅行へ行くことに反対したり、甘い物を食べることまでも反対するといった行動を取るのは、許される行為ではありません。
任意後見制度のメリット
任意後見制度のメリットを紹介します。
1:自分の将来を自由に決められる
法定後見制度の場合、後見人・保佐人・補助人は裁判所が選任します。その為、親族などを後見人にするように希望したとしても、その通りになるとは限りません。
しかし、任意後見制度の場合、被後見人が自由に任意後見人を選ぶことが可能で、契約内容も双方が相談して決めることができます。
一方、法定後見制度の場合、法定後見人が選任されると全ての法律行為を後見人が代理
する為、被後見人や家族が不便な思いをするケースがあります。
また、契約解除について、任意後見制度は法定後見制度に比べて簡単に行えます。
任意後見監督人が選任される前であれば、いつでも被後見人・任意後見人のどちらからでも契約の解除が可能です。任意後見制度が開始された後であっても、正当な理由があれば
裁判所の許可によりどちらからでも契約を解除できます。
2:任意後見人の立場が公的に保証される
任意後見契約を結ぶ際には、公証役場で公正証書を作成して登記が行われます。
公的な立場が保証される為、任意後見人が預貯金の引き出しや役所の申請等を
行う場合もスムーズな手続きが可能です。
3:任意後見監督人のチェックがある
任意後見制度が開始される時には、裁判所によって任意後見監督人が選任されます。任意後見人に信頼できる人物を選任したとしても、後見人が誠実に任務を履行してくれるとは限りません。しかし、任意後見監督人は司法書士や弁護士などの専門家から選任される為、
任意後見人が不正に財産を引き出したり、必要な業務を履行しなかったりすることのない
ようにチェックをしてくれます。
任意後見制度のデメリット
任意後見制度はデメリットもある為、紹介します。
1:取消権がない
法定後見制度の場合、被後見人が締結した売買契約等の法的行為を法定後見人が取り消す「取消権」があります。判断能力がない状態で騙された場合、財産を失わないように保護するためです。しかし、任意後見制度には取消権がありません。任意後見制度で被後見人に代わる手続きが行える権利には、「代理権」があります。代理権は契約で定められた範囲でのみ有効です。代理権の内容例は「預貯金の引き出し」や「公共料金の支払い」「介護契約の締結」に
なります。
2:後見開始と終了の時期に注意が必要
任意後見制度は、契約を結んでも実際に被後見人の判断能力が衰えるまでは効力が発生
しません。
その為、契約を締結するだけでは被後見人が一人暮らしの場合、認知症が進行してもその
まま放置されることも考えられるので注意が必要です。
被後見人が、自身で判断能力の低下に気付いて申立てを行うことも可能ですが、現実的ではありません。
また、任意後見契約は被後見人の死亡により、自動的に契約が終了します。契約内容に
死後の葬儀やお墓の手配を含めることができません。
これらの問題を解消するためには、任意後見制度と同時に「見守り契約」や「死後事務委任契約」を結ぶと良いでしょう。
見守り契約は、定期的に被後見人の安否や健康状態・生活状態を確認し、任意後見制度の
開始を判断するための契約です。
任意後見制度を依頼する人(任意後見受託者)と見守り契約を結ぶこともできますが、
様々な企業や団体も見守り契約を提供しています。
死後の手続き問題は、「死後事務委任契約」を結ぶことにより解消可能です。
⇒死後事務委任契約とは?ご逝去の手続きで「親族に迷惑をかけたくない方・おひとりさまの方」でも安心
任意後見制度を利用する際の流れを紹介
任意後見制度を利用するうえで必要な手続きを、4つのステップに分けて解説します。
ステップ1:任意後見を依頼する人を決める
まずは、任意後見人を選任します。任意後見人は、被後見人の判断能力が衰え、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力を持ちます。それまでは、任意後見を承諾してくれた人を「任意後見受任者」と呼びます。まずは配偶者や子供、信頼できる知人が候補に挙がるでしょう。
身近な方との関係があまり良くないので任せたくない場合は、専門家への依頼を検討してみてください。弁護士や司法書士あるいは任意後見業務や身元保証を専門に行う組織・団体などがたくさんあります。
ただし、民法第847条で定められた以下の人は任意後見人にはなれません。
| ・未成年者 ・過去に後見人になって解任された人 ・破産した人 ・被後見人に訴訟を起こした人やその配偶者・親族 ・行方不明の人 |
ステップ2:契約内容を決める
任意後見人が決まれば、後見人と契約内容を決めていきましょう。
| ・生活面でお願いしたいこと ・介護時にお願いしたいこと ・入院先の病院や入所先の介護施設の共有 ・財産の使用方法や管理方法 ・任意後見人へお支払いする報酬額の決定 |
上記の内容を書面で残す為にライフプランとして契約内容を作成して、内容を明確に
しましょう。
ステップ3:公証役場で契約を締結する
契約の内容が固まったら、下記の必要書類とライフプランを揃えて、被後見人と
任意後見人で共に最寄りの公証役場を訪れます。公証役場で公正証書を作成し、任意後見契約を結びます。尚、被後見人が何かしらの事情で公証役場へ行くことができない場合は、
代わりに公証人を立てて出向くことも可能です。
⇒都道府県別公証役場マップ
| <被後見人が用意する書類> ・印鑑登録証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書) ・戸籍謄本 ・住民票 <任意後見人が用意する書類> ・印鑑登録証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書) ・住民票 |
ステップ4:任意後見監督人選任の審判の申立て
契約を結んでも自動的に後見業務が開始されるわけではありません。実際に後見が必要になった時は、任意後見監督人を選任するための審判を裁判所に申立てる必要があります。
申立てを行えるのは以下の人に限られます。
| ・本人(被後見人) ・配偶者 ・四親等以内の親族 ・法定代理人 ・任意後見受任者 |
一般的には契約を結んだ任意後見受任者が申立てを行います。おひとりさまの場合は、任意後見契約だけではなく日頃から安否の確認や身体状況をチェックする見守り契約などを同時に結んでおくと良いでしょう。
頭の回転はしっかりしていても、体力が衰えて銀行や役所に出向くことが難しい場合は、
任意代理契約の締結も検討してください。
申立てに基づき、裁判所は任意後見監督人を選任します。任意後見監督人は、任意後見人が契約に基づいて適正に業務を遂行しているか監督する人です。
任意後見人は監督人の指示に基づいて、一定期間ごとに報告書や財産目録等の必要な書類を監督人に提出しなければなりません。
任意後見監督人の多くは、親族をはじめ、弁護士・司法書士・社会福祉士などの職業の人から選任されます。
任意後見監督人が選任されることにより、任意後見人の仕事がはじまります。
任意後見制度にかかる費用
任意後見制度を利用するうえで必要な費用には、以下の4項目があります。
1:公正証書を作成する際の費用
任意後見契約を締結するには、必ず公証役場で公正証書を作成しなければなりません。
公正証書の作成に必要な費用は以下の通りです。
| ・公正証書作成の基本手数料:11,000円 ・法務局への登記嘱託手数料:1,400円 ・収入印紙代:2,600円切手代:約600円(裁判所によって異なります) ・用紙代:1枚250円 |
これ以外に書類の作成を司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合は、作成手数料を支払わなければなりません。作成手数料は依頼する専門家や依頼する内容等によって様々ですが、最低でも5万円程度が必要です。
2:任意後見監督人選任の申立て費用
任意後見を登記した後、実際に後見が必要になり、任意後見監督人の選任を裁判所に
申立てする際に以下の費用が発生します。
| ・申立手数料(収入印紙代):800円 ・後見登記手数料(収入印紙代):1,400円 ・切手代:約3,600円(裁判所によって異なります) |
3:任意後見人に支払う報酬
任意後見人の報酬額は、当事者同士の話し合いであれば自由に金額を決定できます。
被後見人の親族や知人が任意後見人になる場合の報酬額と、弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼する場合の報酬額の目安は下記の通りです。
| ・親族や知人:月額0~5万円 ・専門家:月額3~6万円 |
支払時期の設定は自由ですが、毎月月末に振り込まれることが一般的なようです。
報酬額や支払い方法は、任意後見契約の契約書に記載します。また、報酬の支払いは契約を結んだ時点ではなく、「後見を開始した時点」から行われます。
4:任意後見監督人に支払う報酬
任意後見監督人への報酬額は家庭裁判所が決定し、被後見人が支払わなければなりません。報酬は被後見人が所有する財産によって異なります。報酬額の目安は以下になります。
| <管理する財産額による報酬額> ・5,000万円以下:月額5,000円~2万円 ・5,000万円以上:月額2万5,000円~3万円 |
気になる方はお気軽にご相談ください
任意後見制度は、将来に不安のある「おひとりさま」におすすめの制度です。
認知症になり判断能力がなくなってから利用する法定後見制度と異なり、予め被後見人の
希望を叶える契約ができます。
政府や弁護士会団体等も任意後見制度の利用促進を進めていますが、認知度が低く、
まだまだ利用されていないのが現状です。
超高齢社会に入り終活の必要性が高まってきている中で、当社も任意後見制度の必要性を
伝えていきたいと考えております。
一般社団法人 終活協議会では、お客様一人ひとり合った心託サービスを提供しています。料金は入会金とプラン料金のみで、追加費用は一切無く、任意後見制度を含めた各サポートも充実しています。任意後見制度でお困りの方は、専門知識と実績豊富なスタッフが365日お電話にて全国対応しますので、お気軽にご相談ください。
※電話受付時間10:00~17:00
会社やサービスに関する資料請求をご希望の方は、24時間365日受け付けておりますので、下記ページよりご連絡ください。
監修

- 所属:東京司法書士会 一般社団法人 終活協議会理事
-
1997年 東洋大学法学部卒業
大学在学中から司法書士試験の勉強をしつつ、1999年株式会社サイゼリヤに入社
7年間勤務した後、再度司法書士を目指すため2006年退社
2007年 司法書士試験合格
2008年 司法書士登録
試験合格後は、都内の司法書士事務所や法律事務所にて勤務
2021年 「落合司法書士事務所」開設
2021年 一般社団法人終活協議会理事就任
最新の投稿
 2024年6月19日生前贈与とは?非課税枠や知っておくべき注意点を解説!
2024年6月19日生前贈与とは?非課税枠や知っておくべき注意点を解説! エンディングノート2023年12月3日身寄りのない高齢者が死亡した後の財産はどうなるのか?
エンディングノート2023年12月3日身寄りのない高齢者が死亡した後の財産はどうなるのか? おひとりさま2023年9月11日家族が亡くなった後の手続き一覧や対応すべき内容を業界関係者が解説
おひとりさま2023年9月11日家族が亡くなった後の手続き一覧や対応すべき内容を業界関係者が解説 おひとりさま2023年7月10日遺品整理の進め方ガイド|注意点とメリット・デメリットを詳しく解説
おひとりさま2023年7月10日遺品整理の進め方ガイド|注意点とメリット・デメリットを詳しく解説
この記事をシェアする