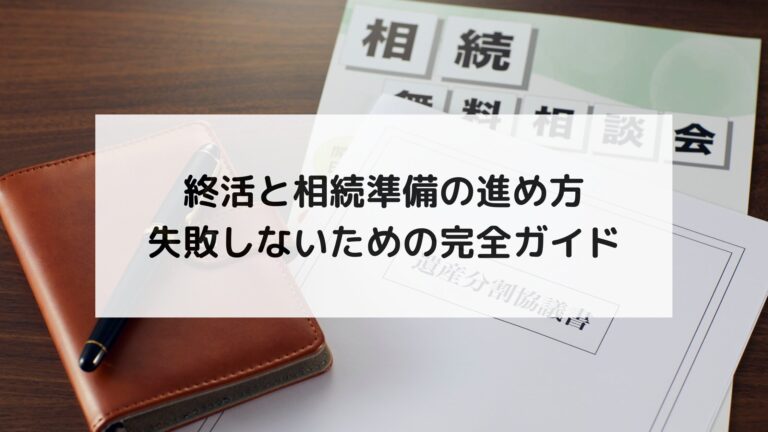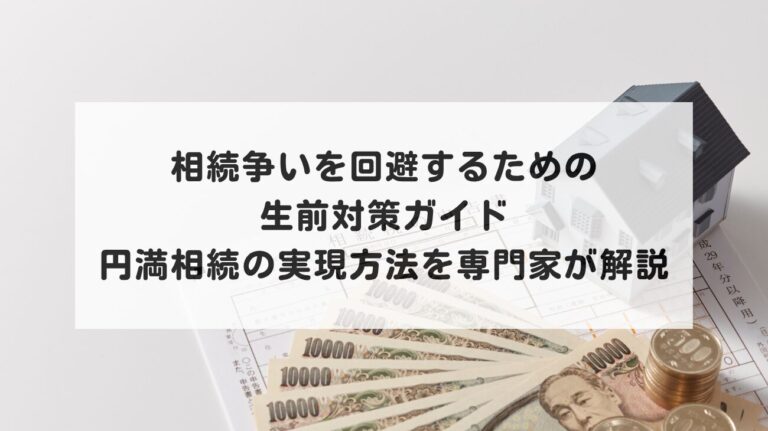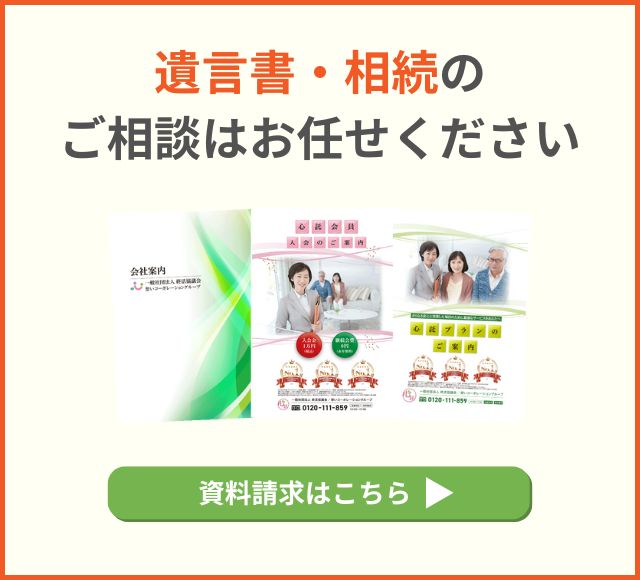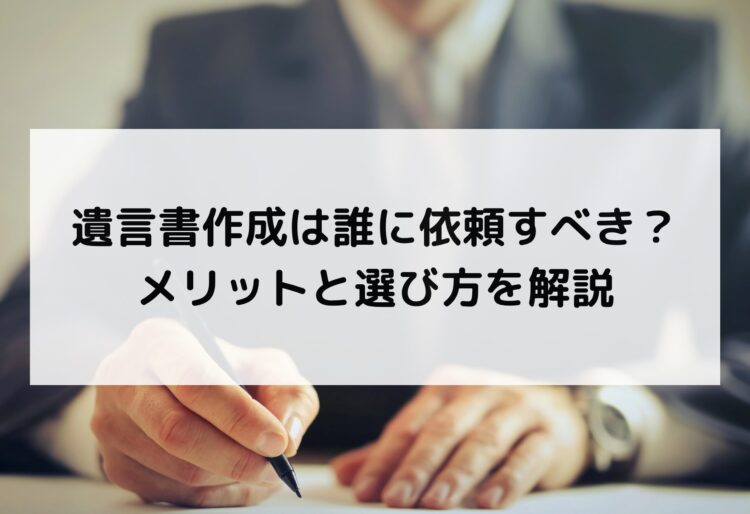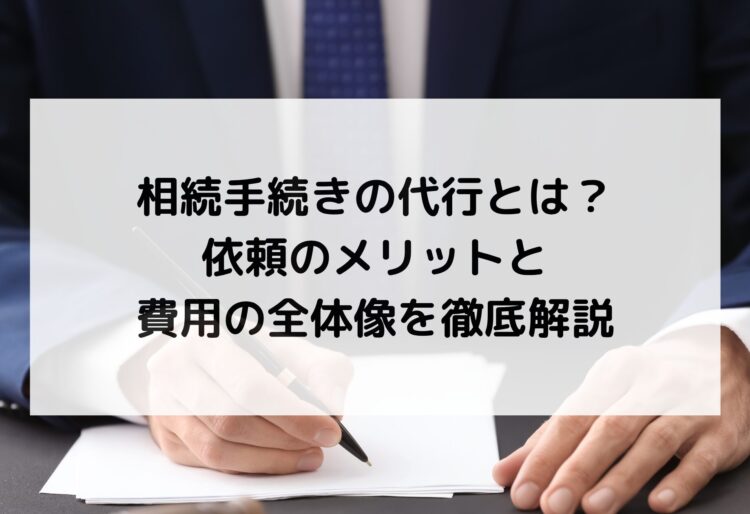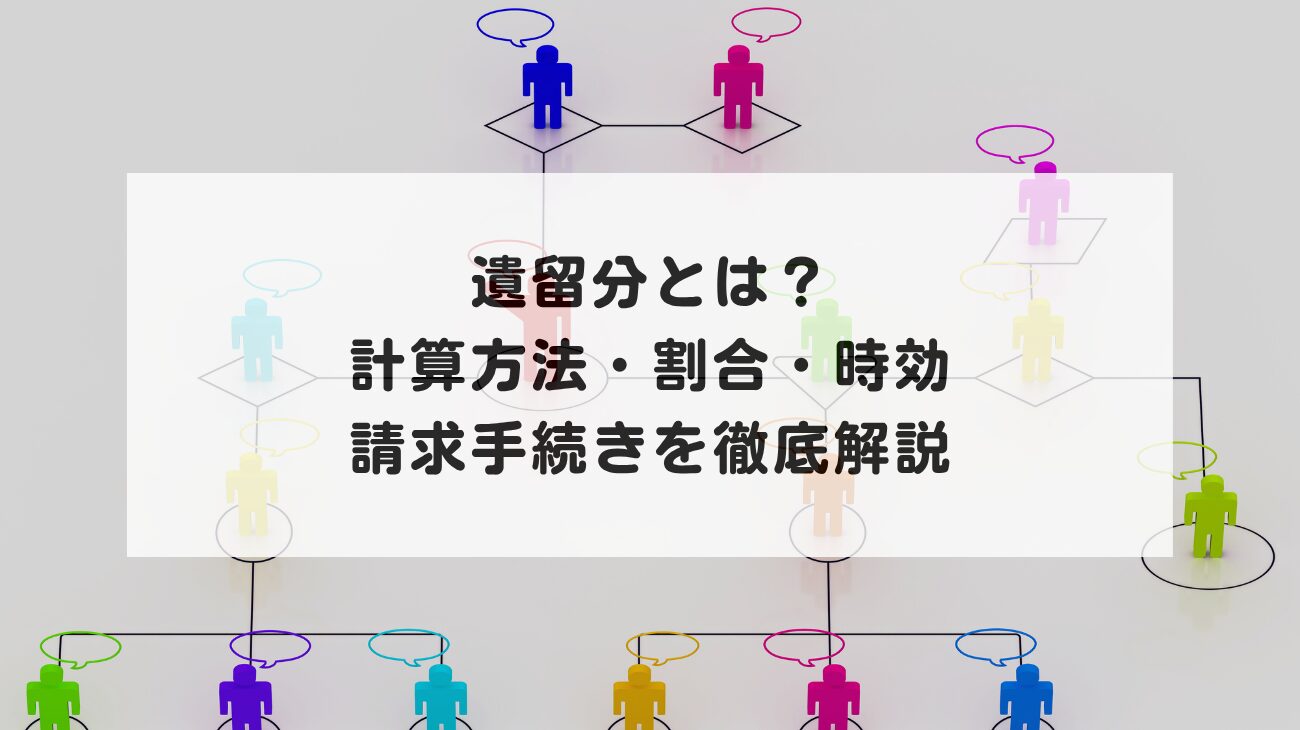
「遺留分」という言葉を知っていますか?
相続において、この遺留分はとても大切な概念なのですが、知らない方も多いかもしれません。
今回は、遺留分の基本的な仕組みから計算方法、割合、時効、請求の流れまでをわかりやすく解説します。
あわせて読みたい
目次
遺留分とは?相続で最低限保証される遺産の取り分

遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する際に、配偶者や子などの一定の相続人に対して法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。
たとえ遺言書に「全財産を特定の一人に相続させる」と書かれていたとしても、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された分を取り戻す権利があります。
例えば、父親が亡くなり、「全財産を長男に」という遺言書が見つかったとします。
この場合、配偶者や次男は全く財産を受け取れないのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
配偶者や次男には遺留分という権利があり、長男に対して「最低限の取り分は渡してください」と請求することができるのです。
これは、遺された家族の生活を保障し、相続における極端な不公平を防ぐための重要な制度です。
遺留分がなぜ重要なのか?制度の目的を解説
遺留分制度の主な目的は、被相続人の財産処分の自由(遺言の自由)と、遺族の生活保障や相続人間の公平性のバランスを取ることにあります。
被相続人が生前に築いた財産は、多くの場合、家族の協力があってこそ形成されたものです。
そのため、遺された家族が相続によって生活に困窮したり、相続人間で深刻な対立が生まれたりすることを防ぐために、この最低保障の仕組みが設けられているのです。
遺留分は、単なるお金の問題ではなく、遺族の生活を守るためのセーフティーネットと言えるでしょう。
法定相続分との違いは?
遺留分とよく似た言葉に「法定相続分」があります。
この二つは明確に異なります。
法定相続分とは、遺言書がない場合に、民法で定められた相続人が遺産を相続する際の目安となる割合のことです。
一方、遺留分は、遺言書の内容にかかわらず、相続人に保障される「最低限の取り分」を指します。
つまり、法定相続分は遺言書によって変更できますが、遺留分は遺言書をもってしても奪うことのできない、より強力な権利なのです。
遺留分は、この法定相続分を基準に計算されます。
遺留分を請求できる人とできない人
遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。
法律で遺留分を請求できる権利を持つ人(遺留分権利者)の範囲が定められています。
遺留分権利者には優先順位があり、上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人になれず、遺留分もありません。
例えば、子がいる場合は、親(直系尊属)は相続人になれないため、遺留分も主張できません。
この順位を正しく理解することが、相続トラブルを避ける上で非常に重要になります。
遺留分権利者の範囲と順位
遺留分を請求できる権利者(遺留分権利者)は、被相続人の配偶者、子(およびその代襲相続人)、そして直系尊属(父母や祖父母)です。
具体的には、以下の通りです。
- 配偶者:常に遺留分権利者となります。
- 子:第一順位の遺留分権利者です。子が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て孫)が代襲相続人として遺留分を主張できます。
- 直系尊属(父母など):子がいない場合の第二順位の遺留分権利者です。被相続人の父母が既に亡くなっている場合は、祖父母が権利者となります。
これらの人々は、遺言によって自身の相続分が侵害された場合に、遺留分を主張する権利を持っています。
兄弟姉妹に遺留分はない
相続において非常に重要なポイントは、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないという点です。
兄弟姉妹は、子や直系尊属がいない場合に第三順位の法定相続人となりますが、遺留分の権利は持っていません。
なぜなら、遺留分制度は主に被相続人と生活を共にしてきた近しい家族の生活保障を目的としているためです。
配偶者や子、親に比べて、兄弟姉妹は被相続人との生活上の結びつきが弱いと一般的に考えられているため、遺留分の保護の対象外とされています。
したがって、「全財産を愛人に遺贈する」といった遺言があった場合でも、兄弟姉妹は遺留分を主張して財産を取り戻すことはできません。
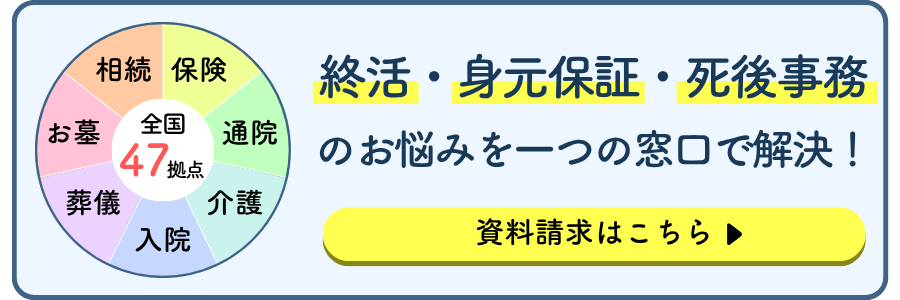
遺留分の割合と具体的な計算方法
ご自身の遺留分が具体的にいくらになるのか、その計算方法を理解することは、権利を主張する上で不可欠です。
「自分の取り分が不当に少ない気がする」と感じていても、具体的な金額がわからなければ、請求のしようがありません。
遺留分の計算は、一見複雑に見えますが、ステップごとに順を追って考えれば理解できます。
ここでは、その計算方法を3つのステップに分け、具体的なシミュレーションを交えながら、誰にでもわかるように詳しく解説していきます。
相続人の組み合わせ別「遺留分の割合」一覧
まず、遺産全体に対して遺留分として確保される割合(総体的遺留分)は、相続人の組み合わせによって決まります。
これは法律で定められており、以下の2パターンしかありません。
- 直系尊属(父母など)のみが相続人の場合:遺産の3分の1
- 上記以外の場合(配偶者や子が含まれる場合):遺産の2分の1
この総体的遺留分を、各遺留分権利者がそれぞれの法定相続分の割合に応じて分け合います。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、総体的遺留分は遺産の1/2です。
これを配偶者(法定相続分1/2)と子2人(同1/4ずつ)で分けるため、それぞれの個別遺留分は配偶者が1/4、子が各1/8となります。
遺留分計算の3ステップ
遺留分の具体的な金額を算出するには、以下の3つのステップで計算を進めます。
この流れを把握することで、複雑な計算も整理しやすくなります。
- ステップ1:遺留分の基礎となる財産を確定する
- ステップ2:総体的遺留分額を算出する
- ステップ3:個別の遺留分額を算出する
まずは全体の財産を把握し、それに法律で定められた割合を掛け、最後に個人の取り分を算出するというイメージです。
次の項目から、各ステップを詳しく見ていきましょう。
ステップ1:遺留分の基礎となる財産を確定する
最初に、遺留分を計算する元となる財産の総額を確定させます。
これは、被相続人が亡くなった時点で所有していたプラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)から、マイナスの財産(借金など)を差し引いた金額が基本です。
さらに重要な点として、特定の生前贈与や遺贈(遺言による贈与)もこの財産に加算して計算します。
これを「みなし相続財産」と呼びます。
特に、相続人への特別な生前贈与(特別受益)は、原則として相続開始前10年以内に行われたものが加算対象となるため、注意が必要です。
ステップ2:総体的遺留分額を算出する
ステップ1で確定した「遺留分の基礎となる財産」の総額に、法律で定められた「総体的遺留分割合」を掛け合わせます。
この割合は、前述の通り、相続人が直系尊属のみの場合は「3分の1」、それ以外の場合は「2分の1」です。
この計算によって、遺留分権利者全体で確保されるべき遺産の総額が明らかになります。
計算式: 遺留分の基礎となる財産 × 総体的遺留分割合(1/2または1/3) = 総体的遺留分額
ステップ3:個別の遺留分額を算出する
最後に、ステップ2で算出した「総体的遺留分額」に、各遺留分権利者の「法定相続分の割合」を掛け合わせます。
これにより、各個人が具体的に請求できる遺留分の金額(個別的遺留分額)が確定します。
例えば、相続人が配偶者と子1人の場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつです。
総体的遺留分額に1/2を掛けることで、それぞれの個別の遺留分額が算出されます。
計算式: 総体的遺留分額 × 各権利者の法定相続分割合 = 個別的遺留分額
ケース別・遺留分の計算シミュレーション
法律の条文や計算式だけでは、ご自身の状況に当てはめて考えるのは難しいかもしれません。
ここでは、具体的な家族構成を想定したシミュレーションを通じて、遺留分計算の実際を見ていきましょう。
「もし自分の場合はどうなるのか?」と状況を置き換えながら読み進めることで、理解が格段に深まるはずです。
一般的なケースから、少し複雑な生前贈与があったケースまで、3つのパターンをご紹介します。
ケース1:配偶者と子供2人の場合
【状況】
相続財産:6,000万円
相続人:配偶者、長男、次男
遺言:「全財産を長男に相続させる」
【計算】
- 基礎財産:6,000万円
- 総体的遺留分額:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 個別遺留分額:
- 配偶者:3,000万円 × 1/2 (法定相続分) = 1,500万円
- 次男:3,000万円 × 1/4 (法定相続分) = 750万円
このケースでは、配偶者は1,500万円、次男は750万円を長男に請求できます。
ケース2:子供がおらず、配偶者と親がいる場合
【状況】
相続財産:6,000万円
相続人:配偶者、被相続人の母
遺言:「全財産を配偶者に相続させる」
【計算】
- 基礎財産:6,000万円
- 総体的遺留分額:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 個別遺留分額:
- 母:3,000万円 × 1/3 (法定相続分) = 1,000万円
このケースでは、被相続人の母は1,000万円を配偶者に請求できます。
ケース3:特別受益(生前贈与)がある場合の計算
【状況】
相続財産:4,000万円
相続人:長男、次男
遺言:「全財産を長男に相続させる」
特記事項:長男は5年前に被相続人から住宅購入資金として2,000万円の生前贈与(特別受益)を受けていた。
【計算】
- 基礎財産:相続財産4,000万円 + 特別受益2,000万円 = 6,000万円
- 総体的遺留分額:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 個別遺留分額:
- 次男:3,000万円 × 1/2 (法定相続分) = 1,500万円
このケースでは、生前贈与を財産に含めて計算するため、次男は1,500万円を長男に請求できます。
もし生前贈与を考慮しないと、次男の遺留分は1,000万円(4,000万円×1/2×1/2)となり、500万円も少なくなってしまいます。
特別受益の有無は、遺留分の額に大きく影響するのです。
遺留分が侵害されたら?「遺留分侵害額請求」の手続きと流れ

ご自身の遺留分が侵害されていることが計算によって明らかになった場合、何もしなければその権利は実現されません。
侵害された遺留分を取り戻すためには、「遺留分侵害額請求」という法的な手続きを行う必要があります。
これは、遺産を多く受け取った相手方に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求める権利です。
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、現物(不動産など)の返還を求めるものでしたが、法改正により金銭での支払いを求める形に変わりました。
この請求には厳格な期限(時効)が設けられており、それを過ぎてしまうと権利を主張できなくなるため、迅速な行動が求められます。
ここでは、遺留分侵害額請求を行うための具体的なステップと、最も注意すべき時効について、詳しく解説していきます。
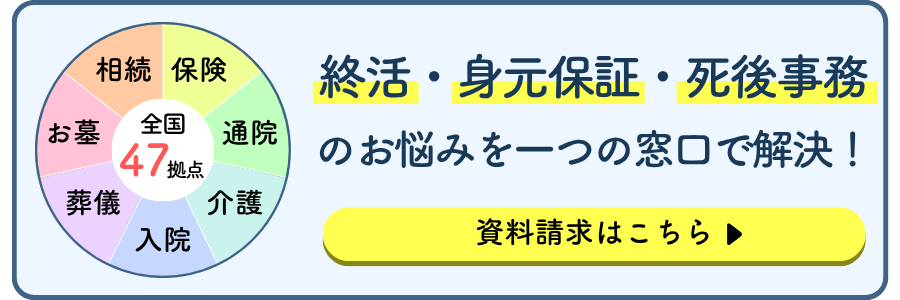
請求には時効がある!すぐに確認すべき2つの期限
遺留分侵害額請求で最も注意しなければならないのが「時効」です。
この権利は永久に主張できるわけではなく、法律で定められた期間内に請求しないと消滅してしまいます。
時効には2つの種類があり、どちらか早い方が到来した時点で権利が失われます。
- 相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年
被相続人が亡くなったこと、そして遺言や贈与によって自分の遺留分が侵害されている事実の両方を知った時から1年以内に請求権を行使しなければなりません。この「知った時」が起算点となるため、非常に短い期間です。 - 相続開始の時から10年
たとえ遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、相続が開始(被相続人が亡くなった時)してから10年が経過すると、権利は完全に消滅します。これを「除斥期間」と呼びます。
特に「知ってから1年」という期間はあっという間に過ぎてしまいます。
遺留分の侵害を疑う状況であれば、まずは時効を中断させるためにも、速やかに行動を起こすことが何よりも重要です。
遺留分侵害額請求の具体的な3ステップ
遺留分侵害額請求は、通常、以下の3つのステップで進められます。
いきなり裁判になるわけではなく、まずは当事者間の話し合いから始めるのが一般的です。
それぞれのステップで何をすべきかを理解し、準備を進めましょう。
- ステップ1:配達証明付き内容証明郵便で意思表示する
- ステップ2:当事者間で話し合う(交渉)
- ステップ3:家庭裁判所に調停・訴訟を申し立てる
この流れに沿って、冷静かつ着実に手続きを進めていくことが、問題解決への近道となります。
ステップ1:配達証明付き内容証明郵便で意思表示する
遺留分侵害額請求を行う最初の具体的なアクションは、相手方に対して請求の意思を明確に表示することです。
この際、口頭や普通郵便ではなく、「配達証明付き内容証明郵便」を利用することが極めて重要です。
内容証明郵便は、「いつ、誰が、どのような内容の文書を、誰に送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスです。
配達証明を付けることで、相手がその郵便を受け取った日時も証明できます。
これにより、「請求された覚えはない」といった言い逃れを防ぎ、遺留分侵害額請求権を行使したという法的な証拠を確実に残すことができます。
これが、前述した「1年の時効」の進行を止めるための最も確実な方法となります。
ステップ2:当事者間で話し合う(交渉)
内容証明郵便を送付した後は、当事者間での話し合い(交渉)に移ります。
相手方が請求に応じれば、具体的な支払金額や支払方法について協議し、合意を目指します。
この段階で円満に解決できれば、時間や費用の負担を最小限に抑えることができます。
しかし、親族間の感情的な対立から、話し合いが難航することも少なくありません。
交渉を有利に進めるためには、遺留分の計算根拠を明確に示し、冷静に話し合う姿勢が重要です。
この段階で弁護士に代理人として交渉を依頼することも有効な手段です。
ステップ3:家庭裁判所に調停・訴訟を申し立てる
当事者間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所での法的な手続きに移行します。
まずは「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てるのが一般的です。
調停は、裁判官と調停委員が間に入り、当事者双方から事情を聞きながら、話し合いによる解決を目指す手続きです。
あくまで話し合いがベースなので、比較的柔軟な解決が期待できます。
もし調停でも合意できない(不成立となった)場合は、最終的に「訴訟」を提起することになります。
訴訟では、当事者が法的な主張と証拠を提出し、最終的には裁判官が判決を下すことで、紛争の解決が図られます。
遺留分トラブルを避ける・有利に進めるための知識
遺留分に関する問題は、単に請求する側の知識だけでは十分ではありません。
請求された側がどう対応すべきか、あるいは将来の相続でトラブルを未然に防ぐために遺言書を作成する側が何を注意すべきかなど、多角的な視点を持つことが重要です。
また、遺留分は「放棄」することも可能ですが、それには特定の法的手続きが必要となります。
これらの知識は、ご自身がどの立場になっても冷静に対応し、無用な争いを避け、またご自身の権利を適切に守るために役立ちます。
ここでは、遺留分をめぐる様々な立場からの注意点や、知っておくべき制度について解説します。
遺留分を請求された側の対応方法
もしあなたが遺留分侵害額請求をされた側になった場合、まずは冷静に対応することが大切です。
内容証明郵便が届いたら、無視せずに内容をしっかり確認しましょう。
その上で、請求されている金額が正当なものか、計算の根拠(財産の評価額や特別受益の有無など)を精査する必要があります。
もし請求額に納得できない点があれば、その根拠を示して相手方と交渉します。
安易に全額を支払うのではなく、必要であれば弁護士に相談し、法的に妥当な解決策を探ることが重要です。
遺言書を作成する際の遺留分への配慮
将来、ご自身が遺言書を作成する立場になった場合、相続人間のトラブルを防ぐために遺留分への配慮は不可欠です。
特定の相続人に多くの財産を遺したいという希望がある場合でも、他の相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は、紛争の火種となり得ます。
遺言書を作成する際には、各相続人の遺留分がいくらになるかを事前に計算し、それを侵害しない範囲で財産の配分を考えることが賢明です。
また、なぜそのような財産配分にしたのか、その理由や想いを「付言事項」として書き添えることも、相続人の納得感を得る上で有効です。
遺留分の放棄は相続開始「前」に家庭裁判所の許可が必要
遺留分は、権利者が自らの意思で「放棄」することも可能です。
しかし、この手続きには厳格なルールがあります。
重要なのは、遺留分の放棄は、相続が開始する「前」に、家庭裁判所の許可を得なければならないという点です。
これは、被相続人からの圧力などによって、不本意に権利を放棄させられることを防ぐためです。
相続が開始した「後」であれば、遺留分を請求しないという意思表示は自由にできますが、法的な「放棄」とは区別されます。
相続開始前の放棄手続きは、申立人が自らの真意で放棄を望んでいるかなどを裁判所が慎重に審査した上で、許可が下ります。
あわせて読みたい
遺留分問題で弁護士に相談すべきタイミングと費用
遺留分の問題は、法律的な知識だけでなく、親族間の感情的な対立も絡むため、当事者だけでの解決が難しいケースが少なくありません。
「いつ弁護士に相談すればいいのかわからない」「費用が心配で相談をためらってしまう」という方も多いでしょう。
しかし、適切なタイミングで専門家の助けを借りることは、問題をこじらせず、ご自身の正当な権利を守るために非常に重要です。
}特に、時効という時間的制約がある中で、一人で悩み続けることは得策ではありません。
ここでは、具体的にどのような状況になったら弁護士への相談を検討すべきか、そして気になる弁護士費用の目安や、無料相談を有効に活用するポイントについて解説します。
不安を解消し、次の一歩を踏み出すための参考にしてください。
弁護士への相談を検討すべき3つのケース
遺留分の問題で、特に以下のような状況に当てはまる場合は、早期に弁護士へ相談することを強くお勧めします。
- 相手方との話し合いが困難な場合:相手が感情的になって話し合いに応じない、あるいは高圧的な態度で請求を無視するなど、当事者間での交渉が進まないケース。
- 財産の全体像が不明、または評価が複雑な場合:遺産に不動産や非上場株式が含まれていて評価が難しい、被相続人が管理していた財産の内容がよくわからないなど、専門的な調査が必要なケース。
- 手続きや交渉に精神的な負担を感じる場合:親族と直接対立することへのストレスが大きい、時効が迫る中でどう動けばいいか分からず不安だ、というケース。
弁護士費用の目安と内訳
弁護士費用は、事案の複雑さや依頼する法律事務所によって異なりますが、一般的には以下の要素で構成されます。
- 相談料:法律相談をする際にかかる費用。30分5,000円~1万円程度が相場ですが、初回無料の事務所も多くあります。
- 着手金:弁護士に正式に依頼する際に支払う費用。結果にかかわらず返還されないのが一般的です。経済的利益の額に応じて算定されます。
- 報酬金:事件が解決した際に、成功の度合いに応じて支払う費用。遺留分として確保できた金額(経済的利益)の10%~20%程度が目安となります。
- 実費:収入印紙代、郵便切手代、交通費など、手続きを進める上で実際にかかった費用。
依頼する前に、必ず費用の内訳や総額の見積もりを明確にしてもらうことが重要です。
無料相談を有効活用するポイント
多くの法律事務所が実施している無料相談は、弁護士に依頼すべきか判断するための絶好の機会です。
この時間を有効に使うために、事前に準備をしておきましょう。
- 事実関係を時系列でまとめる:いつ誰が亡くなり、どのような遺言書があったか、誰が相続人かなどを整理しておく。
- 関係資料を持参する:遺言書のコピー、不動産の登記簿謄本、預金通帳の写しなど、手元にある資料は全て持っていく。
- 質問したいことをリストアップする:聞きたいことを事前にメモしておき、聞き漏らしがないようにする。
これらの準備をすることで、短時間でも的確なアドバイスを得やすくなります。
まとめ:遺留分は正当な権利。時効に注意し、まずは専門家に相談を
遺留分は、遺された家族の生活を守るために法律で認められた、あなたの正当な権利です。
遺言書の内容に納得がいかない、自分の取り分が不当に少ないと感じたとき、この制度は大きな味方となります。
しかし、その権利を現実のものにするためには、ご自身で行動を起こさなければなりません。
この記事で解説したように、遺留分の計算は生前贈与などが絡むと複雑になりがちです。
そして何より、「遺留分侵害を知ってから1年」という厳しい時効が存在します。
少しでも「おかしいな」と感じたら、まずは時効を意識し、迅速に動き出すことが何よりも重要です。
一人で抱え込まず、まずは専門家に相談してみてください。
多くの法律事務所では無料相談を実施しており、話を聞いてもらうだけでも、今後の道筋が見えてくるはずです。
大切なのは、諦めずに、ご自身の権利を守るための一歩を踏み出すことです。
終活協議会では、相続に関するお悩みも承っております。
提携している弁護士や行政書士などの専門家は全国に1,400名以上!
遺留分の対応だけでなく、遺言書や公正証書の作成まで、相続に関するお悩みを一つの窓口で対応可能です。
お気軽にご相談ください。
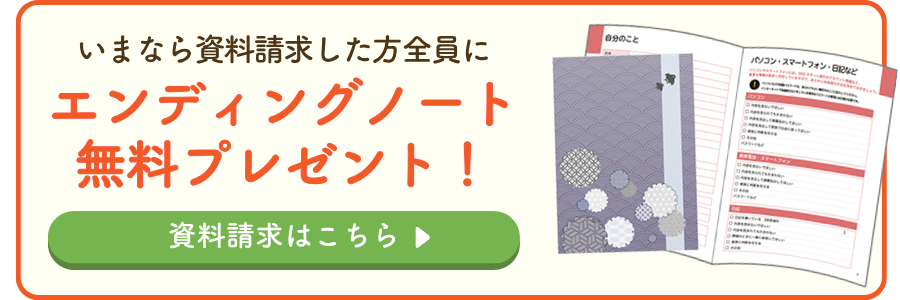
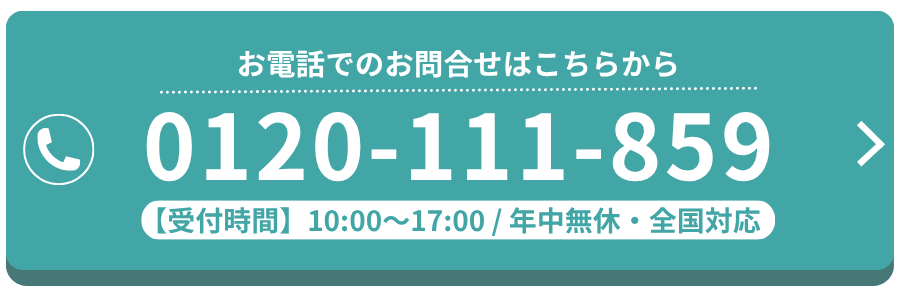
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする