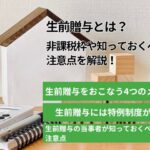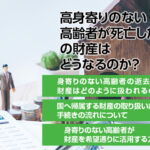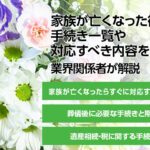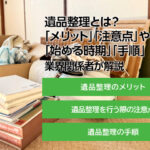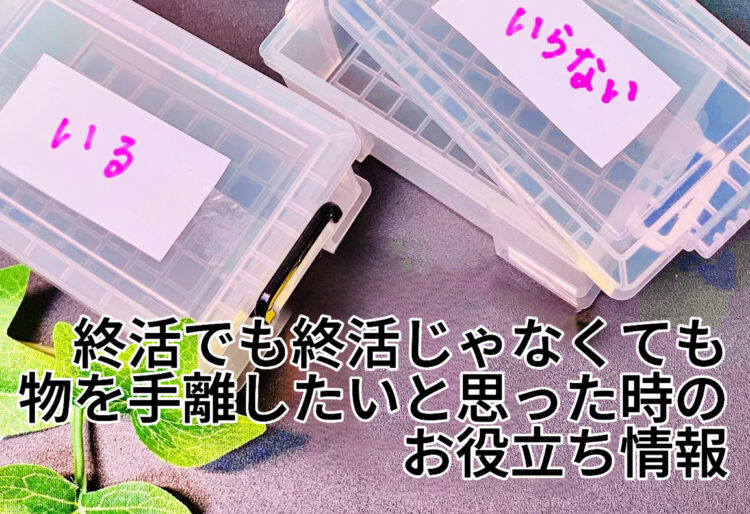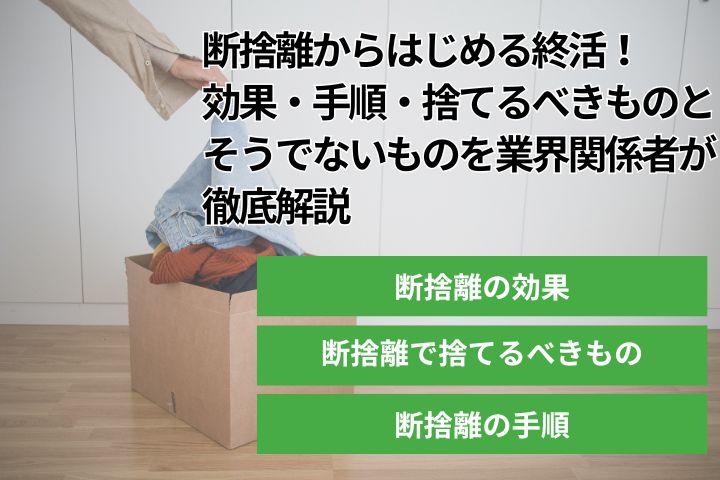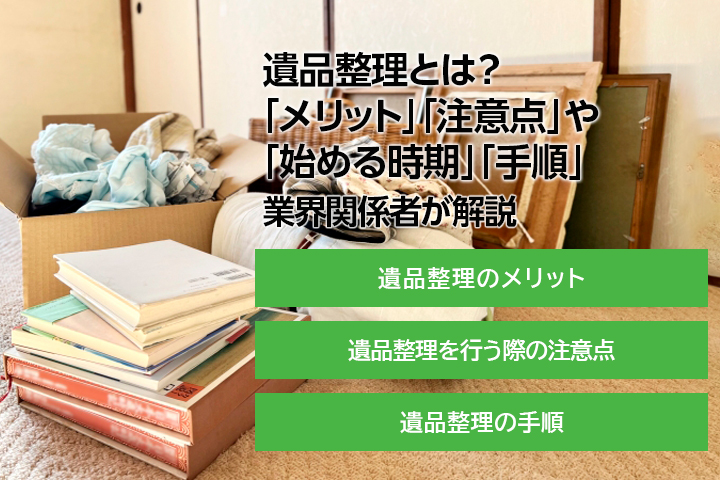
大切な人とのお別れのあと、残されたご遺族は、形見となった数々の品物と向き合うことになります。大切な人を亡くした悲しみの中、そうした遺品を整理し、必要なものと不要なものを仕分けすることは、体力的にも精神的にも大きな負担となります。
そこで、遺品整理は単なる片付けではなく、故人との思い出を整理し、ご遺族が新しい一歩を踏み出すための大切なプロセスでもある、と考えてみましょう。本記事では、遺品整理の具体的な手順から、自分で行う場合と業者に依頼する場合のメリット・デメリット、そして注意すべきポイントまで、詳しく解説していきます。
目次
遺品整理とは?

遺品整理とは、故人が遺した以下のような物品を整理して処分する作業です。
- 家具や衣類などの「家財道具」
- 通帳や有価証券などの「貴重品」
- 写真や手紙などの「思い出の品」など
不要なものは処分し、大切なものや必要なものは残して保管します。遺品のなかには相続に関わる書類や、故人の意向が記されたエンディングノートなどの大切な書類が含まれているケースも多いため、注意する必要があります。
遺品整理の目的
遺品整理の主な目的は、故人との思い出を大切に保存しながら、ご遺族が新しい生活を始めるための環境を整えることです。相続手続きに必要な書類や重要書類の確認、財産の把握といった実務的な側面も重要です。また、遺品を整理する過程で故人との思い出に向き合い、心を整理することで、ご遺族が前に進むためのきっかけにもなります。
遺品整理は誰が行う?
遺品整理を誰が行うかによって、大きく3つのパターンに分けることができます。
- ご遺族が遺品整理を行う
- 買取業者に遺品整理に依頼をする
- 専門の遺品整理業者に遺品整理を依頼する
状況や予算に応じて最適な方法を選択しましょう。また、「タンスだけは買取業者に依頼する」「写真やアルバムは自分で整理する」など、整理する物品によって、組み合わせて対応するのもひとつの方法です。
遺品整理を行うタイミング
遺品整理を行うタイミングについて明確なルールはありません。一般的に遺品整理がおこなわれるタイミングを下の表にまとめました。
| 葬儀直後 | 親族が集まっているため、協力して整理を進めやすいが、精神的に辛い時期でもあるため注意が必要 |
| 諸手続き後 | 死亡届の提出や年金・健康保険などの手続きが完了したあと、通常は亡くなってから1週間後から1ヵ月程度の期間。この時期は、精神的にも落ち着いており、自分たちのペースで手続きを進めやすい |
| 四十九日法要後 | 親族が集まりやすく、遺品整理や形見分けについて話し合う良い機会。このタイミングで整理を始めることが一般的 |
| 相続税の申告前 | 相続税の申告は、故人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行う。相続財産を特定するためにも、遺品整理はこの期限内に行う |
これらのタイミングはあくまで一般的な目安です。ご家族の感情に配慮しつつも、法的な制約や期限を意識して計画的に進めることが大切です。
遺品整理の手順

遺品整理の手順には以下の5つのステップがあります。
ステップ1: 段取りを決める
ステップ2: 残すもの・捨てるものに仕分けする
ステップ3: 必要なものを整理する
ステップ4: 形見分けをする
ステップ5:不用品を処分する
ひとつずつ見ていきましょう。
ステップ1: 段取りを決める
遺品整理を効率的に進めるためには、事前の段取りが重要です。まず、遺品整理をいつまでに行うか、期限を設定します。次に、整理後の品物の配置場所を計画し、必要な備品(段ボール、ゴミ袋など)を準備しましょう。さらに、処分に必要な業者を選定し、見積もりを取得することで、全体の見通しを立てられます。
ステップ2: 残すもの・捨てるものに仕分けする
仕分けは遺品整理の核となるステップです。最初に通帳や権利書などの重要書類の確認から始め、衣類や日用品など判断しやすいものへと進みます。故人が遺言書やエンディングノートを残している場合は、重要なものと同様に、早い段階から探しておきましょう。全ての遺品を「残すもの」「処分するもの」「判断保留のもの」の3つに分類します。迷うものは一時保留にして、全体の整理が進んでから再度検討すれば、効率的な仕分けが可能になります。なお、このステップではまだ処分をしません。
ステップ3: 必要なものを整理する
残しておくものは「重要書類」「引き継いで使うもの」「財産に関するものや思い出の品」の3つに分類しましょう。
「重要書類」は、相続などの死後の手続きが必要になるものが多いため、優先的に回収して手続きを進めます。例えば以下のようなものです。
- 戸籍関連書類
- 金融機関の通帳や証書
- クレジットカード
- 保険証書
- 不動産の権利証や売買契約書
- 税金関連の書類
- 身分証明書
- 印鑑
- 年金手帳
- 遺言書
- エンディングノート
「引き継いで使うもの」は、段取りで決めた場所に運び、邪魔にならないように使いやすい場所へ配置します。
「財産に関するものや思い出の品」は、後日、遺産相続や形見分けをするときにすぐ取り出せるように整理して、リスト化しておきましょう。必要なものをスムーズにチェックできます。
ステップ4: 形見分けをする
故人が残した財産は、遺言書による指定などがない場合は相続人が話し合って分割し、相続します。財産以外の衣類やアクセサリー、思い出の品などは、ご遺族で話し合って形見分けをします。丁寧に遺品整理をしておけば、形見分けをスムーズに進められるでしょう。
ステップ5:不用品を処分する
不用品の処分は、品物の状態や種類に応じて最適な方法を選択します。使用可能な家具や電化製品は買取業者への売却を検討し、大型の不用品は粗大ごみとして適切に処分します。一般ごみについては地域のルールにしたがって分別し、計画的に処分を進めます。
遺品整理を自分で行うメリット・デメリット
ここでは、遺品整理を自分で行う際のメリットとデメリットについて解説します。
メリット
遺品整理を自分で行うことで、「気持ちの整理ができる」「思い出をきちんと残せる」「相続の準備になる」といったメリットがあります。
気持ちの整理ができる
遺品一つひとつに触れることで、故人との思い出を振り返り、自然な形で心の整理をする機会となるでしょう。感情を整理しながら進めることで、次のステップへ進むきっかけを作れます。
思い出をきちんと残せる
自分で整理することで、一見すると何気ない品物のなかから、大切な思い出の品を見つけられることもあります。業者に依頼すると、流れ作業になりがちで見落としてしまうかもしれません。自分で遺品整理をすることで、故人との思い出が詰まった品々を丁寧に選び取れます。
相続の準備になる
遺品を整理する過程で、相続に必要な書類や重要書類を確認し、整理できます。また、故人の財産状況を把握することで、相続手続きをスムーズに進められ、将来的なトラブルの防止にもつながります。
デメリット
自分で遺品整理を行う場合、メリットだけでなく「精神的な負担がある」「体力的負担な負担がある」「時間がかかる」といったデメリットもあります。
精神的な負担がある
故人の遺品に触れると色んなことを思い返すかもしれません。思い出の品々に向き合うことで悲しみが深まったり、喪失感が強まったりすることがあります。特に故人との関係が深かった場合、精神的な負担を感じると思います
体力的な負担がある
遺品の量は想像以上に多くなることが一般的です。特に長年住んでいた家の場合、家具や生活用品の移動だけでも大きな労力が必要です。ご遺族がご高齢の場合、この体力的な負担はより深刻な問題となり、事故やケガのリスクも高まります。
時間がかかる
遺品整理には自分が思っている以上に時間がかかります。仕事や家庭との両立が必要な場合、遺品整理が長期化したり中断したりすることもあるでしょう。賃貸物件の解約のように、期限までに手続きや遺品整理を完了させなければならないケースもあり、時間的な制約が大きな課題となることがあります。
遺品整理を買取業者に依頼するメリット・デメリット
買取業者は不用品の回収・処分に特化したサービスを提供します。遺品整理の効率性と費用面での利点がある一方で、サービスの範囲が「買取」と限定的なため、遺品整理の全般的な対応は難しい場合があります。
メリット
買取業者は不用品の回収に特化していることから、料金が比較的安価に設定されています。また、専門のスタッフが重たい家具や家電を短時間で搬出します。急を要する場合や、予算に制約がある場合に適しています。買取サービスにより、処分費用の軽減につながる可能性もあります。
デメリット
買取業者を利用する際は、サービス範囲が不用品の回収・処分に限定されていることに注意が必要です。遺品の仕分けや供養、貴重品の探索、各種手続きの代行など、遺品整理に必要なその他のサポートは期待できません。また、物品を処分品として扱う傾向があるため、遺品整理の専門業者と比べると、故人の遺品に対する丁寧な扱いや感情面への配慮が不足する可能性があります。遺品整理の全体的なプロセスを考えるのであれば、追加のサービスや支援が必要になることを考慮したほうがよいでしょう。
遺品整理を遺品整理業者に依頼するメリット・デメリット
遺品整理業者は、遺品の仕分けから処分、供養まで、包括的なサービスを提供する専門家です。遺品整理に特化している反面、費用面での検討が必要になります。状況に応じて判断しましょう。
メリット
遺品整理を遺品整理業者へ依頼すると、経験豊富なスタッフに遺品の仕分けから処分まで一括して対応してもらえます。仏壇や仏具などの供養といった難しい手続きにも対応可能です。また、相続に関する相談や法的手続きのアドバイスも受けられます。さらに、重量物の安全な搬出や迅速な対応により、時間と労力を節約できます。
デメリット
遺品整理業者への依頼には、いくつかのデメリットもあります。最も大きなデメリットは費用です。自分で整理したり、買い取り業者に依頼したりするよりも高額になり、物量によってはさらに費用が増加する可能性も考慮する必要があるでしょう。また、効率重視の対応となり、故人との思い出をじっくり振り返る時間が限られることがあります。さらに、業者の選定を誤ると、追加料金の請求や相続に関する予期せぬ影響などのリスクが生じる可能性もあります。
遺品整理を行う際の注意点

遺品整理は、故人への敬意を持ちながら、遺族間の調整や法的な手続きにも配慮が必要です。円滑な進行のために、以下の6つの重要なポイントに注意を払う必要があります。
事前に親族間で話し合う
遺品整理を始める前の親族間での話し合いは、後々のトラブル防止につながります。具体的には、遺品整理の進め方、役割分担、費用負担の方法、形見分けの基準などを明確にします。特に相続に関わる判断はできるだけ早い段階で合意形成することが大切です。
遺言書やエンディングノートを確認する
遺品整理する際には、遺言書やエンディングノートなど、故人の意思が記されているものがあるか確認します。遺言書があれば遺産相続は遺言書の記載内容に沿って行うのが原則となり、なければ相続人全員で話し合いをします。
エンディングノートに法的な拘束力はありませんが、故人の意思が残されており、その意思を尊重すべきと考えられます。生前に遺言書やエンディングノートを用意していると聞いていた場合は、優先的に探すことが重要です。
遺品整理で捨ててはいけないものがある
遺品のなかには、決して処分してはいけない重要書類も含まれています。先述の戸籍関連書類、金融機関の通帳や証書、保険証書、不動産の権利書、税金関連の書類などです。これらは相続手続きを含め、今後の手続きに必要となるため、慎重に保管する必要があります。また、故人の重要な個人情報が含まれる書類も、不正使用防止のため適切に管理しましょう。
デジタル遺品の整理も忘れない
現代では、デジタル遺品の整理も重要な課題となっています。スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器、SNSアカウント、オンラインバンキング、各種サブスクリプションサービスなど、本人しか知らない情報が多く存在します。放置すると必要なデータにアクセスできなくなったり、不要な料金が発生し続けたりする可能性があるため、専門家に相談しながら適切に対応することが重要です。
いつまでに終わらせるのかを決める
故人の住まいが賃貸物件や高齢者施設だった場合、期日までに明け渡しができるよう、スケジュールを決めて遺品整理をしていくことになります。一方、所有物件の場合は、いつまでにやらなければならないという締め切りがなく、先延ばしにしてしまい、遺品整理が進まないケースも。時間があるときに少しずつ遺品整理しようと思っても、なかなか遺品整理が進まないこともあるでしょう。そのため、無理をしない形で「いつまでに何を終わらせるか」を決めてから取り組むことで、円滑に進めることができます。
全て自分でやろうとしない
遺品整理は多大な労力と時間がかかります。不用品の整理や廃棄のための運び出しなど、全て自分でやろうとすると大きな負担になります。自分でやること、ご家族と協力してやること、業者に依頼することを事前に決めて、全て自分でやろうとしないことが大切です。
なお、一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループでは、家財道具や生活用品の処分や引き取りといった遺品整理サービスを提供しています。無料で資料請求が可能なため、参考にしてください。
>>一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループの資料請求はこちらから
一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループは信頼できる遺品整理サービスを提供

遺品整理は、故人の思い出と向き合いながら、新しい生活への一歩を踏み出すための重要な過程です。遺品整理を進めるにあたっては、遺族間での事前の話し合い、遺言書やエンディングノートの確認、重要書類の適切な保管、デジタル遺品への対応など、さまざまな面に注意を払う必要があります。状況に応じて、ご遺族が遺品整理をするか、買取業者や遺品整理業者に依頼するかを検討し、計画的に進めることが大切です。
一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループは、遺品整理を代行するサービスを提供しています。家財道具や生活用品の処分や引き取りにも対応しています。まずは無料の資料請求で、具体的なサービス内容やお見積りについてご確認ください。ご遺族の状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。
>>一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループの資料請求はこちらから
監修

- 所属:東京司法書士会 一般社団法人 終活協議会理事
-
1997年 東洋大学法学部卒業
大学在学中から司法書士試験の勉強をしつつ、1999年株式会社サイゼリヤに入社
7年間勤務した後、再度司法書士を目指すため2006年退社
2007年 司法書士試験合格
2008年 司法書士登録
試験合格後は、都内の司法書士事務所や法律事務所にて勤務
2021年 「落合司法書士事務所」開設
2021年 一般社団法人終活協議会理事就任
最新の投稿
 2024年6月19日生前贈与とは?非課税枠や知っておくべき注意点を解説!
2024年6月19日生前贈与とは?非課税枠や知っておくべき注意点を解説! エンディングノート2023年12月3日身寄りのない高齢者が死亡した後の財産はどうなるのか?
エンディングノート2023年12月3日身寄りのない高齢者が死亡した後の財産はどうなるのか? おひとりさま2023年9月11日家族が亡くなった後の手続き一覧や対応すべき内容を業界関係者が解説
おひとりさま2023年9月11日家族が亡くなった後の手続き一覧や対応すべき内容を業界関係者が解説 おひとりさま2023年7月10日遺品整理の進め方ガイド|注意点とメリット・デメリットを詳しく解説
おひとりさま2023年7月10日遺品整理の進め方ガイド|注意点とメリット・デメリットを詳しく解説
この記事をシェアする