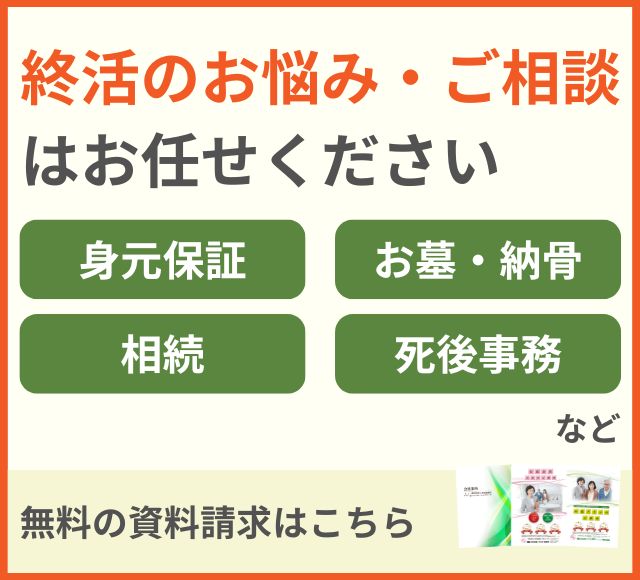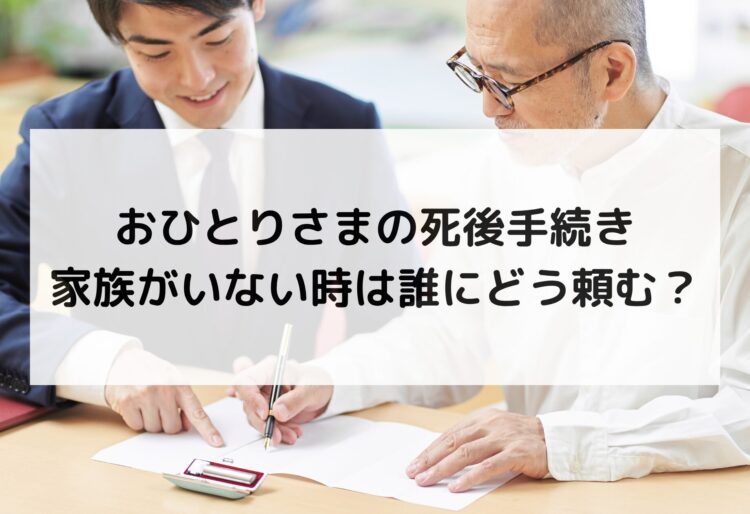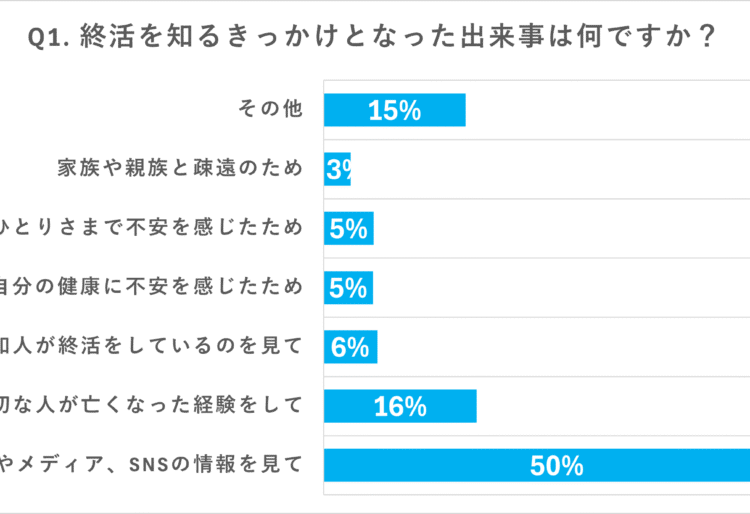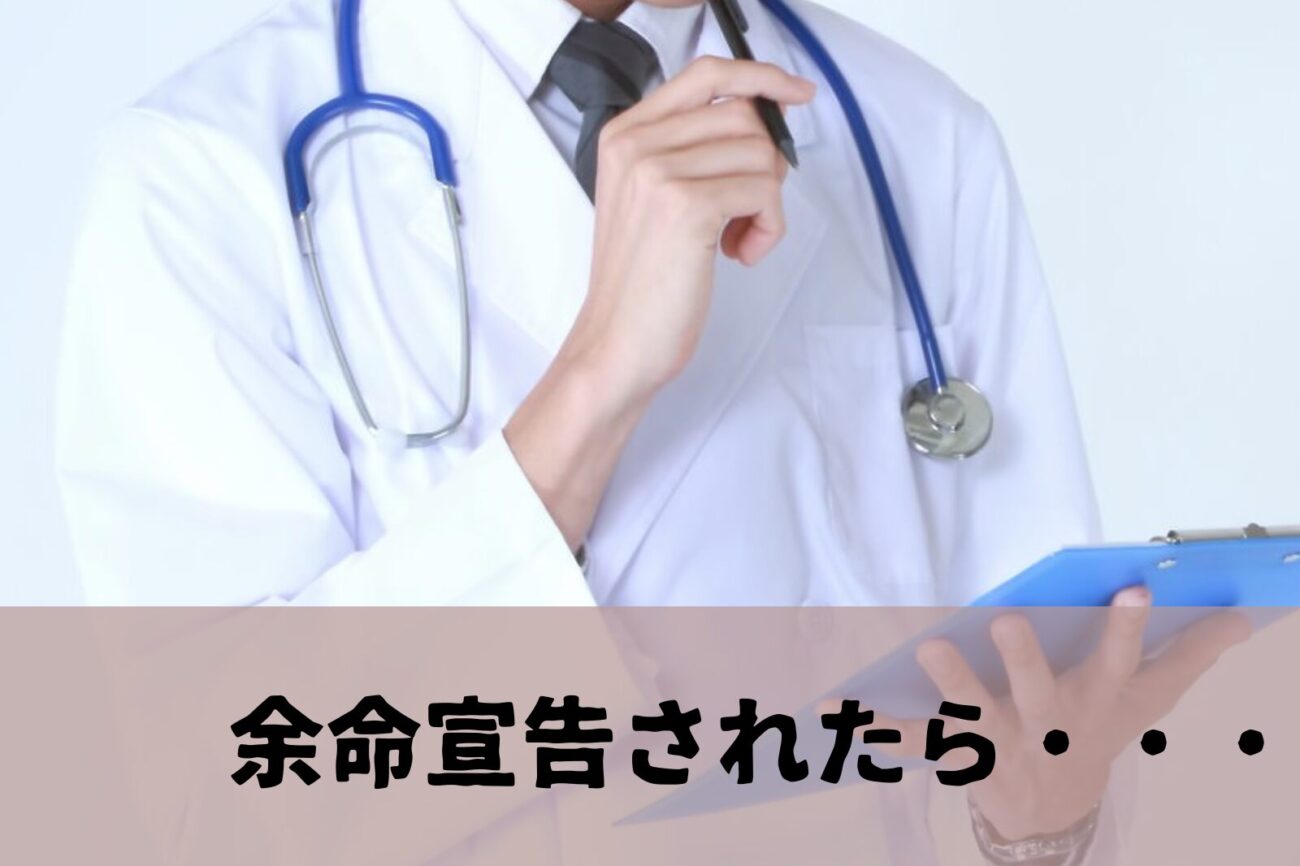
はじめに「余命」というものは、あくまでも予測でしかなく、絶対的なものではありません。しかしながら、余命宣告を受けるとご本人もご家族も大きなショックを受けてしまいます。「これから、一体どうしたらいいんだろう…」などと途方に暮れてしまうかもしれません。
まずは、ご家族の皆様で話し合う時間を取り、「何かできることはないか」「残された時間を大切に過ごしたい」など、ご本人の気持ち、そしてご家族それぞれの気持ちを共有しつつ、焦らず、ご本人のペースに合わせて、これからについて考えていくことが大切です。
私たちも皆様に寄り添い、少しでもお力になれるようなコラムをご提供できればと思います。
目次
そもそも「余命宣告」とは
余命宣告とは、その名の通り、医者が患者に対し、あとどのくらい生きることができるかを伝えることです。人は誰しも高齢になると病気になる可能性が高くなり、病状の進行具合によっては余命宣告を受けることもあるでしょう。
本来は余命宣告は隠すものという認識でしたが、現在は患者の知る権利や情報開示の考え方が広がり、余命宣告を受けることは身近になりつつもあります。
また、余命宣告は治療の効果が少なくなり、治療の方法が他にない状況で行うことが多いようです。患者や家族にとっては、人生の終末を告げる非常に大切な宣告のため、医師は慎重に余命を決定します。
ただし、余命は寿命のことではありません。その人が実際にいつまで生きられるのかは、誰にもわかりません。まずは余命と寿命の違いについてご説明します。
余命と寿命の違い
余命は、医療データや患者の状態から、どのくらい生きることができるのか予測したものです。医師の判断にゆだねられ、医師によっても余命が変わるため、おおむねの期間といえるでしょう。
一方、寿命とは、一般的に平均寿命のことを指し「0歳から数えた平均余命」をいいます。寿命には平均寿命と健康寿命があり、厚生労働省の情報によると、令和元年の我が国の平均寿命は、男性が81.41歳、女性は87.45歳と報告があります。
また、健康寿命とは、健康な状態で生活できる期間をいい、男性は72.68歳、女性は75.38歳と報告されています。
余命宣告されたからといってその期間は絶対ではない
医師が余命を予測する際にはさまざまなデータを参考にしますが、有名な指標として「生存期間中央値」があります。これは、同じ病気の患者群のうち50%が亡くなるまでの期間を示すものです。なお、がんの場合には、5年生存率といった指標も用いられます。
繰り返しとなりますが、余命はあくまで医師の「見立て」に過ぎず、宣告された余命より短く亡くなる方もいれば、長く生きる方もいます。一般的に、余命が長いほど寿命との誤差が大きく、短いほど誤差が小さいといわれています。
それゆえ、余命宣告をされたからといって、余命通りに亡くなるとは限りません。日進月歩で新しい薬や治療法が誕生しており、余命が延びる可能性はあります。余命宣告を受けても寿命が決定するわけではないと捉えて、その後の治療や生活をどのように送るかを考えることが大切です。
余命宣告されたら、まず治療の方針を決める
余命宣告されたら、今後の治療の方針を決める必要があります。一般的には、医師から次の3つの選択肢が提示されます。
- 完治を目指して治療を続ける
- 延命治療を行う
- 緩和ケアに移行する
必ず本人の意向を尊重し、本人が望むものを選んでください。
完治を目指して治療を続ける
積極的な治療を行い、病気の完治を目指す、という選択です。がんの場合は標準治療である手術、放射線治療、化学療法(抗がん剤治療)、免疫療法が主な治療法となります。完治する可能性がある一方で金銭的な負担が大きいことが特徴です。治療に耐えられる体力があるか、副作用のリスクはどうするかなども考慮し、医師と相談しつつ治療の方向性を決めていきましょう。
延命治療を行う
延命治療とは、病気を治すことを目的とするのではなく、余命を少しでも延ばすための医療行為のことです。主な延命治療の方法には、人工呼吸や人工栄養、人工透析などがあります。延命治療は「お世話になった人に挨拶したい」「娘の結婚式が近く、それまでは一緒にいたい」「これから生まれる孫に会いたい」など、本人が家族や友人、知人と少しでも長くいたい場合に検討されます。
緩和ケアに移行する
緩和ケアとは、痛みや苦しみを軽減していつも通りの生活を取り戻すことを目的としたケアのことです。病状が進んでも、普段通りに生活したい場合や治療に専念したい場合に選択されることが多い方法です。具体的には、薬によって痛みを軽減したり、呼吸をサポートしたり、カウンセリングで精神的なサポートをしたりします。
ポイント:セカンドオピニオンを受けてみる
医師によって治療の方針の決め方は異なります。セカンドオピニオンとは、担当医以外の医師に、病気や治療のことについて意見(オピニオン)を求めることです。担当医を変える、転院するということではなく、あくまでも他の医師の見解を知り、選択の幅を広げることを目的としています。セカンドオピニオンを受けることで、他の医師に新たな治療方法を提案してもらえる可能性があります。
余命宣告されたら、他にどんな準備が必要なのか
余命宣告されたら、治療の方針を決めるのはもちろん、さまざまな準備が必要となります。病状が急変する可能性もあるため、なるべく早い段階から準備を始めましょう。なるべく本人とご家族が協力して準備を進めるようにしてください。
生命保険を確認する
「リビング・ニーズ特約」が付加されている生命保険契約の場合、余命6か月と診断された場合に保険金の一部もしくは全部を生前給付金として受け取ることができます。生前給付金の使い道は指定されていないので、治療のためだけではなく、ご本人がやりたいことを実現するために使用しましょう。
リビング・ニーズの生前給付金は、原則本人が請求しますが、寝たきりなど本人が手続きできない事情に限り、家族などが手続きできます。
なお、生命保険によっては加入時にリビング・ニーズ特約が付帯されていない場合もあるので、加入している保険の契約内容を確認してみてください。
エンディングノートを準備する
エンディングノートは、もしもに備えて医療や介護、財産などに関する色んな手続きに必要な情報をまとめておくためのノートのことです。余命宣告されたら、エンディングノートを本人が可能な範囲で書くことからおすすめします。
残される家族のために、本人の「お金に関連する情報」や、「葬儀に関して本人が希望していること」、「家族に対する想い」など、家族へ伝えたいことをノートにまとめておくことで、本人の意思を文字で残すことができます。
また、エンディングノートは自由な形式で普通の大学ノートに書くことができるため、手軽にできる終活の作業になります。
⇒おすすめしたいエンディングノートの書き方を業界関係者が解説
葬儀に備える
本人が亡くなると、すぐに葬儀の準備をしなければいけません。葬儀の準備は想像以上に大変なため、元気なうちに葬儀社を選定しましょう。葬儀社の選定や葬儀内容は本人に希望を聞き、最適な葬儀社を探すのが理想です。ただ、余命宣告を受けている本人へ葬儀の話をすることは難しいと思いますので、地元で評判が高い葬儀社を家族で調べて探すのがおすすめです。
財産を整理して把握しておく
亡くなった後には預貯金、有価証券、不動産などの「財産」を家族へと引き継ぐ相続の手続きが必要です。その準備として、どこにどのような財産があるのか、内訳や所在を把握しておく必要があります。
特にお金に関連する情報は重要度が高いため、本人に財産の整理をお願いして、ネットバンクがあればログイン情報、通帳や不動産の権利書などの必要書類の保管場所といった情報をエンディングノートなどに記録しておきましょう。
また、借金やローンなどの負債も相続の対象です。少額であれば相続した財産から清算することも考えられますが、負債が多い場合は相続放棄を検討しなければなりません。事前に確認しておきましょう。
遺言書を作成する
エンディングノートに財産のことを記載しておくことはできますが、財産を誰にどう分けるか、配分については決めるには遺言書が必要となります。
遺言書には本人の自筆による自筆証書遺言、公証人の作成する公正証書遺言、本人が執筆し公証役場で手続きをする秘密証書遺言の3つがあります。
遺言書は遺族に渡すこともありますが、基本的には自宅で保管していることが多いです。また、エンディングノートに遺言書の保管場所を記載しておくことで、将来遺族が遺言者の意思を必要とした場合、簡単に探すことができます。
⇒意外と知られていない遺言書の「知っておきたい事」「注意点」について業界関係者が紹介
家族が余命宣告されたら?本人にどう伝えるのか?心構えは
余命宣告の告知の形式は医師や病院によって異なり、本人だけが告知を受ける場合、家族だけが受ける場合、家族と本人が同時に受ける場合があり、医療機関によっては入院や検査などの際に、余命宣告を受ける相手を確認するケースもあります。一番困難なのは家族だけが告知された場合で、家族が本人に伝えるかどうかの選択を迫られます。
家族が余命宣告された場合、大切な家族のことなので悲しみや驚きはもちろんのこと、「どうやって本人に伝えればいいか」で非常に悩むと思います。まずは「余命はあくまでも予測であること」をふまえたうえで「医学の進歩で余命が伸びる可能性があること」「本人の希望を最優先にすること」という心構えで、次のような点に注意して余命宣告の件を本人に伝えましょう。
本人に伝える場合の注意点
余命宣告されたことを家族から本人に伝える場合、医師から伝えられた内容を正確に伝えることが大切です。病状について本人の認識が異なってしまうと、治療や生活に悪い影響を与えてしまう恐れがあります。
内容を正確に伝える必要がありますが、本人を傷つけないような言葉を選ぶ必要があります。本人が余命宣告を受けたことを知るとご想像の通り大きなショックを受け、不安になったり、鬱っぽくなったりします。聞き役に徹し、本人に寄り添うように共感の言葉をかけてあげ、余命について理解してもらうことに努めましょう。
本人が落ち着いてきたら「行きたいところはないか」「やりたいことがないか」など聞いてみるとよいでしょう。担当医と相談し、本人が後悔のないよう、希望は可能な限り、叶えてあげたいですね。落ち着いてきたら、後述の治療の方針について決めていきましょう。
ご家族の心のケアも大切です。大きな病院には相談員として「医療ソーシャルワーカー」が在籍しており、「家族が余命宣告を受けて辛い」などの治療に関する悩みを、患者本人や患者のご家族でも相談することができます。ぜひ利用してみてください。
本人に伝えない場合の注意点
余命宣告されたことを本人に伝えることは義務ではありません。本人の心境に配慮して伝えない場合もあります。余命宣告を本人に伝えない場合、余命が明らかになったことを本人に気づかれないよう、家族全員による配慮が必要です。
突然の余命宣告は、本人には気づかれにくいものですが、治療が長期にわたり病状が優れない状況では、本人が病状に対して敏感になることが考えられます。
最近会っていない親族が見舞いに来た、病室のすぐ外の廊下で家族同士、また医師と小声で話しをしている所を見られてしまうと、本人はとても不安になる可能性があります。
また、病院の食堂や待合室で、神妙な顔をして家族の話合いをしていたところ、本人とばったり出くわす可能性もあります。本人が病院内で移動できる状況であれば、病院内で深刻な話しをすることは注意が必要です。
余命宣告されたら…当会の『心託』では準備をお手伝いいたします
当会では医療や健康に関するご不安、葬儀・相続に関する悩みなど将来の暮らしに関するご不安を窓口一本で相談できる『心託』サービスを提供しています。本当にお客様のためになるサービスを提供させていただいており、入会金1万円のみで、継続費用はいただきません。
全国47都道府県に拠点があり、ご相談をお受けしてからは、各地で適正価格でサービスを提供する、評判の高い専門家におつなぎし、解決までサポートさせていただきます。また入院時・施設入居時の身元保証や亡くなった後のお手続きに不安がある方には心託の『完璧』プランをご提案しております。
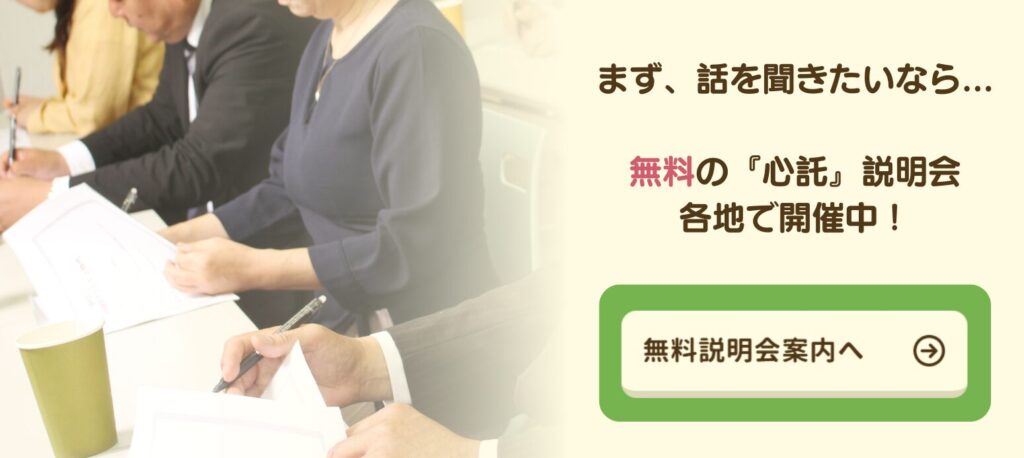
シニアの原宿・巣鴨でサービスを始めてから20年以上、全国で20,000人以上のお客様のご相談をお受けして解決までサポートした実績があり、多くのお客様からご好評の声をいただいております。お悩み事や分からない事がございましたら、フリーダイヤル0120-111-856までお気軽にお問い合わせください。『心託』サービスについて資料請求をご希望の方は、下記よりご請求ください。
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする