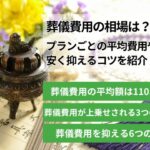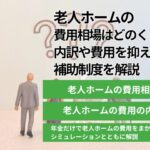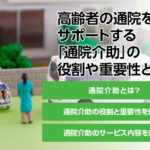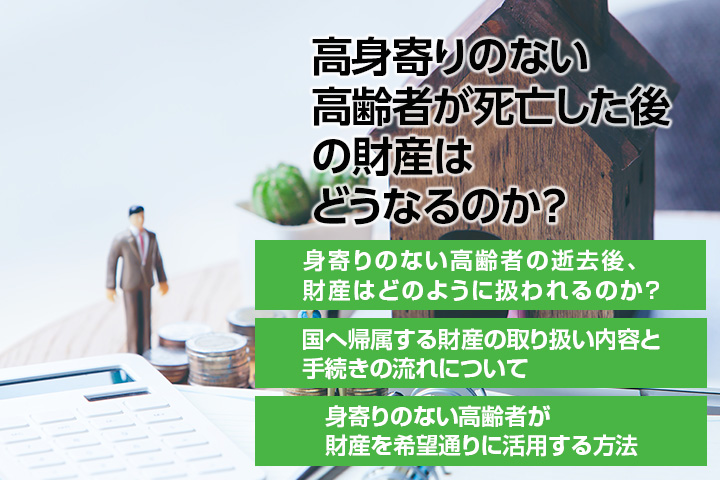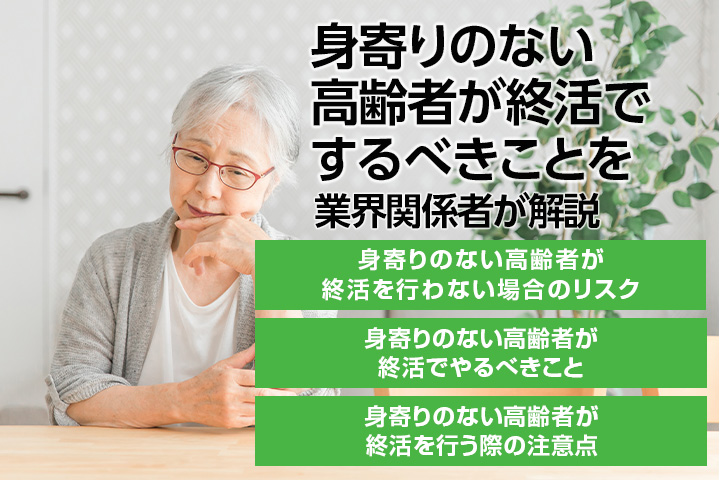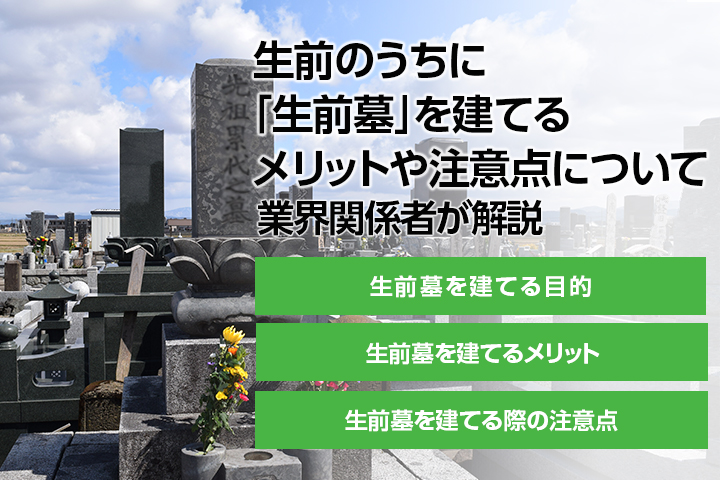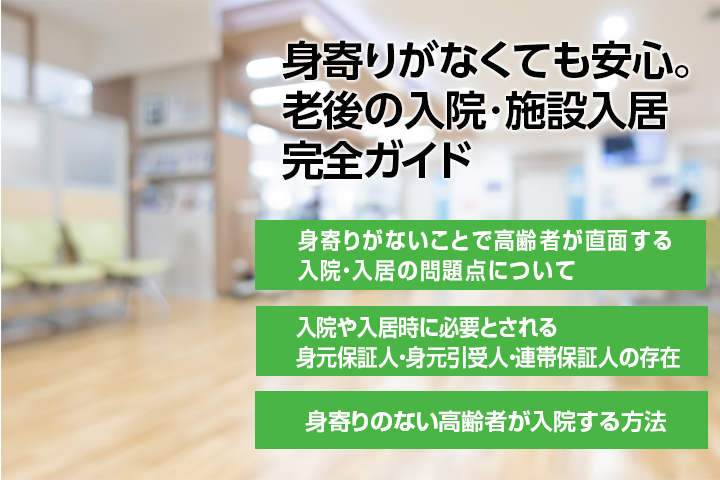
年齢を重ねるにつれて心身の衰えを感じ、誰かの支えが必要になることを考える機会が増えてきます。しかし、身寄りがない高齢者のなかには、今後一人での生活が難しくなった時に病院への入院や高齢者施設への入居ができるのか、入院や入居のためにどのような段取りを踏めば良いのか不安に思う方は少なくありません。
そこで今回は、身寄りがない方でも安心して老後を迎えるための入院や高齢者施設への入居方法などについて解説します。
目次
身寄りがないことで高齢者が直面する入院・入居の問題点について
内閣府の発表した「令和4年版 高齢社会白書」によれば、65歳以上の一人暮らしの割合は男性 が15.0%、女性が22.1%となっています。65 歳以上の男性は7人に1人、女性は5人に1人が一人暮らしをしており、年々増加傾向にあるのが現状です。
一人暮らしであったとしても、自宅近くに家族や親族などの頼れる人が住んでいれば良いのですが、身寄りがない高齢者にとっては、自分ひとりでの生活では困難が多く、体調を崩してしまった時や一人での生活に困難を感じた時に入院や高齢者施設への入居を考えます。しかし、身寄りがないことで下記のような問題が起こることが予想されます。
| 場面 | 内容 |
| 入院・入居時 | 入院や入居に伴う各種手続きや契約、初期費用の支払い |
| 病院・施設での生活 | 病状の把握、治療方針の決定、医療費の支払い、院内・施設内の生活で必要となる集団生活での細かい決まりごとや人間関係 |
| 退院・退去時 | 退院・退去に伴う各種手続き、費用の精算 |
入院や入居時に必要とされる身元保証人・身元引受人・連帯保証人の存在
病院や高齢者施設の多くは患者・利用者が入院や入居する際のリスクに備えるため、身元保証人や身元引受人の存在が必要とされます。
● 入退院に関する手続き
● 入院費などの医療費の担保
● 医療行為の告知と同意
● 緊急時や死亡した場合の連絡
● 亡くなった後の身元の引き取り、未払い債務の精算
本来なら、入院や入居で必要となる手続き・費用支払などは高齢者本人が担います。しかし、認知症に罹患して判断能力が不十分な状態であったり、経済的に困窮して費用が支払えない状態の場合には、代わりに入院や入居についての様々なことに対応する存在が必要になります。
下記に入院や入居で必要とされる、身元保証人、身元引受人、連帯保証人の違いと、それぞれに求められる役割を解説します。
身元保証人の役割
身元保証人は法律によって規定・定義づけされている訳ではありませんが、一般的には次のような役割を持つと考えられています。
●患者や入居者の身元を保証する
●高齢者が入院費用、それに関連する諸費用を支払えない場合、身元保証人が責任をもって支払う
● 緊急時の連絡を受ける
●高齢者の判断能力が不十分な場合、本人に代わって治療方針や介護の方針に関する判断を行う
このように身元保証人は、本来なら高齢者本人が持つべき責任・役割を共同して担う存在であるといえます。
身元引受人の役割
身元引受人についても法律によって規定がある訳ではありませんが、一般的には次のような役割を持つと考えられています。
● 患者や入居者が亡くなった後の身元の引き取り
● 患者や入居者が亡くなった後の諸手続き
病院、高齢者施設によっては身元引受人に対して、先に紹介した身元保証人と同じような責任・役割を求める場合があります。
連帯保証人の役割
連帯保証人とは、主にお金の貸し借りの場面で使われる用語です。債務者が金銭を返済しない・できない場合、債務者に代わって借金を返済する責任を負います。病院や高齢者施設によっては、身元保証人・引受人ではなく、「連帯保証人」という用語を使い、患者・入居者が医療費や入居に関する費用の支払いができなくなった際に、連帯保証人に対して請求を行う場合があります。
身寄りのない高齢者が入院する方法
身寄りがない高齢者でも、入院できる方法はあります。下記の通り、幾つかの具体例を紹介します。
1:医療ソーシャルワーカーに相談
医療ソーシャルワーカーとは、病院に勤務する社会福祉士のことです。病気や障害などで困っている患者・家族の相談に応じ、適切な医療や福祉サービスが利用できるよう連絡・調整をしてくれる専門職です。身寄りがいないけど入院したい、入院費用の支払いに不安があるなどの悩みを抱えていて「医療機関との距離が近い方へ気軽に相談したい」という場合は、医療ソーシャルワーカーへ相談してみると良いでしょう。医療ソーシャルワーカーの相談窓口を探す際には「入院設備が200床以上ある大きな病院」にソーシャルワーカーが在籍しているかを確認し、在籍している際には悩みや疑問を相談してみることをおすすめします。
2:社会福祉協議会へ相談
社会福祉協議会とは、地域住民や社会福祉関係者、行政機関と連携して地域福祉の推進を図る機関です。社会福祉協議会は、地域住民の抱える福祉に関する相談を受け付ける役割を持っています。
社会福祉協議会の実施する日常生活自立支援事業は、判断能力の不十分な高齢者や障害者、その他在宅生活を継続するうえで不安や困難のある方を対象に、医療や福祉サービスの利用を支援(福祉サービス利用契約の支援、金銭管理、日常生活上の消費契約など)する制度です。
もちろん、身寄りのない高齢者でも利用できる制度です。金銭管理が難しく、医療費や入居費用の支払いに不安があり、入院を諦めようとしている方は、この制度を利用することを事前に相談すると良いでしょう。
社会福祉協議会の相談窓口は、下記のサイトから都道府県ごとに確認することができます。
⇒都道府県・指定都市社会福祉協議会の連絡先
3:地域包括支援センターへ相談
地域包括支援センターは、介護保険法に基づいて設置されている相談機関で、地域に住む高齢者の介護や生活に関して無料で相談に応じてくれます。同センターに配置された保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員がそれぞれの専門性を活かし、高齢者の心身の健康保持や生活の安定に向けて必要な支援を行います。
「身寄りがないけれど入院したい」といった意思を伝えることにより、身元保証人が必要でない医療機関の紹介、または、身元保証を行っている支援機関・団体へ繋ぐような対応を取ってくれるでしょう。
地域包括支援センターの相談窓口は、下記のサイトから都道府県ごとに確認することができます。
⇒都道府県別地域包括支援センターの連絡先
4:成年後見制度の利用を検討する
成年後見制度とは、認知症などが原因で判断能力が不十分な高齢者に、本来ならば高齢者本人が行うべき手続きや財産管理の代行、身上保護を法的に保障してくれる制度です。
成年後見人は下記の役割を果たすことで、高齢者の意思決定が困難な場面でも必要な医療を受けることができます。
● 契約の締結:入院の手続き、医療費の支払い
● 身上保護:高齢者の医療情報の整理
● 本人意思の尊重:治療方針に関する高齢者の意思を尊重
身寄りのない高齢者が、判断能力が不十分な状態になっても適切な医療が受けられるようにする制度です。
⇒成年後見制度とは?メリットや手続き方法を業界関係者が分かりやすく解説
身寄りのない高齢者が施設へ入居する方法
身寄りがない高齢者でも、入院の場合と同様に施設へ入居する方法はいくつかあります。下記の通り、幾つかの具体例を紹介します。
1:地域包括支援センターへ相談
先述の通り、地域包括支援センターは地域に住む高齢者の課題解決のために相談に応じてくれる専門機関です。
同センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)に対し、「身寄りがないけど施設に入居したい」「どの施設へ入居できるのか」「費用の支払いはどうしたらいいのか」などの不安・疑問を伝えれば、身元保証人が必要でない施設の紹介や、身元保証を行っている支援機関・団体へ繋いでくれるでしょう。
⇒都道府県別地域包括支援センターの連絡先
2:ケアハウスへの入居
ケアハウスとは、軽費老人ホームの一種で、社会福祉法人などが運営する高齢者施設です。
経済的な理由や、家族からの援助が難しい方が入居し、無料または低額な料金で日常生活上の世話や介護を受けることができます。
身寄りのない高齢者も入居することができますが、月額費用が他の介護施設と比べて安いため、多くの高齢者が入居を希望します。そのため入居の申し込みをしたとしてもすぐに入居できるとは限りません。
3: 身元保証人が不要な民間の介護施設へ入居
厚生労働省の発表した「令和3年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調査
(第 13 回)結果」によれば、有料老人ホームは全国で約15,000を超える施設があります。その中には、身元保証人を不要とする施設も一部あります。
数こそ少ないものの、身寄りのない高齢者にとっては貴重な存在であるため、見つけたら入居を検討してみるのもおすすめです。ただし、「身元保証人が不要な民間の介護施設はどこにあるか」の情報量が少ないため、探すのは大変困難です。
4:民間の身元保証サービスを利用
身元保証サービスとは主に身寄りのない高齢者のために、民間事業者が入院・施設入居の際の身元保証を引き受けてくれる有償サービスです。サービスの利用によっては、入院・入居後の日常生活上の支援や、亡くなった後の諸手続きも代行してくれる業者もあります。
⇒身元保証サービスを考えている方へ「サービス内容」「サービスの選び方」を業界関係者が紹介
身寄りがない高齢者の入院や入居時の注意点
身寄りがない高齢者でも、入院や入居できる方法を解説しましたが、入院や入居する際には注意点があります。
1:万が一に備えて事前に相談
すぐに入院や施設への入居をしなければならない状況でなくとも、万が一に備えて社会福祉協議会や地域包括支援センターへ先に相談し、情報を得ておくことをおすすめします。たとえば身元保証人を必要としない施設が自宅近くにあるか、身元保証をしてくれる支援機関にはどのような機関があるかなど、情報収集をしておくことで、実際に入院や入居が必要な状況になった時でも安心です。
2:任意後見制度の利用
老化に伴い心身機能が低下する中で、判断能力が不十分な状態になる前に任意後見制度の利用を検討することをおすすめします。
任意後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した時に備えて、元気なうちに信頼できる方や機関に財産管理や身上保護を委任しておく制度です。あらかじめ任意後見の契約をしておくことで、判断能力が低下したときには、任意後見人が財産管理・身上保護を行ってくれます。このような制度を利用することで、入院や施設への入居時に備えることができます。
⇒任意後見制度について|内容と手続きの流れや費用・法定後見制度との違い
3:不適切な身元保証会社とは契約しない
先に紹介した身元保証サービスを提供する事業者には、NPOやボランティア団体、民間の営利会社などがあります。しかし身元保証に関する事業やサービスは、指導監督に当たる行政機関が明確ではないため、一部では不適切な事業者が悪徳なサービスを提供している例があるようです。このような背景を踏まえ、信頼できる事業者であるかを調べて納得したうえで利用しましょう。
身寄りがなくて入院や入居でお困りな方は当社専門スタッフがサポート
今回は、身寄りがない高齢者の入院や高齢者施設への入居に関することを解説しました。身寄りがない方でも入院や入居する方法はあります。
今回紹介したように、社会福祉協議会や地域包括支援センターに相談する、事前に成年後見制度や身元保証サービスを利用するなどの様々な方法によって、手続きをスムーズに進めることができるため、まずは入院や入居に関する情報を収集することから始めてみて下さい。
一般社団法人終活協議会では、成年後見制度や身元保証サービスを追加費用やオプション費用は一切無く「入会金と基本料金のみ」で全て対応するサービスを提供しています。
しつこく契約を迫るような悪質な営業は一切無く、当社のサービス内容と料金に納得頂いたうえでご契約を交わした中で、20,000人以上のサービス提供実績があります。
身寄りがない中での適切な対策方法や、成年後見制度や身元保証サービスについての疑問や悩みを専門知識と経験豊富なスタッフが丁寧且つ親切にお答えしていますので、気軽にご相談ください。365日(受付時間10:00~17:00) 対応しています。
また、会社やサービスについて資料請求をご希望の方は、下記のページより資料をご請求ください。24時間365日受け付けております。
⇒心託サービス資料請求ページ
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 2024年6月19日葬儀費用の相場は?プランごとの平均費用や安く抑えるコツを紹介
2024年6月19日葬儀費用の相場は?プランごとの平均費用や安く抑えるコツを紹介 2024年5月15日家庭介護、家庭看護とは?家族の役割やメリット・デメリットを解説
2024年5月15日家庭介護、家庭看護とは?家族の役割やメリット・デメリットを解説 施設入居2024年5月7日老人ホームの費用相場はどのくらい?内訳や費用を抑える補助制度を解説
施設入居2024年5月7日老人ホームの費用相場はどのくらい?内訳や費用を抑える補助制度を解説 おひとりさま2023年12月3日高齢者の通院をサポートする「通院介助」の役割や重要性とは
おひとりさま2023年12月3日高齢者の通院をサポートする「通院介助」の役割や重要性とは
この記事をシェアする