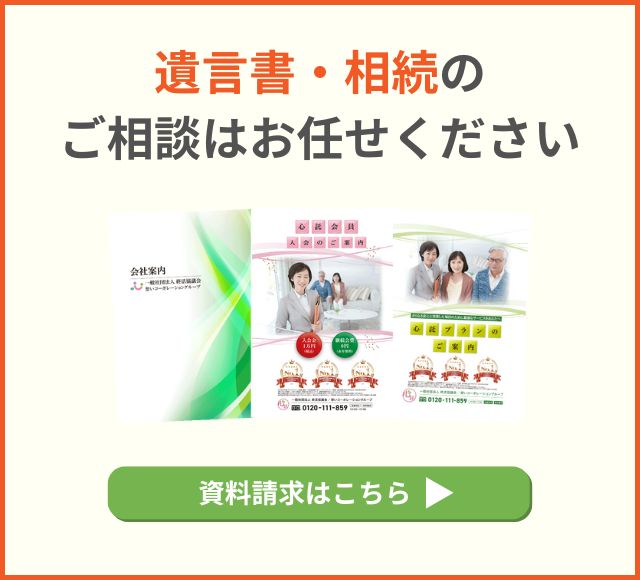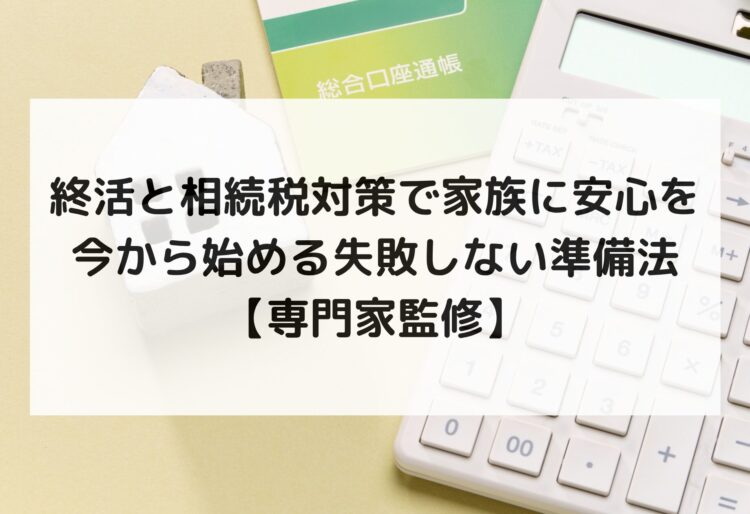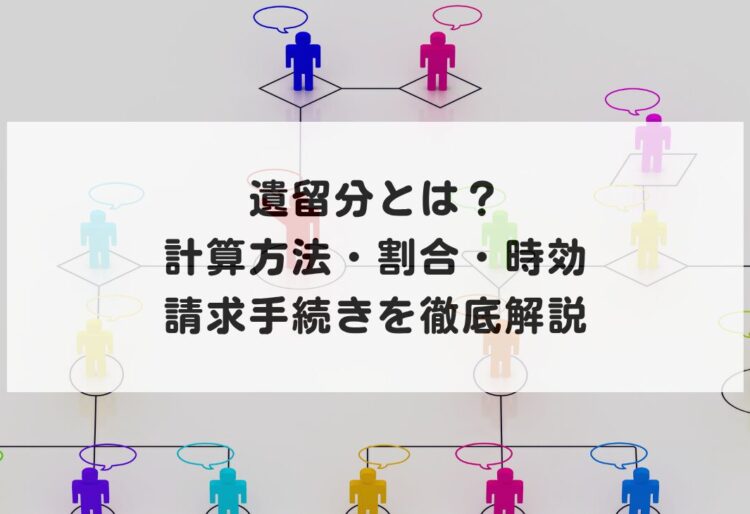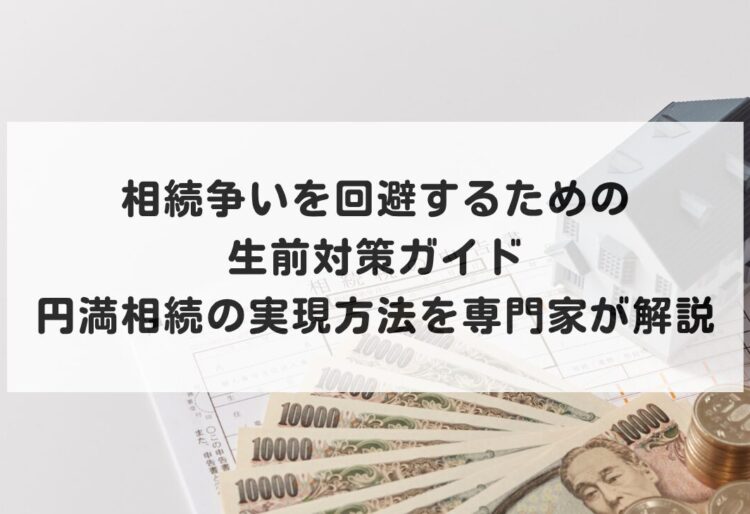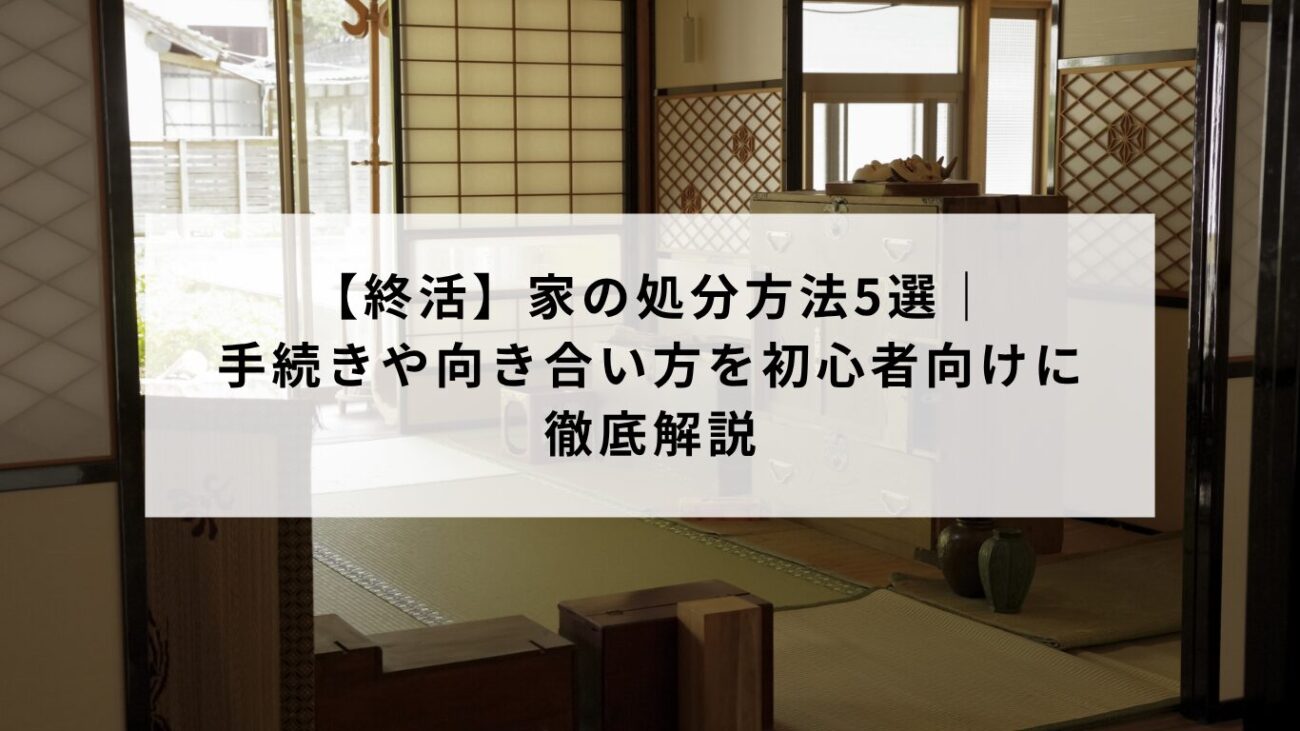
「終活」で忘れがちなのが、長年住んだ「家」の扱いです。空き家となった実家は、固定資産税や管理、最終処分などで、残された家族に精神的・金銭的に大きな負担をかけます。
家の終活は、こうした将来の不安をなくし、大切な家族への負担を減らすための準備です。ご自身が元気なうちにそうするかを決めておくことで、家族は心穏やかに過ごせます。この記事では、その具体的な第一歩を解説します。
目次
一軒家の処分方法5選!メリット・デメリットを比較
一軒家の処分には、様々な方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、ご自身のライフプランや家族構成、家の状況によって最適な選択は異なります。
「家に住み続けたいか」「現金が必要か」「特定の誰かに引き継ぎたいか」など、ご自身の希望を考えながら、一つ一つ見ていきましょう
売却:老後資金の確保と資産の現金化
家の処分方法として最も一般的なのが「売却」です。家を売却することで、まとまった現金を手にすることができます。この資金を老後の生活費や、新しい住まいへの住み替え費用、医療・介護費用などに充てることができるため、将来の金銭的な不安を大きく軽減できるでしょう。
【メリット】
- まとまった老後資金を確保できる。
- 固定資産税や維持管理の負担がなくなる。
【デメリット】
- 長年住み慣れた家や地域を離れる寂しさがある。
- 買い手が見つかるまで時間がかかることがある。
- 不動産会社に売却を依頼した場合、仲介手数料が発生する。
【こんな方におすすめ】
老後の資金を確保したい、住み替えを検討している方。
生前贈与:特定の家族に家を確実に引き継ぐ
「この家は、長男に継いでほしい」など、特定の誰かに家を確実に引き継ぎたいという明確な意思がある場合、「生前贈与」が有効な選択肢となります。
生前贈与とは、ご自身が元気なうちに、特定の相手に無償で財産を譲り渡すことです。相続とは異なり、ご自身の意思で確実に財産を渡す相手とタイミングを決めることができます。
【メリット】
- 自分の意思で、特定の相手に家を確実に引き継げる。
- 贈与する相手に喜んでもらえ、安心感を与えられる。
【デメリット】
- 高額な贈与税がかかる可能性がある(数百万円〜場合によっては数千万円)。
- 不動産取得税や登録免許税など、贈与を受ける側に税負担が発生する。
- 一度贈与すると、取り消すことは原則できない。
【こんな方におすすめ】
「長男に実家を継いでほしい」「同居している子に家を渡したい」といった、家を継いでほしい相手が決まっている方
解体して更地にする:土地の活用や売却の選択肢を広げる
老朽化や売却が難しい家は、「解体して更地にする」という選択肢があります。
建物の管理や倒壊リスクの心配もなくなり、精神的負担が軽減されます。相続する家族にとっても、管理しやすい更地にしておく方が負担が少なくなります。
【メリット】
- 駐車場経営など、土地活用の幅が広がる。
- 建物の維持管理や倒壊のリスクがなくなる。
【デメリット】
- 数百万円単位の解体費用がかかる。
- 固定資産税が高くなる可能性がある。
【こんな方におすすめ】
建物が古く、買い手が見つからずに困っている方
遺言書で指定:相続トラブルを防ぎ、意思を明確に伝える
ご自身の死後、誰に家を相続させるかを明確に決めておきたい場合、「遺言書」を作成することが非常に有効です。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が家を相続するかを決めなければなりません。しかし、相続人が複数いると、「自分が住みたい」「売却して現金で分けたい」など意見が対立し、深刻なトラブルに発展するケースが少なくありません。遺言書で明確に示しておくことで、こうした争いを未然に防ぎ、ご自身の最後の意思を確実に実現することができます。
【メリット】
- 誰に家を相続させるか、自分の意思を明確に示せる。
- 相続人間の無用な争い(争続)を防ぐことができる。
【デメリット】
- 法律で定められた形式を守らないと無効になる可能性がある。
- 遺留分(兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分)を侵害すると、トラブルの原因になることがある。
【こんな方におすすめ】
相続人が複数いる、特定の人に家を譲りたい方。
関連記事:無効にしないための遺言書の書き方|意外と知らない5つの注意点とよくある質問を解説
終活協議会の『心託』というサービスでは「公正証書遺言」の作成も受け付けています。
リースバック:家に住み続けながら現金化する
リースバックは、自宅を不動産会社などの事業者に一度売却し、その後、その事業者と賃貸契約を結ぶことで、売却後も同じ家に家賃を払いながら住み続けられる仕組みです。まとまった売却資金を一度に受け取れるため、老後の生活費や医療費、趣味などに活用できます。
また、所有権が事業者に移るため、固定資産税の支払いがなくなるといったメリットもあります。
【メリット】
- 売却後も今の家に住み続けられる。
- 将来的に買い戻せる可能性がある(契約による)。
【デメリット】
- 所有権を失う。
- 毎月の家賃が発生する(売却価格の3〜5%程度/月で設定されることが多い)。
【こんな方におすすめ】
老後資金は必要だけど、長年住み慣れた家を離れたくない方。
長年住んだ家への想いと向き合うには?心の整理の進め方
家族との思い出が詰まった家を手放すことは辛く寂しいものですが、その感情を受け止めることで心の整理が進み、前向きな一歩を踏み出すことができます。
焦らず、自分の気持ちを大切にしながら、ゆっくりと準備を進めましょう。
思い出の品はどう整理する?デジタル化や一部保管のすすめ
家の中にあるアルバムや子どもたちの作品など、思い出の品々をすべて処分する必要はありません。すべてを保管するのは難しくても、例えば写真はデータ化して「デジタル遺品」として残したり、特に思い入れの強い品だけを厳選して小さな箱に「思い出ボックス」としてまとめたりする方法があります。無理に捨てるのではなく、形を変えて大切な記憶を残す工夫をすることで、気持ちの整理がつきやすくなります。
家族との話し合いが最も重要!トラブルを避けるためのコミュニケーション術
家の終活で最も大切なのは、家族とのコミュニケーションです。ご自身にとっては大切な我が家でも、子どもたちにはそれぞれの生活があり、家に対する考え方も異なるかもしれません。
ご自身の想いや、なぜ家の終活を考えているのかを正直に伝え、家族の意見にも真摯に耳を傾けましょう。一方的に決めるのではなく、家族みんなで話し合うことで、お互いの気持ちを理解し、全員が納得できる最善の方法を見つけ出すことができます。
誰に相談すればいい?信頼できる専門家の見つけ方と役割
家の終活には、不動産の知識だけでなく、税金や法律といった専門的な知識が不可欠です。自分一人や家族だけで全てを判断しようとすると、思わぬ落とし穴にはまってしまったり、損をしてしまったりする可能性があります。
そんな時に頼りになるのが、各分野の専門家です。大切なのは、どの専門家が何をしてくれるのか、その役割を理解し、ご自身の悩みに合わせて適切な相談相手を見つけることです。
不動産会社:売却や賃貸のパートナー
家を「売りたい」「貸したい」と考えたときに、最初の相談相手となるのが不動産会社です。地域の不動産市場に精通しており、あなたの家がいくらで売れそうか、あるいは貸せそうかの査定をしてくれます。
複数の会社に査定を依頼し、対応の丁寧さや提案内容を比較して、信頼できるパートナーを見つけることが成功の鍵です。
税理士:税金に関する的確なアドバイス
売却で利益が出た場合の譲渡所得税や、生前贈与にかかる贈与税、相続税など、家の処分には複雑な税金が絡んできます。
税理士は、税金の専門家として、どうすれば税金の負担を最も軽くできるか(節税)について、具体的なアドバイスをしてくれます。特に贈与や相続を検討している場合は、早めに相談することをおすすめします。
司法書士・弁護士:相続や贈与の法的手続きの専門家
家の所有権を移転する「登記」の手続きは、司法書士の専門分野です。売買や贈与、相続が発生した際には、司法書士が関わることが多いです。
また、法的に有効な遺言書の作成をサポートしたり、相続人間でトラブルが起こってしまった場合には、弁護士が代理人として交渉や法的手続きを行ってくれたりします。
家の終活は、家族への想いを形にする第一歩
終活における家の処分は、単に不動産を整理する作業ではありません。それは、ご自身が築き上げてきた大切な資産を、残される家族が困らないように、そしてご自身のセカンドライフがより豊かなものになるように、未来への道筋をつけることです。
様々な選択肢の中からご自身の想いや状況に合った方法を見つけ、準備を進めること。それこそが、家族への最大の思いやりであり、愛情の表現と言えるでしょう。
終活に関するお悩みは終活協議会へ
終活の一環として家の処分を視野に入れている方は、まず専門家に相談してみてはいかがでしょうか。終活協議会では、1,0000名以上の弁護士、司法書士などの専門家が登録しており、終活全般に関する悩みや疑問にお応えしますので、お気軽にご相談ください。
まずは直接お話を聞いてみたい、という方はお電話での相談も受け付けております。
年中無休・全国対応可能なため、お悩みに合わせて終活のプロが対応いたします。
少しでも悩んでいる方は、お気軽にお電話ください。
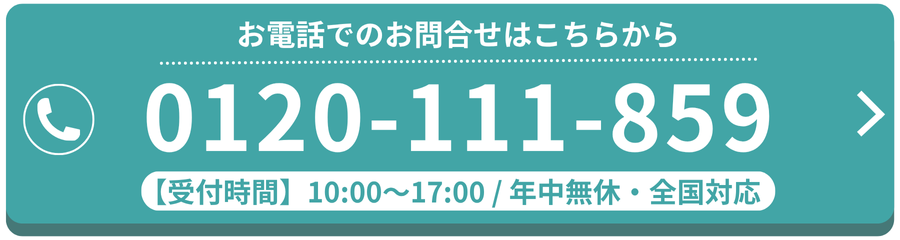
監修

- 一般社団法人 終活協議会 理事
-
1969年生まれ、大阪出身。
2012年にテレビで放送された特集番組を見て、興味本位で終活をスタート。終活に必要な知識やお役立ち情報を終活専門ブログで発信するが、全国から寄せられる相談の対応に個人での限界を感じ、自分以外にも終活の専門家(終活スペシャリスト)を増やすことを決意。現在は、終活ガイドという資格を通じて、終活スペシャリストを育成すると同時に、終活ガイドの皆さんが活動する基盤づくりを全国展開中。著書に「終活スペシャリストになろう」がある。
最新の投稿
 お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説
お金・相続2026年1月9日遺産相続の時効を知って終活を安心に|手続きの期限と備え方を解説 お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説
お金・相続2026年1月2日未支給年金|生計同一者がいない場合はどうする?手続き・備え・終活サポートまで徹底解説 お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説
お金・相続2025年12月26日生前に実家の名義変更する方法|手続きの流れ・税金・注意点をわかりやすく解説 資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
資格・セミナー2025年12月20日終活ガイド資格三級で始める、日当5,000円の社会貢献ワーク
この記事をシェアする