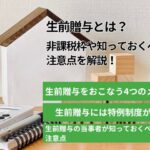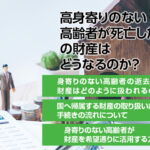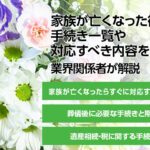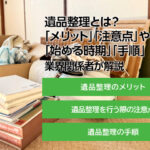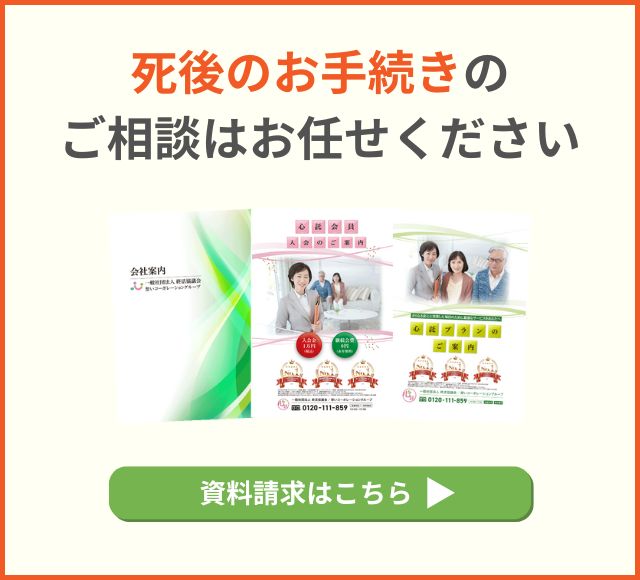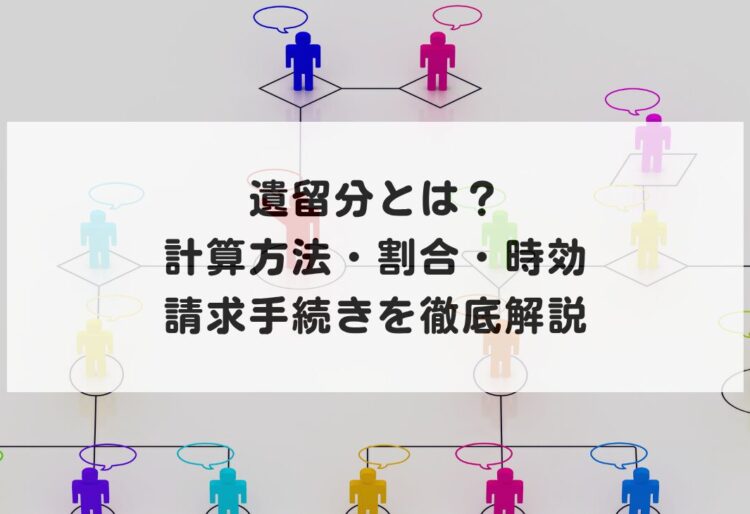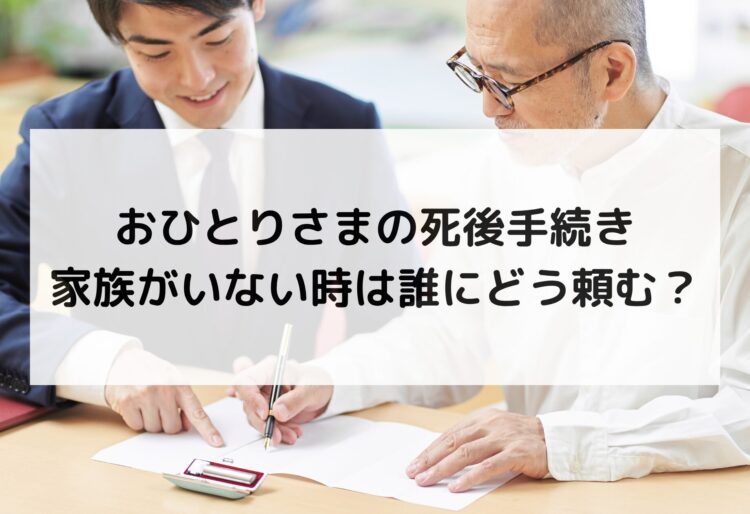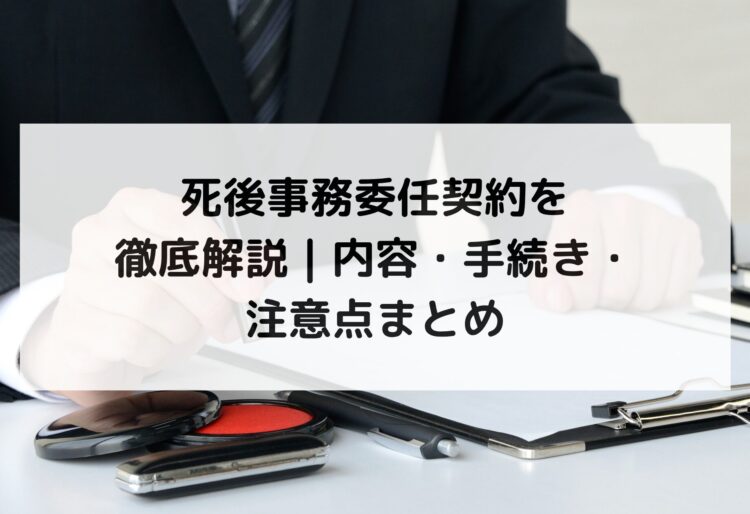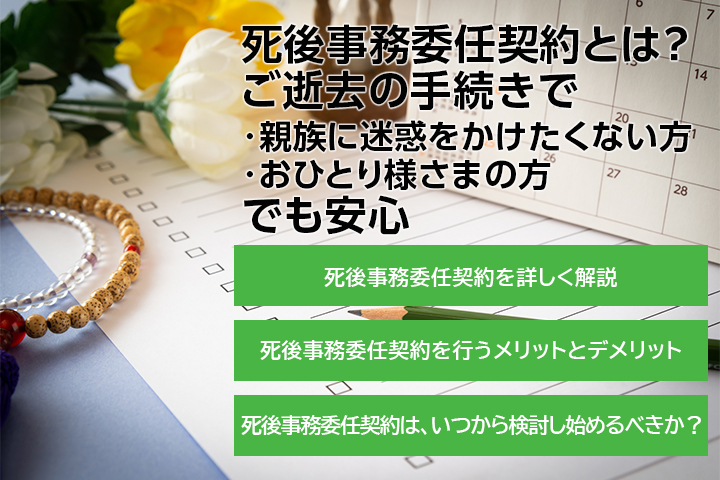
「死後事務委任契約」とは「自分が亡くなった後の事務処理(専門用語で「死後事務」といいます)を第三者に委任する契約」です。
これまでは葬儀や遺品整理などの死後のことは、残された家族が行うものという考え方が常識とされてきました。
ところが近年では、家族に負担をかけたくないと考える方や、おひとりさまの方が増えたことにより家族以外の第三者へ依頼するという選択肢「死後事務委任契約」が注目されています。
今回は、死後事務委任契約で委任することが多い内容をご紹介したうえで、死後事務委任契約を締結するメリットやデメリット、死後事務委任契約を検討するタイミングなどを専門家が詳しく解説します。
目次
「死後事務委任契約」とは
人が亡くなると、葬儀の手配をはじめとして、役所や銀行、病院などでさまざまな手続きが必要になります。自身の死後に親族へ迷惑をかけたくない方やおひとりさまの方は、こうした死後の手続きを誰にお願いすればいいのかについて不安を抱えがち……。
元気なうちに、これらの事務手続き(死後事務)を第三者に託しておくのが死後事務委任契約です。
近年は、自身が亡くなったあとのことを見越して行う活動である終活が注目を浴びています。終活で自分が亡くなったあとのことを想像し、対策をしておくことは、今を自分らしく安心して生活するために重要なことです。
死後事務委任契約の検討も実は終活の一環で、亡くなった後の面倒事を頼める方を決めておけば、死後の心配がなくなり、安心して老後の生活を楽しめます。
一般社団法人終活協議会の身元保証サービス『心託』では「死後事務委任契約」の締結も受け付けています
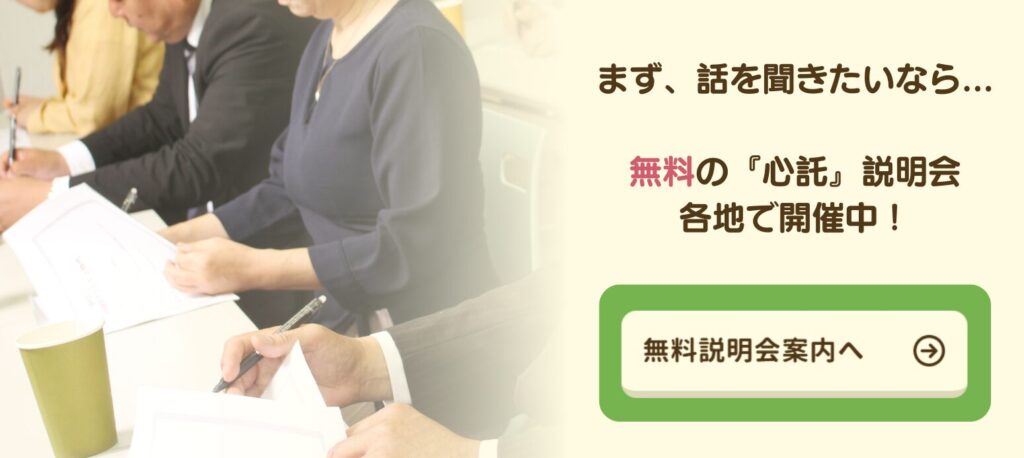
死後事務委任契約で依頼できること
死後事務委任契約で任せられることは主に次の7つです。
遺体の引き取り、親族・知人への連絡
人が亡くなって、まず初めにしなければならないことは、病院や施設などからの遺体の引き取りと親族・知人への連絡です。
おひとりさまである、親族が遠方に住んでいるといった、身寄りのない方は、自分が亡くなった事実を親族・知人に伝える手段もありません。死後事務委任契約で親族・知人への連絡を必須にしておけば、自分が亡くなった事実を伝えたい人に確実に伝えられます。
行政手続き
亡くなった後には行政に対して以下のような手続きが必要です。
- 死亡届の提出
- マイナンバーカード(運転免許証、健康保険証)の返還
- 年金の受給資格の抹消
「最後は行政がやってくれる」と思うかもしれませんが、親戚関係をたどり、遠い親戚が行政から対応を求められることがあります。死後事務委任契約でこうした手続きを任せておくことで、親戚に迷惑をかける心配はありません。
葬式や永代供養の手続き
「無縁死」が社会問題となっていますが、葬式や永代供養の手続、遺骨の引き取りなども、身寄りがいないと病院、警察、行政など周囲に迷惑がかかる可能性があります。
身寄りのない方が、葬儀などの亡くなった後の手続きを滞りなく進めるには、元気なうちから葬儀業者や霊園などと密に連絡を取り合う必要があります。
死後事務委任契約では、こうした手続きをすべて依頼できますし、葬儀や永代供養にかかる費用も預けておけば、周囲に迷惑をかける心配はありません。
費用の精算や納税の手続き
亡くなった後には、家賃や入院費などの費用の精算手続も必要です。固定資産税などの納税もしなくてはいけません。死後事務委任契約では、費用の精算手続も依頼できます。
死後事務委任契約を締結する際には、受任者が費用を負担することがないように預託金を預けておくケースが多いです。
受託者は、預託金の中から支払いなどを行います。 契約終了後に預託金が残っていた場合は、委託者の相続財産として取り扱われます。
各種契約の解約手続き
亡くなった後は、契約しているSNSや携帯電話、ライフライン(水道ガス電気)などの解約手続きが必要です。解約手続きをしない限り、利用料が発生し続けてしまう可能性もあるので、こうした手続きも亡くなってから早めにしておかなければなりません。死後事務委任契約ではこうした契約の解約も依頼することができます。
居宅の清掃・家財整理
亡くなった後は、契約しているSNSや携帯電話、ライフライン(水道ガス電気)などの解約手続きが必要です。
解約手続きをしない限り、利用料が発生し続けてしまう可能性もあるので、こうした手続きも亡くなってから早めにしておかなければなりません。死後事務委任契約ではこうした契約の解約も依頼することができます。
ペットの引継
ペットを飼っている方は亡くなった後にペットがどうなるか心配だと思いますが、死後事務委任契約で引取先を指定しておけば、受任者が引取先へのペットの引継などの対応をしてくれます。
逆に死後事務委任契約で依頼できないこと
亡くなった後に必要な手続きには他にも「相続手続き」もありますが、実は相続手続きは死後事務委任契約で任せることができません。
「誰にどのくらい相続させるか」「残された借金をどうするか」という財産に関する希望を実現したいなら死後事務委任契約ではなく、「遺言書」の作成を検討します。
遺言書がなければ法定相続人(親族)は遺産分割協議を行って遺産の配分を決めますが、遺言書があれば遺言を残した方の意思が尊重され、遺言書の配分に基づいて相続手続きを行います。死後事務委任契約と遺言書の作成はセットで行うことも多いです。
死後事務委任契約を検討すべき?死後事務委任契約が推奨されるケース
死後事務委任契約はどのような人が契約すべきでしょうか?自分に当てはまっているかどうか確認してみてください。
おひとりさまで身寄りがいない
未婚・独身、パートナーや子供との死別などさまざまな理由で一人暮らしをしている「おひとりさま」は少なくありません。いざというときに頼れる、身寄りがいないことも多く、亡くなった後のことに対して漠然とした不安を抱えているなら、死後事務委任契約を検討しましょう。
家族と絶縁状態である
過去に家族と仲違いして以来疎遠となり、絶縁状態で、今さら連絡する気も起きないというケースもあります。家族がいても頼りにくい状況となるので、死後事務委任契約がおすすめです。
家族はいるが、負担をかけたくない
家族はいるが遠方に住んでいる、または、家族も自分と同じく高齢であるなど、亡くなった後のことで家族に負担をかけたくないケースもあります。こちらも家族がいても頼りにくい状況となるので、死後事務委任契約をおすすめします。
家族と亡くなった後の希望が異なる
家族とは良好な関係を気付いているが、自分が理想とする最期を迎えたいという方もいるかもしれません。家族と価値観が違うことからそりが合わないこともあります。自分の亡くなった後のことは、必ずしも家族に頼む必要はありません。死後事務委任契約で家族以外の第三者に自分の亡くなった後のことをお願いしてみましょう。
死後事務委任契約をするメリットとデメリット

自分の死後の心配を少なくできる死後事務委任契約ですが、メリットとデメリットがありますので、それぞれ説明します。
死後事務委任契約のメリット
自分が亡くなったときに、周囲に負担をかけるのを心配している方は少なくありません。
死後事務委任契約を行うメリットとしては、次の4点を挙げられます。
死後事務委任契約を締結しておけば、死後の不安を解消し老後の生活を楽しめるようになります。それぞれのメリットの内容を詳しく見ていきましょう。
死後の不安を解消できる
年を重ねると、自分の死後に思うような身辺整理ができるか、家族に余計な迷惑をかけないかなど、不安に感じることが多くなります。
死後事務委任契約を締結しておくことで、自分の意思に沿った形で死後の身辺整理ができるため、今考えることでこの先の心配をせずに暮らせるようになります。
不安をたくさん抱えていると日常生活を楽しめなくなってしまいます。死後事務委任契約の不安を1つでも解消しておくことは、シニアライフを楽しむうえで必要なこととも言えます。
家族や親族に負担や迷惑をかけずに済む
死後事務委任契約では、家族や親族が行うことの多い死後の事務手続を第三者に依頼できます。
そのため、自分が亡くなっても家族や親族に負担や迷惑をかけずに済みます。
自分が亡くなったときに、ご家族に負担をかけるのを心配している方は少なくありません。
第三者へ死後の手続きを依頼していくことで、余計な心配をせずに生活できます。
おひとりさまの方でも死後の手続きを依頼できる
おひとりさまの方は、ご家族がいる方にも増して死後の手続きに不安を抱えている方が多いでしょう。死後事務委任契約は、おひとりさまの方に恩恵の多い契約です。
死後事務委任契約で、自分が希望する最後になるように任せておけば、おひとりさまの方でも、身寄りがいる場合と同様に、ご自身の意思を反映したエンディングを迎えることができます。
死後に必要な手続きの漏れがなくなる
人が亡くなったときに必要な手続きは非常に多いです。そのため、ご家族や親族が死後の事務手続きの対応をしても、対応漏れが生じるケースが多いです。
例えば 、本人しか把握していない銀行口座や有料の会員登録があると、対応の遅れにより口座を凍結されたり、会費が発生し続けたりしてしまいます。
死後事務委任契約で死後に必要な手続きを網羅しておくと、受任者が業務が手続きの対応を行うため、手続き漏れの心配はありません。
死後事務委任契約のデメリット
死後事務委任契約のデメリットとして、やはり亡くなった後のことですので「きちんと実行されているかどうかを確認できないこと」があります。
死後事務委任契約は、受任者の死亡や廃業により、契約が途中で終了してしまうリスクがあります。任せる相手も慎重に信頼できる人を選ばなくてはなりません。
実績が豊富であることが、責任をもって最後まできちんと対応している証ですので、実績が豊富な事業者を探して死後事務を依頼することが大切です。
死後事務委任契約は、いつから検討し始めるべきか?
死後事務委任契約はいつから始めるのがベストなのかと、お悩みの方は少なくないでしょう。結論から言うと、考え始めたその時です。20代であろうと30代であろうと関係ありません。検討するのが遅すぎることはあっても、早すぎることはありません。
死後事務委任契約を締結しておくことで、自分が亡くなったときの整理の方法を決めておけるので、死後の心配をせずに安心して生活できるようになります。
残された家族にとっても、不慮の事態が起こったときに死後の手続きを行うのは精神的に負担が大きいです。死後の手続きをする人が決まっていれば、負担なく安心して手続きを進められます。
高齢者の方はもちろんのこと、若い方でも不慮の事態に備えて死後事務委任契約を締結しておくことをおすすめします。
死後事務委任契約の内容は、状況の変化に応じて変更することもできます。若い方でも、最初の契約から内容を完全に固める必要はないので、契約を検討してみてください。
死後事務委任契約締結から完了までの流れ

ここでは、死後事務委任契約を締結し業務を終えるまでの活動内容を紹介します。活動内容の流れは、次のとおりです。
- 1:受託者と委任する業務の内容を決める
- 2:契約書を公正証書で作成する
- 3:委託者の死後に受託者が業務を行う
- 4:相続人への報告・精算を行う
1:受託者と委任する業務の内容を決める
死後事務委任契約を締結するには、まずは業務を依頼する受託者を決めなければなりません。信頼できる知人がいない方は、専門家に報酬を支払って業務の依頼ができます。
受託者を決めたら、次に委任する業務の内容を決めます。死後事務委任契約を締結し、死後の身辺整理の不安を解消するには、死後に必要な事務手続きを漏れなく把握しておくことが重要です。
2:契約書を公正証書で作成する
死後事務委任契約は口頭でも成立しますが、契約書がなければ適切に死後事務を行うことが難しくなります。
そのため、死後事務委任契約を締結する際には、契約書を「公正証書」で作成します。
公正証書とは、各地の公証役場にて公証人の立ち会いのもと作成した契約書のことで、単なる契約書と比べて公的な信用が高く、契約を反故にされるリスクが少ない契約の形式です。それゆえ、死後事務委任契約のように、死後に契約が履行されることを担保するような重要な契約で、公正証書が使用されます。
3:委託者の死後に受託者が業務を行う
委託者が亡くなった際には、受託者が死後事務委任契約にて定められた内容を誠実に行います。
委託者の意思に従って、漏れなく手続きを進めることが重要です。
4:相続人への報告・精算を行う
委任事務の終了時には、相続人や相続財産管理人に業務内容の報告を行い、預託金の余りがあれば返還します。
委託者の死後に受託者が行う業務は、複雑なものもあるため、専門家のサポートを受けられるようにしておくと安心です。
死後事務委任契約にかかる費用
お気づきの通り、死後事務委任契約は「死後のことを第三者に頼む」ということになるので「費用」がかかってきます。
費用の内訳としては以下の通りです。
・死後事務委任の契約にかかる費用
・公証役場の手数料
・預託金
ここからは死後事務委任契約にどのくらいの費用がかかるのか解説します。
死後事務を委任する事業者によっても費用は大きく異なるので、これから紹介する金額はあくまでも目安としてください。
死後事務委任の契約にかかる費用(数万円~数十万円)
死後事務委任契約を締結する際には「公正証書」で締結するのが一般的です。この公正証書を作るためには専門家に依頼しなくてはならず、そのために必要な費用の相場観は数万円~数十万円となっています。
公証役場の手数料(1万1,000円)
公正証書を作成する際に公証人への手数料11,000円が発生します。
預託金(100万円~1,000万円)
事業者(受任者)が葬儀費用や医療費の精算、税金の支払いをするためには、あらかじめ受任者に託しておく「預託金」が必要です。
また、葬儀や納骨の手配、行政手続きなどの死後事務を第三者に任せることになるので、手続きの代行に対する報酬が必要になります。預託金にはこの報酬が含まれているのが一般的です。
預託金の金額は100万円~1,000万円となります。
なお、遺産精算方式を採用する事業者では、死後事務契約時に遺言をセットで作成することで、遺産から清算できるようにしており、預託金を預からないケースもあります。
預託金精算方式を採用しているかどうかは事前に確認しておきましょう。
高額な費用が発生するが、親族に任せる場合と同等

死後事務委任契約ではトータルで100万円~1,000万円という費用が発生しますが、親族に依頼する場合でも結局同じくらいのコストがかかります。
まず、死後事務委任契約を締結しない場合、親族が死後のことを対応することになりますが、複数人の親族が葬儀の対応のために仕事を休んだり、遺品整理のために体力を使ったりとそれなりの負担があります。
さらに、親族が対応することになった場合、特に葬儀や納骨で本人の希望をくみ取りきれず、「とにかく葬儀を盛大にしよう」などと、葬儀費用だけでも死後事務委任契約と同じくらいの費用がかかってしまうことも少なくありません。
死後事務委任契約であれば、葬儀については小さく火葬式、納骨については高価で維持費もかかる墓は持たずに永代供養などと希望しておくことで、亡くなった後にかかる費用を抑えることができます。
死後事務委任契約を頼めるだけのお金がない場合は?
現財産から支払う預託金精算方式ではなく、遺産生産方式を採用している事業者を探すことをおすすめします。また、事業者によっては死後事務委任契約のプラン料金は異なり、安価な値段でサービスを提供する事業者も存在します。
当会は終活業界で運営実績20年を誇り、身元保証・死後事務委任契約プラン「心託」をご提供しています。言い値の多い終活サービスの中で、適正価格でのサービス提供をお約束し、入会時に必要な188万円(税込)だけで、身元保証から死後事務まですべてお任せいただけるサービスとなっています。
詳細は「心託サービスについて」から。
死後事務委任契約でトラブル?
死後事務委任契約をしておくと、将来の心配なく安心して生活できるようになります。
本人の問題だけでなく、家族の負担も解消できるのは死後事務委任契約の大きなメリットです。
ただし、
- サービス内容について詳細に説明されないまま契約してしまった
- サービスごとに発生する費用について説明されない契約してしまった
- 事業者が、預託金を事業者の運転資金と分けて管理しておらず、使い込んでしまった
こうしたトラブルが起きることもあります。
死後事務委任契約でのトラブルを防ぐためには、契約前の面談時に次のことを確認してみてください。
- 事業者からサービスの全容について詳細な説明を求めます。「このプランではどのようなサービスがいくらで提供されていますか」と提供されるサービスをすべて説明してもらいましょう。
- 「預託金は運転資金とは別の口座で管理されていますか」と質問しておき「別の口座で管理されている」という回答をもらうようにしましょう。
また、ご存じの通り、死後事務委任契約のサービスを提供する事業者は玉石混交を極め、「どこに頼んでいいかわからない」という状態にあると思います。そんな時には運営実績を確認してみてください。例えば、サービスの利用者数や運営年数、事業規模を確認しましょう。
死後事務委任契約なら、一般社団法人終活協議会にお任せください!
当会は、お客様の老後のお困りごとを解決するお手伝いをしております。2002年にシニアの原宿、巣鴨で創業して以来20年以上、シニアの相談を受け付けております。
現在は老後のことなら何でも相談できる、お心、お気持ちを託していただけるような「心託」というコンシェルジュサービスを提供しており、全国で2万人以上の方に利用されています。
心託では、死後事務委任契約についてももちろん取り扱っており、死後のことを全般をお任せいただくことが可能です。あなたのコンシェルジュとして、NOといわないサービスをモットーとしておりますので、冷蔵庫を動かしたいなど、どんなに些細なお悩みでもご相談ください。
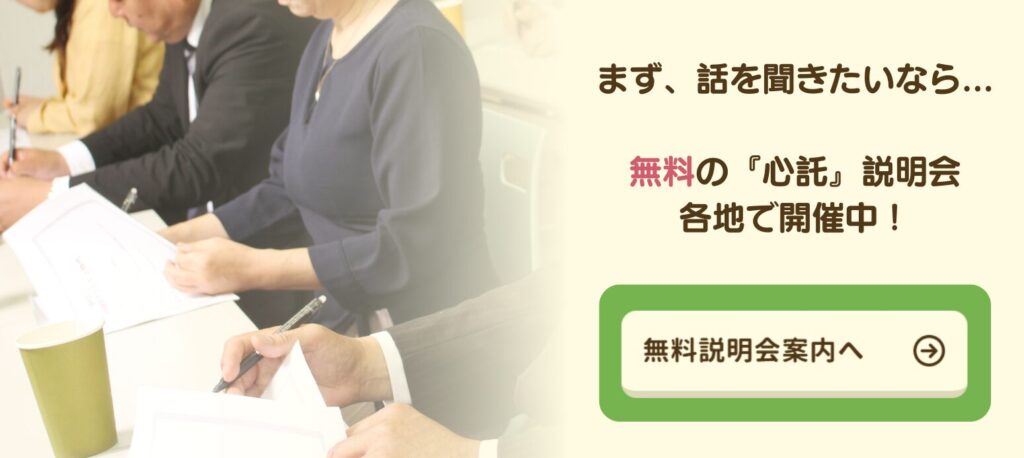
監修

- 所属:東京司法書士会 一般社団法人 終活協議会理事
-
1997年 東洋大学法学部卒業
大学在学中から司法書士試験の勉強をしつつ、1999年株式会社サイゼリヤに入社
7年間勤務した後、再度司法書士を目指すため2006年退社
2007年 司法書士試験合格
2008年 司法書士登録
試験合格後は、都内の司法書士事務所や法律事務所にて勤務
2021年 「落合司法書士事務所」開設
2021年 一般社団法人終活協議会理事就任
最新の投稿
 お金・相続2024年6月19日生前贈与とは?非課税枠や知っておくべき注意点を解説!
お金・相続2024年6月19日生前贈与とは?非課税枠や知っておくべき注意点を解説! お金・相続2023年12月3日身寄りのない高齢者が死亡した後の財産はどうなるのか?
お金・相続2023年12月3日身寄りのない高齢者が死亡した後の財産はどうなるのか? 暮らし2023年9月11日家族が亡くなった後の手続き一覧や対応すべき内容を業界関係者が解説
暮らし2023年9月11日家族が亡くなった後の手続き一覧や対応すべき内容を業界関係者が解説 身の回り整理2023年7月10日遺品整理の進め方ガイド|注意点とメリット・デメリットを詳しく解説
身の回り整理2023年7月10日遺品整理の進め方ガイド|注意点とメリット・デメリットを詳しく解説
この記事をシェアする